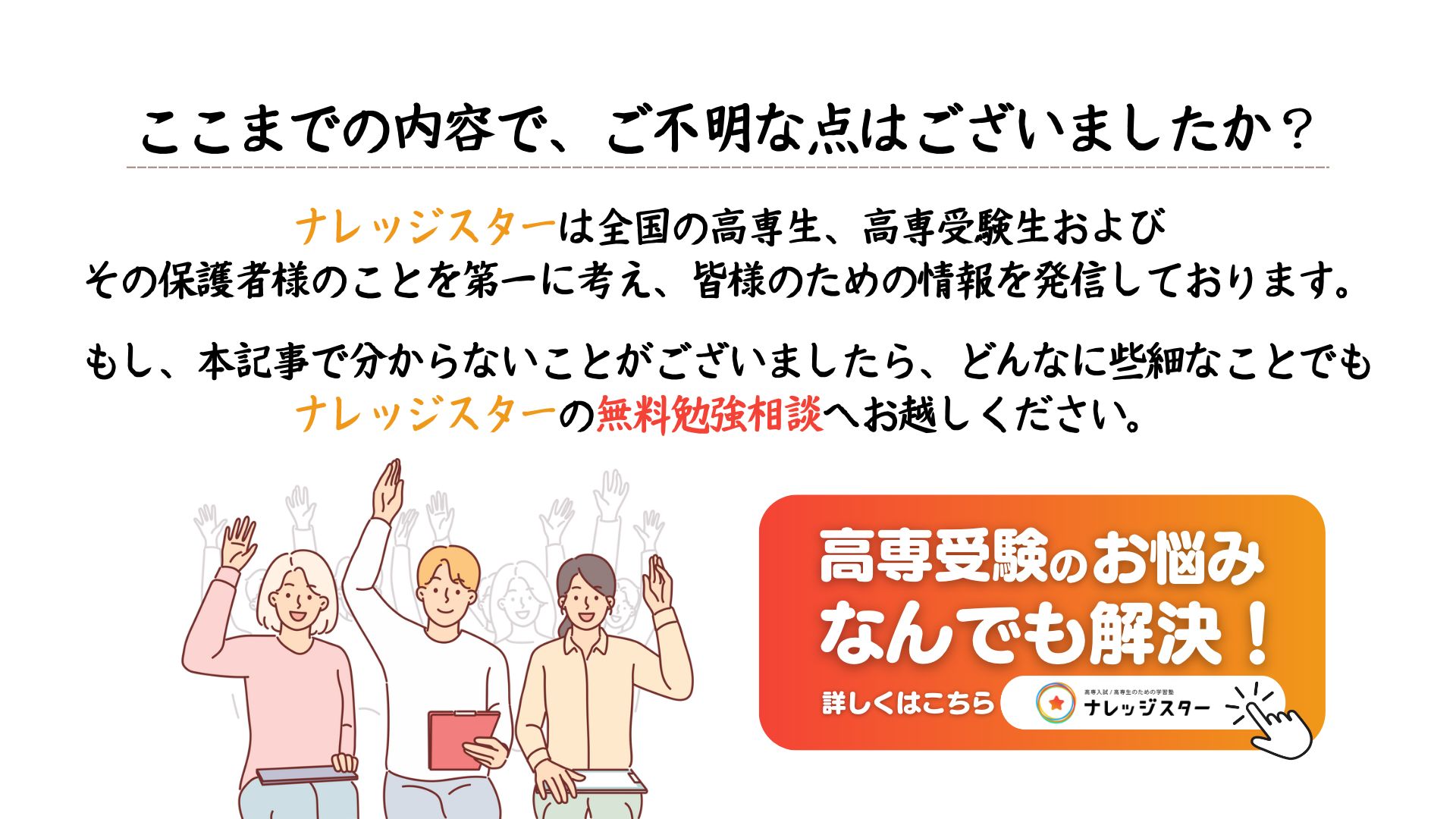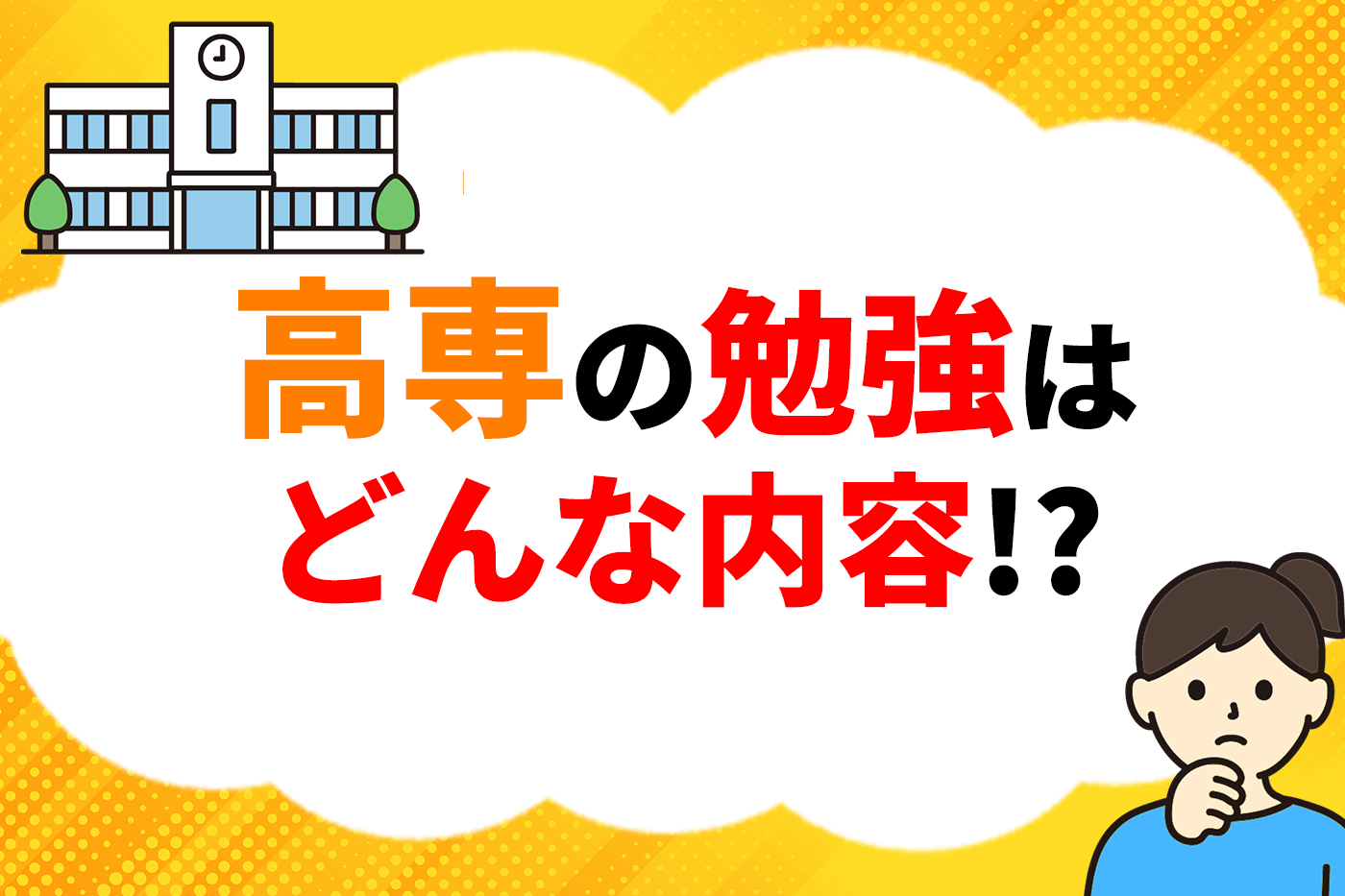A.結論
A.高専では、低学年は一般教養で基礎をしっかり固め、学年が上がるごとに専門科目が増えていく「くさび型カリキュラム」によって、技術者に必要な力を段階的に身につけていきます。
学年別の学習構成
1年生
約7〜8割が一般科目(国語・数学・英語・理科・社会など)で、基盤づくりの時期。専門科目は少なめで、理系の基本をじっくり学びます。
2年生
専門科目が徐々に増え、比率はおよそ3:7に。微分積分など、高専で必要となる大学初年級の内容が入ってきます。
3年生
一般科目と専門科目が半々に。専門科目にはプログラミングや材料科学など、多分野の学びが登場します。
4年生
専門科目の比率が約8割。実験や実習を含む本格的な学びが中心となり、日々の積み重ねがとても重要です。
5年生
授業は少なく、卒業研究が主役。残った時間で不足単位を補う形になります。
ライターの一言
高専では、1年生でしっかり一般教養を身につけ、徐々に専門性を追求する教育スタイルが特徴です。階段を上るように、基礎から専門までを段階的に習得していける構成になっているので、しっかり準備すれば安心です。
また、定期試験の評価システムには課題や常時の参加も含まれており、勉強に真面目に取り組む姿勢が成績に反映されやすい仕組みになっています。赤点を取ってしまっても、救済措置で巻き返しができる環境も整っています。これらも含めて、高専の学びは「主体的に関わりながら積み重ねる力」が大きな鍵だと言えるでしょう。
私自身、高専に入学したばかりの頃は「高校の延長かな?」と甘く考えていた節がありました。しかし実際の授業はスピードが速く、専門科目の難しさにも圧倒されました。それでも、1年生の基礎がしっかりしていたことで2年以降の勉強についていけたことは大きかったです。
また、試験で点が悪くても、課題提出や出席など努力が評価される構造に助けられた経験が何度もありました。「再試験があるから次も頑張ろう」と思える環境は、心の支えになった部分もあります。
高専は単なる学び舎ではなく、「自分で学び続ける人」を育ててくれる場所です。最初は大変かもしれませんが、基礎を固め、疑問を残さず、積極的に関われる人なら、自分の手で技術と知識をグッと伸ばせる、そんな教育環境が高専にはあります。
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。
高専について質問がある人はこちらから!!