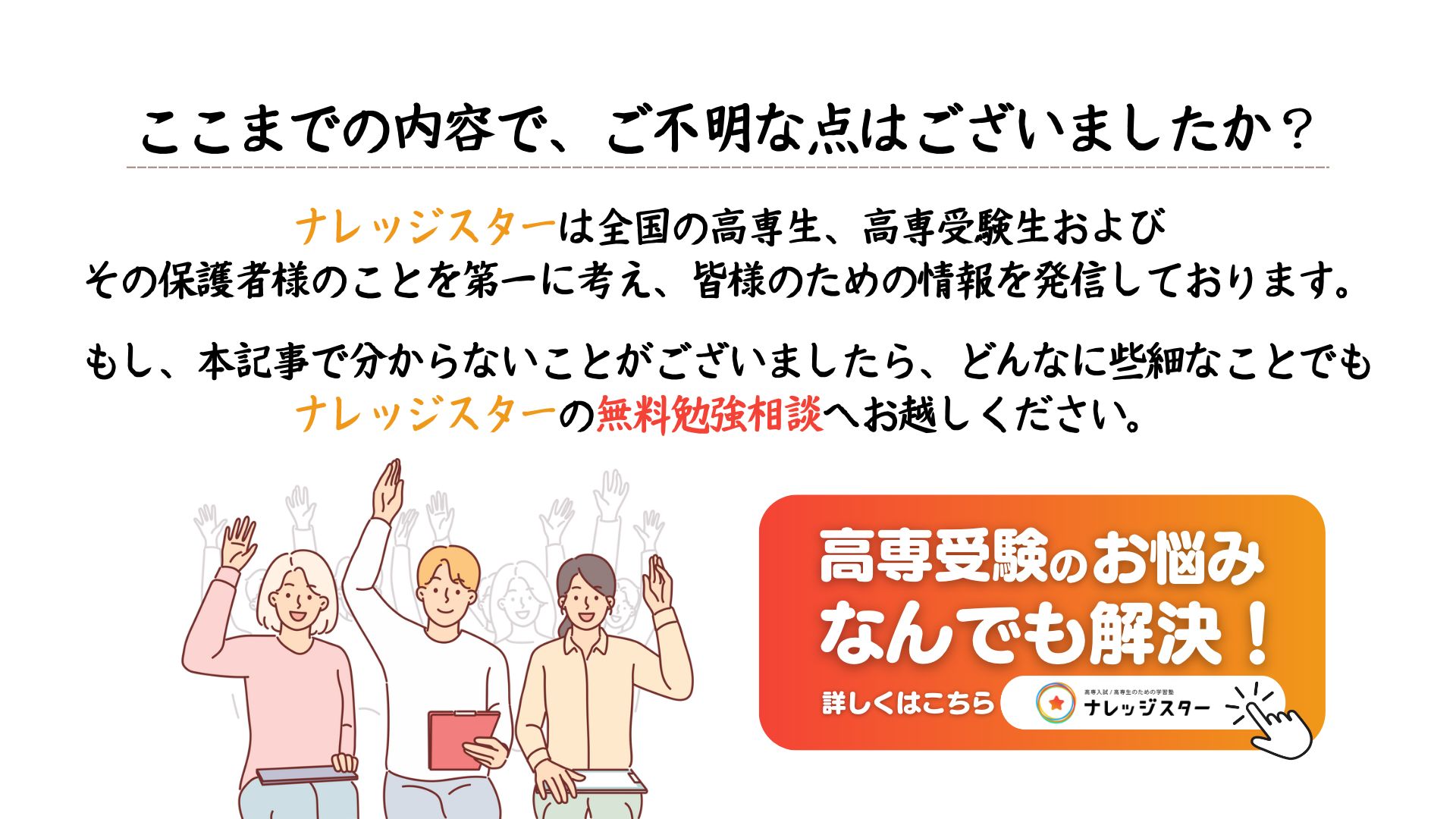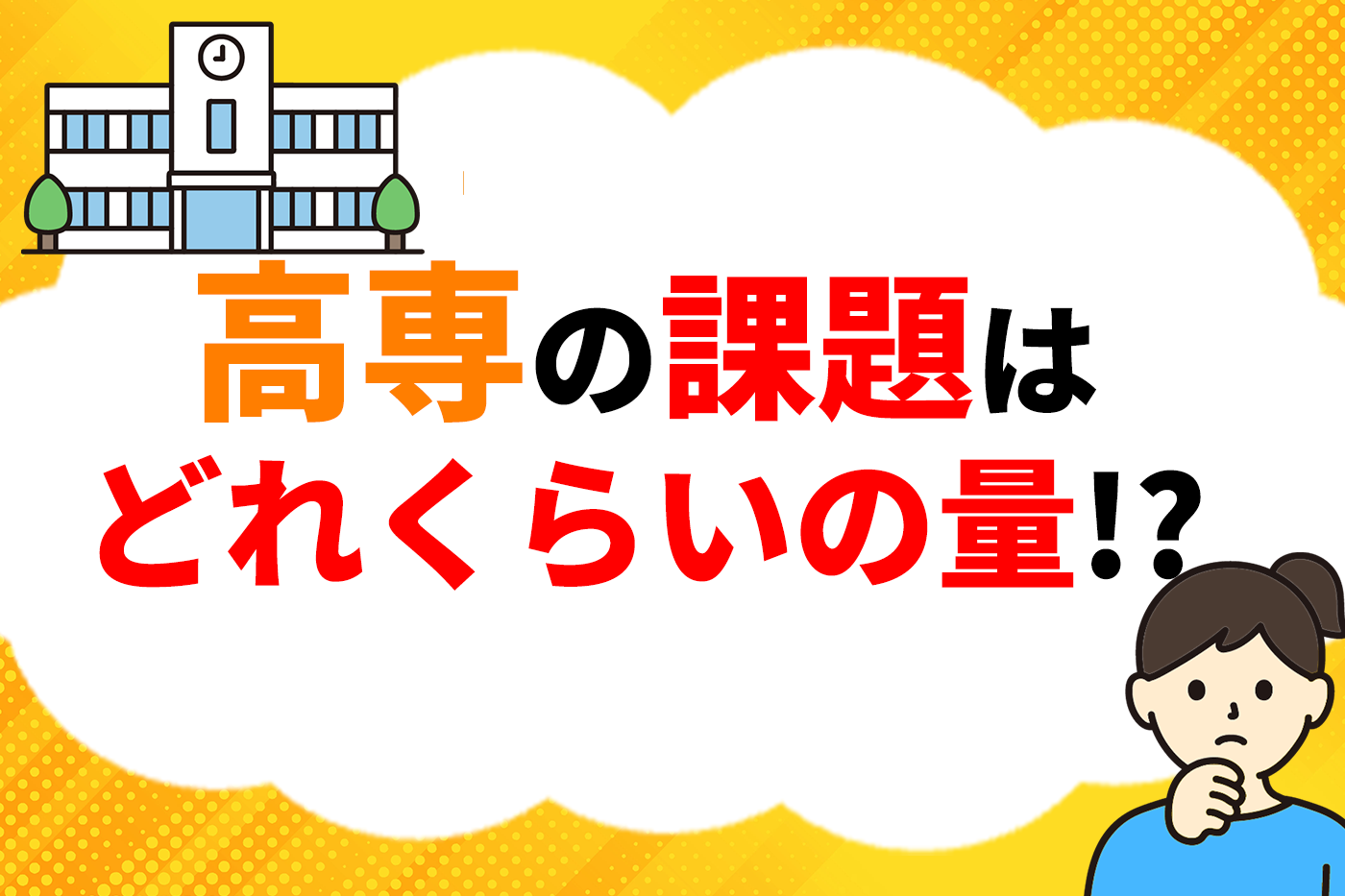A.結論
A. 高専では、学年が上がるにつれて課題やレポートの量が増え、とくに実験や実習の後には専門性の高い「レポート」、授業の理解度を測る「課題(宿題)」が頻繁に課されるため、計画的な取り組みが重要です。
具体的な内容と頻度
1年生
レポートは月に1回程度で、内容は比較的シンプル。実験テーマも身近なものが多く、手書きまたはWord形式など形式に違いがありますが、提出とフィードバックを通じて書き方を少しずつ学ぶステップになります。
2年次以降~学年が上がるにつれて
2年生以降になると、専門の分野に関連する実験レポートや文章・図を用いて説明する課題レポートの頻度・難易度ともに上がります。高学年では週1回ペースでレポートが出される学科もあり、レポートをこなすことが成績や進級に直結することを実感する場面も多いです。
専門課題の性質
レポートには、実験の目的・方法・結果・考察を整然とまとめる文章力や、他者が読み取れるような図表化するスキルが求められます。これらは技術者として必須の能力を養う訓練でもあります。
ライターの一言
高専では、1年次の頃からレポートや課題に触れ始め、学年が上がるにつれてその量と専門性は確実に増していきます。特に実験系の授業では、月1回→週1回ペースへと提出頻度が変化することもあり、計画的な学習態勢が不可欠です。
レポートは形式だけでなく、「目的を明確にし、結果を正しく表現し、考察を論理的にまとめる」という思考力も同時に鍛えられる教育手法です。この取り組みを習慣化することが、高専生活の学びをより深め、後々の専門性の土台にもつながります。
私が1年のとき、初めて出されたレポートは「テーマが分かるように説明するだけでも精いっぱい」で、見返すとなかなかにひどいレポートでした(笑)。それが先輩に見せてもらったサンプルを参考に「目的・方法・結果・考察」の型を真似するようになると、徐々に評価が上がり、自分でも「伝える力」の成長を実感できました。
学科や授業によって頻度や負荷は異なると思いますが、週1回のレポートが当たり前になる時期も遠くありません。だからこそ、今のうちから少しずつ「考えを整理して書く癖」をつけておくと、余裕をもって高専生活をスタートできますし、学びの深さも変わってきます。
そして、レポートや課題でついた実力が卒業研究・論文で発揮されます!
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。
高専について質問がある人はこちらから!!