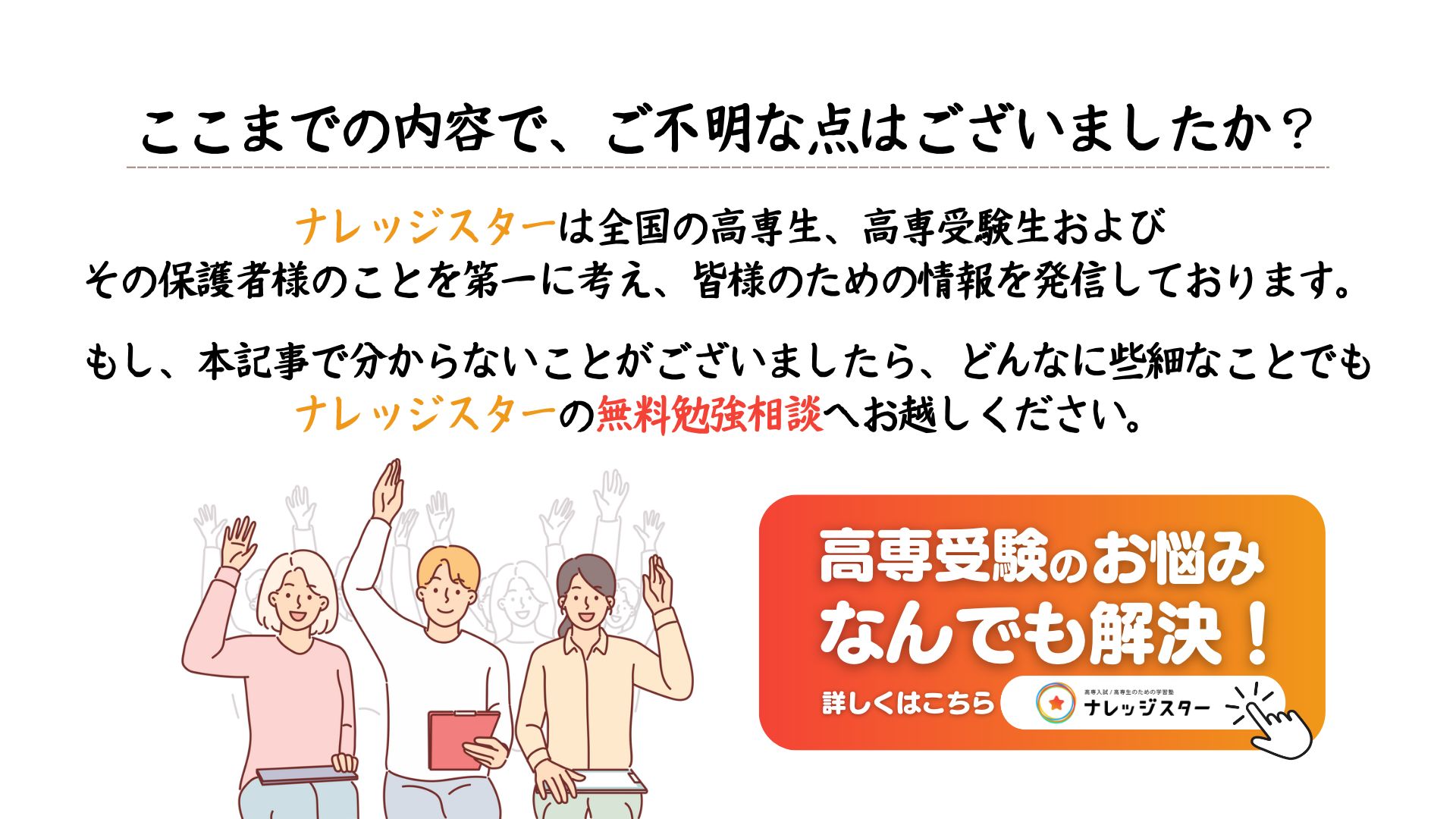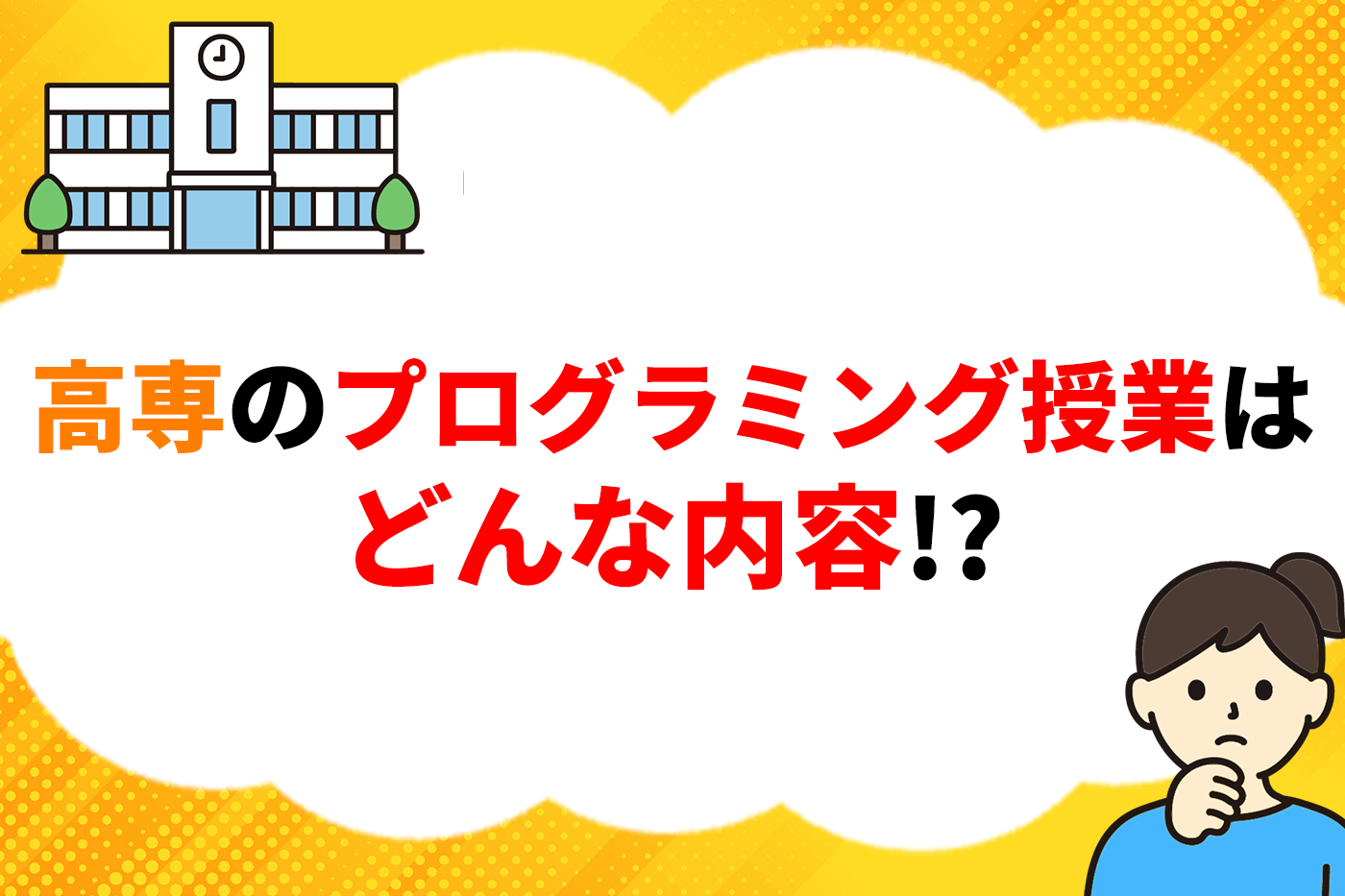A.結論
A. プログラミングの学びは学科によって異なりますが、基本的なITリテラシーから始まり、情報系では専門的なソフトウェア開発、電気・機械系では制御やシミュレーション、その他の学科でも必要に応じたプログラミングへの対応力を学びます。
高専でのプログラミング授業の概要
共通科目としての基礎教養
1〜2年次には「情報リテラシー」や「プログラミング基礎」でパソコンの操作やOfficeツール(Word・Excel・Teamsなど)を学ぶ場合がありますが、高専や学科により異なることもあります。
情報系学科では体系的に学ぶ
プログラミング言語はJava、C言語、Pythonなど複数を習得し、アルゴリズムやデータ構造、オブジェクト指向、さらにはAI・IoTなどの最新技術にも触れて深く学びます。 プログラミング演習やプロジェクト形式の実践も多く含まれます。
電気・機械系学科では実践的応用中心
MATLABやPythonを使用し、制御システムやロボット、回路のシミュレーションなど、プログラムを使って現実の工学問題を解く力を身につけます。
その他の学科では必要に応じた学び
Excel関数やRによる統計分析、CADなどの専門ソフトといった情報活用スキルもレクチャーされ、ITリテラシーや実務ツール習得に役立ちます。
「できる人」と「できない人」の差って?
授業内容をこなすだけでなく、ハッカソンや部活など課外での活動、継続的に学ぶ意欲、バグ解析への粘り強さが、プログラミングが得意になる鍵となります。
ライターの一言
高専のプログラミング授業は、まずは全学生を対象に基礎的なITリテラシーを習得し、情報系ではソフトウェア開発の核心に迫る専門科目を体系的に学びます。一方で、電気・機械系ではプログラミングを実験・制御という実践の中で身につけ、その他の学科でも必要に応じた情報活用スキルを磨く内容が含まれています。
授業そのものをこなすだけでなく、授業外での挑戦や持続的な学びへのモチベーション、バグと向き合う粘り強さが、プログラミングができるかできないかの大きな分かれ目になります。高専は「技術を使って自分のアイデアを形にする力」を育てる、非常に実践的な学びの場です。
私が高専に入学して最初に驚いたことは、情報系だけでなく他の学科でも「自分でプログラムを書いて動かす」という体験が当たり前だったことです。たとえば1学年のプログラミング実践の授業でロボットのセンサーをPythonで制御したときには、「思った通り動いた!」という喜びを強く感じました。もちろんバグとの格闘も日常ですが、自分のコードに自分で反応してくれる瞬間が本当に楽しい。プログラミングはツール以上の存在になって、自分のアイデアを実現する手段として、徐々に生活に溶け込んでいく感覚があります。
だからこそ、少しでも興味がある人は、最初は小さなコードからでも触れてみてほしいです。
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。
高専について質問がある人はこちらから!!