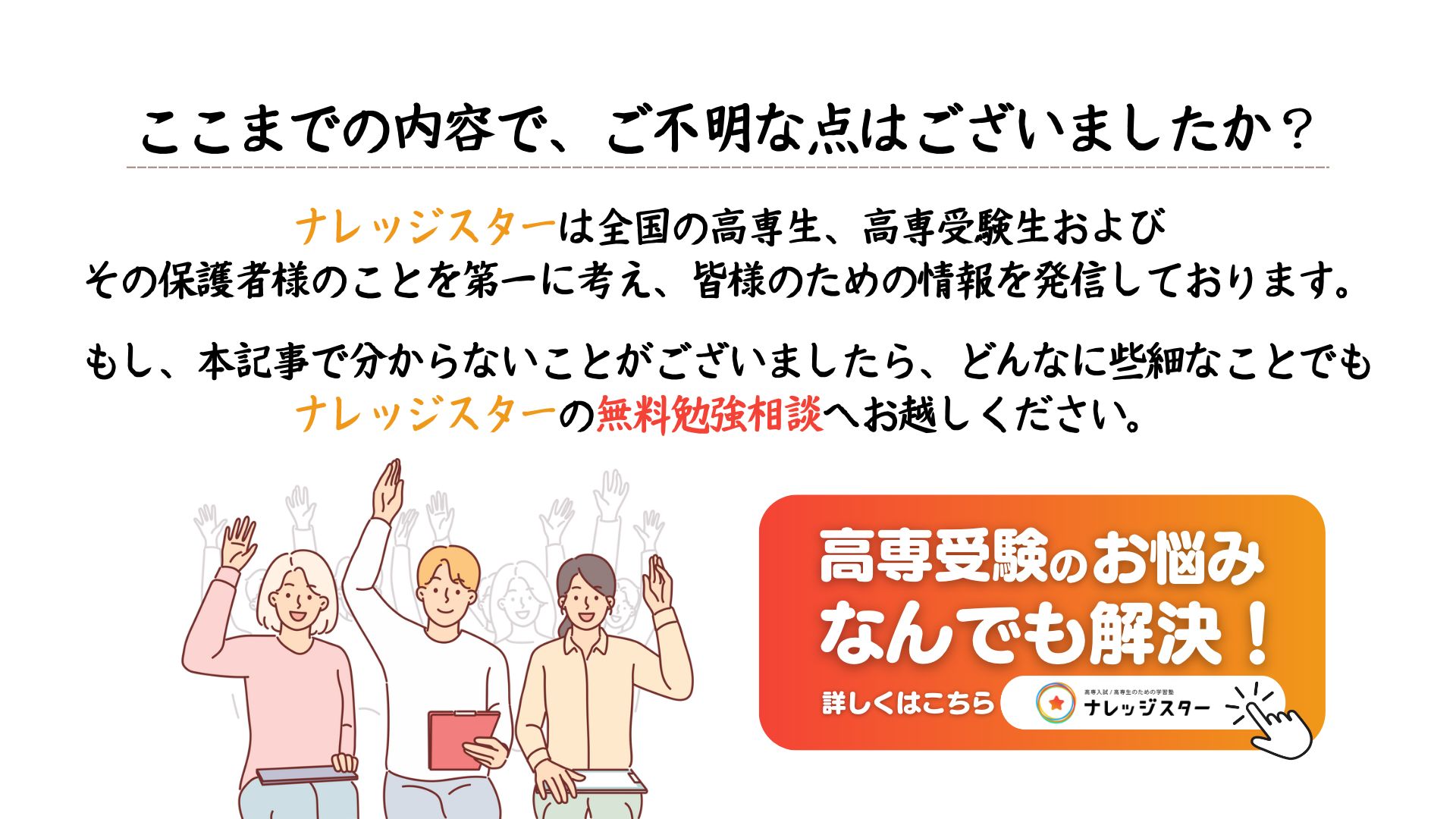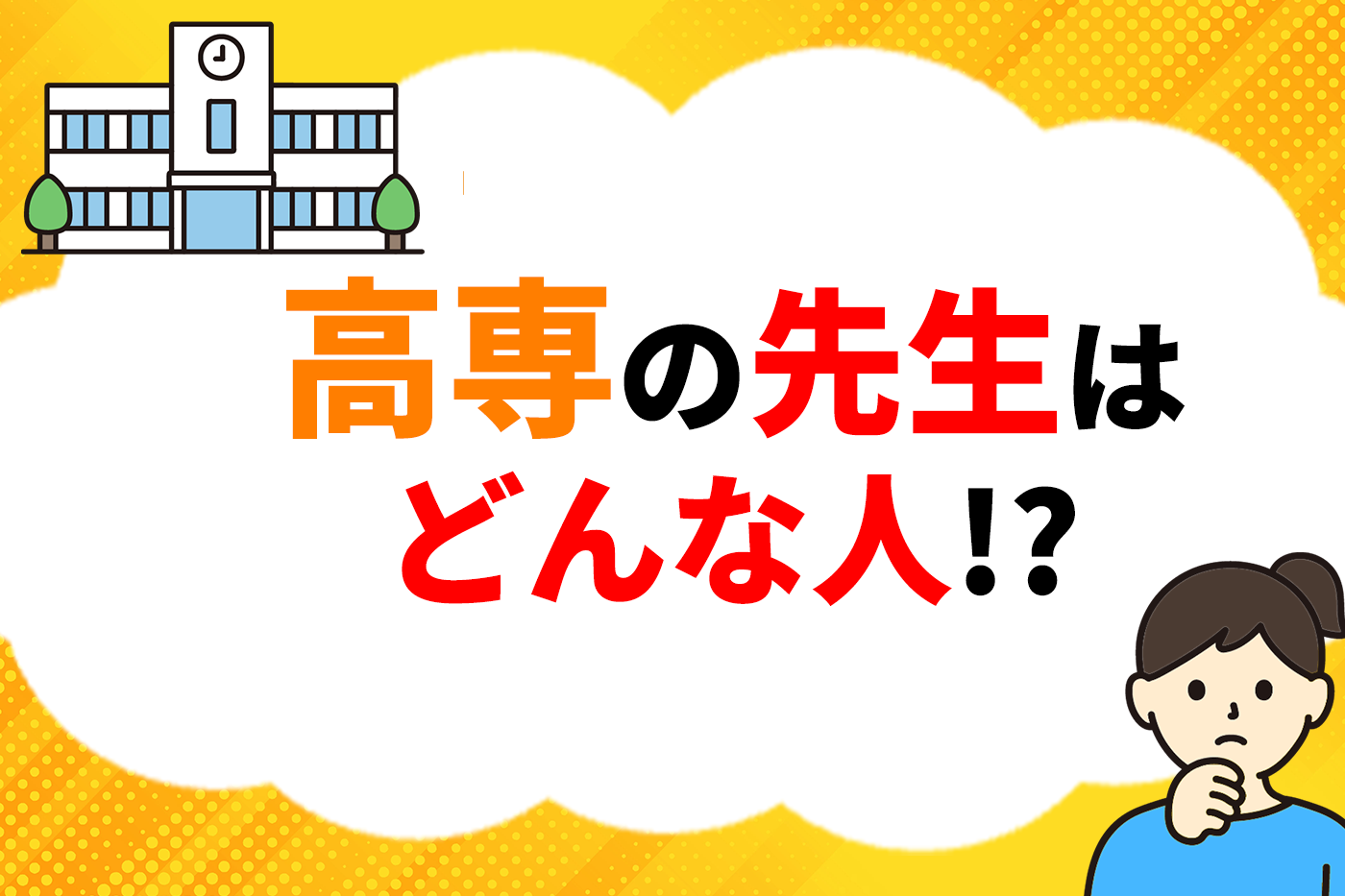A.結論
A. 高専の教員は「研究者としての専門性が豊かで、生徒理解に寄り添う温かさを持つ人」が多く、学びの深化と学生支援の両面で力を注いでくれる存在です。
教員の特徴と役割
① 教員免許ではなく、研究実績が採用基準
高専の教員は大学と同じ高等教育機関であるため、博士号や論文・学会発表などの研究実績が重視されます。これにより、最新の知見を授業で得られる一方で、教育ノウハウには個人差があります。
② 授業には「クセ」がある場合も
研究出身の先生の授業は、専門用語や数式が多く飛び交う難しめの内容になりやすいです。図解や身近な例えを使いながら丁寧に教える先生もいて、授業も個人差があり面白いです。
③学生の「主体性」を引き出す先生が多い
教員自身が研究者として「自ら考える力」を大切にしており、高専教育では「教える場」ではなく「学びに行く場」という姿勢が求められます。学生が主体的に動くことを後押しする先生が多い環境です。学生と教員の距離が近いのも高専ならではの特徴です!
ライターの一言
高専の先生は、研究者としての知識にものすごく詳しく、専門性が高い人が多い一方で、生徒との距離感も近く面倒見がよい存在です。授業は難しく感じることもあるかもしれませんが、主体的に学ぶ姿勢があれば、先生方は親切に対応して教えてくれます。
大学よりも教員との距離感が近く、設計や実験などの学びにも寄り添ってくれるので、学びやすさを感じるはずです。高専に入る前は「先生ってどんな人だろう?怖くないかな?」と不安に思う人も多いと思います。しかし実際には、先生は研究者でありながらも学生に寄り添う存在です。
授業中の質問だけでなく、進路や部活、時には人生相談まで乗ってくれる先生もいます。特に専門の先生は、その分野の第一線で活躍してきた方ばかりなので、話を聞くだけでも刺激になりますよ。高専で先生との距離感をうまく使えると、学びの幅が大きく広がります!
先生の教員室でお昼ご飯を一緒に食べたり、体育祭で同じ競技に出場したりしたのはとても良い思い出です。
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。
高専について質問がある人はこちらから!!