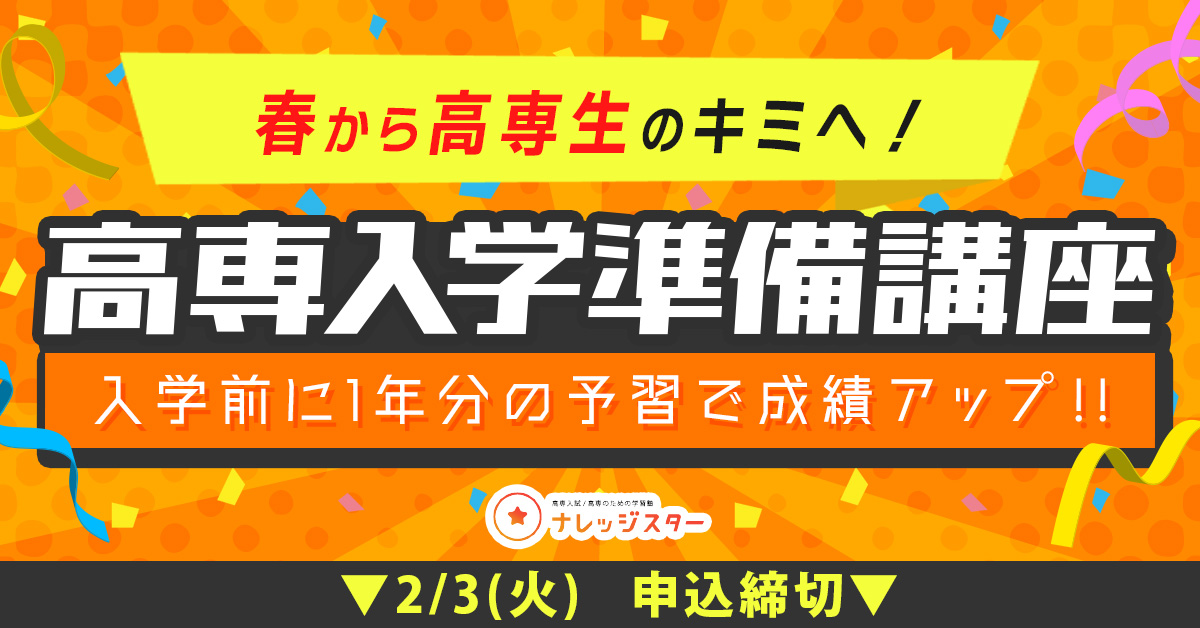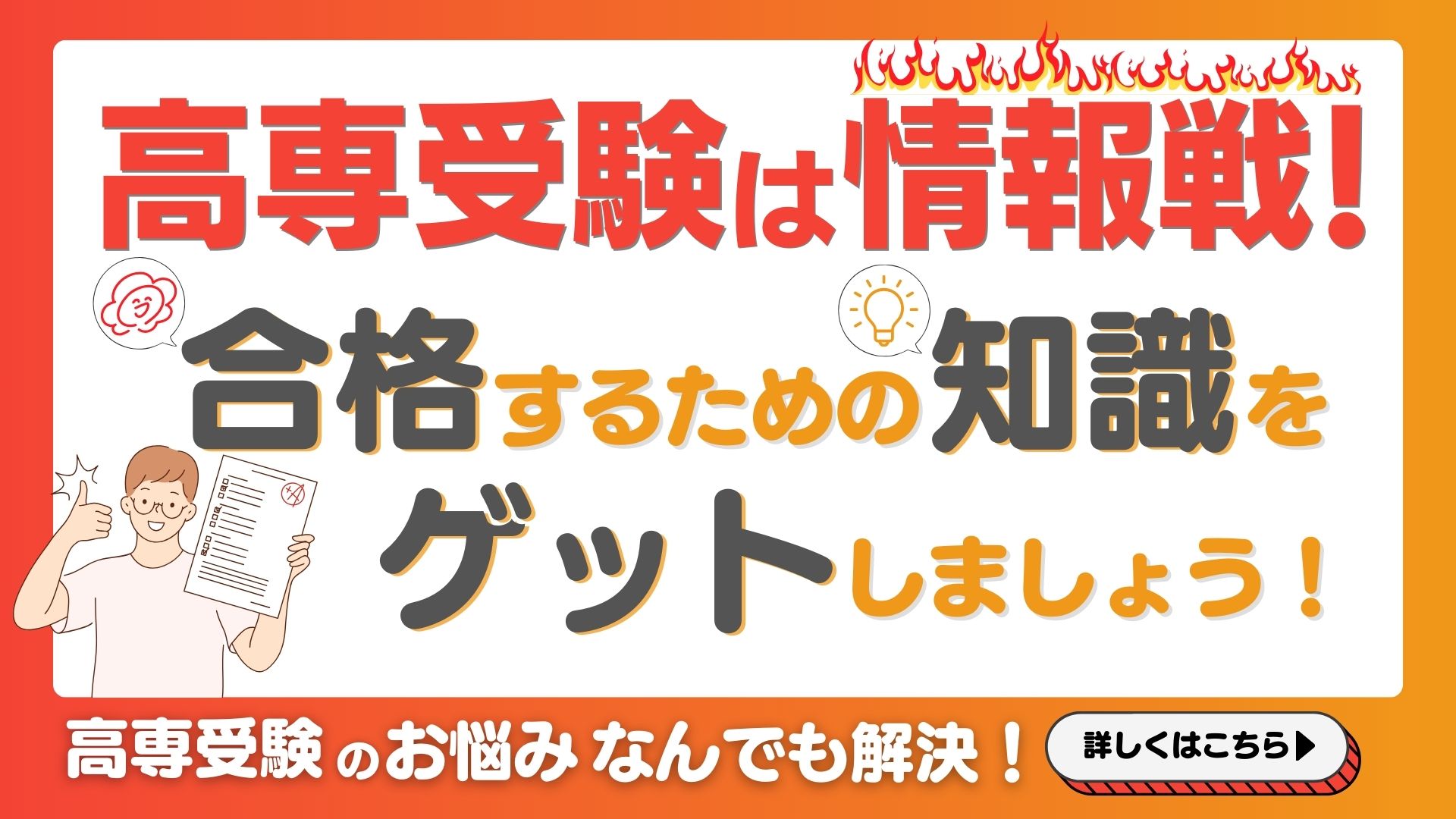
王道の汎用AI:ChatGPT/Claude/Gemini
文書作成、コード補助、データ分析の初手はこの3つで十分です。同じ課題でも得意なことが違います。計算の正確さ、長文の読解、図表の説明など、微妙な差が結果に出ます。まずは同じ指示を3つに投げ、最も整った出力を土台にします。出た案は根拠と手順を確認し、必要なら別AIに「検証役」を依頼します。無料枠でも授業・レポート・簡単な実験計画の素案づくりに使えます。使い分けの感覚は、数日で身につきます。
同じ課題を3サービスで試すメリット
1つのAIに依存すると、誤りに気づきにくくなります。並行テストは「比較→良い所取り→統合」までが速いのが利点です。たとえば、Claudeで長文の骨子を作り、ChatGPTで数式と擬似コードを整え、Geminiで画像・音声周りの補助を頼む流れです。出力の矛盾は箇条書きで洗い出し、どのAIの根拠が強いかを確認します。こうした「相互参照」を習慣化すると、精度とスピードが同時に上がります。
Perplexity:調査と要約に強い
Perplexityは検索と要約が一体化し、引用元を併記してくれるのが強みです。研究背景の把握、技術用語の初期確認、統計の出典探しに向きます。レポートでは、まずPerplexityで主要ソースを洗い出し、要点の重複や偏りをチェックします。次に汎用AIで文章化し、最後にもう一度出典を見直します。引用の整合性が担保されるので、参考文献リストの作成も楽になります。短時間で「抜け漏れが少ない調査」を実現できます。
DeepL:論文などの翻訳に強い
論文や技術資料を読むならDeepLが頼りになります。専門用語の訳は辞書を併用しながら、段落ごとに読み進めます。原文と訳文を二窓で並べ、数式や単位、図表のキャプションは原文で確認します。和訳→要約→英文キーワードの逆引きの順に進めると理解が安定します。自分で書く場合は、先に日本語で骨子を作り、DeepLで英文化→汎用AIで英語表現の自然さを整える手順が効きます。訳しっぱなしにせず、数式・定義の整合を必ずチェックしましょう。
NotebookLM:資料を集約して「専用AI」を作る
NotebookLMは、複数のPDF、URL、テキストを読み込ませて、その集合に特化したチャット相手を作れます。研究テーマの先行研究まとめ、大学編入の過去問整理、複数動画の内容比較に向きます。手順は、①素材を限定して投入、②「この範囲でのみ回答して」と明記、③抜けている資料を追加入力、です。限定範囲でのQ&Aは、汎用AIよりも一貫性が出やすいのが利点です。課題の背景整理や面談準備にも活躍します。
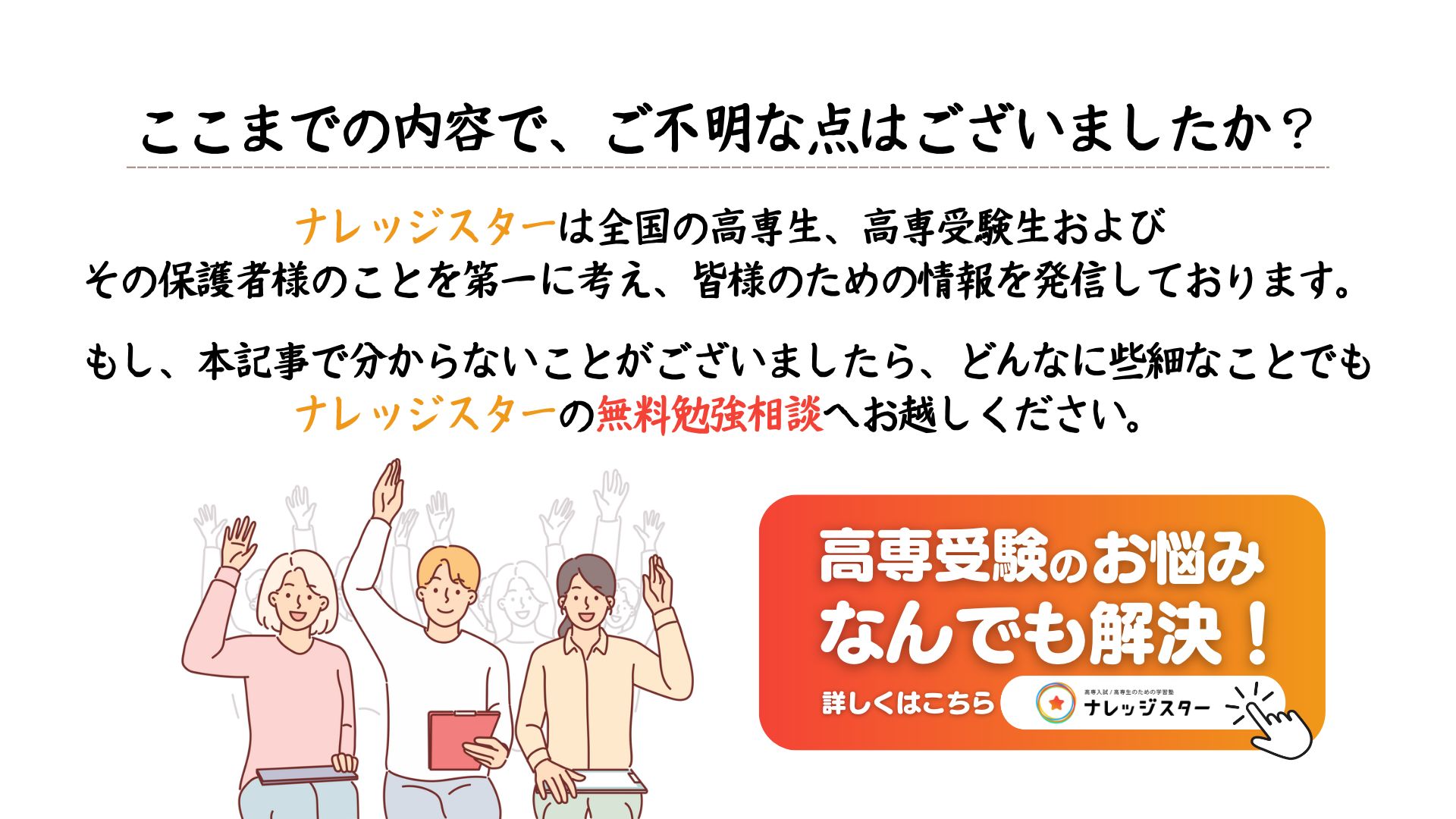
Gamma:スライド資料量産で課題発表を時短
Gammaは文章や見出しから体裁の整ったスライドを自動生成します。課題の締切が近いときの「叩き台」づくりが速いです。流れは、要旨→章立て→各スライドの要点→補足図の順で投入し、出力後に自分の言葉で言い換えます。研究発表の本番では体裁調整が必要ですが、授業のミニ発表や事前共有資料には十分です。無料枠は制限があるので、作成→ダウンロード→不要データ削除の運用で回すと長く使えます。
Genspark/Manus:表や図まで任せるエージェント
エージェント系は、文章生成だけでなく、表の比較や簡単なグラフ化まで一気通貫でサポートしてくれます。レポートの「実験条件一覧」「関連研究の比較表」づくりに向きます。計算の信頼性にはばらつきがあるため、数値は必ず自分で再計算しましょう。ワークフローは、①要件と出力形式を明記、②途中結果にフィードバック、③最終は人間が検算、です。コード補助や整形にも役立ちますが、機密情報は投入しないのが基本です。
AIを使う上で安全と倫理に注意
AIにアップロードしてよいのは、公開可能な資料だけです。個人情報、研究の未公開データ、学籍・成績などは避けましょう。生成AIの文章は自然でも、出典や数値が誤ることがあります。重要な数式・統計は電卓やスプレッドシートで再確認しましょう。引用はURLや文献情報を残し、レポートでは参考文献欄を作成します。ツールは便利ですが、最終責任は提出者にあります。便利さより正確さを優先してください。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ:効率化の先に「理解の深さ」を
AIは作業を短縮しますが、学びの中心は理解の深さです。下書きや訳に頼り切らず、根拠・計算・定義を確認して自分の言葉へ落とし込みましょう。無料枠の範囲でも、複数ツールを組み合わせれば十分に戦えます。使い込むほど精度は上がります。
Q&A(よくある質問)
Q1. 無料だけでどこまでできますか?
A1. 調査・下書き・翻訳・簡単な表作成までは十分可能です。最終の検算と出典確認だけは必ず自分で行ってください。
Q2. どのAIが一番いい?
A2. 用途で変わります。まずは同じ指示を3サービスに投げ、良い所取りを推奨します。
Q3. 論文読みがつらいです。
A3. DeepLで段落訳→要約→キーワード逆引き→図表は原文確認、の順で進めると理解が安定します。
Q4. 情報の安全が不安です。
A4. 未公開データや個人情報は投入しない方針にしてください。公開ソースのみ使用が原則です。
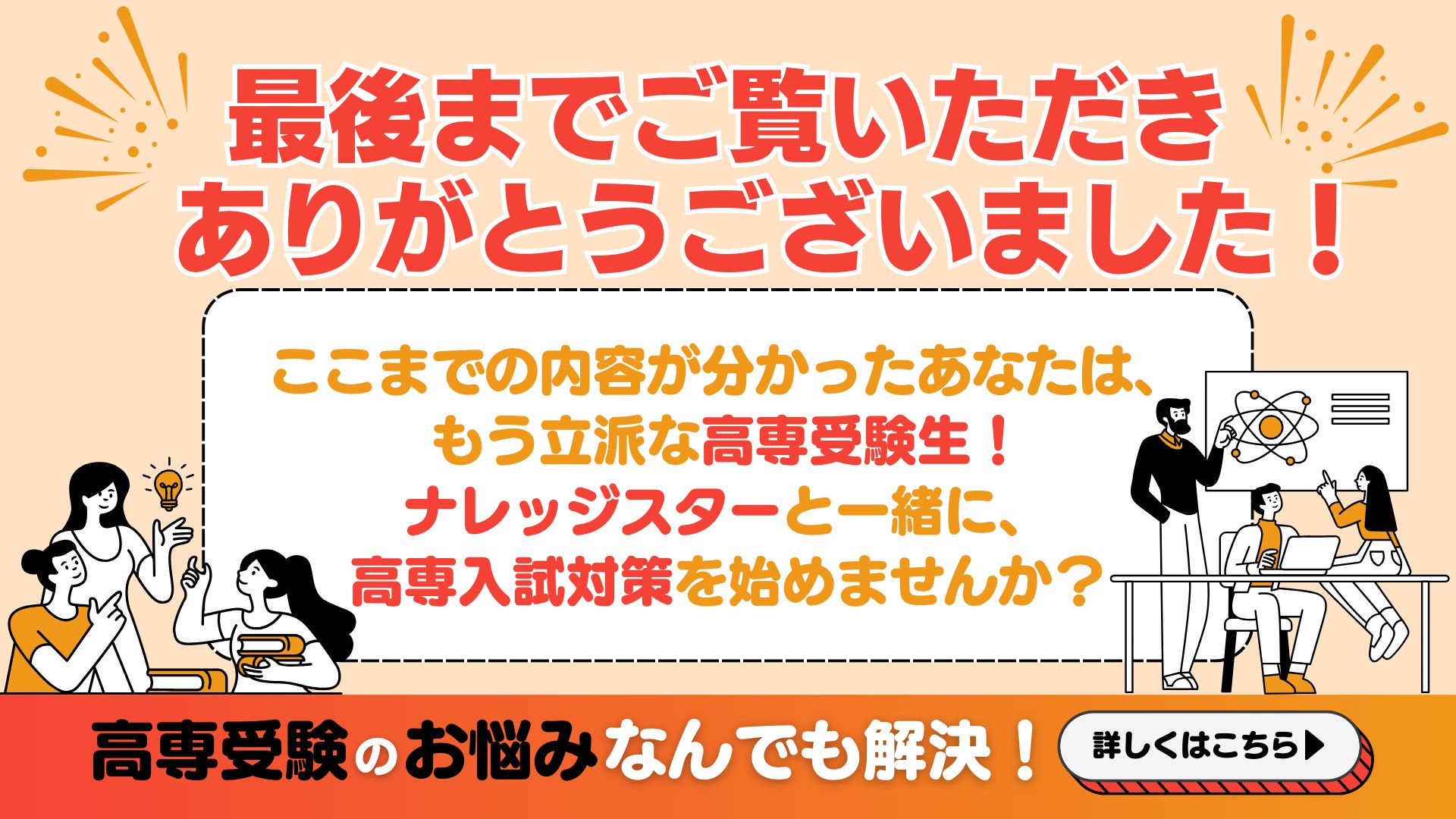
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。