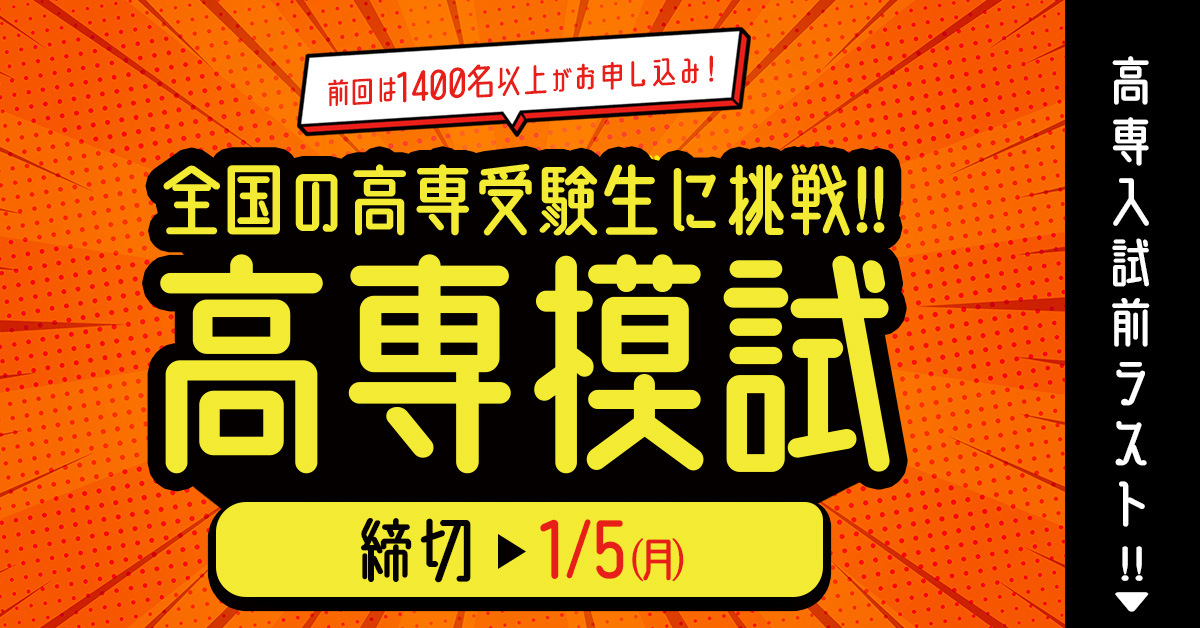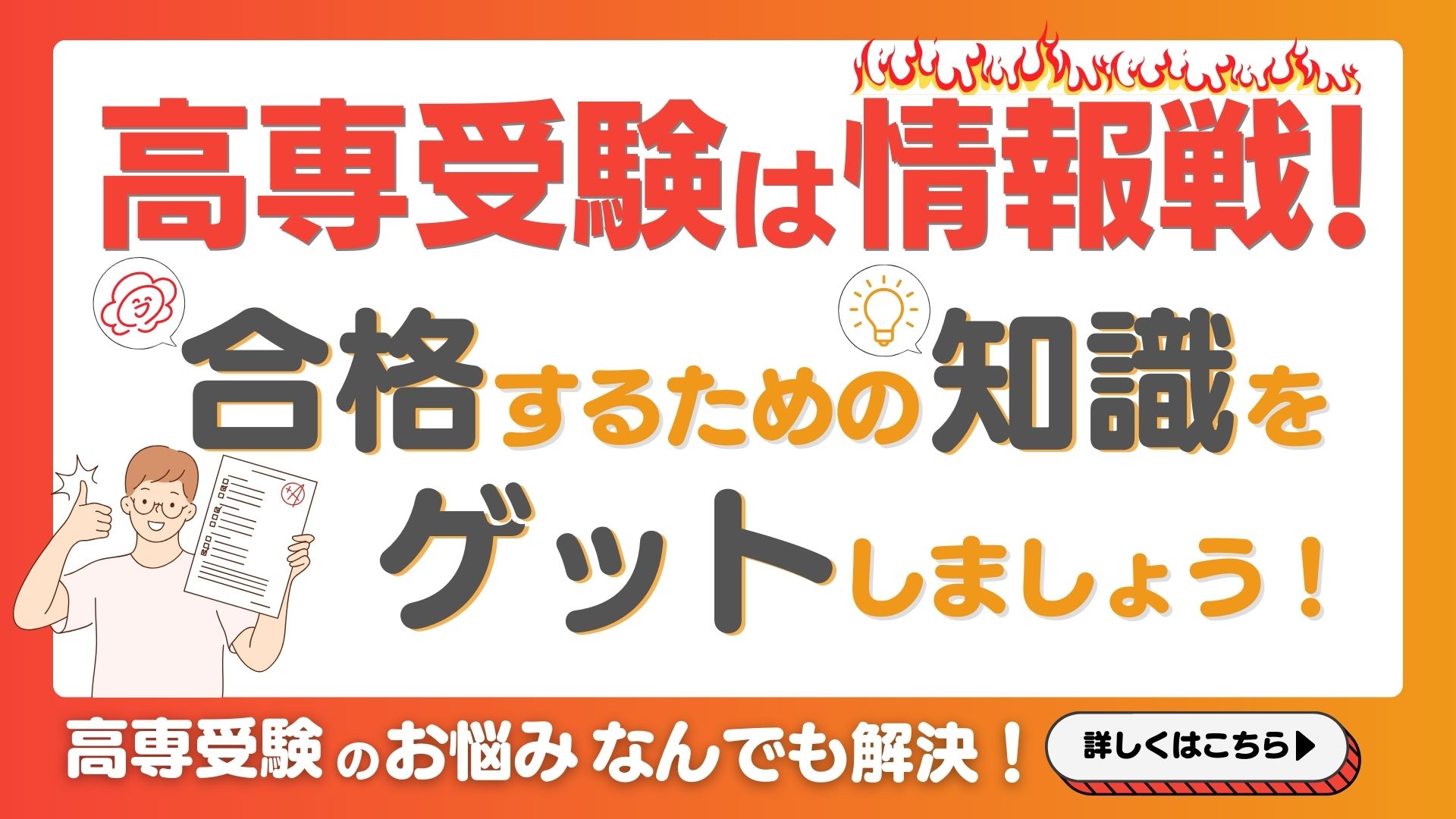
高専とは?
中学卒業から5年間を通して、エンジニア育成のために専門的な技術と知識を、身につけるための高等教育機関です。こちらの記事で、高専の特徴について詳しく解説しているので、興味のある方は是非、ご覧ください。
高専にも定期試験がある!?その実態とは
高専にも、もちろん定期試験があります。年間の回数は年4回で、内訳は「前期中間」「前期期末」「後期中間」「後期期末」です。このスケジュールはほとんどの高専で共通しており、学年の進行に合わせておよそ2〜3か月ごとに実施されます。
一方、普通高校の三学期制の学校では年5回実施されます。高専と同じ4回に加え、「学年末試験」があるためです。また、二学期制の学校では高専と同じ年4回(前期中間・期末、後期中間・期末)実施されますが、どちらの学期制でも進学校になると実力テストや模試などが組み合わさり、試験回数はさらに増えることも珍しくありません。
このように、高専の定期試験は回数こそ少なめですが、専門科目や実験科目の試験も含まれるため、範囲や内容の濃さは普通高校とは少し違った負担があります。
テスト範囲は広い?教科数と試験スケジュール
高専の定期試験は、普通高校と比べると範囲がやや広く感じられます。普通高校では、年間5回の試験(前期中間・前期期末・後期中間・後期期末・学年末)が一般的ですが、高専は年間4回しかありません。その分、1回あたりの試験範囲が広くなる傾向があります。
さらに、高専では低学年から徐々に専門科目が加わっていきます。入学したばかりの1年生でも、数学や英語などの一般科目に加え、専門分野の基礎科目が含まれるため、最初はハードルが高く感じられる人も少なくありません。
また、普通高校に通う友達に質問しても、高専特有の内容については答えてもらえないことが多いという特徴もあります。特に理数系の進み方はスピードが速く、高校3年間で習う数学を高専では2年間で終え、3年生からは大学数学の範囲に進むのが一般的です。そのため、数学や物理が苦手な人にとっては、勉強のハードルが高めと言えるでしょう。
教科数は学年によってどう変わる?
高専では、学年が上がるにつれて履修する教科のバランスが大きく変わります。低学年のうちは数学・国語・英語・社会などの一般科目も多く、これらも定期テストの対象になります。しかし、学年が上がるにつれて一般科目は減り、その分、専門科目が増えていきます。特に4年生はカリキュラムが非常に詰まっている学校が多く、専門科目だけで1日3科目の試験が組まれることも珍しくありません。
また、1日に受ける試験科目数にも特徴があります。学年や時間割の構成によっては、1日に1科目だけの日もあれば、最大で3科目の日もあります。低学年は比較的教科数が多く、高学年になると専門科目が中心になり、試験の科目数が少なくなる傾向があり、1日あたりの科目数が調整される場合もあります。
以下に高専の学年による違いをまとめているので、興味がある方はこちらも併せてご覧ください。
試験は何日間?スケジュールの流れ
今回は、私が通う大阪公立大高専の3年生の期末試験の日程を基にスケジュールをご紹介します。
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 |
| 基礎物理60分 | 専門科目90分 | 国語50分 | 線形代数・微分方程式80分 | ||
| 専門科目50分 | 英語50分 | 情報50分 | 解析80分 |
大体、試験日程は5,6日間で、土日を挟むかはその時その時によって変わります。大阪公立大高専では、3年生はテスト教科数が少ない学年なので多くて1日2教科でした。
試験勉強は試験2週間前、遅くても1週間前から始めると良いと思います。高専では、試験1週間前から部活動が原則活動禁止になるため、そのタイミングから始めても良いかもしれません。
難易度は?普通高校と比べた“レベル感”
実際に高専に通っている私の実感としては、授業のレベルは「かなり高度」だと感じます。特に数学や専門科目は、普通高校と比べても進むスピードが段違いです。内容自体も中学からの延長というより、高度な理論や応用に一気に踏み込むため、最初はついていくのに必死になることもあります。授業中の理解度が試験の結果に直結しやすいので、日々の予習復習や課題への取り組みは欠かせません。
一方で、国語・英語・社会といった一般教養科目は比較的ゆったりと進む印象です。これらの科目は試験1週間前から本格的に勉強を始めても対応できる場合が多く、理数系や専門科目に比べて負担は少なめです。
ただし、最初のうちはそのスピード感や課題量に圧倒されがちですが、何度か定期試験を経験するうちに「これくらいが普通」という感覚に自然と慣れていきます。試験前だけでなく、普段から少しずつ理解を積み重ねておけば、過度な心配は必要ありません。高専の勉強は確かにハードですが、その分、専門的な知識やスキルが着実に身についていく実感も得られます。
以下のブログで、より詳しく高専の定期試験と赤点の仕組みについて解説しているので興味がある方はぜひ併せてご覧ください。
高専生が実践!おすすめテスト対策法
高専の定期試験は範囲が広く、授業スピードも速いので、試験直前になって一気に詰め込むやり方ではなかなか通用しません。普段から計画的に勉強を進め、効率的に試験対策をすることが大切です。ここでは、私が実際に試して効果を感じた勉強法を「授業中のノートの取り方」「過去問の使い方」「実験レポートとの両立法」の3つに分けてご紹介します。どれも今日から取り入れられる方法なので、ぜひ参考にしてみてください。
授業中のノートの取り方
私が授業中に意識しているノートの取り方は、効率と記憶のしやすさを重視しています。まず、iPadなどのデジタルツールではなく紙にシャーペンで書くことを基本にしています。これは、紙に手を動かして書いた方が、試験のときに記憶がよみがえりやすいと感じた経験があるからです。色ペンは多くても3色までに限定し、ノートを美しく仕上げることに時間をかけすぎないようにしています。先生が黒板に書かず、口頭で補足した内容もノートの端にメモしておくことは特に重要で、高得点を狙う上で欠かせません。数学などの科目では、授業中に出された練習問題を必ず解くようにしています。こうした問題は定期試験や小テストにそのまま出題されることも多く、得点につながる大きなポイントになります。
過去問の使い方
「高専は過去問を制した者が試験を制する」と言われるほど、高専の定期試験において過去問の活用は非常に重要です。高専の試験は、普通高校に比べて出題の再利用率が高く、過去に出題された問題の一部を細かく変えただけ、あるいは数値を入れ替えただけの問題が頻繁に出てきます。中には、ほぼ同じ形式で繰り返し出題されるパターンも少なくありません。
過去問を使う最大のメリットは、「試験範囲の本命」が見えてくることです。過去問を分析すると、「この先生はこの単元をよく出す」「この公式は必ず出る」といった傾向がわかり、いわゆる“ヤマを張る”ことが可能になります。これによって、試験勉強の方向性が明確になり、無駄な勉強時間を減らすことができます。
さらに、過去問を事前に解くことで、試験本番の問題形式や難易度に慣れておくこともできます。本番で初めて見る形式の問題に戸惑うリスクを減らせるのは、大きな安心材料です。加えて、過去問を活用すれば、試験範囲をゼロから順に勉強するのではなく、出題頻度の高い問題から優先的に取り組むことができ、限られた時間の中で効率的に得点を狙うことができます。
実験レポートとの両立法
高専では、定期試験の前後に実験レポートの提出が重なることも少なくありません。流石にテスト期間中にレポートの提出が設定されることは少ないですが、テスト前やテスト後すぐに提出期限が迫る場合もあります。そのため、レポートは早めに取り組んでおくことがとても重要です。
もし、テスト勉強とレポートの両方を同時に抱え込んでしまうと、どちらも中途半端になりがちです。特に、テスト勉強期間のぎりぎりまでレポートを残してしまった場合、どちらを先に片付けるべきか迷うことがあります。この場合、優先すべきは間違いなくレポートです。レポートが未完成の状態でテスト勉強をしても、心のどこかでレポートのことが気になり、集中力が下がってしまいます。
実際に効率よく両立するコツとしては、提出期限を見越して計画的にレポートを進めること、そしてテスト直前にはすべてのレポートを完成させておくことです。これにより、テスト勉強に集中でき、限られた時間で最大限の効果を得られます。
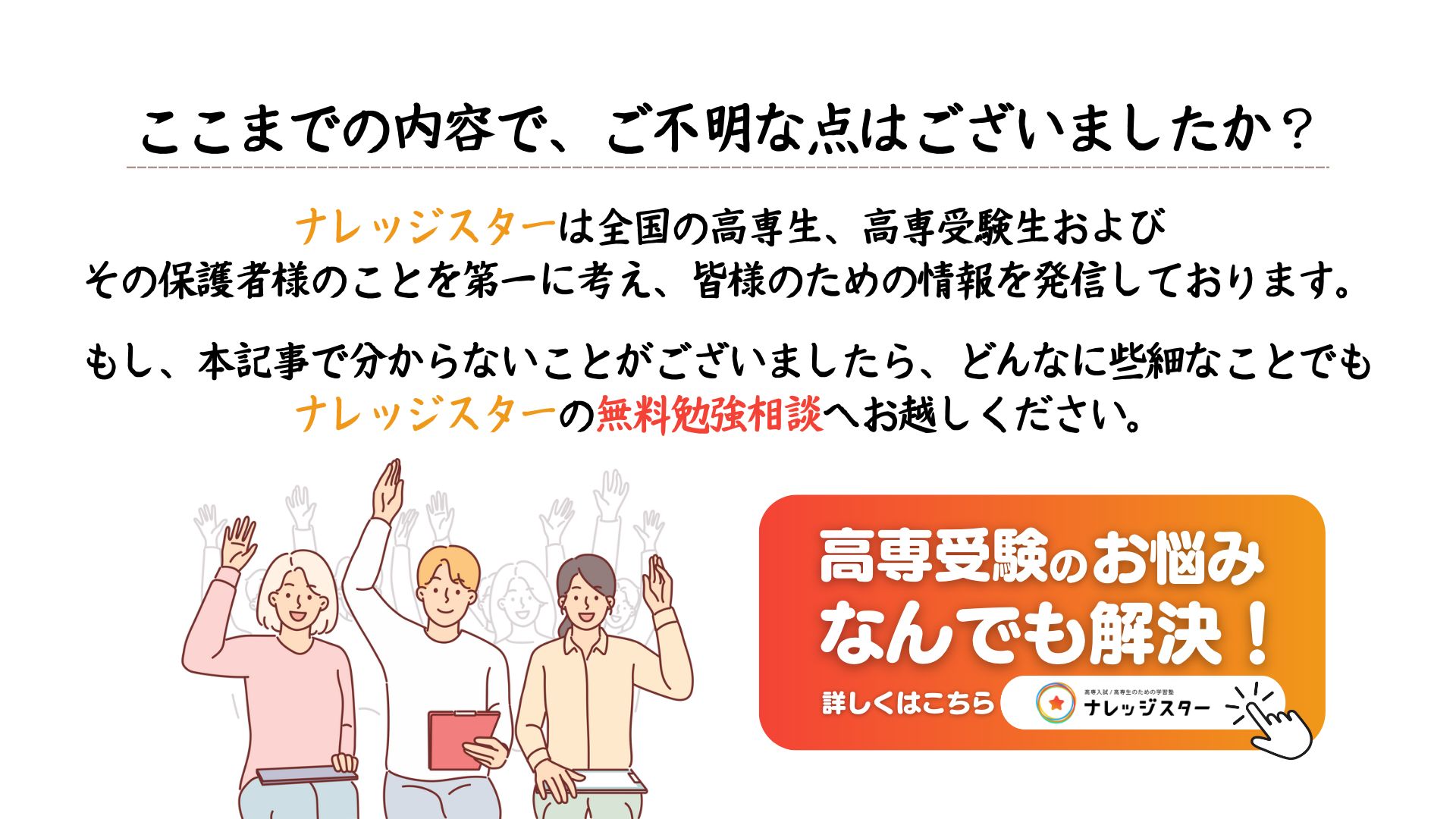
テスト勉強はいつから始める?高専生のリアルな準備期間
私の場合、定期試験の2週間前から10日前までには、まず課題を終わらせるようにしています。その後、テスト日程が遠い科目から順に、ざっくりと試験範囲を勉強していきます。暗記科目は紙に書きながら口に出して反復練習を行い、理解が必要な科目や計算系の科目は、授業中に扱った問題を優先して解き直します。その後、問題集や章末問題など、より発展的な問題に取り組むようにしています。試験の1週間前からは、放課後の時間をすべてテスト勉強にあて、集中して準備を進めます。
テスト前日の勉強法としては、暗記科目は夜遅く(27時くらい)まで反復練習し、その後、朝はギリギリまで寝て効率的に暗記内容を確認します。一方、計算や論理が必要な科目は、遅くても23時までには就寝し、翌朝5時頃に起きて問題を解くのが私のやり方です。どちらの場合も、最低6時間の睡眠は確保するようにしています。
よくある失敗例として、試験期間中に徹夜して勉強したり、睡眠時間を削ったりする方法がありますが、5〜6日続く試験期間では体力が持たず、途中で体調を崩してしまうことがあります。そのため、勉強量と睡眠時間のバランスを意識し、効率よく準備を進めることが重要です。
一般的に、高専生のテスト準備は次のような流れで進められることが多いです。試験の2週間前には教科書やノートの確認を始め、重要な公式や実験のポイントを整理します。1週間前になると、過去問や練習問題を解きながら理解度をチェックし、弱点科目に重点を置いて復習を進めます。さらに3〜4日前からは、間違えた問題や理解が不十分な部分を中心に集中して復習し、テスト前日には全体の最終確認としてノートのまとめや暗記科目の確認に時間を割く、という流れが一般的です。
このように、学年や科目によって開始時期や重点の置き方は変わりますが、計画的に進めることで無理なくテストに臨むことができます。
まとめ
高専の定期試験は、普通高校に比べて科目数や専門科目の割合が多く、範囲も広めです。特に数学や専門科目は進度が速く、日々の学習や試験勉強の積み重ねが重要になります。しかし、国語や英語、社会といった一般科目は比較的ゆったり進むため、科目ごとに勉強の計画を立てることで無理なく準備できます。
テスト対策としては、授業中のノートを工夫して取り、過去問を活用して出題傾向を把握し、実験レポートとの両立も意識することがポイントです。勉強開始のタイミングは早めが安心で、2週間前から課題や基礎復習を進め、1週間前から放課後の時間をしっかり活用するのがおすすめです。睡眠時間を確保しつつ効率的に勉強することも、試験期間を乗り切るためには欠かせません。
高専の定期試験は決して簡単ではありませんが、準備の仕方やコツを押さえることで、効率よく得点を伸ばすことができます。日頃の学習習慣と計画的な対策で、一緒に試験をうまく乗り越えましょう!!
高専に興味を持った・高専受験を考えている方に!
ナレッジスターの高専入塾体験がおススメ!!
高専入試対策や長期講習、講座など様々なコースがあります。
また、高専によって異なる特別選抜の対策コースも充実しております!
高専入試に慣れたい・雰囲気を知りたい方向けの
高専模試も年5回、開催しております!
オンラインなのでどこでも受けることが可能です。
自分の立ち位置がわかり、合格まで自分が何をすればよいか分析することができます。
さらに、塾生は高専模試全5回すべて無料に!
高専に関する勉強の不安などは、ナレッジスターの無料勉強相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
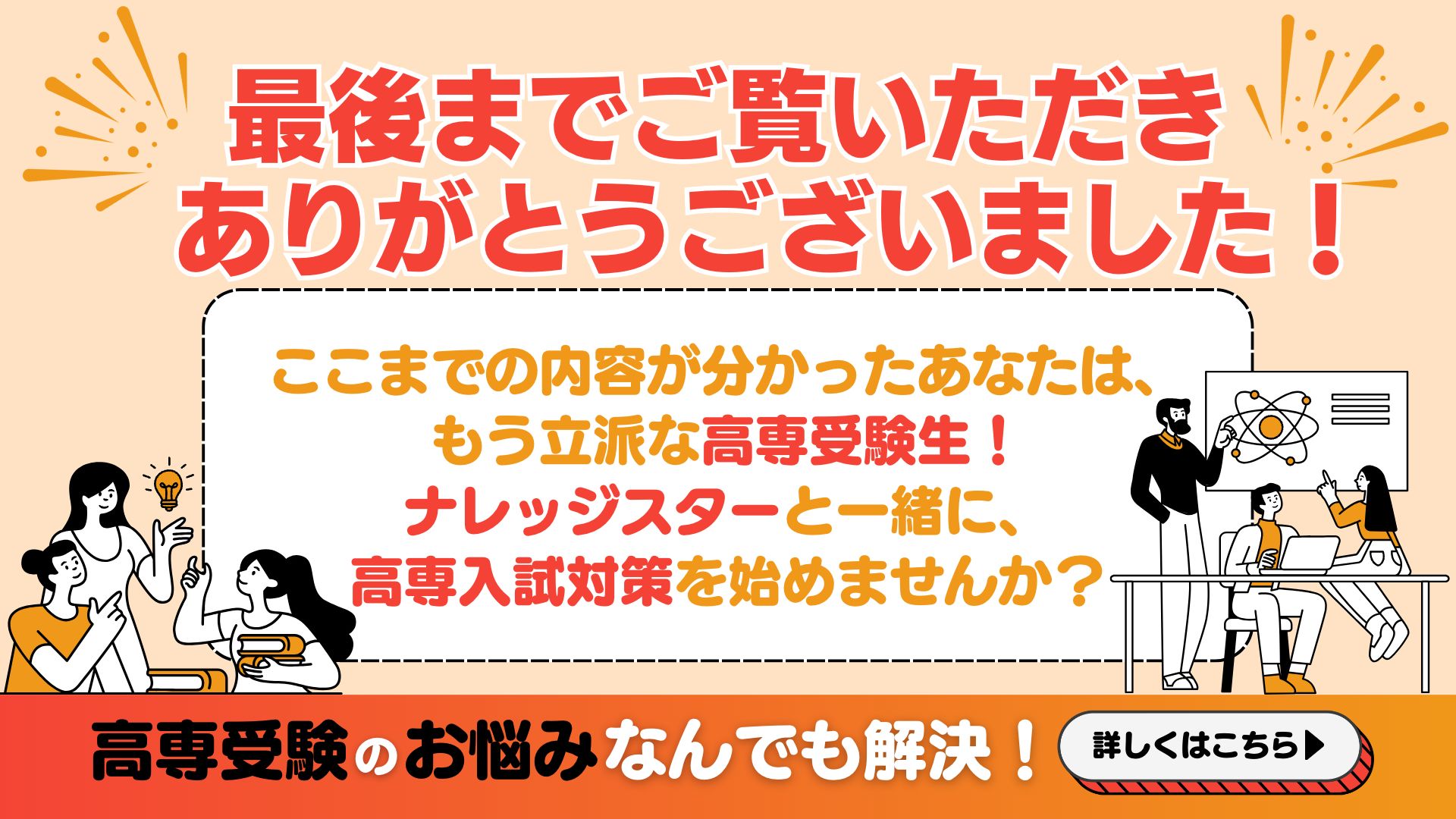
——————‐—————–‐————–‐————–‐
所属高専:大阪公立大学工業高等専門学校
学科:総合工学システム学科 エレクトロニクスコース
氏名:大原佳蓮
ニックネーム:かれん
自己紹介:高専3年生の出戻りひよっこライター。特技は人前で緊張せず話せること。高専のことについて皆さんが知りたい有益な情報などを調査・勉強中です。