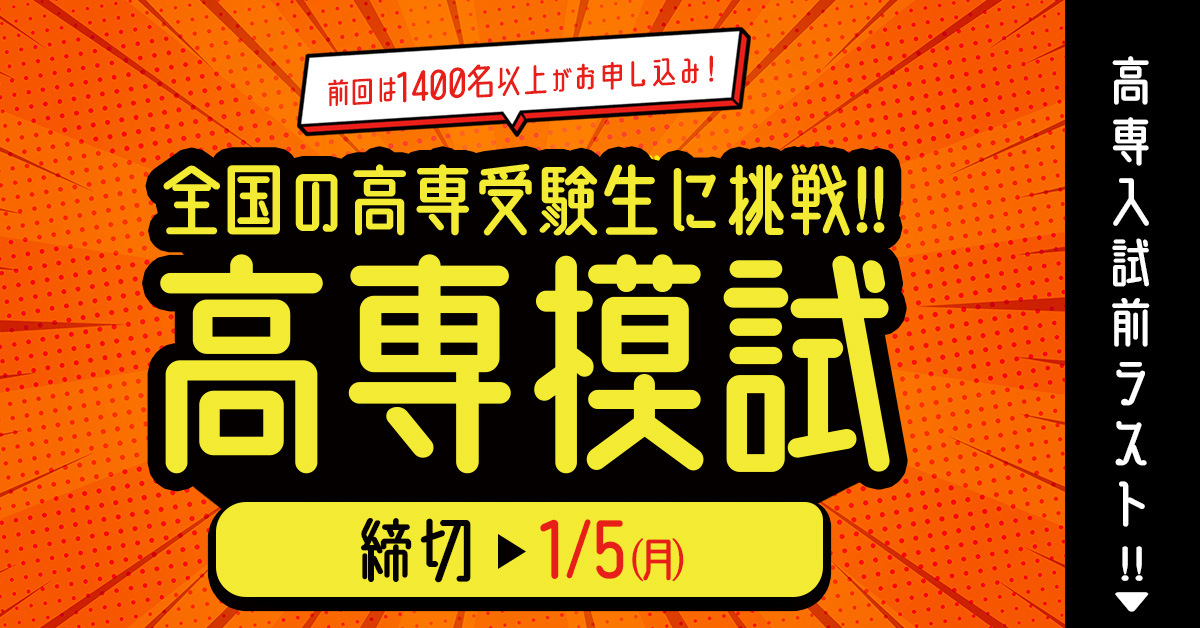高専とは
高専(高等専門学校)は、中学校卒業後に入学する5年制の高等教育機関です。
1年生から専門的な工学分野を学ぶことができ、実験や実習も多く取り入れられているのが特徴です。大学より早い段階で専門知識を身につけられるため、将来の進路の選択肢も広がります。
高専のしくみや魅力について詳しく知りたい方は、こちらのブログをご覧ください。
高専における「低学年」と「高学年」って何年生のこと?
高専では、一般的に1〜3年生を「低学年」、4・5年生を「高学年」と呼びます。
低学年は主に基礎的な学びや生活面での土台づくりが中心で、高学年になると専門性が一気に高まり、進路も意識するようになります。低学年と高学年では、学びの内容や実験・実習の深さも大きく異なります。
ここからは、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
低学年
学習内容の特徴
- 一般科目(国語・英語・数学・理科・社会など)が中心
- 専門科目はまだ基礎的な内容がほとんど
低学年では、高校と同じような一般教科を満遍なく学びながら、専門科目への導入として、簡単な理論や基礎知識を身につけていきます。難易度もそこまで高くなく、初めてでも理解しやすい内容が多いのが特徴です。
実験・実習の特徴
- 実験や実習は扱う道具もシンプル
- レポートの量や難易度もまだそれほど重くない
この時期は「専門の入口」に立っているようなもので、実験や実習も体験を通して学ぶスタイルが中心です。レポートも、手順の記録や簡単な考察程度で、まずは書き方に慣れることが目的となっています。
高学年
学習内容の特徴
- 専門科目の比重が一気に増える
- 分野ごとの応用内容や実践的な授業が中心
高学年になると、機械・電気・情報など、自分の専攻に応じた専門科目が大半を占めるようになります。内容も理論だけでなく、現場で役立つような応用的な知識や技術を扱うことが増えてきます。
実験・実習の特徴
- 実験や実習の頻度・難易度が大幅に上がる
- 本格的なレポート作成やデータ処理も求められる
実験では、測定精度や考察力が問われるなど、より専門的な視点が必要になります。実習内容も複雑になり、レポートも「まとめる」だけでなく「分析・評価する力」が求められるようになります。
進路準備
- 就職活動や大学編入試験に向けた準備が始まる
- 放課後や長期休暇に研究・インターンなどを行う人も多い
高学年は「進路を意識する時期」でもあり、研究室配属や卒業課題、企業インターンなど実社会とのつながりも増えてきます。 そのため、学業と進路準備の両立が求められ、時間の使い方にも工夫が必要になってきます。
学ぶ内容にどんな違いがあるの?
一般科目
- 国語・数学・英語・理科・社会など、いわゆる5教科をしっかり学ぶ
- 保健体育なども低学年のうちは時間が確保されている
- 高学年では、科目によって授業数が減ったり、選択制になったりすることもある
高専では、低学年のうちは高校と同じように一般科目を中心に学びます。数学や英語は内容の違いで複数の授業に分かれることもあり、週ごとの時間割にも多く登場します。
一方で、高学年になると専門科目の比重が高まり、一般科目の授業数は少なくなっていく傾向があります。
専門科目
- 専門科目は各学科・コースによって異なる内容(例:回路、製図、プログラミングなど)
- 低学年では週に数コマ程度だが、学年が上がるごとに授業数が増える
- 高学年では、一般科目より専門科目の時間が多くなることが一般的
専門科目は、学年が上がるほど応用的かつ実践的な内容へと発展していきます。
高学年になると、より専門分野への理解が求められ、自分の進路にも直結するような学びが増えてきます。
実験・実習のレベルも大きく変わる!
高専では、学年が上がるにつれて実験や実習の内容も大きく変わっていきます。
低学年のうちは、器具の名前や使い方を覚えるところからスタートし、先生の指示に従って一つひとつ手順を確認しながら進めていくことがほとんどです。実験のペースもゆっくりで、初めてでも安心して取り組めます。
一方で、高学年になると、器具の使い方はすでに身についている前提で、自分たちで準備・測定・考察まで進めるような、自主性のあるスタイルに変わっていきます。もちろん、分からないことがあれば先生に質問できる環境は整っているので、「自分だけでやらなければいけない」という不安は不要です。
例えば電気電子系の学科では、マイコン(マイクロコンピューター)とブレッドボード(電子回路の基板)を組み合わせて、実際に信号を制御するような実験も行われるようになります。こうした高度な内容にも、段階的な授業を通して自然と取り組めるようになっていくのが、高専ならではの強みです。
実験の難易度は上がっていきますが、それに合わせて力も確実についていくので、「難しそう」と不安に感じすぎる必要はありません。
時間割や放課後の過ごし方にも変化が?
高専では、「くさび型教育」という特徴的なカリキュラムが導入されており、学年が上がるにつれて専門性がどんどん高まっていきます。この仕組みでは、低学年のうちは一般科目を中心に学び、段階的に専門科目の比重を増やしていくことで、確かな基礎の上に実践力を築いていきます。
(出典:高専とは?、国立高等専門学校機構)
時間割の変化:
高学年になると専門科目の授業数が大幅に増えます。また、学校によって差はありますが、多くの高専で4限まで授業が組まれることが一般的です。さらに、その中の1コマはほぼ必ず専門科目が組み込まれているため、専門性の高い内容に日々向き合うことになります。一方で、低学年では週2~3コマ程度が専門科目で、それ以外は一般教科が中心の比較的ゆとりのある時間割となっています。
放課後の過ごし方:
放課後の過ごし方にも違いがあります。高学年になると実験レポートや課題が増え、それを放課後に進める学生も多く見られます。一方、低学年のうちは放課後に余裕があるため、アルバイトや部活動にしっかり取り組むことがしやすい時期です。もちろん高学年でも部活動を続ける人はたくさんいますが、毎回の練習に出るのが難しくなる場合もあるようです。
このように、学年が上がることで勉強の負担は増えますが、その分だけ学びの深さや達成感も大きくなっていきます。時間の使い方や優先順位を見直しながら、自分のペースで成長していけるのが高専の魅力の一つです。

高学年では進路の話も本格的に!
高専では4年生・5年生になると、「卒業後どうするか?」という進路について、いよいよ本格的に考え始める時期になります。多くの学生は、就職するか、進学するかを選ぶことになりますが、中には起業を目指す人もいます。
就職について:
就職の場合、学校から推薦をもらうルートと、自分で応募先を探す自由応募のルートがあります。推薦枠は内定率が非常に高いのが特徴で、安定した進路を選びたい人に向いています。一方、自由応募ではより幅広い業種にチャレンジできる自由度があります。
進学について:
進学を考える人には、大学3年生から入学できる「編入学」という制度や、さらに2年間高専で学ぶ「専攻科」という選択肢があります。特に大学編入は、試験科目が少なく、難関大学でも比較的低い競争率で受験できることが魅力です。
こうした高専ならではの進路の特徴については、別の記事で詳しく紹介しておりますので、興味のある方は、併せてこちらをご覧ください。
https://know-star.com/blog/kosen-info/kosen-career-job-university-startup/
低学年のうちにやっておくと良いことは?
高専生活の前半である低学年のうちは、時間的にも気持ち的にも少し余裕がある時期です。だからこそ、この時期に意識しておくと良いことがあります。実際に私が過ごして感じたことをもとに、いくつか紹介します。
まずは、部活動を通じて上級生とのつながりを作ることです。高専は5年一貫なので、先輩との距離が近く、学年を越えて仲良くなれるチャンスがたくさんあります。勉強や進路の相談にも乗ってもらいやすくなるので、早いうちから関係を築いておくのがおすすめです。
また、数学は基礎からしっかり理解しておくことがとても大切です。高専の数学は学年が上がるごとに急に難しくなります。低学年のうちに土台を固めておけば、後々の専門科目の理解にもつながります。
さらに、いろいろな先生と顔見知りになっておくことも意外と大事です。普段の授業だけでなく、困ったときや相談したいときに声をかけやすくなるだけでなく、先生との信頼関係ができていればサポートも受けやすくなります。
そして何より、単位を落とさないこと。高専では教科によりますが、1つでも単位を落とすと留年のリスクが出てきます。最初のうちは油断しがちですが、基本的な学習習慣を身につけておくことがとても重要です。
先輩から見た「高専の高学年」ってこんな感じ!
私は現在、高専3年生です。そろそろ高学年に差し掛かり…というところで、学習の内容もどんどん難しくなってきたと感じています。特に最近は「確実に単位を取っておかないと、あとで焦ることになるな」とひしひしと実感しています。
レポートもかなりレベルアップしていて、低学年の頃と比べると、完成度も求められる内容も段違いです。でもその分、「自分も成長してきたな」と感じられるのはちょっとしたやりがいにもなっています。
部活動についても、3年生まではしっかり参加しておくべきだと思います。というのも、4・5年生になると課題や進路の準備で忙しく、部活に顔を出すのが難しくなる先輩も多いからです。「もっと先輩と関わっておけばよかった…」とならないように、時間のあるうちにたくさん関わっておくのがオススメです。
また、最近は授業で扱う専門科目の内容が、社会や仕事とどうつながっているかが少しずつ見えてきました。「なんでこの内容を学んでるんだろう?」という疑問が、「これって実際に現場で役立つ技術なんだ」とつながる瞬間が増えてきて、学び方も変わってきた気がします。
さらに、周囲では進路の話がちらほら出てきていて、「もう自分も考えないと…」と意識するようになりました。進学するのか、就職するのか、まだ決めきれていない人も多いですが、なんとなく将来を考える時間が増えてきています。
こうした忙しさの中で、時間の使い方もすごく大事になります。課題、部活、友だちとの時間など、すべてを上手にこなすためには、自分なりのリズムを作ることが大事だと感じています。高専の高学年は、これからの人生を決める大切な時期なので、目標を持って学ぶことが重要だと思います。
まとめ
高専では、学年が上がるにつれて授業内容や実験のレベル、課題の量がどんどんステップアップしていきます。低学年ではまだ一般科目中心ですが、高学年になると専門的な学びが本格化し、放課後の過ごし方や進路への意識も大きく変化します。
しかし、だからといって不安になる必要はありません。低学年のうちから「今やっておくといいこと」をコツコツ積み重ねていけば、高学年での高専生活をきっと楽しく、充実したものにできるはずです。
私自身も、レポートや授業に苦戦することもありますが、その分、自分の成長を感じられる場面も増えてきました。そして何より、高専の仲間や先生方とのつながりが、そんな日々を支えてくれています。
これから高専に入る人も、今まさに低学年の人も、「高学年になった自分」を少しだけイメージしてみてください。今がその準備期間だと思えば、毎日の過ごし方もきっと変わってくるはずです!
高専に興味を持った・高専受験を考えている方に!
ナレッジスターの高専入塾体験がおススメ!!
高専入試対策や長期講習、講座など様々なコースがあります。
また、高専によって異なる特別選抜の対策コースも充実しております!
高専入試に慣れたい・雰囲気を知りたい方向けの
高専模試も年5回、開催しております!
オンラインなのでどこでも受けることが可能です。
自分の立ち位置がわかり、合格まで自分が何をすればよいか分析することができます。
さらに、塾生は高専模試全5回すべて無料に!
高専に関する勉強の不安などは、ナレッジスターの無料勉強相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
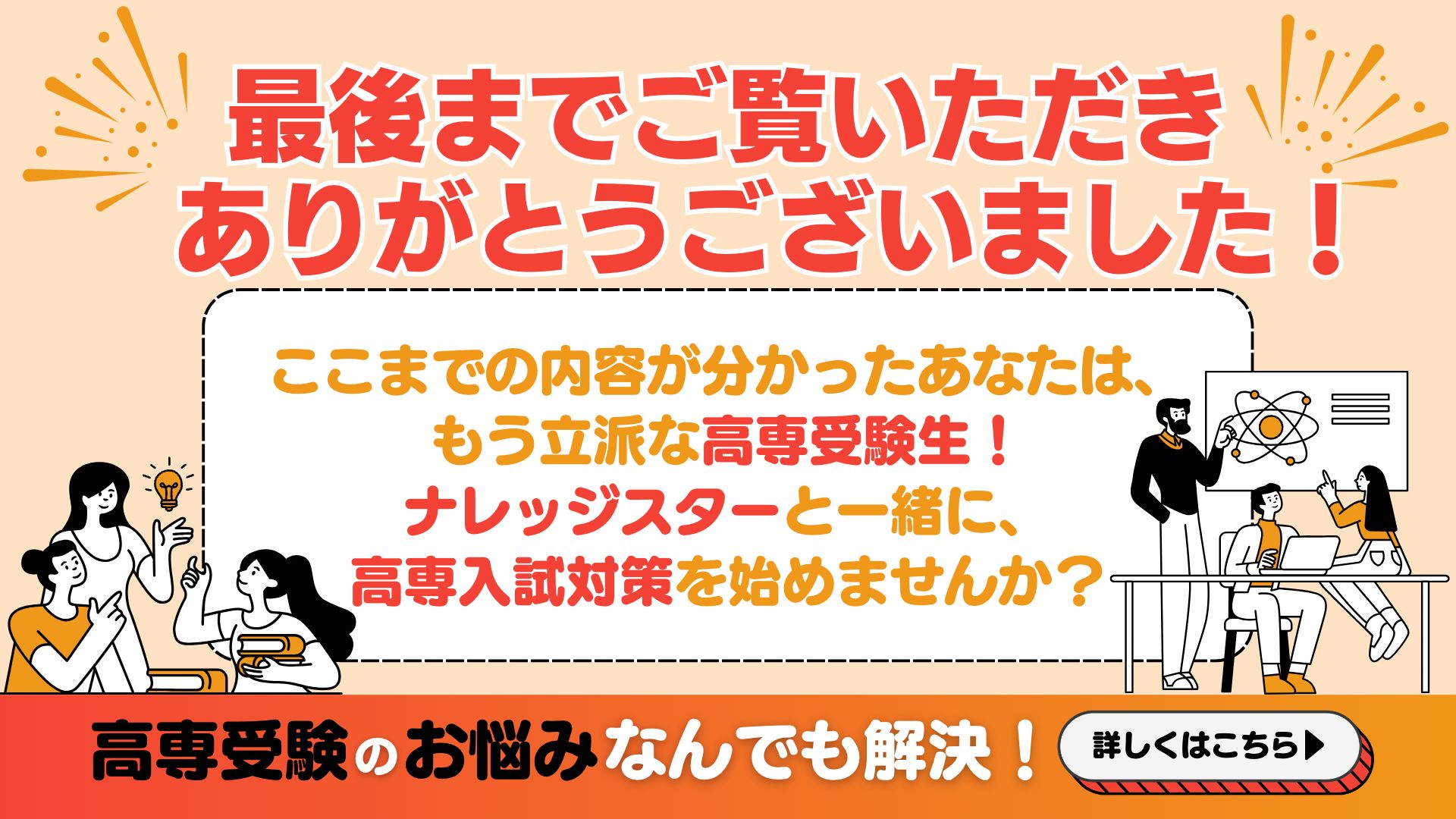
——————‐—————–‐————–‐————–‐
所属高専:大阪公立大学工業高等専門学校
学科:総合工学システム学科 エレクトロニクスコース
氏名:大原佳蓮
ニックネーム:かれん
自己紹介:高専3年生の出戻りひよっこライター。特技は人前で緊張せず話せること。高専のことについて皆さんが知りたい有益な情報などを調査・勉強中です。