高等専門学校(高専)での5年間の学びの集大成、それが「卒業研究」です。本科の最終学年になると、学生はそれぞれの専門分野に応じた「研究室」に所属し、1年間にわたって一つのテーマを深く探求します。この記事では、高専の研究室で過ごす1年間がどのようなものか、その全貌を解説します。
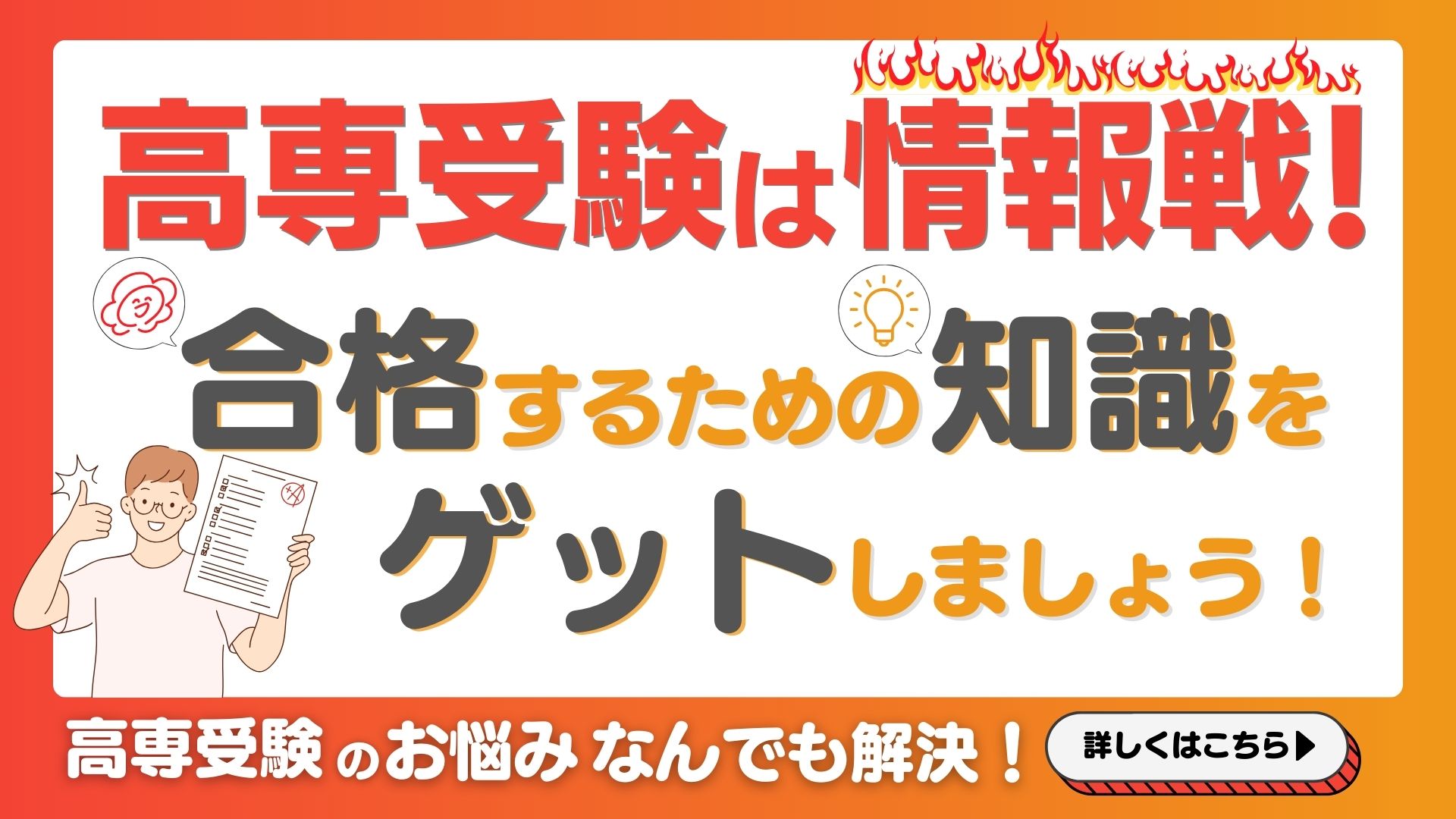
そもそも高専の研究室とは?
高専生活のクライマックスとも言える研究室での活動です。ここでは、その基本的な仕組み、大学の研究室との本質的な違い、そして将来を左右するほど重要な研究室選びのポイントについて、解説していきます。
研究室配属の時期と流れ
高専における研究室配属は、5年生の1年間の研究活動における最重要イベントです(4年次に配属される高専もあります)。一般的に1〜2ヶ月程度の時間をかけて自身の興味・関心に関連する研究室に配属されます。そんな配属までの過程を見ていきましょう!
4月頃:研究室紹介
各研究室の指導教員が、自身の研究内容や活動方針、過去の卒業研究テーマなどを紹介する説明会や研究室訪問などの催しが開かれます。この期間に、興味のある研究室の情報を収集します。
5月上旬:希望調査・面談
学生は配属を希望する研究室にいくつか順位をつけて希望調査に回答します。教員によっては、希望する学生と個別に面談を行い、研究への意欲や適性を確認することもあります。
5月下旬:研究室配属決定
希望調査や面談、学業成績などを総合的に加味して、各学生が所属する研究室が正式に決定されます。原則他の研究室に移ることはできません。
5月~翌年3月:研究活動開始
配属決定後、すぐに研究活動がスタートします。最初の数ヶ月は、主に研究テーマの決定と、その分野の文献調査を行い、本格的な実験を行うのは夏頃からです。一部の高専では、4年生から研究室に仮配属され、2年間かけて卒業研究に取り組むケースや、最初の1年間は本格的な研究ではなく、論文を読んだり、基礎的な実験のトレーニングに時間を充てる場合もあるので、志望している高専のスケジュールを確認してみましょう!
大学の研究室との違い
高専の研究は、多くの場合、1年間という限られた期間で行われ、社会に出て即戦力となるための実践的な能力を育成することが主な目的です 。そのため、テーマも具体的な「モノづくり」やシステムの開発、応用技術に関するものが中心となる傾向があります 。一方、大学の研究は、学部4年生から大学院修士課程までの3年間を見据えて行われ、より基礎的な科学の探求や、世界でまだ誰も解明していない問題に取り組むことが多いです。そのため、設備や予算も高専とは比較にならないほどスケールが大きく、高専よりも研究を深めやすい環境が整っています。
高専の卒業研究で得られる経験は、企業の開発部門や品質管理部門などで高く評価されますが、基礎研究や応用研究といった「研究職」を目指すのであれば、大学院への進学がほぼ必須というのが現状です。
研究室選びで失敗しないためのポイント
どの研究室を選ぶかは、研究テーマだけでなく、日々のスケジュール、人間関係、そして卒業後の進路までが大きく変わる、とても重要な選択です。
本章では、後悔しないための研究室選びのポイントを説明していきます!
自分の将来像を明確にする
まず最初に考えるべきは、「卒業後、自分はどうしたいのか」という点です。進路によって、研究室選びの優先順位は大きく変わります 。
大学編入を希望する場合
この場合の最優先事項は「編入試験の勉強時間を確保できるか」です 。研究室によっては、卒業研究が忙しすぎて試験勉強が確保できず、志望校に落ちてしまうこともあります 。
逆に、指導教員が編入に理解があり、試験が終わる9月頃まで研究活動を本格化させない方針の研究室もあるので、教員の柔軟性や研究室の年間スケジュールを、事前に徹底的に調査することが重要です。
就職を希望する場合
希望する業界や職種で役立つ知識やスキルが得られる研究室を選ぶことが王道です 。例えば、自動車業界志望ならメカトロニクス系の研究室、IT業界なら情報セキュリティやAI関連の研究室といったように、志望業界と研究室での研究活動を結びつけることで、就活の際に圧倒的な強みとしてアピールすることができます。
研究室の情報を多角的に集める
自分の進路の方向性が見えたら、次は具体的な研究室の情報を集めます。
研究内容とアウトプット
webサイトなどに公開されている過去の卒業研究テーマ一覧を見て、その研究室が力を入れている分野があなたのやりたいことに合っているかを調べます。
また、アカデミックな経験を積みたいなら、その研究室が学会発表や論文投稿を活発に行っているかも重要な指標になります。
研究室の運営方針
研究室によっては毎週指定された時間に研究室にいなければならない時間(コアタイム)が指定されていることがあります。研究室によってその時間は異なりますが、9時~12時や10時~17時などが指定されていることが多いです。
また、編入試験に理解がある研究室では、試験が終わる9月まで研究を本格化しない方針の研究室もあります。
進路を実現するためには、自身に合った運営方針の研究室を選ぶことがとても重要です。
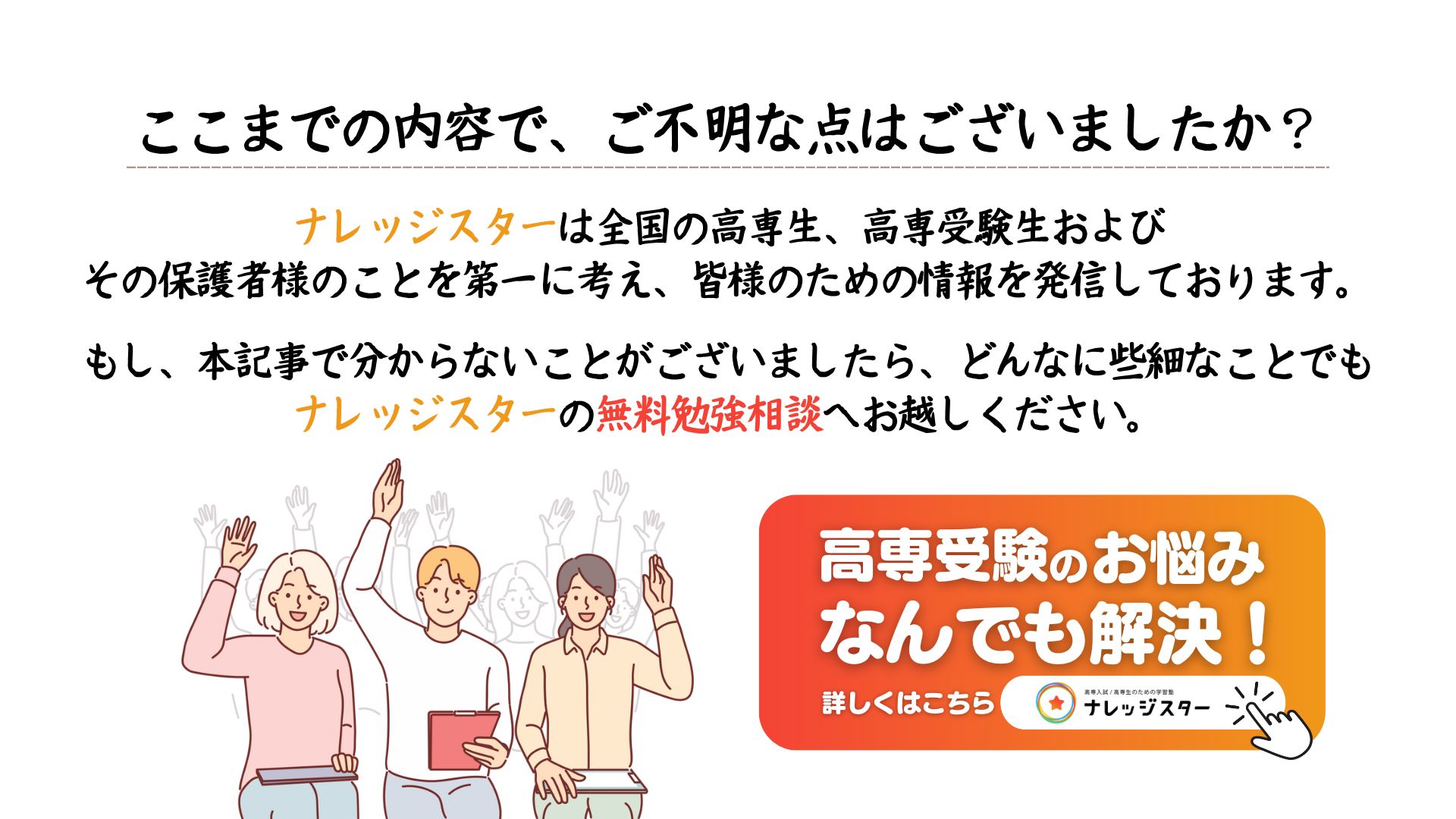
人間関係と雰囲気をみる
研究内容や条件が良くても、最終的に満足度を左右するのは「人」です!以下に気をつけて、研究室の雰囲気を確認してみましょう。
指導教員との相性
研究室では、指導教員の性格、指導スタイル、学生への接し方が、研究生活の質を決定づけると言っても過言ではありません。指導教員との相性の良し悪しによっては、「何を学ぶか」以上に「誰に学ぶか」が重要になることもあります 。尊敬でき、かつ円滑なコミュニケーションが取れる指導教員かどうかを見極めることはとても重要です。
研究室の「生の声」を聞く
教員による公式な研究室紹介は、基本的に良いことしか語られません 。本当の姿を知るためには、現在所属している先輩たちから話を聞くことが必要不可欠です。
必ず教員がいない場所で、「実際のところ、週に何時間くらい研究していますか?」「先生はどんな人ですか?」「編入の勉強はできますか?」といった具体的な質問を投げかけ、本音を引き出しましょう 。
高専の研究室での主な活動内容
研究室での活動は、学生一人ひとりが特定のテーマに取り組み、その成果を論文と発表会で報告する、各学生の「卒業研究」プロジェクトを中心に展開されます。
卒業研究のリアルな活動内容を覗いてみましょう!
研究テーマについて
高専の卒業研究ではたくさんの分野・テーマから1つ選んで研究を進めていきます。例えば、情報・AI分野では深層学習を用いた画像のノイズ除去や災害時の救助を支援するIoTシステムの開発、土木・建築系ではコンクリート建造物の劣化診断、豪雨による斜面災害についての分析など、社会の課題を解決するための多種多様な研究を行うことができます。
研究室で1年間の中にあるイベント
一見1年間ととても長く感じる卒業研究活動ですが、その期間には多種多様なイベントがあり、実はとても忙しいです。
卒研での特徴的なイベントをいくつか紹介します。
①ゼミや輪講で知識を深める
卒業研究を円滑に進め、専門知識を身につけるために、多くの研究室では「ゼミ」や「輪講」と呼ばれる定期的なミーティングが実施されます。
ゼミとは、 週に1回程度の頻度で開かれ、学生が自身の研究の進捗状況を報告し、指導教員や他の学生とディスカッションを行い、研究の方向性が正しいか、問題点はないかなどを確認するための場です。毎週のゼミを目標に、毎日少しづつ研究を進めていくのです!輪講とは、専門分野の教科書や英語の学術論文を、学生が分担して読んで理解し、その内容を発表形式で共有する勉強会です。輪講を通じて、研究の背景となる理論や最新技術の動向を深く理解し、研究をスムーズにすすめることができます。
②中間発表会
多くの高専では、年度の途中に研究の方向性と現在の進み具合を報告する「中間発表会」が開催されます。
ここではポスターを使ったプレゼンテーションを行い、研究室の指導教員だけでなく、学科の先生から多くの意見をもらうことができます。多くの卒研生は夏までは中間発表へ向けて先行研究の文献調査などの活動を進めていきます。
③卒業研究発表会
「卒業研究発表会」は卒業研究の集大成、1年間の研究の成果をスライドにしてプレゼンテーションを行います。
これを乗り越えないと卒業できない上、指導教員以外の先生からも厳しい質問が飛んできたりするので、一刻も油断できません。
④歓迎会、忘年会などの催し
研究室の中には新しい学生が研究室に入る4月や、創業研究が大詰めとなる12月などに歓迎会、忘年会といった楽しい催しを開催するものもあります。
担当教員や研究室の仲間と情報を交換しながら楽しく食事や会話をし、研究を頑張るためのモチベーションとなる、とても楽しい催しです。
上で説明した以外にも、多くのイベントが卒研生を待っています。
多くの高専では以下のような流れで研究を進めていきます。
* 4月~6月: 研究テーマ決定、先行研究の文献調査
* 7月~9月: 実験計画の立案、装置の製作やプログラミングの開始、中間発表会
* 10月~12月: 本格的な実験・開発、データ収集と解析
* 1月~2月: 卒業論文の執筆、最終発表会に向けた準備
* 3月: 卒業研究発表会
学会発表や論文執筆への挑戦
卒業研究で優れた成果が得られた場合、あるいは意欲の高い学生は、国内外の学術学会での発表や、査読付き学術雑誌への論文投稿に挑戦することもできます。
こういったアカデミックな活動を多くの大学生よりも早い時期である高専在学中に、学会発表や論文執筆を経験できることはとても貴重なことなのです!
【密着】ある高専生の1日のスケジュール(卒業研究編)
研究室での生活は、実際はどのように進んでいくのでしょうか。ここでは、ある情報工学科に所属し、卒業研究に取り組む高専生の典型的な一日を、時間ごとに追いかけてみましょう。
午前:実験とデータ整理に集中
9:00 AM:研究室へ
高専では午前中から活動を開始する学生が多いです。研究室に到着後、まずはメールをチェックし、前日の実験結果やシミュレーションのログを確認、指導教員や先輩からの連絡事項がないかを確認し、その日の作業計画を具体的に立てます。
9:30 AM – 12:00 PM:研究活動(前半)
午前中は、集中力が必要な作業に没頭する時間。開発中のソフトウェアのコーディング、機械学習モデルのトレーニング、あるいは電子回路の試作と測定など、各自のテーマに沿った実践的な作業を進めていきます。
開発がうまくいかない場合は、輪講で読んだ関連する論文を読み返したり、専攻科の先輩に相談したりしながら、粘り強く研究を進めます。
昼休み:仲間とのランチと情報交換
12:00 PM – 1:00 PM:昼食
研究室のメンバーと一緒に学生食堂へ。研究の進捗状況を報告し合ったり、「このエラーが解決できない」「あの測定装置の使い方がわからない」といった技術的な相談をしたりします。雑談の中から、自分の研究のヒントが得られることもよくあります。
午後:教授とのミーティングと論文調査
1:00 PM – 3:00 PM:研究活動(後半)
午後は、午前中の作業の続きや、得られたデータの整理・分析を行います。グラフを作成したり、結果を考察したりして、進捗を報告するための準備を行います。
3:00 PM – 4:00 PM:指導教員とのミーティング
週に一度の定例ミーティング。1週間の進捗をまとめた資料をもとに、指導教員に進捗を報告。実験結果に対する考察や、今後の研究方針について議論を交わします。教員からの鋭い指摘やアドバイスを受け、次の1週間の目標を決めていきます。
4:00 PM – 5:30 PM:文献調査・論文執筆
実験や開発が一区切りついたら、研究について深く考える時間。最新の学術論文を読みながら、自分の研究の新規性や位置づけを確認します。また、卒業論文の執筆を少しずつ進め、序論や関連研究の章を書きためておきます。
放課後:翌日の準備と自主学習
5:30 PM以降:一日のまとめと自己投資
その日の作業を終えると、翌日の作業内容をリストアップし、スムーズに研究を再開できるように準備をします。研究室を出た後は、大学編入を目指す学生は図書館で受験勉強に励み、部活動に所属する学生は練習に参加するなど、各自の目標に向けた時間になります。
高専の研究室に関するよくある質問
ここでは、高専生が研究室生活を始めるにあたって抱きがちな、素朴な疑問にQ&A形式で答えていきます!
研究室には毎日行く必要がありますか?
基本的に学校側から指定されているコアタイム(メンバー全員が原則として在室している時間)以外は行くも行かないも学生次第です。研究室での過ごし方も、研究を進めたり、授業の課題をこなしたりと自由度がとても高いので、研究室の中でもとても充実した時間を過ごすことができます。
研究テーマはどのようにして決まりますか?
研究テーマは、学生が一方的に決めたり、教員から割り当てられたりするのではなく、多くの場合、学生と指導教員との相談で決められます。研究テーマを決める際には、指導教員が自身の専門分野に関連する研究テーマのリストを提示し、その中から研究テーマを選んだり、前年度の先輩の研究成果を引き継いで、それを発展させたり別角度から研究するといったこともあります。
また、学生が何かやりたいテーマを持っていれば、教員に相談することでその研究を実施することもできます。
卒業研究はどのくらい大変ですか?
卒業研究はこれまでの授業で取り扱ってきた「正解」のある問題ではなく、指導教員も知らないような問題に挑戦します。そのため、複雑な計算や理論の理解などが必要で、思うように結果が出ないことも多く、能力的にも精神的にもとても大変です。
その分、論文を書き上げたり、最終発表を終えた後の達成感はとても大きく、やりがいがあります。
研究室生活で得られるスキルは何ですか?
研究室での1年間を通じて得られるものは、卒業論文や研究成果だけではありません実験・測定機器の操作スキルなどの専門的な「技術スキル」や、問題を解決していく「課題解決能力」「プロジェクトマネジメント能力」、仲間とともに研究を行うための「チームワークと協調性」など、社会人として必要な能力を身につけることができます。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ –研究室は未来のエンジニアへの第一歩!充実した高専ライフを送ろう
高専の研究室生活は、単に卒業研究をこなすだけでなく、将来を具体的に描き、技術者としてのキャリアを決める貴重な体験の場です。高専での学びの集大成であり、エンジニアリングの醍醐味を直接肌で感じられます。
さらに、教科書だけでは学べない問題解決能力やプロジェクト管理能力といった「実践的なスキル」を手に入れるまたとない機会です。この1年間を最大限に活用するために、事前の自己分析と情報収集を怠らず、積極的に研究活動に取り組み、指導教員や先輩との交流を深めましょう。
高専の研究室は、未来の技術者としての第一歩を踏み出すための「実践的な訓練の場」です。ぜひこの機会を活かして、自身の可能性を広げ、真の技術者とは何かを改めて考えてみましょう!
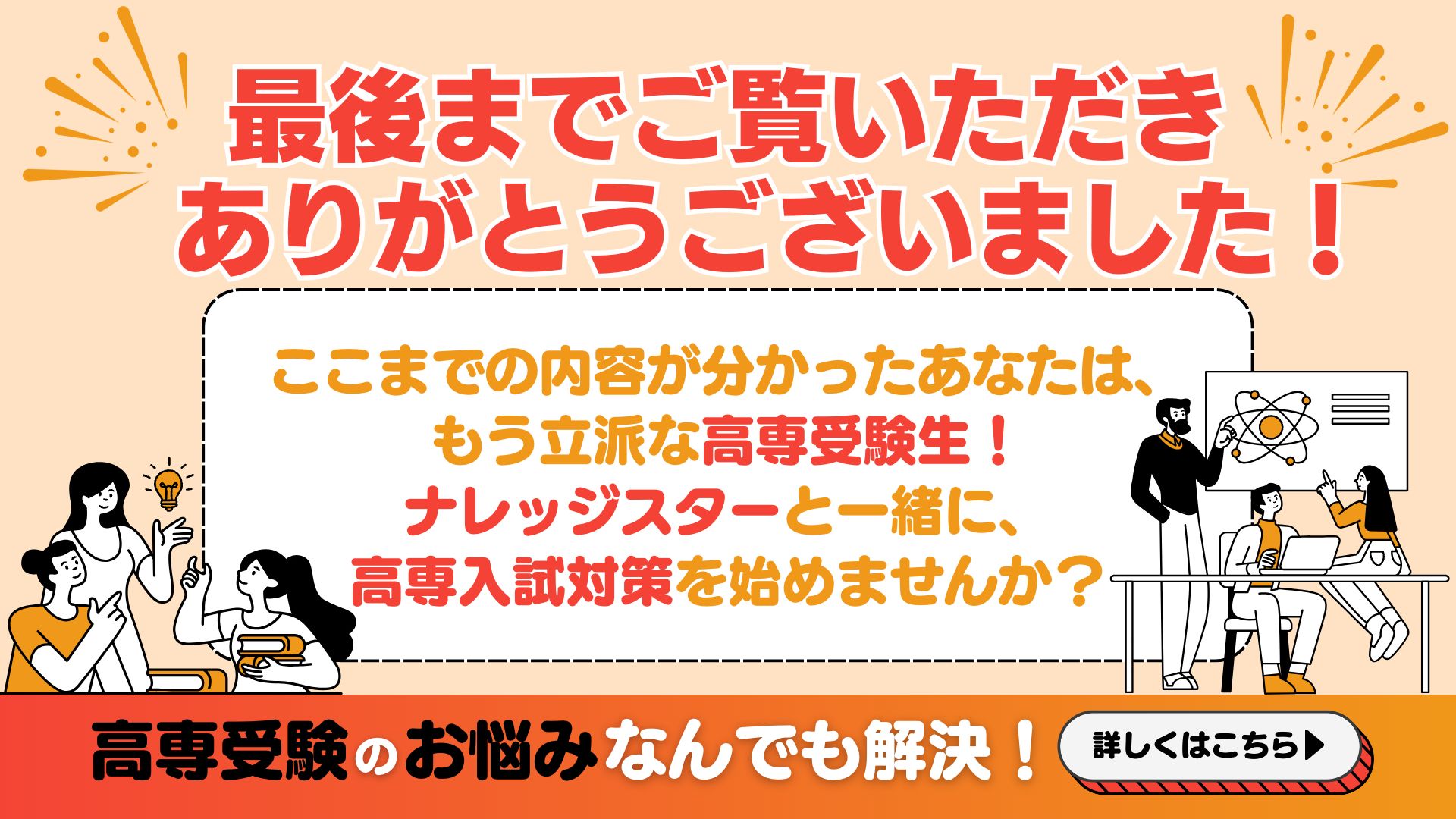
ライター情報
ニックネーム:やまり
所属していた高専:佐世保高専
自己紹介:佐世保高専OBのやまりです!5年間佐世保高専電気電子工学科で学んだことや活動を通じて得た経験を皆さんに発信して行きたいと思っています!よろしくお願いいたします!









