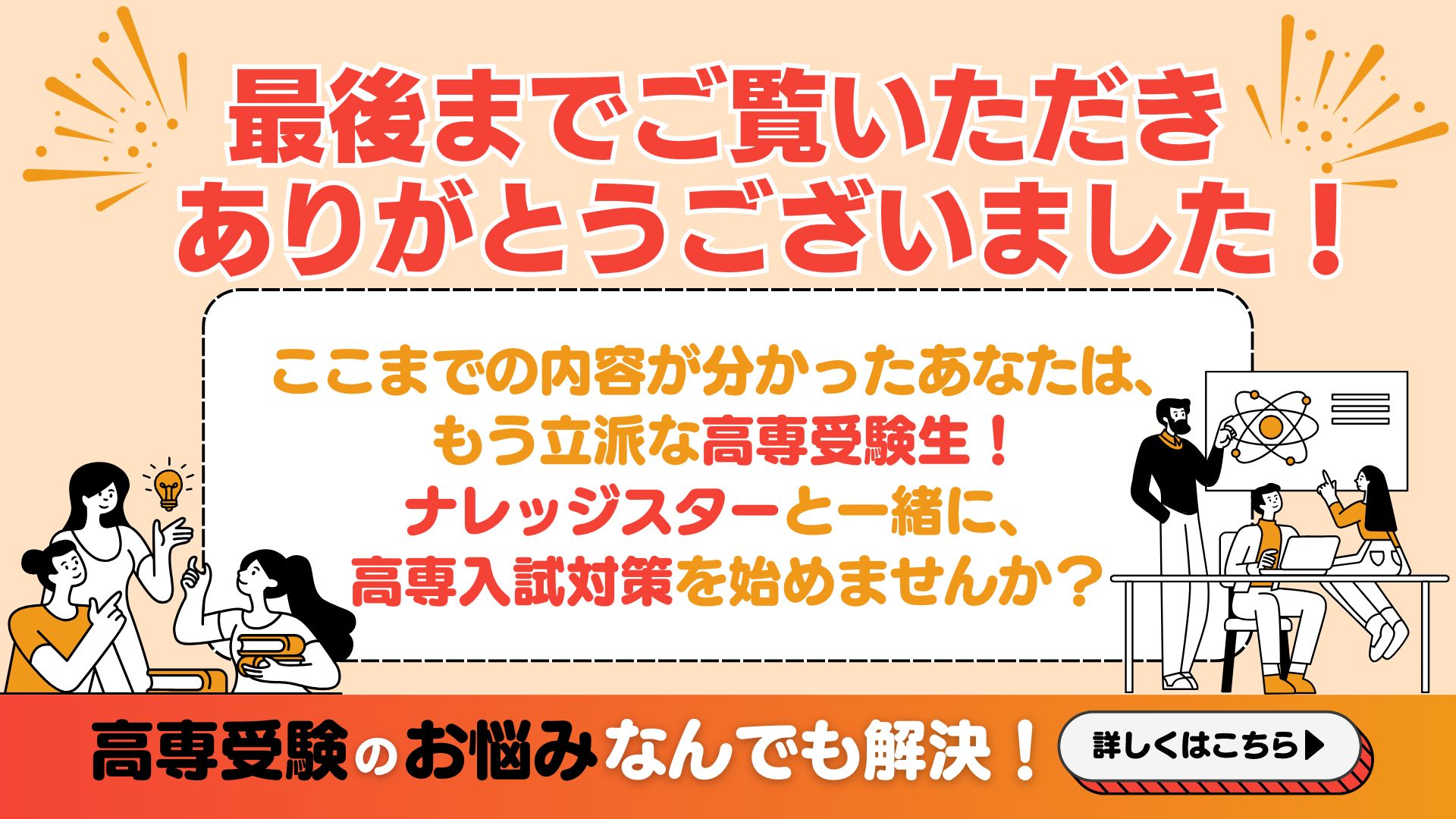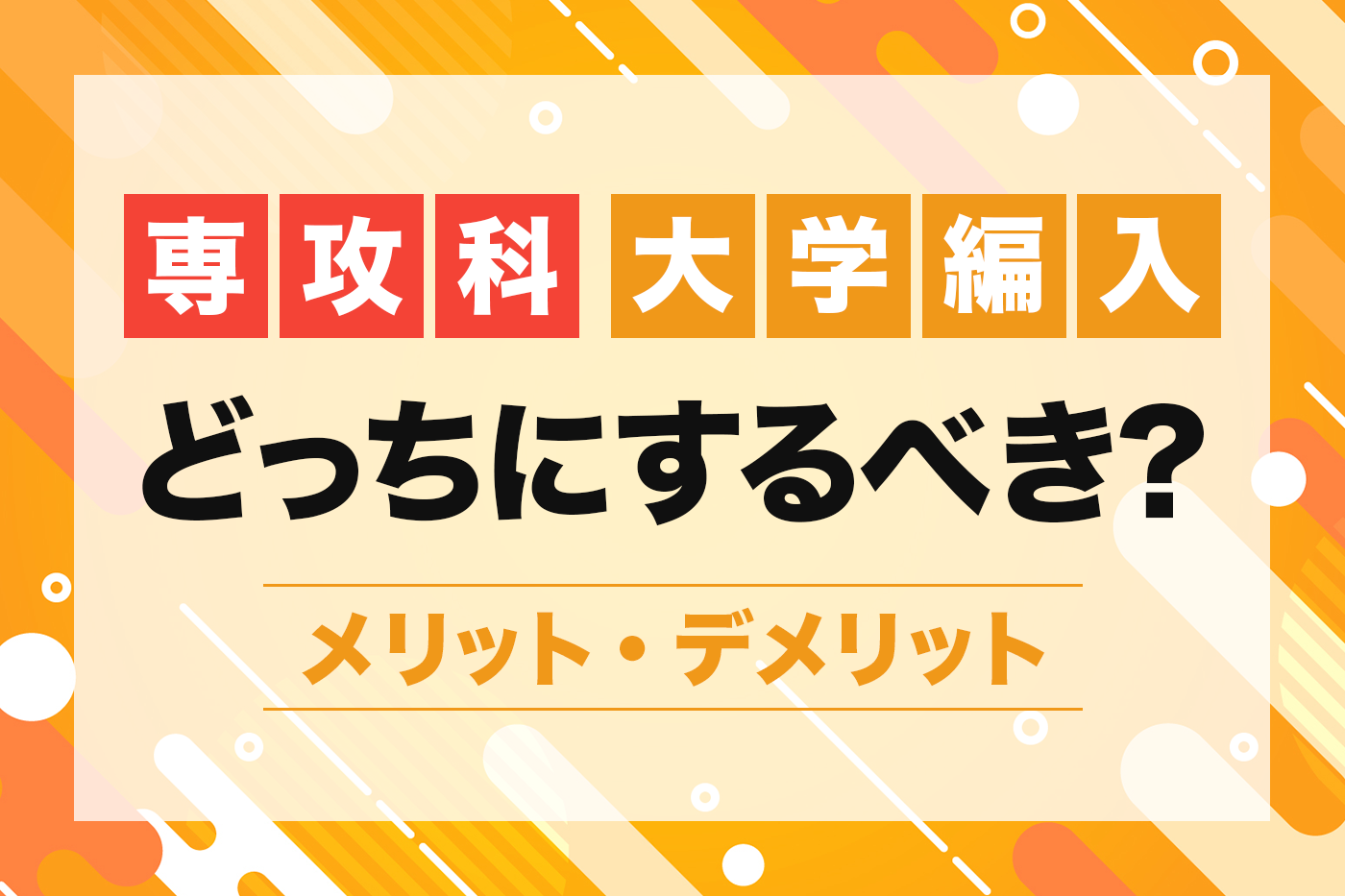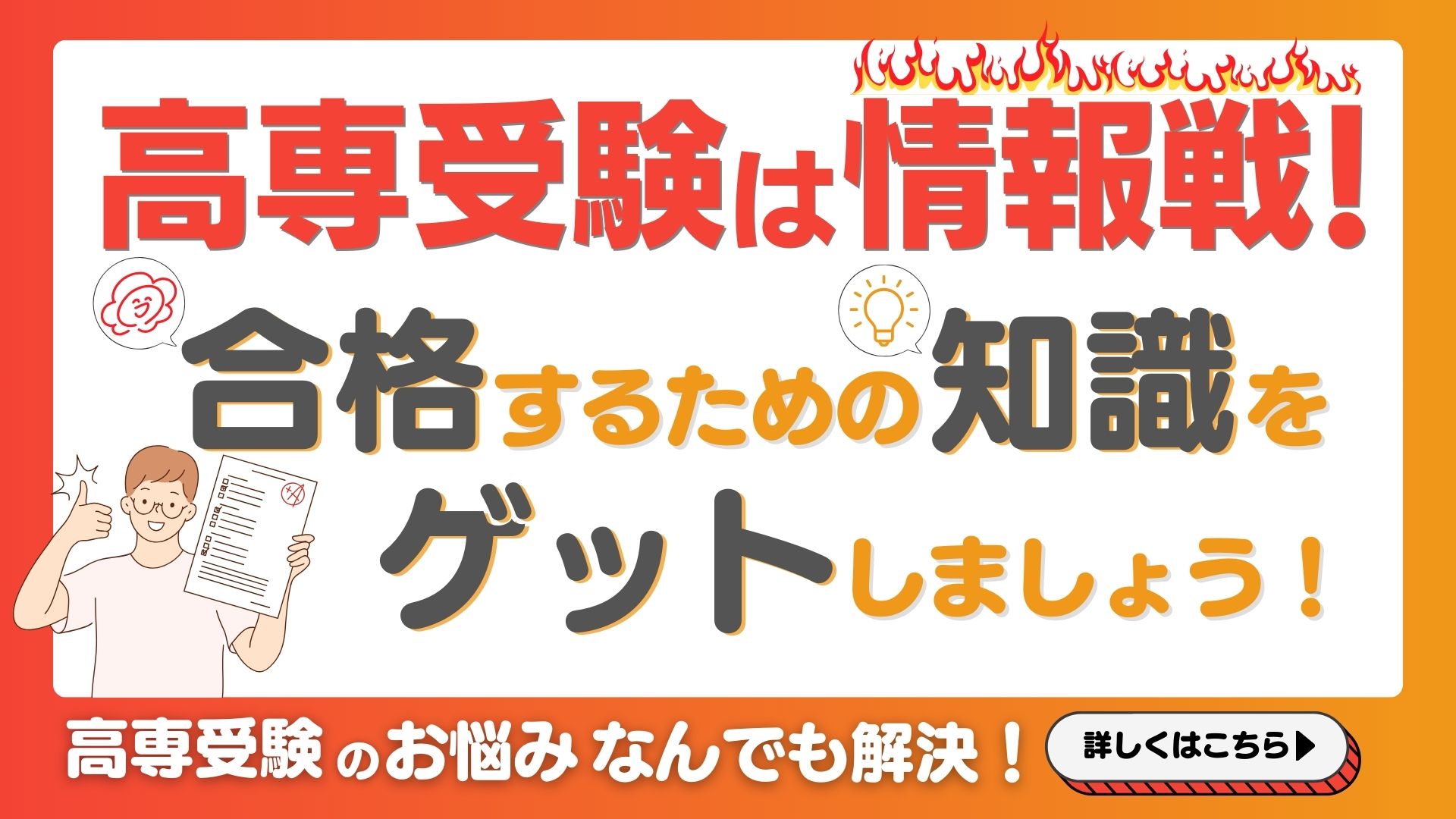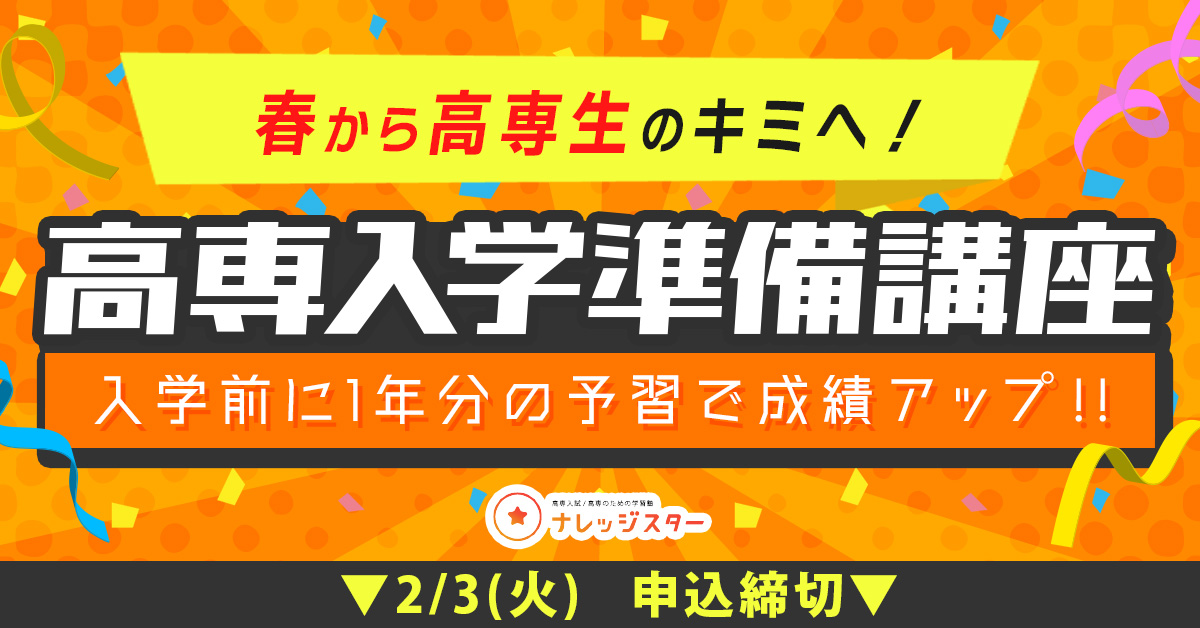高専人生最大の決断
今回は「高専人生最大の決断」と言っても過言ではない進路のお話です。特に今回は高専生の進学に焦点を当てて「専攻科」と「大学編入」について徹底解説していきます!
高専受験は情報戦!合格するための知識をゲットしましょう!
専攻科の特徴
専攻科とは、国立高等専門学校機構のHPで次のように記されています。
高専の科学の知識と技術を更に深めたい学生のため、より高度な技術者教育を行うことを目的として、2年間の専攻科が設置されています。
つまり、本科5年を過ごした後、高専にあと2年通い、よりハイレベルな技術者を育成しようというものです。
専攻科進学のメリット
専攻科のメリットは大きく4つあります。
大学卒業と同じ「学士」が得られる
国立高専の専攻科を修了し、大学改革支援・学位授与機構(NIAD-QE)の審査に合格すると「学士」を取得できます。さらに、一部には大学との連携教育プログラムがあり、連携先大学から学士が授与されるケースもあります。学士取得後は大学院進学や「大学卒業」を要件とする採用への応募が可能です。
学費が安い
専攻科の学費目安は入学料 84,600円+授業料 234,600円/年(全国立高専で共通)。2年間合計は約 55.4万円。
参考:国立大学の標準額は入学料 282,000円、授業料 535,800円/年。3年次編入(2年在学)で約 135.36万円、2年次編入(3年在学)で約 188.94万円が目安です(標準額ベース)。
※2025年度から多子世帯は所得制限なく無償化枠の対象(本科4・5年/専攻科)。詳細は文科省・各校案内を確認。
本科在学時の研究を専攻科でも続けられる
高専では学生が研究室に所属し、その研究室のメンバーで研究を行いますが、他の進路へ進むとどんなに面白い研究も卒業時にその研究からも卒業しなければなりません。しかし、専攻科に入ることでそのまま研究室に残って研究を続けることができます。
高専の友達と青春延長戦ができる
(仲の良い友達も専攻科に進む、ということが前提にはありますが)
本科を卒業しても顔なじみの同級生たちと専攻科で再び同じ時間を過ごすことができます。また、本科の時に比べ時間に余裕が出てくるので社会へ出るためのスキルアップに力を入れることができます。
専攻科進学のデメリット
研究施設が少ない
大学に比べると、一部の大型・高額装置は整備規模に差がある高専もあります。とはいえ、各高専には研究設備の共同利用(学内外向け)や受託試験の窓口が整備され、企業・他大学との連携で設備利用を補完できる体制が拡大しています。設備面は志望専攻やテーマごとに個別チェックするのが重要です。
新たな人脈形成が難しい
同じ高専で学び続けるため、大学編入より環境の入れ替わりが小さいのは事実です。いっぽうで、大学との連携教育プログラム(専攻科と大学に同時在籍し双方の課程を修了→大学発行の学士)や、海外短期プログラム/全国コンテスト等の制度を活用すれば、学外ネットワークを広げる機会は十分にあります。専攻科を選ぶ場合は、連携・交流制度の有無と実績を事前に確認しましょう。
ここまでの内容で、ご不明な点はございましたか?
ナレッジスターは全国の高専生、高専受験生およびその保護者様のことを第一に考え、皆様のための情報を発信しております。
もし、本記事で分からないことがございましたら、どんなに些細なことでもナレッジスターの無料勉強相談へお越しください。
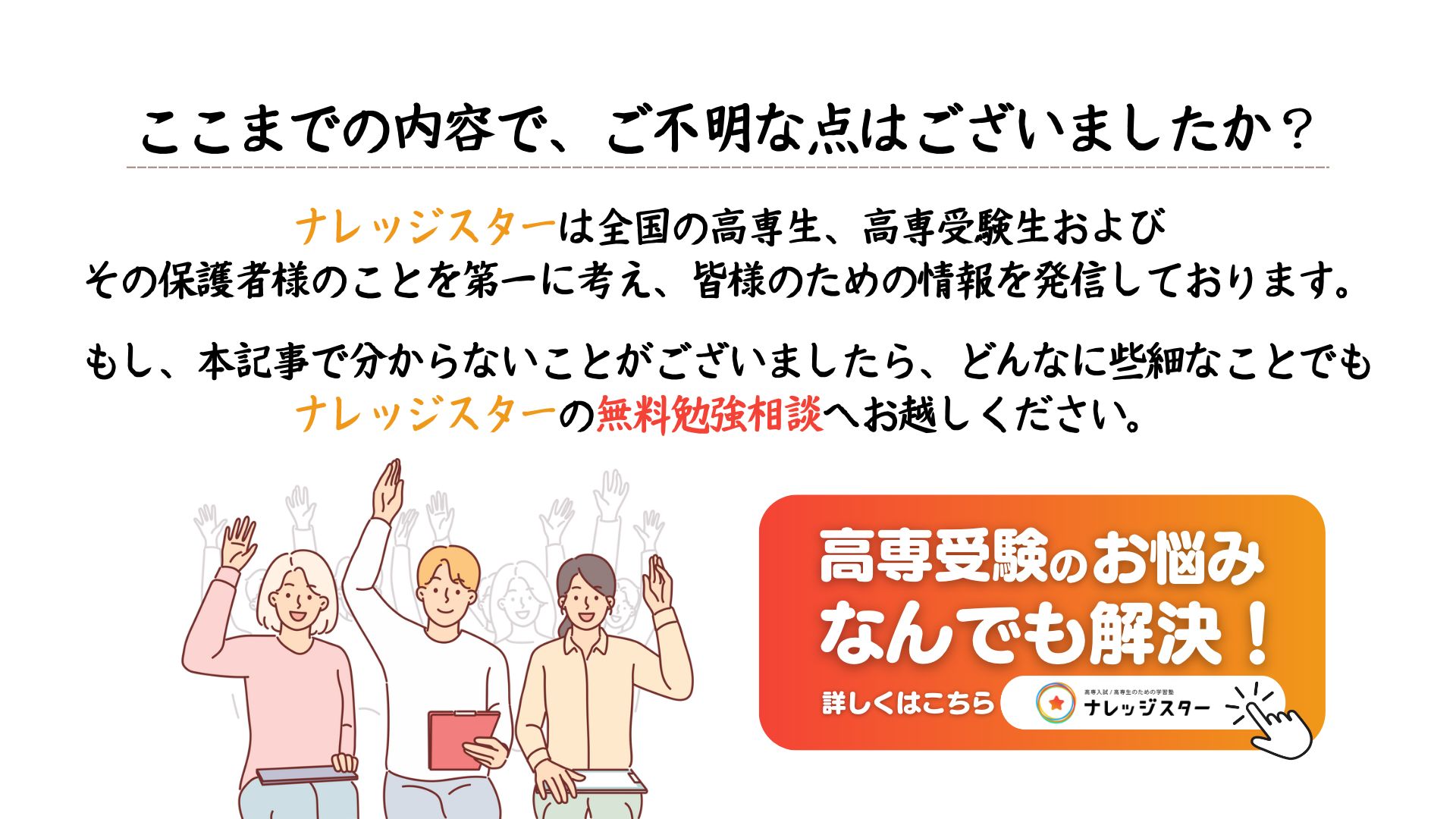
高専から大学編入する場合
大学編入の特徴
大学編入方法
大学編入は、原則3年次編入で実施される大学が多く、出願資格を満たす場合に2年次編入を認める大学もあります。
入試方式はおおむね「学力試験」と「推薦入試」の2本立てで、理工系では数学・専門科目+面接が中心、英語は外部試験(TOEIC/TOEFL)のスコア提出・換算を用いる大学が増えています。
※例:筑波大学は「編入学の年次=原則3年次/単位状況により2年次の可能性あり」「英語=TOEICまたはTOEFLのスコア換算」を明記。
※例:東京農工大学は「推薦入試/学力検査入試/社会人特別入試」の区分を明記。
学力入試
概要:多くの大学で評定平均の数値条件は設けない一方、出願資格(高専卒[見込み]等)や提出書類、および英語スコアの提出など個別の要件があります。理工系では数学や専門科目、面接が主流です。
英語の取り扱い:大学独自の筆記ではなく、TOEIC/TOEFLのスコア提出を必須としたり、スコアを英語点に換算する方式が一般的です。スコアの有効期間・基準日が定められることもあるため、早めの受験で最新スコアを確保しておくのが安全です(例:大阪大学=TOEIC/TOEFLの原本提出必須、IPやITPは無効/筑波大学=令和5年6月以降の受験スコアを有効)。
推薦入試
概要:在籍校による推薦書・成績(評定・席次等)を基に受験資格が与えられ、面接(口頭試問)で専門性や研究内容を問うケースが一般的です。推薦書様式で学年別成績や席次の記載を求める実例があります(東京農工大学の様式)。また、試験当日は個別面接を課す大学が多いです。
大学編入のメリット
有名大学への編入も可能
編入制度を設ける有名国立大は実在します。例:
- 東京大学(工学部のみ/高専卒対象・若干名)。募集要項が毎年公開されています。
- 京都大学(法・経・工で学部編入を実施。工学部は高専編入=2年次)。
- 東京科学大学(旧・東京工業大学+東京医科歯科大学、2024年統合)でも2年次/3年次相当の編入枠を公開。
- 筑波大・大阪大・名古屋大・北大・東京農工大なども編入枠あり。
新しい価値観に出会える
5年間通った高専を卒業し大学に入れば、いままでとは違った多様な人と出会えるので、新たな人脈を築くことができるでしょう。
大学編入のデメリット
単位変換の問題がある
高専から大学へ編入する場合、単位変換の問題で、大学によって何年生として編入するかが変わってきます。実は、『高専で取得した単位がすべてその大学で認められる』わけではありません。つまり高専に5年間通っても、大学2年生までにとっておかないといけない単位をすべて持っているわけではないのです。
そこでキーワードになってくるのが、『3年次編入』と『2年次編入』です。
- 『3年次編入』:大学3年生に編入するという意味で、編入後、大学に2年通うことになります。高専で取得した単位を変換した際、大学が3年次編入資格として指定している単位数を満たしていれば、3年次編入となります。
- 『2年次編入』:大学2年生から編入するという意味で、編入後、大学に3年通うことになります。高専で取得した単位を変換した際、3年次編入資格として指定している単位数を満たしていない場合は、2年次編入となります。
2年次編入は、大学に3年間通うため授業料がかさみます。しかし、その分ゆっくり基礎から学べるため、マイナスにとらえる必要はないと思います。
また、大学によっては「そもそも編入生は〇年生として受け入れる」と決めている場合もあるので、希望する大学がどの方法で編入生を取っているのか必ず確認してください!
就職サバイバル
専攻科進学だと高専は学校推薦(求人票)中心の就活インフラが強く、就職率は毎年ほぼ100%という高水準。一方、大学編入後は自主応募中心で、一般的な学部生と同様の就活(エントリー/インターン/面接対策等)に適応が必要です。
専攻科と大学編入を比較
これらのことを踏まえて、実際に専攻科と大学編入を比較してみましょう!
専攻科に向いている人
- コスパよく大卒資格(学士)を取得したい人
- 研究テーマをさらに深堀りしたい人
- 安定した環境で学び続けたい人
大学編入に向いている人
- 大学のブランドや教育環境を重視する人
- 新しい環境で、広い視野と多様な人脈を求める人
- 学問的な基礎を固めた後、さらに高みを目指したい人
- 工学系以外の道に進みたくなった人
まとめ
さて、ここまで専攻科進学と大学編入について触れてきましたがいかがでしたか?
この記事を読んで、「進学したいけど、成績が心配」「大学受験に必要な勉強ってなんだろう」と思った方!高専塾ナレッジスターでは、高専在学中の学生・保護者様に向けて無料勉強相談を行っております。無理な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にご相談下さい。
最後までご覧いただきありがとうございました。みなさんの参考になれば嬉しいです!