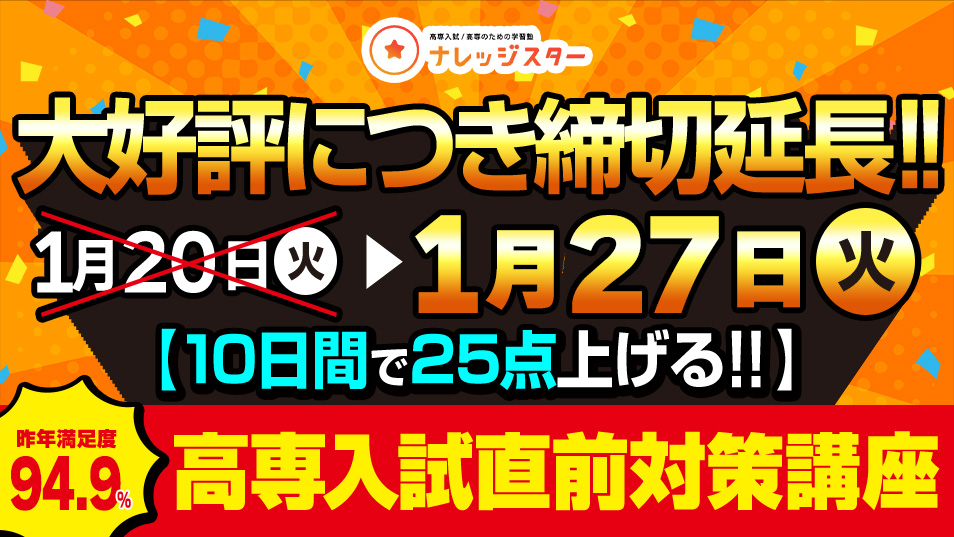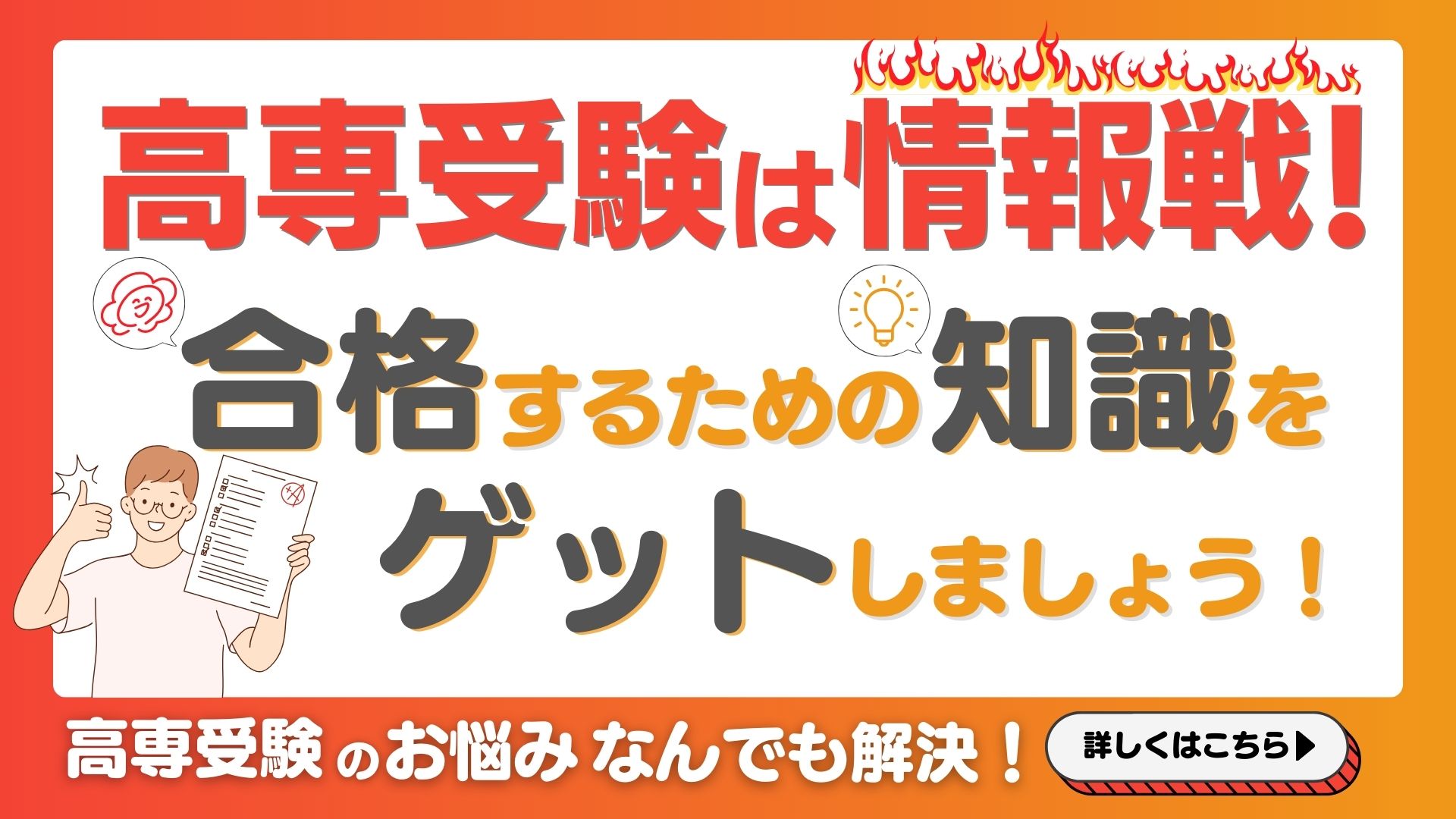
そもそも高専大会ってなに?
高専大会とは、全国の高等専門学校(高専)の運動部が出場する、高専生のための体育大会です。高専は5年制の教育機関であるため、普通高校のような「高校総体」などの大会には、1〜3年生しか出場できません。そこで、4・5年生も含めた全学年が出場できる「高専大会」が存在します。なお、4,5年生は例外的に全日本大学選手権大会(インターカレッジ)などへの出場が認められる場合もありますが、参加するスポーツのインカレの規定によって異なります。
高専大会は、地域ごとの予選を勝ち抜いた代表校が全国大会に出場する形式で行われており、規模も雰囲気もかなり本格的です。あまり知られていませんが、高専生にとっては大きな目標となる大会のひとつです。
高専大会の目的と役割
高専大会は、単にスポーツの勝敗を競う場というだけではありません。
高専という全国に広がる専門教育機関の生徒同士が交流し、刺激し合う場としての意味も持っています。
全国大会では、地域や文化の異なる高専の選手たちが一堂に会し、試合を通じて高専生ならではの団結力や誇りを実感します。これにより、「技術系の学校に通う同世代の仲間が全国にいる」という認識が芽生え、視野が広がる貴重な機会となります。
また、日々の授業や実習の合間に取り組んできた部活動の成果を発揮することで、文武両道の達成感や達成目標の明確化にもつながります。とくに、5年間継続して部活動を続けてきた学生にとっては、高専大会がひとつの集大成であり、自己成長を感じる重要な節目でもあるのです。
普通高校との違い(大会が分かれている理由)
高専生の運動部活動における大きな特徴のひとつが、普通高校とは別の大会が設けられていることです。これは、高専の教育制度が5年間の一貫教育であることに由来しています。
普通高校の大会(高体連)は、主に高校1〜3年生を対象にしたもので、高専の4・5年生は出場資格がありません。そのため、高専の上級生たちが公式戦の舞台で活躍できる機会が自然と限られてしまいます。
そこで設けられたのが「高専大会」です。その目的としては、
1. スポーツ実践機会の提供と技術向上
高専生に広くスポーツに親しむ機会を提供し、競技を通して技術の向上を図る。
2. スポーツ精神の高揚と心身の育成
スポーツの経験を通じて、フェアプレーの精神や協調性を育み、心身ともに健康な学生を育成する。
3. 高専間の親睦と交流
大会を通じて、各高専の学生や教職員間の交流を深め、相互の理解と親睦を促進する。
高専大会の大きな特徴は、高専に在籍するすべての学年(1〜5年生)が参加できるという点にあります。
この制度により、4・5年生も含めたチームづくりが可能になり、学年の枠を超えた競技経験が積めるようになっています。また、普通高校の大会では部活動の引退時期が3年生の夏ごろに集中しますが、高専では5年間を通して継続的に競技を続けられる環境があるのも特徴です。これは、高専ならではの強みでもあり、長期的な視点で選手としての成長を追える点でも他の学校とは異なる魅力といえます。
参加資格は?
出場できる学年・条件
高専大会には、出場できる学年と年齢の条件があります。原則として、本科5年生まで出場できます。
ただし、年齢による制限もあり、その年度内に21歳の誕生日を迎える学生は出場できません。ストレートで進級している場合は5年生でも20歳以下なので問題ありませんが、留年すると年齢が上がり、21歳以上になると出場資格を失います。
たとえば、1年留年している場合は4年生まで、2年留年している場合は3年生までしか出場できない場合があります。
これは、2年留年すると3年生の時点で21歳を迎える年度になるため、年齢制限により出場資格を失うからです。
また、大会に出場するには、各競技の中央競技団体への登録が必要です。たとえばバレーボールであれば「日本バレーボール協会」、サッカーであれば「日本サッカー協会」などが該当します。このルールは高校の大会(高体連)と同じで、登録をしていない選手は大会に出場できません。
高体連との関係と制限事項
高専に通う学生の多くは、運動部に所属していても、一般的な高校生が参加する「高体連(全国高等学校体育連盟)」の大会には、基本的に参加できません。
これは、高専が中学卒業後の5年一貫教育課程であり、4・5年生が「高校生」の枠に該当しないためです。
高体連の大会は原則として高校1~3年生を対象としており、高専の4・5年生は年齢制限などの関係で出場資格が認められていません。そのため、4・5年生も含めたすべての高専生が平等に競技できる場として、「高専大会」が設けられています。
ただし、例外的に1~3年生のみでチームを構成した場合に限り、高体連の大会に出場できるケースもあります。このような場合は、地域の高体連や所属する競技団体の規定に沿って、参加が認められることがあります。
また、いずれの大会に出場する場合でも、各競技の中央競技団体への登録が必須であり、ルールや登録の有無によって出場可能な大会が異なる点には注意が必要です。
高専大会がある運動部は?
全国的に共通の部活
高専には、全国の多くのキャンパスで共通して見られる運動部がいくつかあります。これらの部活動は、毎年行われる高専大会の種目としても採用されており、全国的に活動が盛んなのが特徴です。代表的な部活としては、以下のようなものがあります。
・サッカー部
・硬式野球部
・陸上競技部
・卓球部
・バレーボール部(男子・女子)
・バスケットボール部(男子・女子)
・テニス部(硬式・軟式のいずれか)
・水泳部
これらの部活は、多くの高専で設置されており、高専大会の競技種目としても全国的に統一されているため、地域ごとの差が少ないのが特徴です。特に男子バレーボールや女子バレーボール、サッカー、陸上競技などは、どのブロック大会でも高い競技レベルと参加校数を誇ります。
ただし、部活動の種類や活動状況は、各高専の規模や設備、生徒の人数などによって若干異なることもあります。そのため、同じ競技種目であっても、地域によってチーム数に差があったり、予選方式に違いがあったりすることもあります。
このように、全国的に共通して存在する運動部がある一方で、学校ごとに独自にサイクリング部やアイスホッケー部、アーチェリー部など、普通高校では珍しい部活動も存在します。これらの部活は高専大会の開催はありませんが、外部の大会へ出場することもあるそうです。
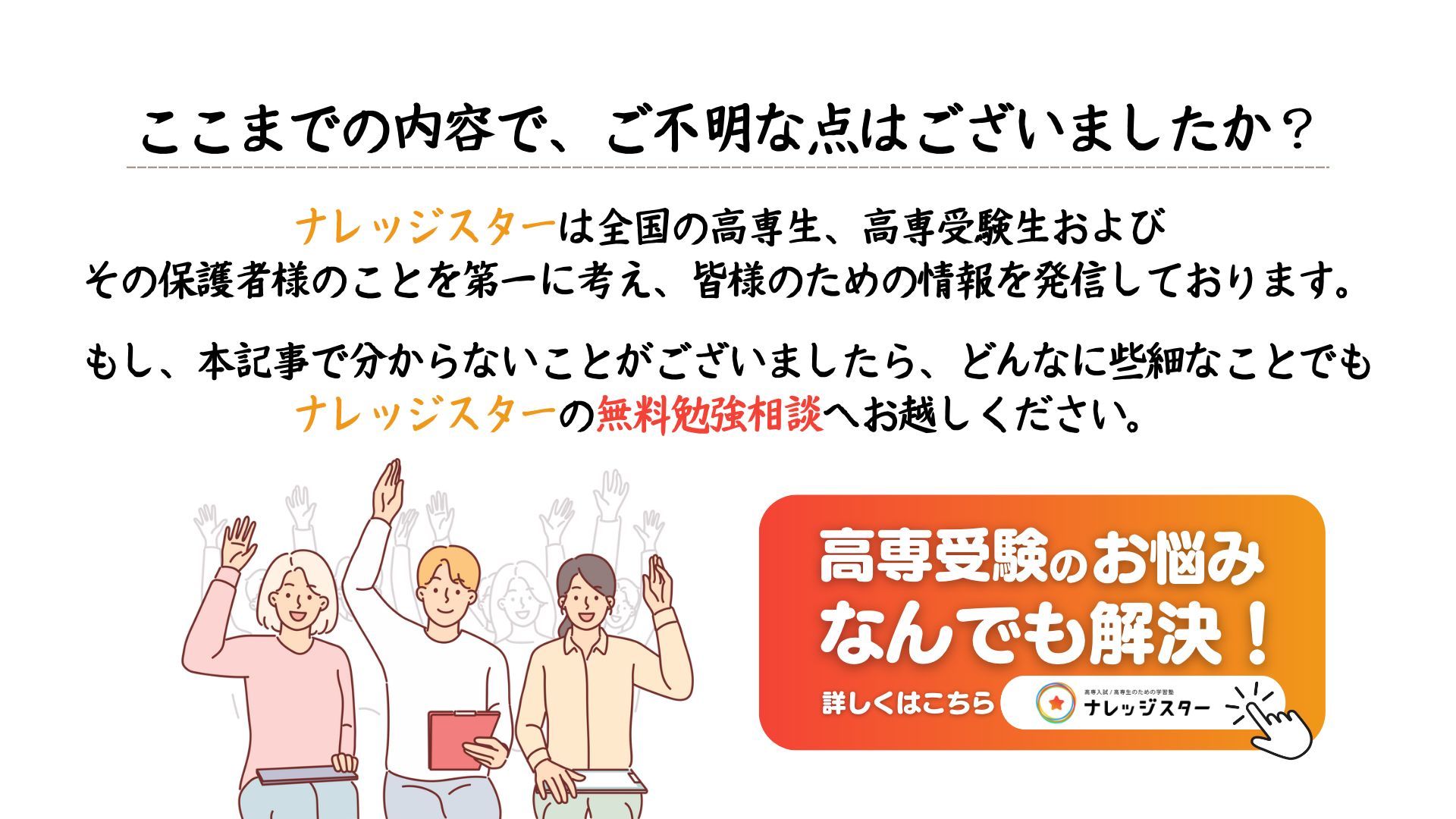
高専大会の開催時期と流れ
地区予選から全国大会まで
高専大会は、全国にある高等専門学校の運動部が競い合う唯一無二の大会であり、全国大会へ進むためには、まず「地区予選」を勝ち抜く必要があります。 地区予選は、おおむね各ブロック(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国・四国・九州沖縄)に分かれて実施されます。
予選の仕組みは競技種目によって多少異なるものの、基本的にはその年の代表校を1~2校程度に絞るため、どの地域でも非常にハイレベルな戦いが繰り広げられます。
特に運動部の中でも参加校数の多い競技(例:サッカー、男子バレーボール、陸上競技など)は、ブロック大会で何試合も戦う必要があり、選手たちは「まずは予選を突破する」という大きな壁に立ち向かうことになります。
ブロック大会を勝ち抜いたチームは、夏休み期間中(主に8月)に開催される「全国高専体育大会(全国大会)」に出場できます。 この全国大会は年に1回、各競技に応じて会場が決められ、全国各地の高専生が一堂に会して競い合う、非常に大きなイベントです。
また、全国大会は同時期に一斉開催されるわけではなく、競技ごとに日程・開催地が異なるのも特徴です。 例えば、サッカーは○○県、陸上は△△県のように、それぞれ独自に準備が進められています。
このように、「高専大会に出場する」という目標の先には、地区ごとの戦い、そして全国の舞台という2つのステージがあり、どちらも高専生にとって特別な経験となるのです。
年間スケジュールの一例
~大阪公立大学工業高等専門学校・男子バレーボール部の場合~
高専の運動部は、高専大会だけでなく、高体連の大会や校内行事、試験期間などを考慮しながら、年間を通じて活動しています。 ここでは、私が所属している大阪公立大学工業高等専門学校・男子バレーボール部の2024年度の年間スケジュールを一例としてご紹介します。
| 4月 | 春季大会(高体連) | 新年度が始まるとすぐ高体連主催の春季大会に向けて本格的な練習がスタート |
| 5月 | 春季大会 2次予選 | 春季大会の続きとして、地区代表を決める2次予選が行われる |
| 6月 | 試験期間のため活動控えめ | 中間試験があるため、部活の活動は自然と控えめに |
| 7月上旬 | 高専大会 近畿地区予選 | 予選敗退 |
| 8月~12月 | 公式戦なし | 自主練習や基礎練習に多くの時間を割く |
| 1月 | 新人戦(高体連) | 年明けには1~2年生を中心とした新人戦が行われる |
| 2月~3月 | 活動控えめ | 学年末試験や進級・卒業の準備期間に入るため活動は再び控えめに |
開催地
高専大会は、地区予選と全国大会の2段階で行われます。
地区予選は、各高専ごとに定められた「地区ブロック」単位で実施されており、開催地は毎年異なります。 たとえば、近畿地区であれば、ある年は大阪開催、翌年は奈良開催というように、地区内の複数の高専で持ち回り開催されるのが一般的です。大会ごとに遠征や宿泊が発生するため、準備や移動の面でも工夫が求められます。
一方、全国大会の開催地は、全国各地の高専が順番に担当する形式で決まっており、毎年どこかの都市に一堂に会します。
| 回数 | 年度 | 開催地 |
| 第60回 | 令和7年度 | 九州沖縄 |
| 第61回 | 令和8年度 | 東海北陸 |
| 第62回 | 令和9年度 | 中国 |
| 第63回 | 令和10年度 | 近畿 |
| 第64回 | 令和11年度 | 東北 |
普通高校の大会との違いとは?
高専の特徴
高専(工業高等専門学校)は、中学校卒業後に入学し、5年間一貫で専門的な技術を学ぶ高等教育機関です。一般的な高校とは異なり、1年生から専門科目が始まり、専門分野を中心にした実験・実習・課題が多いのが特徴です。
また、学生の年齢層も幅広く、1年生から5年生(15歳~20歳前後)までが同じキャンパスに在籍しています。運動部などの課外活動でも、学年を超えた交流が日常的で、上級生との関係が深く、縦のつながりが強いのも高専ならではの文化です。
学業との両立も大きなテーマの一つで、試験期間中は練習が減る、あるいは休止になる部活も多く、勉強とのメリハリをつけて活動しているチームが多く見られます。
このような学びと生活環境の中で、部活動に打ち込む姿勢もまた、普通高校とは一味違った独自の雰囲気を持っています。
普通高校の特徴
一方、普通高校は基本的に3年間の教育課程で、大学進学を目指す学習が中心です。一般科目(国語・数学・英語・理科・社会)をバランスよく学ぶ一方で、専門分野の勉強や実験はあまり扱われません。
部活動では、主に1~3年生で構成され、顧問の先生が指導の中心になるのが一般的です。年齢差が少ないため、上下関係は高専に比べるとやや緩やかで、チームとしての一体感を重視した活動が多く見られます。
運営や雰囲気の違い
高専大会は、大会の運営においても高専ならではの特徴があります。普通高校の大会(高体連など)では、主に教員や競技団体の担当者が中心となって運営されますが、高専大会では学生自身が関わる場面が多いのが大きな違いです。たとえば、部の先輩が審判を務めることもあり、試合の裏側にも学生の手が加わっていることを実感できます。
また、雰囲気面でも高専大会には独特の空気があります。参加している選手の年齢層が広く、1年生から5年生までが出場しているため、試合では年齢差による力の差やプレースタイルの違いが見られるのも特徴の一つです。高校生同士の試合では見られないような高度な技術や冷静なプレーが繰り広げられることもあります。
このように、高専大会はただの「試合の場」ではなく、高専生同士が同じ環境・目的を共有し、運営から応援までを一緒に支え合う独自の文化的イベントとも言えるのです。選手として出場するのはもちろん、マネージャーや運営側として関わることにも、やりがいや面白さがあります。
現役マネージャーの私が感じた高専大会のリアル
男子バレーボール部マネージャーとしての1日の流れ
| 平日の放課後練習 | 休日の試合当日 | ||
| ~16時or17時 | 授業 | 試合直前 | 記録用紙の確認、対戦相手のチェック |
| 16時or17時~19時 | 部活(球出しetc…) | 試合中 | ベンチで記録、選手へのサポート |
| 19時~ | キャプテンとプチミーティング | 試合後 | 撤収の準備、 忘れ物確認 |
私の部活は、マネージャーが洗濯、ドリンクの用意をする等はないので、比較的、仕事自体は少ないと思いますが、やはり、クラブによってはプレイ以外は全てマネージャーの仕事だという部もあるみたいなので、これから運動部に所属しようと考えている方は、詳しく話を聞いてみることをお勧めします。
大会準備や当日の裏側エピソード
高専大会に向けた準備は、そこまで大がかりなものではありません。日々の練習を大切に積み重ねていれば、特別な準備をしなくても大会に臨むことができるのが高専部活動の特徴でもあります。マネージャーとしても、試合直前の連絡事項や準備物のチェックなどを行い、チームが落ち着いて当日を迎えられるようサポートします。
しかし、本当に忙しくなるのは試合当日です。朝早くに集合して、ユニフォームやボールの準備を済ませ、ウォーミングアップの時間を計算しながら行動します。試合が始まると、マネージャーはスコアの記録、選手交代の管理、ベンチの整備、タイム中の補水など、次々とやるべきことが発生します。一見目立たないかもしれませんが、試合の円滑な進行には欠かせない存在です。
試合中は、緊張感のある空気のなかで選手が全力を尽くす姿を間近で見守ることになり、マネージャーとしても気が引き締まる瞬間の連続です。勝って喜ぶ瞬間も、悔しい結果に涙する場面も、全てがチームの大切な思い出になります。
大会当日の慌ただしさの中で、私は毎回、「このチームを支えていてよかった」と実感するのです。
チームの絆や応援の熱さを肌で感じた瞬間
どの大会もそうですが、大会は、ただ技術を競い合うだけの場所ではありません。試合を通して生まれる仲間との信頼、支え合い、そして応援の力が、心に深く残る瞬間を作り出します。
特に印象に残っているのは、大会でのある試合です。実力はほぼ互角の高校との対戦で、私たちはフルセットまでもつれ込む接戦となりました。最後のセットはデュース※にもつれ込み、どちらが勝ってもおかしくない状況で、結果は惜しくも敗戦となりましたが、悔しいけど、気持ちのいい試合だったと思います。
そんな瞬間を見守りながら支える立場として、自分もまたチームの一員であることを実感します。ただの勝ち負け以上の価値を持って心に残り続けています。高専大会は、こうした「絆」や「熱さ」こそが一番の魅力なのかもしれません。
※互いに得点が並んだ状態で、点差がつくまで勝敗が決まらないルール
全国大会に進むとどうなる?
移動・遠征・開催地について
高専大会の全国大会は、各地域の予選を勝ち抜いた代表校が集まり、全国規模で競い合う大会です。夏に開催されることが多く、種目ごとに全国の高専が一堂に会して、試合が行われます。
全国大会の開催地は、毎年決まった場所ではなく、全国の高専が持ち回りで開催を担当しています。ですので、開催される地域によっては、遠方への移動が必要になることもあります。そのため、移動や宿泊のスケジュールをあらかじめしっかりと立てておく必要があります。
移動手段は、開催地の場所によってバス・新幹線・飛行機など様々です。宿泊先や交通手段については、開催校や大会運営本部から案内がある場合もありますが、多くの場合は各校で手配します。
全国大会は、数日間にわたって開催され、予選リーグや決勝トーナメントといった流れで進行していきます。
開催地や詳しい日程については、毎年大会の公式発表がありますので、出場が近づいてきたら確認するようにしましょう。
高専大会の魅力とは?
5年間でチームに深く関われる
高専大会の大きな魅力は、大会に参加することで1年生から5年生までの長い期間、チームに関われることです。高校のように3年間で引退ではなく、5年間じっくりと関係を築けることで、チームの一体感が深まり、後輩への伝統や文化も自然と受け継がれていきます。
また、長く在籍することで、プレーだけでなく練習やチーム運営に対しても意識が向くようになります。自分たちでチームをつくっていくという意識が育ちやすいのも特徴です。マネージャーとしても5年間の関わりは大きく、選手との信頼関係が深まり、チームの一員としてのやりがいや成長を実感できます。ただ試合に出るだけでなく、長く関わることで得られる経験や絆こそが、高専大会の大きな魅力だといえます。
まとめ
高専大会は、普通高校とは異なる環境で部活動に打ち込む高専生にとって、大きな目標となる大会です。5年間という長い時間をかけて、一つのチームで深い信頼関係を築きながら成長できるのは、高専ならではの魅力だと言えます。
また、全国の高専生と出会い、刺激を受けたり、友情が芽生えたりするのも、この大会ならではの経験です。マネージャーや運営の立場からも関われるため、プレーヤー以外にも活躍の場があります。
これから高専を目指す人も、すでに入学して部活を迷っている人も、高専大会を通じてしか得られない経験が、きっとあなたの学生生活を豊かにしてくれるはずです。ぜひ一歩踏み出して、部活の世界に飛び込んでみてください。
高専大会から高専に興味を持ってくださった方、受験勉強に不安を抱える方へ、ナレッジスターの無料勉強相談を受け付けております。以下のサイトからお気軽にご相談ください。
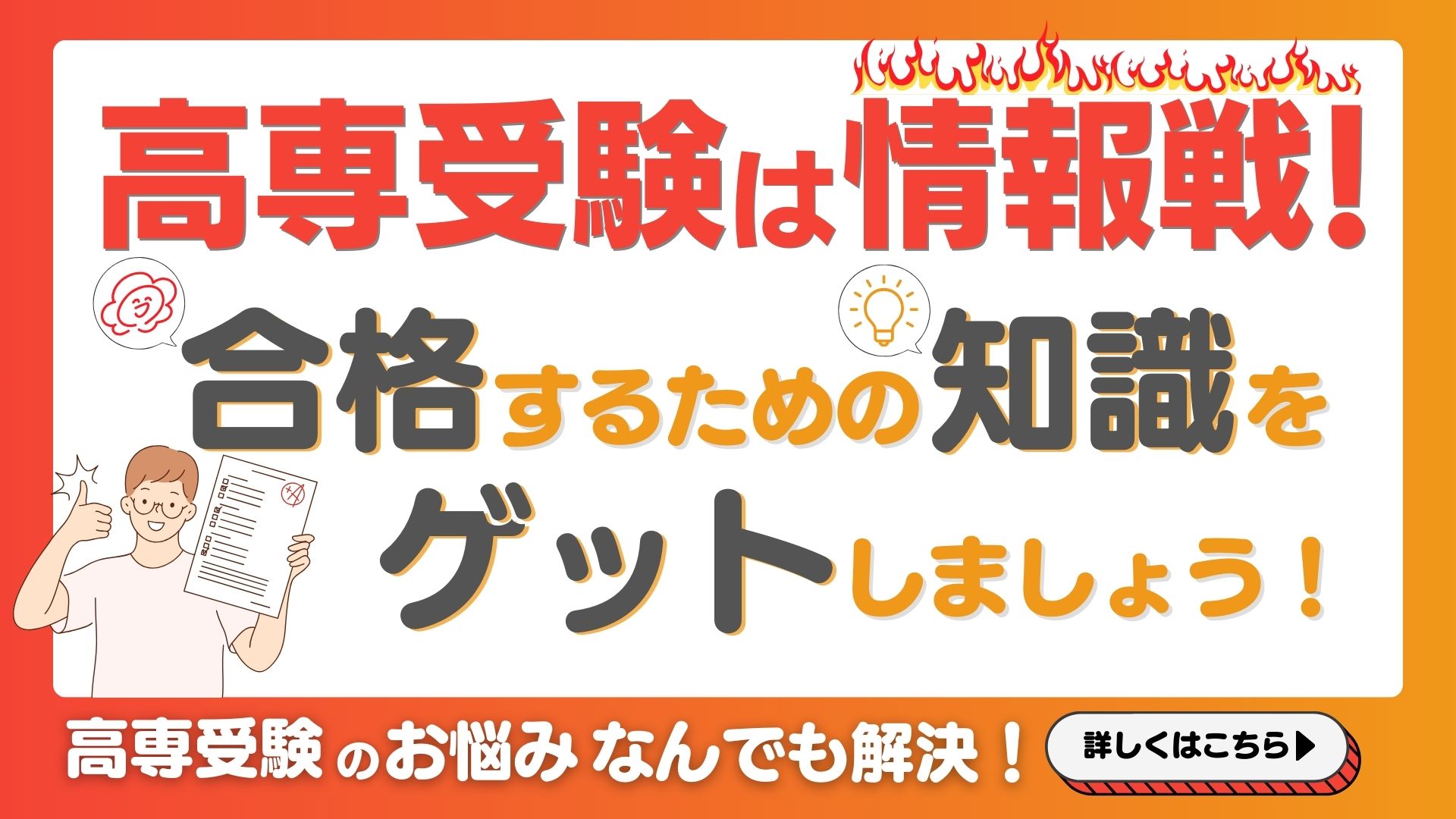
——————‐—————–‐————–‐————–‐
所属高専:大阪公立大学工業高等専門学校
学科:総合工学システム学科 エレクトロニクスコース
氏名:大原佳蓮
ニックネーム:かれん
自己紹介:高専3年生の出戻りひよっこライター。特技は人前で緊張せず話せること。高専のことについて皆さんが知りたい有益な情報などを調査・勉強中です。