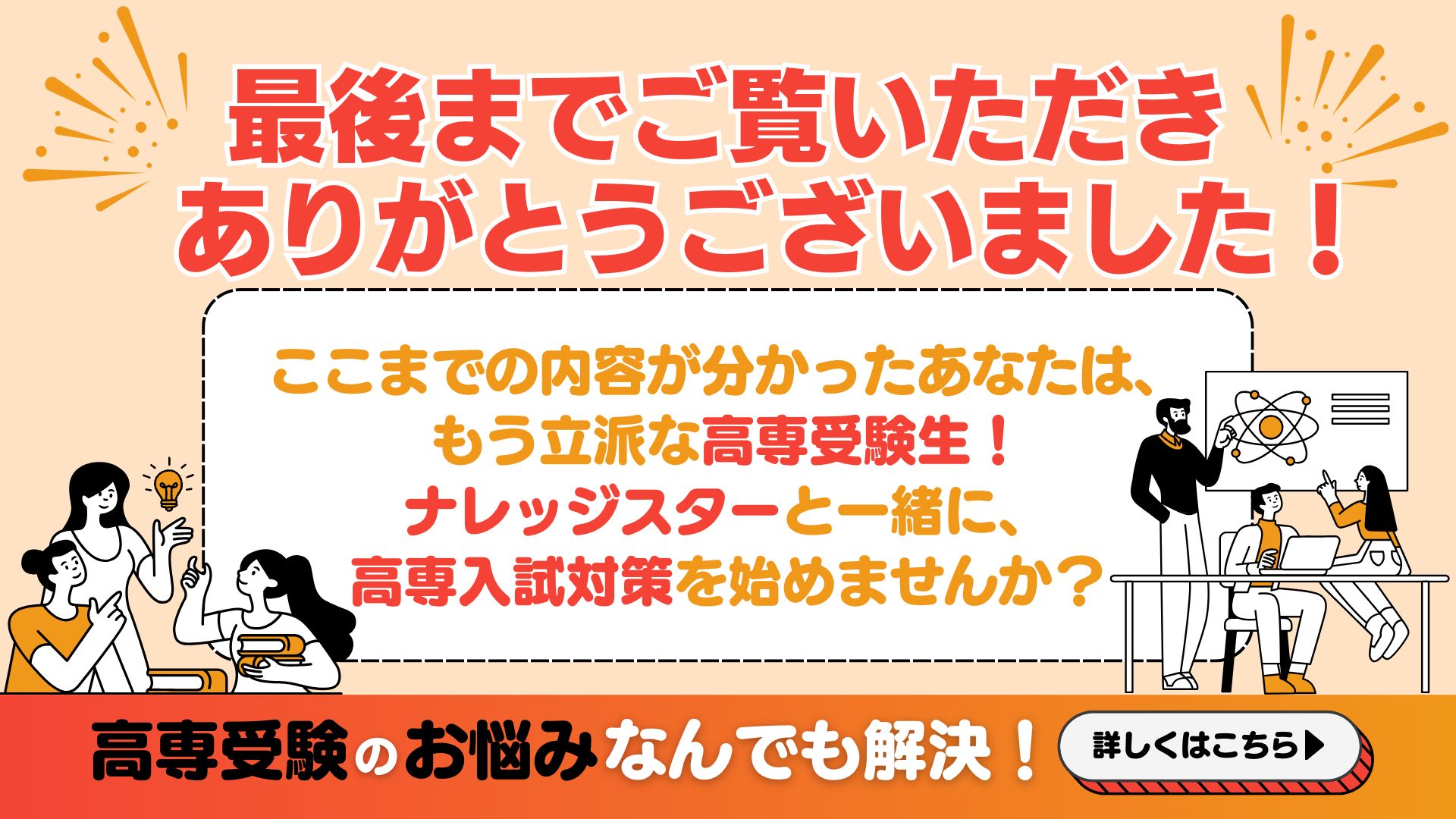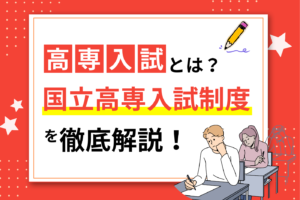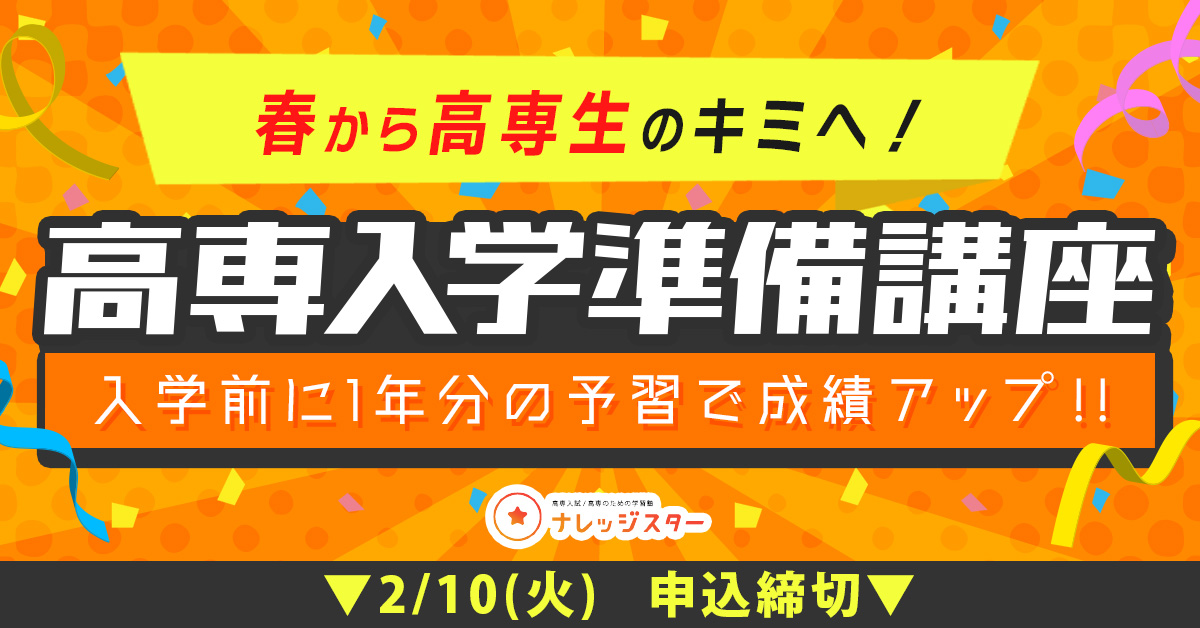こんな悩みを持っている人に読んでほしい
今回は、高専推薦入試のために評定を上げる方法について解説します。
こんな悩みを持っている人に読んでほしい
- 推薦入試を受けたいけど、評定が低いから不安。
- 評定が低いと推薦入試は受からないの?
- 評定を上げるために、今からできることはあるの?
こんな疑問や不安を持っている人に読んでほしいです!!
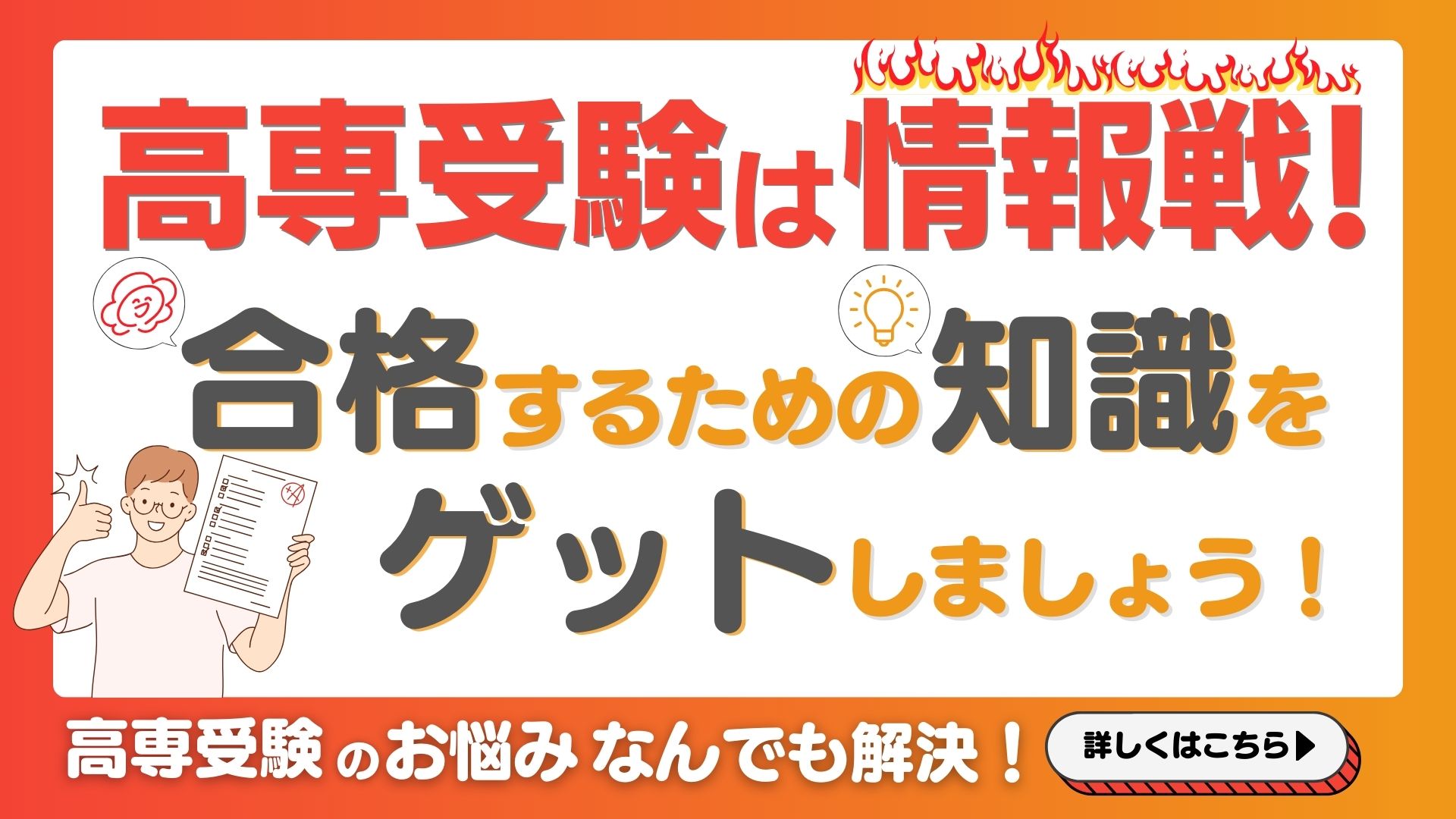
高専推薦入試とは
高専に入学するためには、大きく分けて「学力試験による選抜」と「推薦による選抜」の二つの方法があります。
学力試験による選抜は、全国一斉に行われる学力検査の成績に基づいて選抜されます。
推薦による選抜は、中学校の校長からの推薦と、面接、筆記試験、適性検査などの総合的な評価に基づいて選抜されます。推薦入試は、評定が一定以上必要となる場合が多いですが、高専によっては面接のみで選考される場合もあります。ただし、推薦入試が必ずしも楽に合格できるわけではありません。各高専によって選考方法は大きく異なり、面接に加えて筆記試験や適性検査を実施しているところも多くあります。
推薦入試を受験する場合は、事前に各高専の選考方法をしっかりと調べて対策しておくことが重要です。
評定の重要性
評定は、高専入試において重要な選考基準の一つです。推薦入試を受けるためには、多くの高専で一定以上の評定が必要となります。学力試験入試では、一部の高専では評定にも配点がある場合があります。
推薦入試では、評定に加えて面接や筆記試験などの結果も総合的に評価されます。必ずしも評定が高いだけで合格できるわけではありませんが、推薦入試における評定の配点は高い傾向にあります。
学力試験入試では、高専によって評定にも配点があります。東京高専の場合、学力試験の得点に加えて、評定分が30点満点で加算されます。
高専入試対策を成功させるためには、評定の重要性を理解した上で、学力試験と推薦入試(面接・小論文など)の準備をしっかり行うことが重要です。
東京工業高等専門学校の募集要項(学力試験)
評定はどれくらい必要?
推薦入試で合格を目指す場合、評定の平均4.5以上を目標として目指すといいと思います。しかし、高専によって基準が異なるため、評定の平均が4.5に達していないからといって合格できないわけではありません。志望している高専の出願条件となっている評定に届くように頑張りましょう。ただし、出願条件ギリギリでは合格が難しいので、なるべく余裕を持つことが大事です。
また、評定の中で注意しないといけないのは理系科目の評定です。高専によって理系科目の評定に重みを付けて評価することがあるので、特に数学、理科の評定をあげるように頑張りましょう。
推薦入試を受けるための心構え
受かったらラッキーというマインド
推薦入試は全国的に評定の割合が高いので、良い評定をとり、コスパよく対策する必要があります。ただし推薦の対策に時間をかけすぎていると学力まで失敗してしまう可能性があるので、推薦は受かったらラッキー程度で受けましょう!
推薦試験に不合格でも学力試験がある
推薦試験に不合格であっても学力試験で合格を目指すことができます。高専合格には複数の方法があり、推薦試験はそのうちの一つに過ぎません。推薦試験だけでなく学力試験もしっかり対策をして、合格を目指しましょう
評定を上げる方法(中3からできること)
1.定期テストでいい点数をとる
まずは定期テストでいい点数を取りましょう!!
評定の中で定期テストの点数は大きな割合を占めます。5科目400点以上(推薦狙う人は450点以上)を目指しましょう。副教科の評定も入試に影響してくるので、手を抜かずに良い点数をとるように頑張りましょう。
2.授業に積極的に参加する
授業に積極的に参加しましょう!先生は生徒が授業に積極的に参加しているかどうかを見ています。授業中に先生の質問に答えたり、質問したりして自分の積極性をアピールしましょう。また、グループディスカッションのような生徒と話す授業のときも同様に積極的に参加しましょう。
3.苦手科目は早めに克服しておく
評定はほとんどの場合9教科の評定の和として計算されます。もし苦手科目があると評定に大きく響くので早めに苦手科目を克服しておきましょう。具体的にはなぜその科目が苦手なのかを考えて、克服するようにしましょう。教科の中でわからないことがあったら積極的に先生に聞いてみましょう。
4.提出物の完成度を高める
授業のなかで宿題として提出物がある場合があります。これも評定を決める際の重要な要素になるので、完成度を高めるようにしましょう。
具体的には
- 内容を見直して、問われていることの答えとして正しいか
- 先生から言われた構成(はじめ・中・終わりなど)でまとめているか
- 日本語の文法を守り、誤字脱字がないか
- (意見を書く場合)自分なりの意見をまとめてわかりやすく書いているか
を確認して提出物の完成度を高めましょう。
5.評定の根拠と対策について先生に聞いてみる
先生に評定について質問してみると評定の根拠について答えてくれることがあります。
自分がなぜこの評定なのかが分かると、何を対策するといいのかが分かるので先生に質問してみましょう!
ただし、質問する前に自分なりに評定を分析し、疑問点を整理してから先生に質問するようにしましょう!
評定を上げるための効果的な勉強法
教科ごとの勉強法
まず教科を暗記科目と理解が必要な科目に分けて勉強しましょう。例えば社会は単語とその意味を覚える暗記の多い科目です。それに対して数学は問題を解くためにどうしてそうなるのかを理解しなければならない科目です。このように一度分けて整理してみましょう。
暗記科目
暗記科目は出題範囲の確認と周回が重要です。まず、出題範囲からどの単語や事象が出題されるかどうかをまとめます。次にまとめた内容を一部隠しながら理解しているかどうか確認します。最後にこの工程を何度も繰り返します。
理解が必要な科目
理解が必要な科目は早めに理解しておくことが一番重要です。暗記科目に取り組む前に理解科目(数学の公式や解き方)の理解を十分行っておきましょう。
定期テストの攻略法
定期テストの攻略法は4つあります。
授業中の先生の話を聞き逃さない
授業中の先生の話は、テストに出題される可能性が高い内容です。ノートをしっかりと取り、後から見直せるようにしましょう。また、話を聞いていないと、先生が授業態度が悪いと捉え、悪い評価につながる可能性があります。
テストの範囲をまとめておく
テスト範囲が発表されたら、まずはその内容を全て確認しましょう。ページ数、問題の数、暗記が必要な単語数などを具体的に把握することで、必要な勉強量が見えてきます。また、テスト範囲を把握しておくことで、効率的に学習計画を立てることができます。
勉強のスケジュールを立てて取り組む
勉強スケジュールを立てることで、無駄な時間を減らすことができ、集中力を高めることができます。1週間単位や1日単位で、具体的な学習時間と内容を決めておきましょう。スケジュールを立てるときには科目の優先順位(どの科目がどのくらい重要か)を考えましょう。
何周も解いて、量をこなす
問題を何周も解いて、量をこなすことは、知識を定着させるために効果的です。問題を解くことで、弱点を発見し、克服することができます。間違えた問題は特に重点的に復習しましょう。
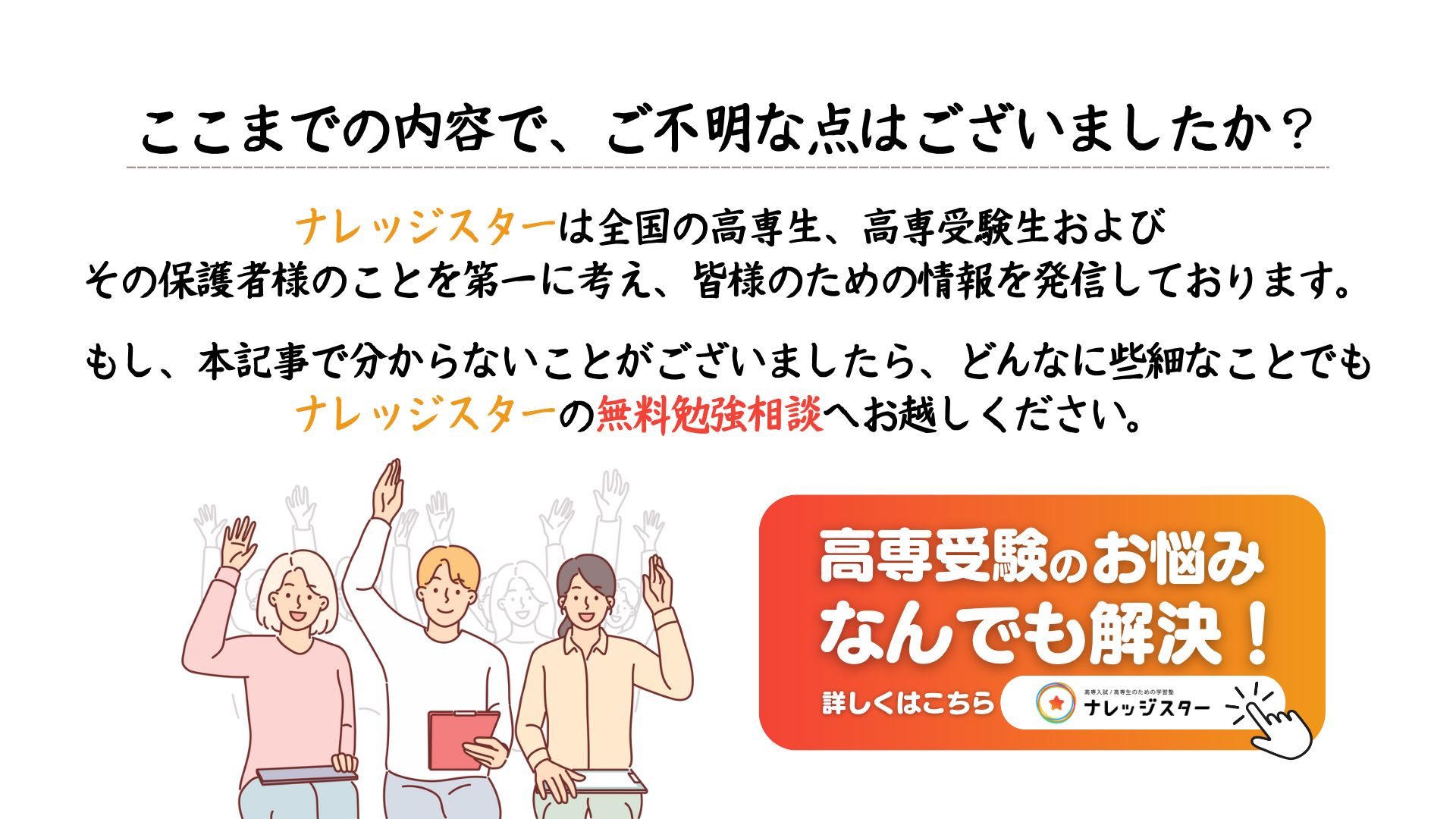
よくある質問
評定アップに効果的な参考書は?
評定アップに効果的な参考書はありません。評定は主にテストの点数、提出物、授業での積極性によって評価されます。参考書によってどうにかなるものではなく、テストの点数、提出物、授業での積極性が評価されるようにしましょう!
内申点の計算方法を教えてください
内申点とは、中学校における主要5教科(英語、数学、国語、理科、社会)と実技4教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)の9教科のそれぞれに対して1から5までの5段階評価された成績を総合的に評価した点数です。学年末の通知表に書かれている教科ごとの評価が内申点だと思って問題ないです。
高専の入試において評定の取り扱いは高専ごとに大きく異なります。志望する高専の学生募集要項には、内申点の計算方法や入試における内申点の役割について詳しく記載されています。必ず確認し、しっかりと対策を立てましょう。
例を3つ示します。
熊本高専の推薦を受けるために必要な評定は135満点中108以上です。
熊本高専学生募集要項
北九州高専の推薦を受けるために必要な評定は135満点中110以上です。
北九州高専学生募集要項
茨城高専の推薦を受けるために必要な評定は135満点中118以上です。上で紹介した高専と少し違って中学一年生の時の評定が関係してきます。
茨城高専学生募集要項
推薦入試でよく聞かれる質問は?
推薦入試でよく聞かれる質問は
- 志望動機
- 最近気になっているニュース
- 中学生のときに取り組んできたこと
- 高専でやりたいこと
だと思います。またアドミッション・ポリシー(求めている学生像)に関係する質問をされることがあるので、準備しておきましょう。
部活動は内申点に影響しますか?
部活動は、内申点に直接影響するわけではありませんが、間接的に影響する可能性はあります。例えば、部活動で積極的に活動し、リーダーシップを発揮したり、協調性を身につけたりした場合、それが授業態度や学力向上につながり、内申点がアップする可能性があります。
また面接試験では中学生のときに取り組んできたことについて聞かれることがあるので、良いアピールポイントになると思います。
推薦入試の面接対策は?
まず志望している高専の募集要項とホームページを確認するところから始まります。
以下の項目を調べて分析をしましょう!
学力、推薦の選抜方式
- 推薦に必要な評定
- 学力における評定の割合
- 学力試験の強化による点数の重みの違い
- 推薦で面接がある場合、1対多なのか、集団面接なのか
どういう特徴のある高専なのか
- どういう学科があるか
- どんな施設があるか
- どういう研究室があるか
- どの工学分野に力を入れているか
- 過去の大会、研究、イベント等の実績はどうか
- 卒業生はどんな企業、進路に進んでいるか
- 高専の歴史的な背景
過去の入試結果
- 学科別の合格倍率はどうだったか
- 過去に聞かれた質問は何だったか
アドミッション・ポリシー
- どういう学生を求めているのか
- 具体的にどのようなスキルを求めているか
次に自己分析をして、よく面接で聞かれている質問に対して回答を作りましょう。注意してほしいのは「楽しいそうだから高専に入りたい」のような主観的な理由ではなく、自分の性格や自分が今まで行ってきたことを根拠として自分がアドミッション・ポリシー(求める学生像)に合致する人間であることを論理的に説明するようにしましょう。
最後に先生に模擬面接を行ってもらいましょう。質問の回答として自分の回答が適切であるかどうか確認してもらうとともに、面接に慣れるように練習しましょう。
まとめ
- 評定はめっちゃ重要!
- 評定をあげるために(中3)でもできることはある
- 高専によって学力・推薦の試験内容が大きく異なるので、できる限り早く志望する高専を調べておく
- 学力試験の対策も並行して行う