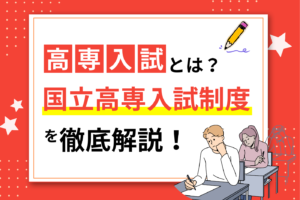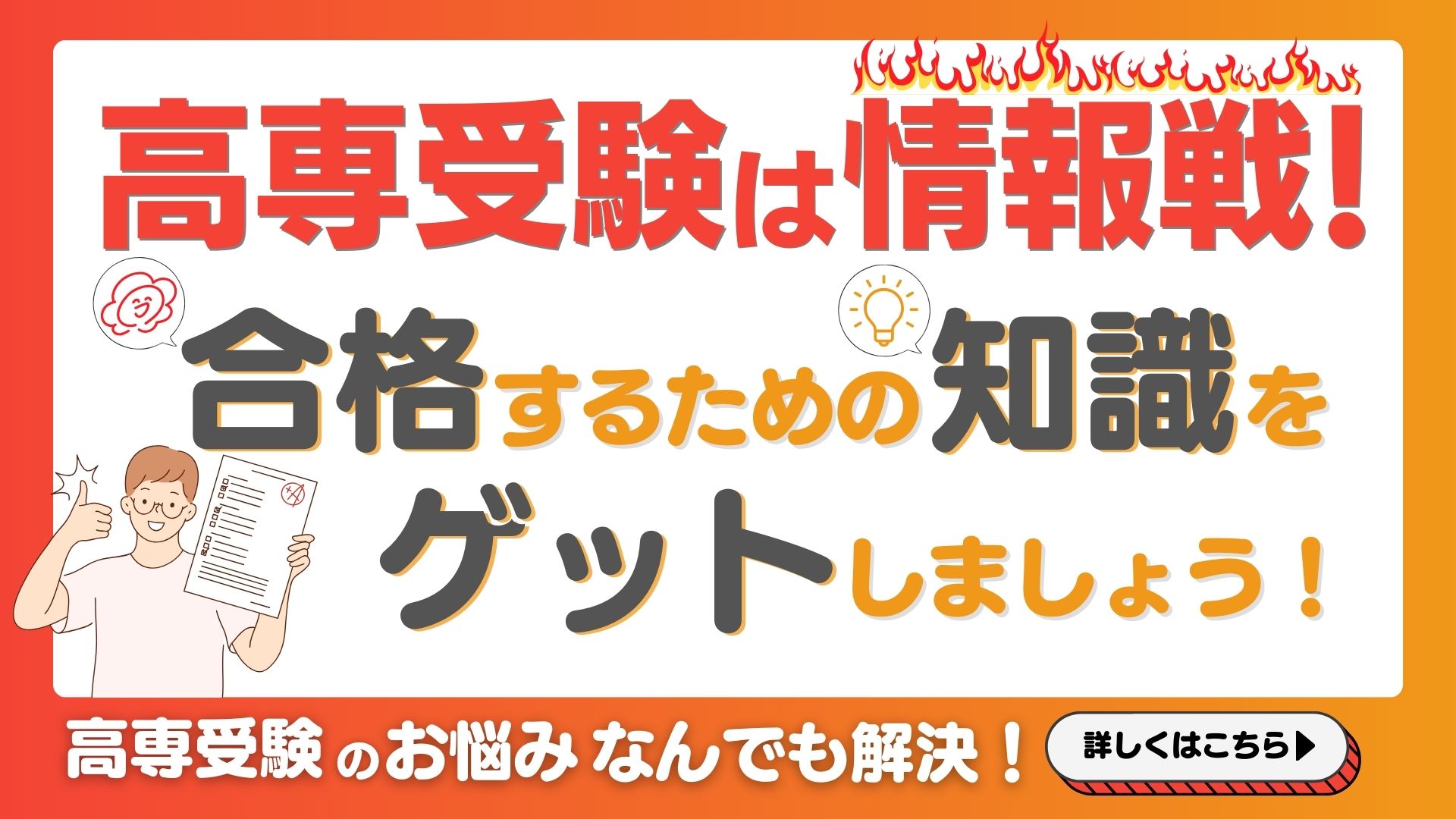
はじめに
10月は高専受験の分岐点です。まず募集要項を確認し、推薦条件、試験科目、傾斜配点を押さえましょう。つぎに推薦を狙う人は評定アップを最優先にし、定期テストの点と授業内の取り組みで評定を最大限に上げる努力をしましょう。同時に学力入試へ備え、上旬は基礎の抜けを短期で埋め、中旬以降は応用演習に移ります。過去問はまだ使わず、冬以降の仕上げの時期にに温存します。さらに高専模試を毎月受け、結果をみて弱点を判断し弱点を減らしていきましょう。
推薦は受かったらラッキーという考えを大切に、主戦場は学力で、配点と伸び幅に時間を集中させることが大事です!
募集要項を確認:推薦条件・科目・傾斜配点
募集要項を読まないと戦略が決まりません。理由は、推薦条件や受験科目、傾斜配点が高専ごとに異なるためです。推薦の評定基準が「3年間の合計」か「3年のみ」かで、今から伸ばせる余地が変わります。社会がない学校や、数学に倍率がかかる学校もあります。たとえば数学に2倍の傾斜がある場合、同じ10点でも合計点への影響は20点相当になります。
校名ごとの募集要項を必ずチェックしましょう。
推薦の評定基準と対象学年をチェック
推薦は「受けられるか」が出発点です。評定平均や、対象学年の扱いを確認しましょう。3年間合計なのか、3年のみなのかで、直近の定期テストの重みが変わります。評定はテスト点だけでなく、提出物や授業態度も含む総合評価です。いまから未提出をゼロにし、ノートやレポートを整えましょう。保護者の方は提出物の締切や持ち物を一緒に確認すると効果的です。担任や教科の先生に「評定を上げるための改善点を教えてください」と相談するのも有効です。まずは条件を満たすこと、それが推薦対策の第一歩です。
傾斜配点で決める科目の優先度
傾斜配点があると、優先科目は明確になります。倍率が高い科目へ学習時間を厚く配分することが求められます。理由は、同じ点差でも合計点への影響が大きくなるからです。具体例として、数学に2倍の傾斜があるなら、数学の10点上昇は20点分の価値になります。苦手でも配点が高ければ、まず基礎の穴を埋め、頻出の応用パターンに絞って伸ばします。週ごとに「傾斜×伸び幅」で学習時間を再配分し、結果を記録して微調整しましょう。こうした戦略設計は、冬以降の得点の伸びを左右します。
推薦対策は評定アップが最優先
推薦の合否は評定の比重が大きいです。10月の主なタスクは評定アップです。面接や小論文の配点は相対的に小さいことが多く、早い時期からの時間投資はコスパが低くなりがちです。まずは提出物の未提出をなくし、定期テストの目標点を教科別に決めます。実技科目は技能よりも準備と態度で得点源にできます。ただし評定を整える努力は、学力入試の土台にもなります。内申が安定すれば、直前期の心の余裕にもつながります。
定期テストの点を伸ばす勉強計画
テスト日程から逆算して準備します。7~10日前は基礎の暗記と基本問題を解きましょう。4~6日前は学校ワーク2周目でミス直しをし、2~3日前はテスト範囲の類題演習を集中的に行いましょう。前日は暗記カードと弱点ノートに絞り、英語は教科書本文の音読とディクテーションをするとよいです。理科は用語と法則を因果で覚え、計算は単位と式の型を統一します。国語は記述で「根拠→要点→接続語」を一連で練習します。当日はケアレスミス防止のチェックリストを使い、見直し時間を確保します。短いサイクルを繰り返せば、得点は積み上がります!
授業内アピールと提出物で評定を維持する
評定は授業で決まる場面が多いです。提出物は必ず期限内に提出しましょう。ノートは見出しと図解を入れて読みやすくします。実技は出席や課題を全力で行いましょう。先生への相談は「次回までに何を直せば評定が上がりますか」と具体的に聞くとよいです。保護者は提出物の管理を手伝うだけでも効果があります。毎週末に提出状況とテスト計画を確認しましょう。
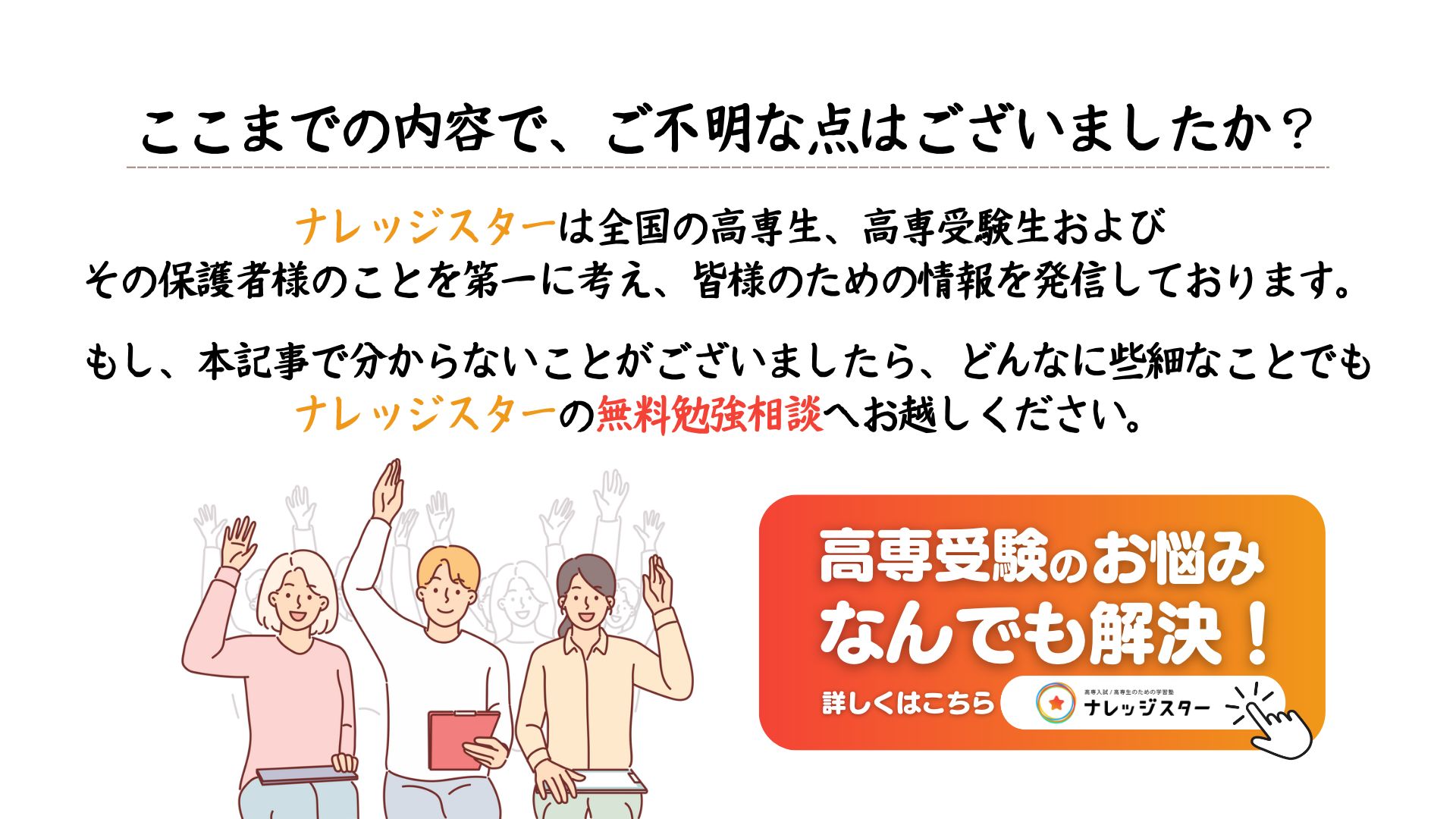
学力入試:基礎から応用演習へ
高専入試は思考力・応用力が求められる出題が多いと言われています。結論として、10月は応用力を育てる準備期間です。超基本だけでは合格点に届きにくいからです。上旬は数学・英語・理科の基礎を早めに仕上げましょう。基礎が終わったら、応用問題へ主軸を移しましょう。難しすぎると感じたら、レベルを一段下げた“簡単な応用”で橋渡しをします。基礎を短期で固め、応用に長く触れる時間を確保することが、合格点に最短で届く道です。
10月上旬は基礎の穴を短期で埋める
基礎は「覚えたつもり」の穴が危険です。チェックリストを作り、項目ごとに◯△×をつけましょう。数学は計算規則、関数、図形の公式を五秒で想起できる状態に。英語は時制、受動態、関係代名詞の型を例文で即答できるか確認します。理科は公式と単位、グラフの読み取りをセットで練習します。△と×だけ翌日に再演習し、72時間以内に再度復習し完璧にしあげましょう。暗記は朝と夜に分け、短時間で復習しましょう。
10月中旬以降は応用問題にシフト
応用は「基礎の組合せ」をできれば対応できます。数学は関数と平面・空間図形、場合の数と確率で差がつきます。英語は長文読解や穴埋めの文法問題が重要項目です。理科はエネルギー、電磁気、化学計算で計算プロセスを流れで覚えることが時間短縮につながります。
過去問は最終確認に温存する理由
過去問は最良の教材ですが、早期に使うと“初見力”が薄れます。模試や応用演習で土台を作ったあと、本番1〜2か月前に年度別で通し実施しましょう。時間を計り、設問タイプごとに弱点を特定し、参考書へ戻って再学習するのがよいです。過去問は「仕上げの検品」。温存することで、本番に近い手応えを得やすくなります。
高専模試の活用:毎月受けて教材化する
模試は合否判定を見るだけではもったいないです。模試を「自作過去問」として使うことも良いです。当日中の解き直し、翌日の2回目、週末の3回目で3週は行いましょう。毎月の模試と3周の復習で、応用の感覚が磨かれます。弱点が見えるので、学習時間の投資判断も明確です。
成績だけ見ない復習手順(3ステップ)
復習は①誤答の分類(計算ミス・知識欠落・選択ミス)、②頻出テーマの抽出、③型の再現練習の三段階です。分類で原因を特定し、抽出で同系統の問題を集め、再現で三問連続を解いて手順を固定します。3日以内の再演習で記憶が安定します。最後に「次の模試で試す行動」を1つ決めます。たとえば見直し時間の配分や、飛ばす問題の基準などです。小さな改善の積み上げが、翌月の伸びにつなげることが求められます。
10〜1月の学習ロードマップと科目配分
10月は基礎の総仕上げと応用への橋渡しを行いましょう。11月は応用演習の量と範囲を増やします。12月は弱点特化と時間配分を見つけ、1月以降は過去問で仕上げます。配点が高い数学は毎日触れ、英語は長文と文法を交互に回しましょう。理科は計算分野を優先し、用語は朝夜で短時間で回します。社会と国語は学校の進度に合わせ、短いサイクルで復習しましょう。週計画は「傾斜配点×自分の伸び幅」で重みづけし、日曜夜に見直すとよいです。無理のない計画が継続を支え、点の伸びを合計点につながります。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ:推薦はラッキー、勝負は学力
募集要項で条件と配点を確認し、推薦は評定アップを最優先にします。同時に学力入試へ向け、10月は基礎の総仕上げ、以降は応用演習を主軸にします。過去問は仕上げに温存し、高専模試を毎月の教材として解きましょう。推薦は受かったらラッキーという心構えで、学力で勝ち切る準備を重ねましょう。配点と伸び幅に時間を集中すれば、得点の伸びは合計点に直結します。今日から1週間の計画を作り、まずは実行です。
Q&A(よくある質問)
Q1. 応用が難しすぎて解説も分かりません。
A1. ワンランク下げた問題を何問か解き、応用に繋げることで徐々に理解できます。
Q2. 過去問はいつから始めればいいですか?
A2. 12月後半〜1月に年度別で本番同様に実施しましょう。
Q3. 面接や小論文は今やらなくて大丈夫?
A3. 評定比重が大きいので、まずは定期テストと授業内の取り組みを優先しましょう。直前期に要点だけ押さえれば十分です。
Q4. 模試で点が伸びません。
A4. 復習の三段階(分類→抽出→再現)を3日以内に時間以内に行いましょう。次回に試す行動を一つ決めると効果が見えます。
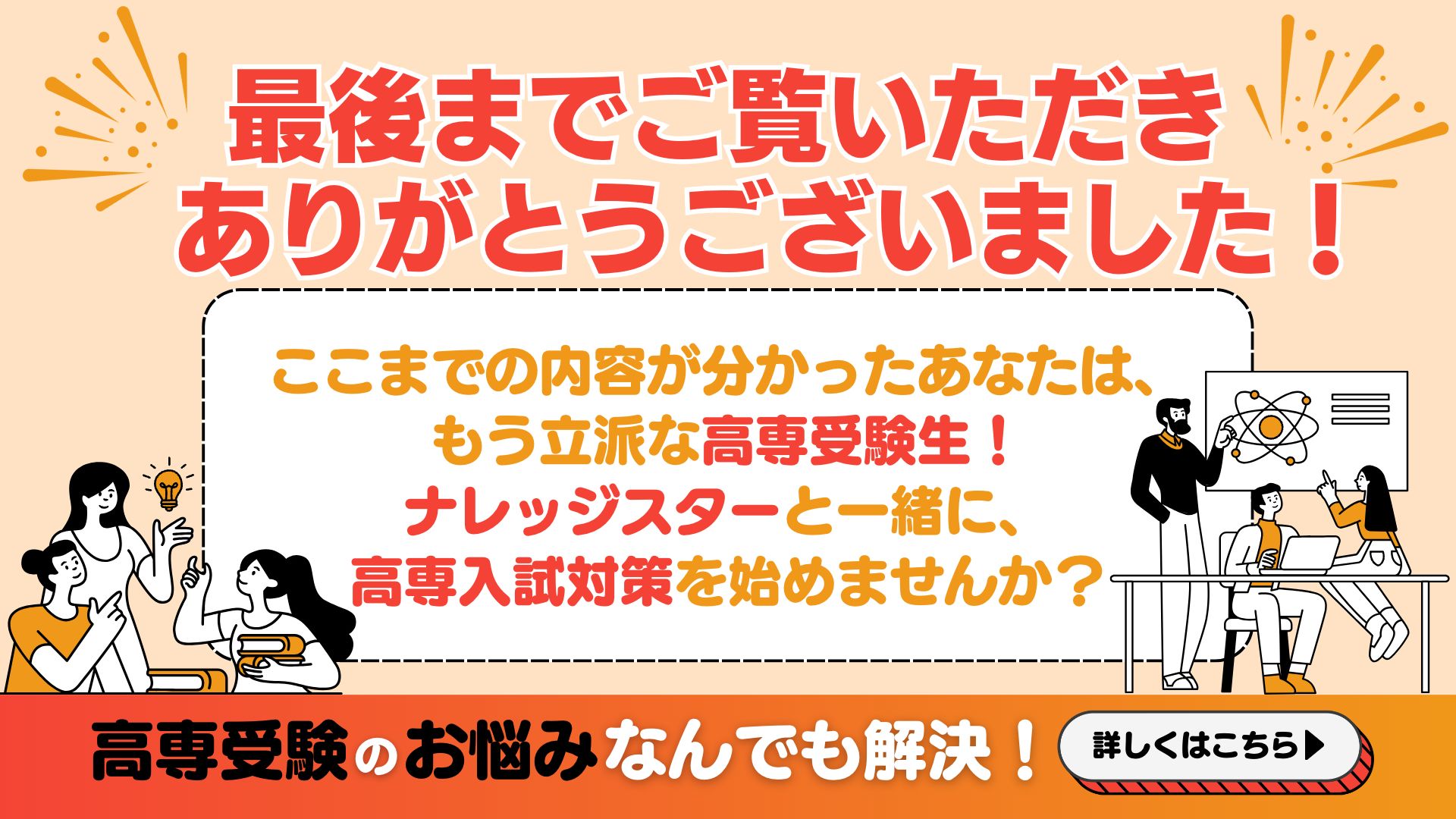
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。