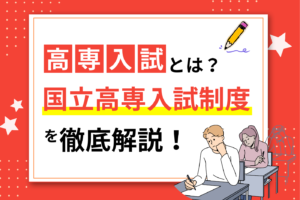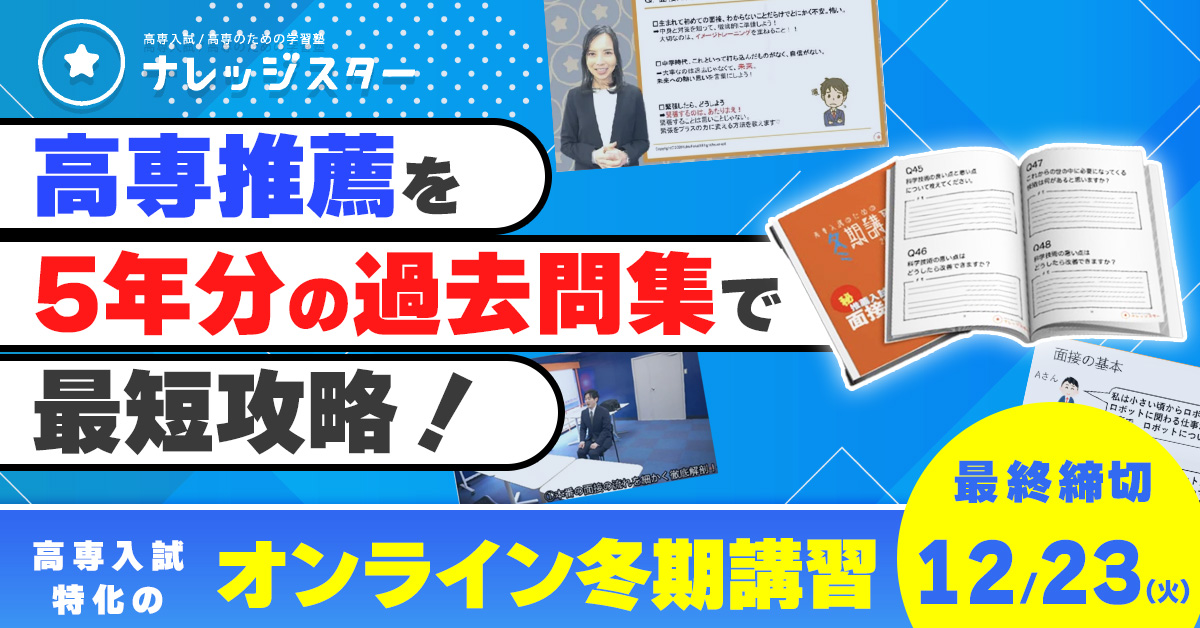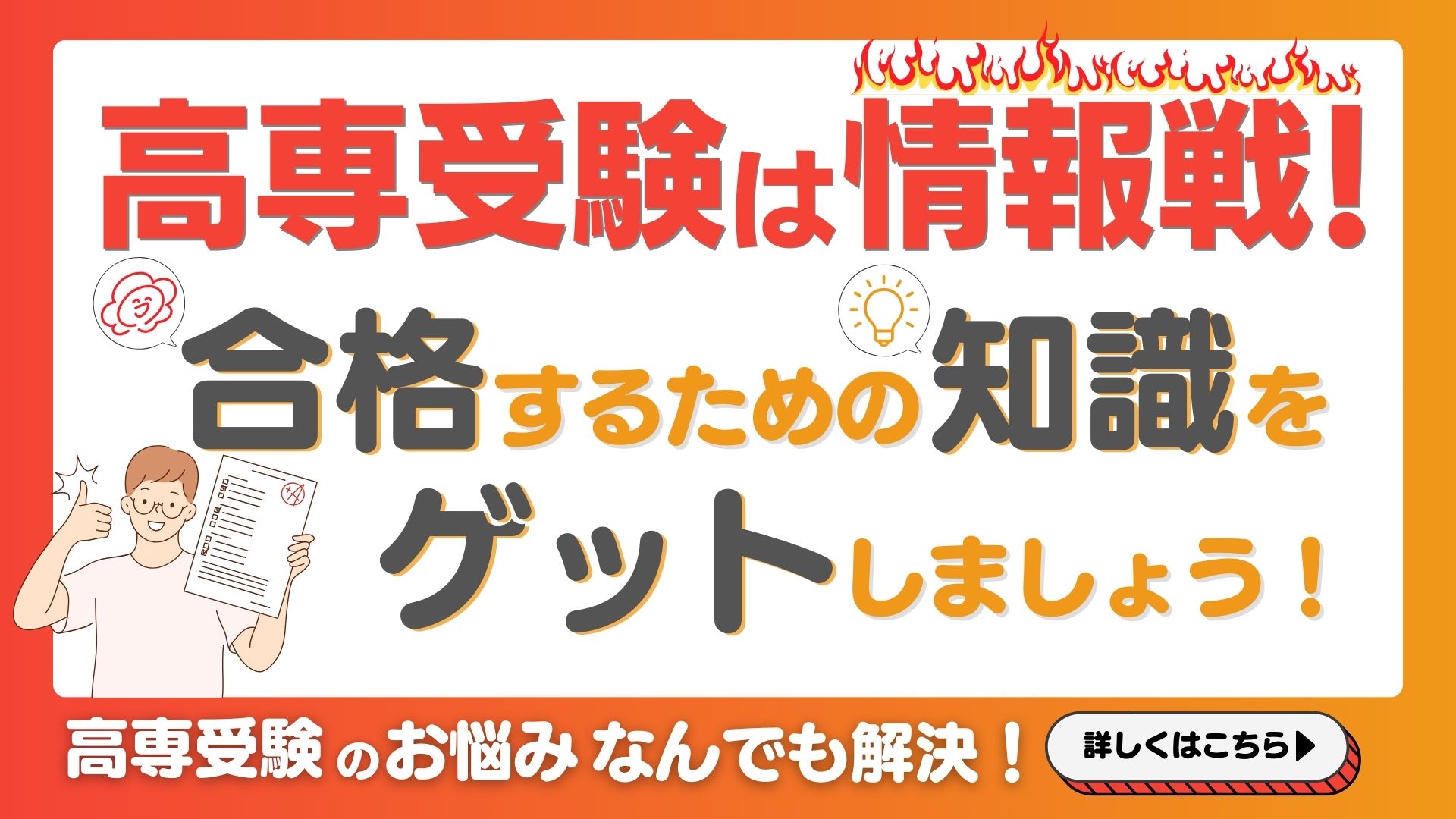
高専入学後にすること
高専に合格したあとも、入学までにやるべきことは意外と多くあります。まず最初に取りかかるのが入学手続き書類です。これは、入学を正式に確定させるために必要なもので、期限までに提出しなければ入学できなくなる場合もあります。内容は高専によって多少異なりますが、誓約書、健康診断書、写真、制服や教科書の注文書などが含まれることが多いです。提出期限や記入ミスに注意しながら、保護者の方と一緒に早めに準備を進めましょう。
次に大切なのが入学準備です。各高専によりますが、入学式までの期間に、制服や通学バッグ、ノートパソコン(学校指定の場合)などを揃えます。また、高専では中学よりもレポート提出やパソコンを使う機会が増えるため、基本的なタイピングやWord・Excelの操作に慣れておくとスムーズです。さらに、春休みのうちに中学の内容の復習をしておくと、新学期のスタートで慌てずにすみます。
高専の授業は中学の延長じゃない!
高専の授業は、中学の内容をそのまま続けるだけではありません。もちろん、中学で学んだ知識を基礎として活かす部分もありますが、それ以上にまったく新しい分野の勉強が一気に始まります。特に理系科目は専門的な内容が多く、高校よりも深く踏み込んだ学習を行うのが特徴です。
中でも注意したいのが数学です。高専では、わずか2年間で高校3年間分の数学を終えるカリキュラムになっており、授業の進むペースがとても速いです。中学のときに「なんとなく理解していた」範囲ではついていけなくなることもあります。
また、理科では物理や化学がより本格的になり、実験やレポートの量も増えます。さらに、専門分野の授業も早い段階から始まるため、入学後は新しい知識を吸収する毎日になります。
高専生活をスムーズにスタートさせるためには、「中学の延長」と思わず、新しい学びに挑戦する気持ちを持っておくことが大切です。
高専で重要になる中学の科目
数学
中学校の数学は、まず「解けるようになること」がゴールだと思いますが、高専では「なぜそうなるのか」「どんな場面で使うのか」までを理解する力が求められます。
特に高専の数学はスピードが速く、1〜2年のうちに高校3年分の内容を一気に終わらせます。中学のうちに、公式を暗記するだけでなく、グラフや図形を使って式の意味をイメージできるように練習すると良いです。
また、文章題では“何を求めるか”を自分で整理する力が大切です。解き方を覚えるのではなく、考え方の筋道を理解することを意識すると、高専の専門科目でも生きてきます。
英語
高専の英語は、「実践で使って理解する英語」が中心になります。授業では英語の長文読解やリスニングだけでなく、専門分野で使われる技術英語を学ぶ場面も出てきます。特に高学年の専門分野では、プログラミングや機器のマニュアルが英語で書かれていることが多く、英文を読み解く力が求められます。
また、レポートやプレゼンテーションを英語で行う機会もあり、「自分の考えを英語で伝える」スキルが必要になります。つまり、単語や文法の暗記に加えて、英語で考える力や発信する力も鍛えておくことが大切です。
英語が苦手だと感じている人は、完璧な文法を意識するよりも、「自分の知っている単語でとにかく伝える」練習から始めるのがポイントです。英語を“勉強するもの”としてではなく、“ツールとして使うもの”として慣れておくと、高専入学後の授業やレポートで大きなアドバンテージになります。
理科
理科は高専で最も重要な基礎のひとつです。中学では広く浅く学びますが、高専では特に物理と化学を深く掘り下げるようになります。たとえば、物理では力・電気・波動などの計算を本格的に扱い、化学では反応式やモル計算など、理論的に考える問題が中心になります。
中学の段階では、結果だけで終わらせず、「なぜそうなるのか?」を自分の言葉で説明できるようにするのが大切です。たとえば、電流が流れる理由や、物質が燃えるときの化学変化など、現象の原理をイメージできる力を養っておくと、高専の授業理解が格段に早くなります。
技術
高専では、技術の授業が専門科目の基礎になります。中学の技術で学ぶプログラミング、電気回路、ものづくりなどの経験が、入学後にそのまま活きます。高専では、「理論+実践」で学ぶことが特徴で、実際に回路を組んだり、プログラムで機械を動かしたりする授業があります。
中学のうちに、パソコン操作やタイピングなどの簡単な動作に慣れておくと、入学後の実習やレポート作成がスムーズに進みます。また、物を作るときに「なぜそう動くのか」「どうすればもっと良くできるか」を考える習慣をつけておくと、将来的に強い武器になります。
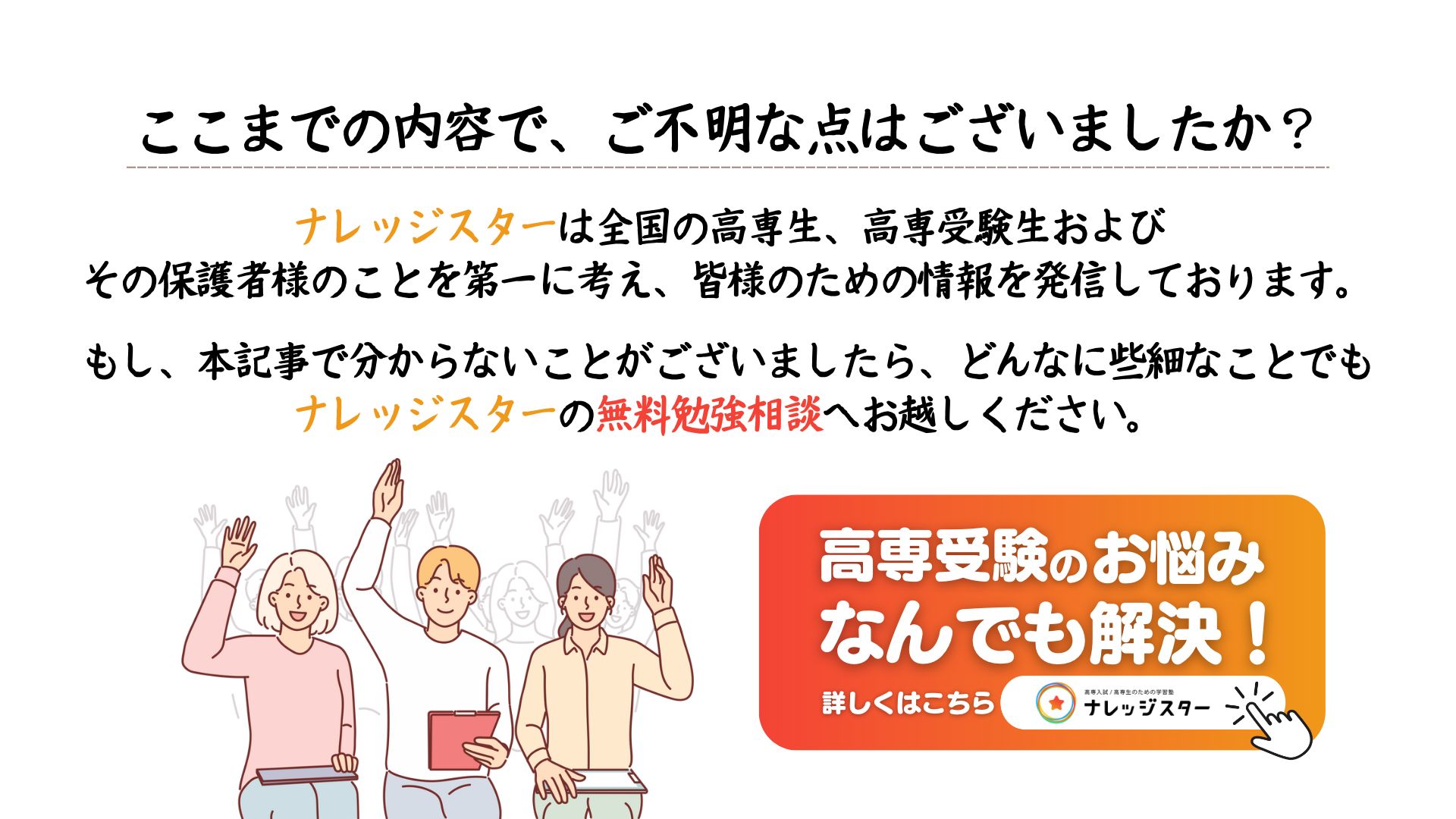
高専で特に重要な科目
高専では、中学や普通高校のように「国語・数学・英語」といった一般科目に加えて、学科ごとに異なる「専門科目」が多く学べるのが特徴です。その中でも、特に重要になるのが数学・化学・物理の3科目です。
これらの科目は、どの学科に進んでも専門科目の基礎として欠かせない存在です。
たとえば、数学は機械・電気・情報などあらゆる分野で使われ、計算だけでなく「理論を理解する力」や「論理的に考える力」にも直結します。化学は主に化学系や材料系で必要になりますが、電気や環境系でも反応や物質の性質を理解するうえで重要です。物理は特に機械・電気分野では欠かせず、力学やエネルギー、電磁気などの考え方を正確に理解していないと、専門の授業でつまずいてしまうこともあります。
一方で、専門科目は高専ならではの科目です。
学科によって学ぶ内容は異なり、たとえば
- 機械科…設計図の読み方や加工技術、力学の応用
- 電気科…回路設計や電子制御、プログラミング
- 建築科…建築設計や構造計算、CAD
- 化学科…有機・無機化学、分析実験、材料の特性研究
といったように、それぞれの専門に特化した知識を深めていきます。
このように、高専では「一般科目で学んだ理論を専門科目で応用する」ことが多く、どちらもおろそかにはできません。中学のうちから数学や理科の基礎をしっかり身につけておくと、入学後の理解スピードが格段に上がります。特に、公式を丸暗記ではなく“なぜそうなるのか”まで理解する姿勢が、高専では何より大切になります。
数学は「理解の深さ」が命
数学の勉強で大切なのは、「問題をたくさん解くこと」と「なぜそうなるのかを自分の言葉で説明できるくらい深く理解すること」です。
公式や解法を暗記するだけでは、少し形を変えただけの応用問題に対応できなくなってしまいます。表面だけを覚える勉強では、知識がつながらず、実力として定着しにくいのです。
一方で、原理や考え方の筋道を理解しておくと、見たことのない問題にも柔軟に対応できるようになります。問題文を読んだときに、「この式はあの考え方につながるな」と自然に結びつけられるようになると、数学が一気に楽しくなります。
つまり、真の数学力は「どれだけの問題を解いたか」ではなく、「どれだけ深く理解しているか」で決まります。
焦らずに一つひとつの考え方を丁寧にたどり、自分の中で納得しながら積み重ねていくことこそが、成績アップへの最短ルートです。
物理基礎から固める!
高専では、物理の基礎知識がそのまま専門科目に直結することが多いため、入学前から基礎をしっかり固めておくことがとても重要です。中学で学ぶ力学や電磁気、熱や光の基本原理は、高専の授業で扱うより高度な内容の土台となります。
数学と同様に、公式をただ覚えるだけではなく、なぜその公式が成り立つのか、どんな場面で使えるのかを理解しておくと、実験や応用問題にもスムーズに対応できます。実際、高専では公式や原理を組み合わせた複雑な問題が出題されることも多く、基礎が曖昧だと解くのが難しくなります。
そのため、中学の段階で理科・物理の基礎を復習し、公式や現象の意味をしっかり理解しておくことが、高専での学習をよりスムーズにするポイントです。基礎を固めておくことで、応用問題や実験にも自信を持って取り組めるようになります。
英会話で実践スキルを磨く
高専では、英語はただ文法や単語を覚えるだけではなく、実際に使えるスキルとして求められる場面が増えてきます。中学で学ぶ基本的な文法や単語力はもちろん大切ですが、それに加えて「聞く・話す」力を意識的に伸ばしておくと、高専での授業や実習でとても役立ちます。また、留学のサポートなどもあるのでより海外での実践英語を学ぶこともできます。
高専では、授業科目としてプレゼンテーションやグループディスカッションで英語を使うこともあるため、聞き取った内容に応答する練習も欠かせません。中学の段階で実践的な英語力を身につけておくと、入学後に授業や実習で戸惑うことが少なく、自信を持って取り組めるようになります。
専門科目
高専では、学科ごとに専門的な内容の授業が始まります。たとえば機械科なら機械工作や材料力学、電気科なら回路や電子工学、化学科なら化学実験や有機化学など、専門分野に直結する内容です。中学の勉強では扱わなかったような新しい知識や技術を学ぶため、最初は戸惑うことも多いかもしれません。
しかし、専門科目でも中学で習った基礎知識が大いに役立ちます。数学の計算力や理科の現象理解、技術・家庭科でのものづくりの経験は、授業をスムーズに理解する土台になります。中学でしっかり基礎を固めておくと、入学後の専門科目でも応用力を発揮しやすくなります。
また、専門科目は実験や演習が多く、グループで協力して取り組む場面も増えます。基礎がしっかりしていると、自分の考えを持って積極的に実験に参加できるようになり、学習効率も上がります。中学のうちから興味のある分野に触れ、簡単な工作や理科実験などを体験しておくと、高専での専門科目の理解がさらに深まります。
“苦手”を”できる”に変える工夫
中学のうちに苦手だと感じていた科目や分野も、高専では避けて通れないことがあります。しかし、ちょっとした工夫で苦手を「できる」に変えることは十分可能です。
まずは自分の苦手の原因をはっきりさせることが大切です。例えば「計算が遅い」「用語を覚えられない」「問題文の意味がわかりにくい」など、具体的に分けることで対策が立てやすくなります。
また、苦手科目は一度に全部を克服しようとせず、少しずつ小さな目標を立てて取り組むことも効果的です。1日1つの問題集の章を理解する、1週間で1つの単元をマスターするなど、段階的に進めることで無理なく力を伸ばせます。
さらに、分からないところは恥ずかしがらずに先生や友達に質問する習慣も重要です。早めに疑問を解消することで、苦手意識を持ち越さずに済み、学習効率も上がります。中学のうちからこうした工夫を意識しておくと、高専入学後に「苦手だった科目が得意科目に変わる」ことも珍しくありません。
今からできる準備のコツ
中学生のうちから高専入学後の学びを意識して準備することは、とても大きな意味があります。ここで大切なのは、科目ごとの知識や技能だけでなく、学ぶ姿勢や気持ちの持ち方を意識することです。
わからないことや難しい課題に直面したとき、ただ暗記するのではなく、理解しようという前向きな気持ちで取り組むことが大切です。理解を深めようと努力する過程で、自分の考え方を整理し、学ぶこと自体を楽しむ力が自然と身についていきます。
また、学習を進める中で自分の成長を意識することもポイントです。小さな達成や理解できた瞬間を大切にし、学習の積み重ねを楽しむ姿勢は、高専に入ってからの応用力や探求心につながります。
さらに、学習に対して主体的に取り組む姿勢を持つことで、苦手な分野や難しい内容にも前向きに挑戦できるようになります。中学の段階でこうした学び方や考え方の習慣を身につけておくと、高専の授業のスピードや専門性に追いつきやすくなり、学ぶこと自体をより楽しめるようになります。
知識や技能の準備だけでなく、学ぶ心構えや姿勢を整えることが、中学生のうちにできる最も大きな準備と言えるでしょう。
基礎を大切にする人ほど高専で伸びる
高専では、専門的な学習が一気に増えるため、基礎がしっかりしているかどうかが学びや理解のスピードに大きく影響します。中学の段階で身につけた基礎知識や学習習慣は、入学後の授業内容を理解する土台となり、応用力や考察力を伸ばすための支えになります。
基礎を軽視して進めてしまうと、応用問題や専門科目の学習でつまずきやすくなります。一方で、時間をかけて基礎を確実に固めておくと、新しい内容や高度な問題に直面したときでも、理解が早くなり、より深く考える力が育ちます。
大切なのは、基礎を単に覚えるだけでなく、理解し、自分のものにすることです。この姿勢を中学のうちから意識しておくことで、高専入学後に焦らず学習を進めることができ、結果的に着実に成長していくことができます。
まとめ
中学での学習は、高専での授業をスムーズに進めるための土台になります。特に数学や理科、英語、技術などの基礎をしっかり身につけておくことが、高専での理解力や応用力につながります。また、授業のスピードや内容は中学の延長ではなく一気に専門的になるため、早めの準備や基礎の定着が大切です。
中学のうちに基礎を意識して学ぶ姿勢や、苦手を克服するための工夫を身につけておくことで、高専に入ってから焦らず学習を進められます。日々の勉強を大切にし、少しずつ理解を積み重ねることが、将来の成長につながります。
中学生の皆さんも、基礎を軽視せず、自分のペースで確実に学習を進めることを意識してみてください。それが高専での学びをより充実させ、実力を伸ばす近道になります。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
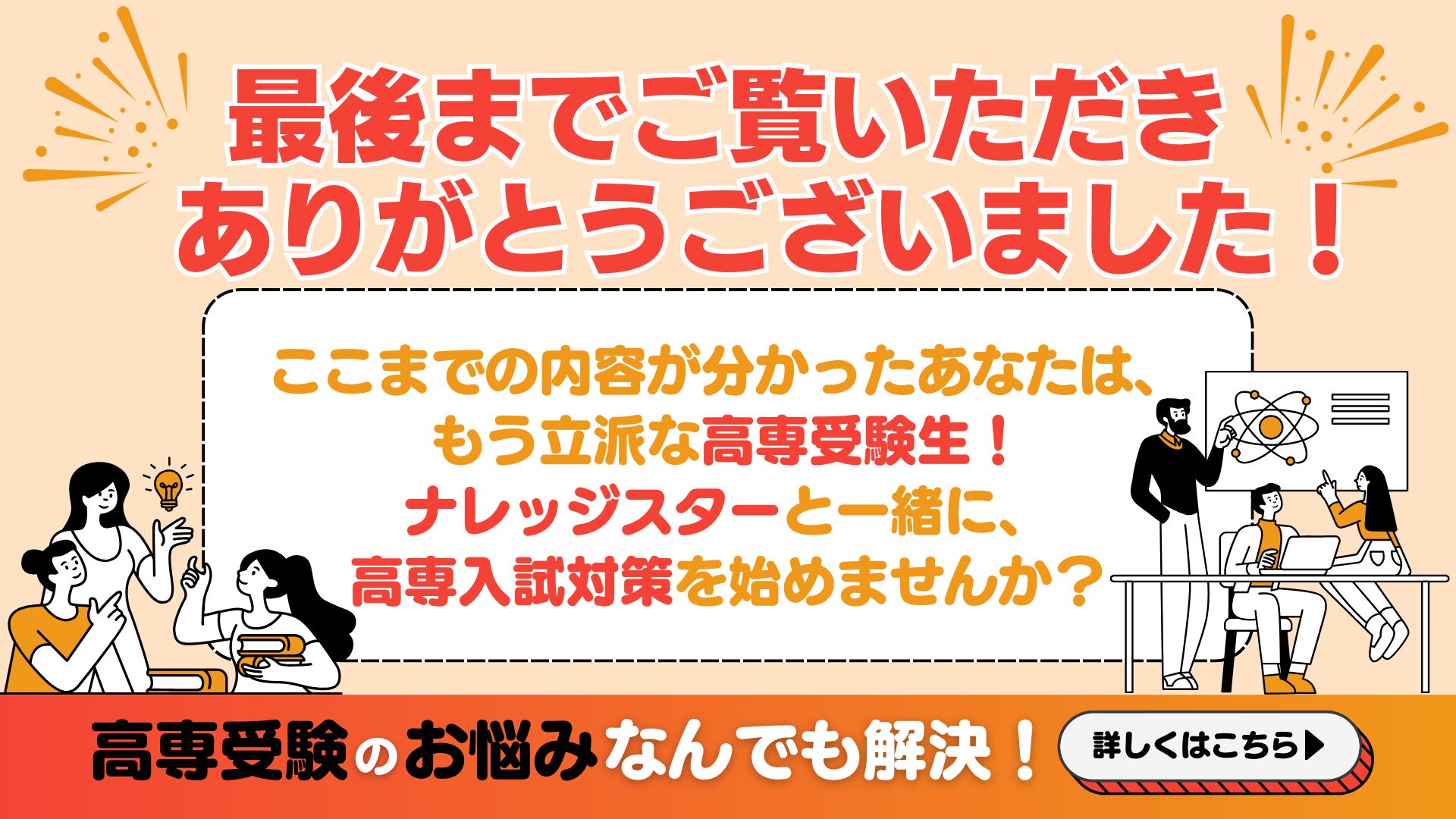
——————‐—————–‐————–‐————–‐
ライター情報
所属高専:大阪公立大学工業高等専門学校
学科:総合工学システム学科 エレクトロニクスコース
氏名:大原佳蓮
ニックネーム:かれん
自己紹介:高専3年生のひよっこライター。特技は人前で緊張せず話せること。高専のことについて皆さんが知りたい有益な情報などを調査・勉強中です。