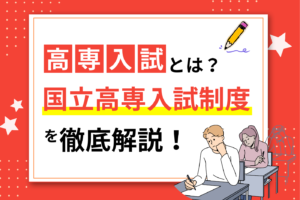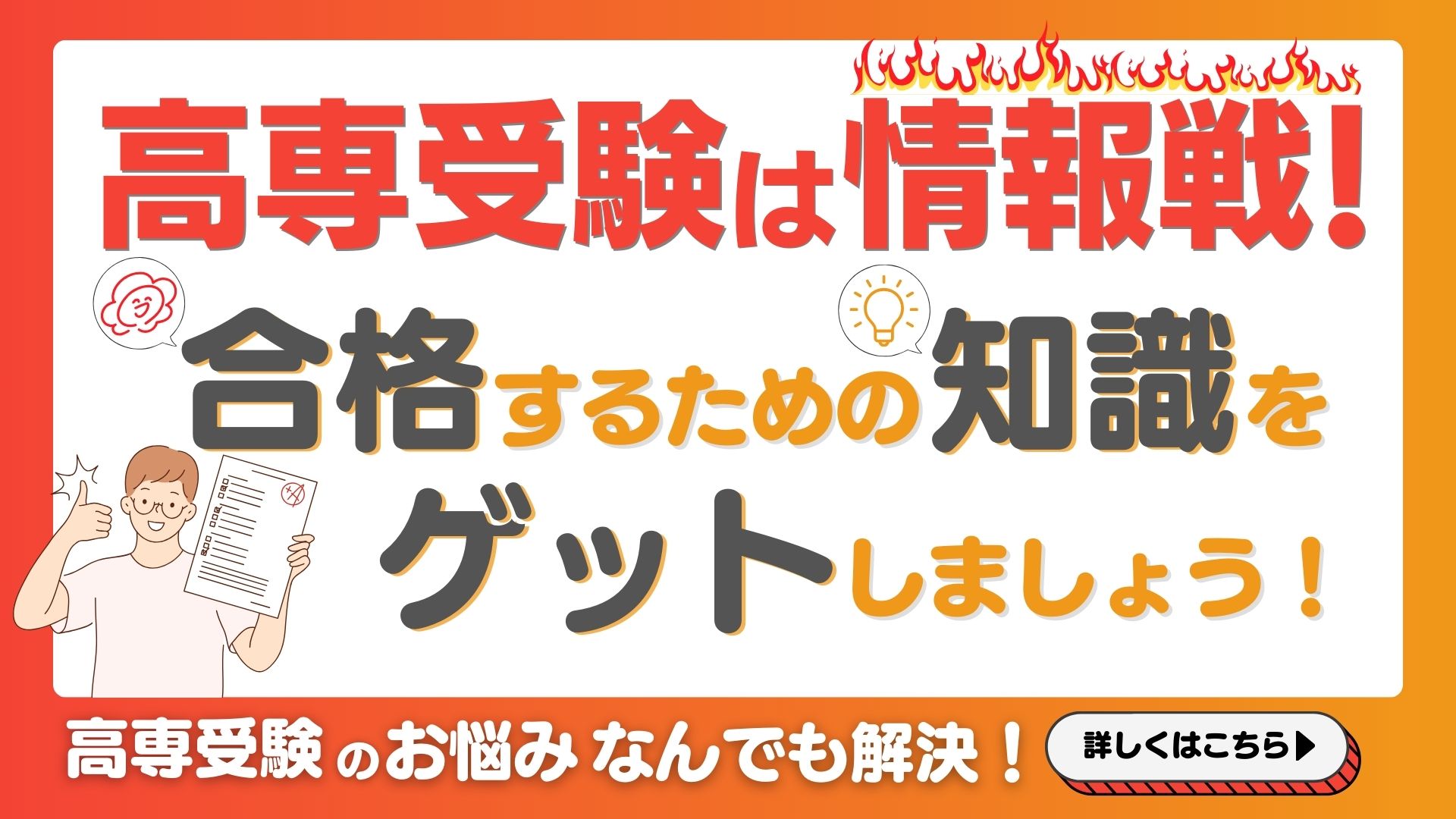
はじめに
高等専門学校(高専)は、高校の代替となるわけではなく、未来の技術者を目指す学生にとって、専門知識と実践的スキルを5年間の一貫教育で身につけるための最短ルートになります。しかし、その門をくぐるための入学試験は、一般的な高校入試とは大きく違う独自のシステムであり、特化した対策を行うことが不可欠です。
この記事では、高専入試の全体像を解き明かし、受験生が合格を勝ち取るために、入試の種類から、科目別の詳細な学習法、面接での効果的な自己アピール術に至るまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。
高専入試の種類とそれぞれの概要
高専への入学ルートは、「推薦選抜」「学力選抜」の2つが代表的です。自身の強みと中学校での実績などから、どちらのルートが最適かを見極めましょう。
推薦選抜
推薦選抜は一回の学力試験の結果だけでなく、主に中学校生活全体を通じた継続的な学習態度と成果を評価する選抜方法です。
推薦選抜に出願するためには、在籍する中学校長の推薦書が必要となります 。そして、多くの高専では出願の際に調査書の基準を設けており、これは5段階評価で平均4.0以上ととても高い壁になっています。高専の推薦選抜は例年1月中旬ごろに実施され、入学定員の40~50%が決定される高専も少なくありません。
推薦選抜の評価の対象となるのは、調査書、推薦書、そして個人面接が基本です 。高専によっては、これに加えて作文や小論文、数学・理科・英語などの基礎学力を問う適性検査、さらには協調性を評価するためのグループワークが課されることもあります 。
もちろん、高専によって出願基準や評価方法は異なるので、志望高専の公式サイトなどで情報をしっかり集めましょう!
学力選抜
学力選抜は、2月中旬ごろに行われ、ペーパーテストを通じた純粋な学力で合否を審査します。
国立高専では、独立行政法人国立高等専門学校機構が作成する全国統一問題によって、同日一斉に実施されます 。試験形式は、すべての科目でマークシート方式が採用されており、記述式の問題は一切ありません。
試験科目は、国語、社会、数学、理科、英語(リスニング問題を含む)の5教科が基本で、一部の高専では社会が実施されない高専もあります。この中でも、数学や理科は一般的な高校よりも問題の難易度が格段に高いうえ、「傾斜配点」がつけられ、点数が1.5倍や2倍に換算されて計算される高専も多いので、これらの科目は重点的に対策する必要があります。
合否は、学力試験の点数だけでなく、中学校から提出される調査書の内申点が点数化され、学力試験の得点に加算された「総合点」で最終的な順位が決定されます 。
高専によってテストの形式や合否判定の基準は大きく異なるので、志望高専の公式サイトなどで情報をしっかりと集めるようにしましょう!
一般的な高校入試との違い
高専入試は一般的な高校入試とは求められる能力などが大きく異なるため、その違いを理解することが、正しい対策への第一歩となります。
①入試日程が早い
推薦選抜は1月、学力選抜は2月と、公立高校入試(3月上旬)より1〜2か月程早く入試が実施されるので、周りの雰囲気に流されず、学習計画を前倒しにして進める必要があります。
②理数科目が重視されている
5教科のバランスが求められる一般的な高校入試とは対照的に、高専では理科・数学が重視されており、問題の難易度がとても高いうえ、傾斜配点によって全体のなかでも特別大きな比重で評価されます。
③情報の希少性:
全中学生のうち、高専の受験者は約1.6%ととても少ないため、一般的な学習塾や中学校の先生でさえ、高専入試の詳細な情報を持っていないケースが少なくありません 。受験生自身が主体的に情報を収集し、対策を講じる必要があります。
高専入試で問われる「3つの力」
将来、技術者として社会で活躍するための資質を見極めることを目的としており、大きく「基礎学力」「専門分野への適性」「人間性」という3つの力を見極めるための試験を実施しています。
これらの「力」がどんなものなのか、本章では解説していきます。
基礎学力:特に理数科目の深い理解力
高専では、知識の量より「深さ」と「応用力」がもとめられ、公式を暗記しているだけでは到底太刀打ちできないような難しい問題が出題されます。
学力試験の特に数学では、複数の単元の知識を融合させて解く複雑な関数や図形問題が出題されたり、理科では、物理の力学や電気、化学の化学反応に関する計算問題など、実験のプロセスを理解し、科学的原理に基づいて思考する力が試されます 。
推薦選抜でも、この力は厳しくチェックされます。面接時に行われる口頭試問や適性検査では、科学法則の原理を説明させたり、その場で簡単な論理問題を解かせたりといった形で、「深さ」と「応用力」が問われます。
専門分野への適性:モノづくりへの興味や探究心
高専は、テクノロジーや「モノづくり」が好きで、本気で学びたい学生を求めています。その分野で学び続けるための「適性」が重要視されます。
面接では、「なぜ普通の高校ではなく高専なのか」「なぜこの学科を選んだのか」「将来、高専で学んだ技術を活かして何をしたいか」といった質問が展開され「適性」を審査されます 。
プログラミングで簡単なゲームを作った経験、ロボットコンテストへの挑戦など、自らの手と頭を動かした体験を語って、「適性」をアピールすることが合格への近道です!
また、各高専が公開している「アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)」を読み込むことも重要です!
人間性:面接や調査書で見られるポイント
5年間の高専生活では、寮生活やグループでの研究など、他者と協働し、困難を乗り越えていくための「人間性」も評価項目となります。
面接では、その受け答えを通じてコミュニケーション能力、論理的思考力、そして積極性などが評価されます 。それに加えて予期せぬ質問への対応や、話を聞く姿勢、マナーといった非言語的な側面も評価されるため、徹底的に面接練習を行うことが重要です 。
また、調査書に書いてある、出欠状況、部活動や生徒会活動の記録、そして先生からの所見など、「成績以外の情報」からも「人間性」を評価されます。
中学での生活にも全力で取り組み、「人間性」をアピールするための土台造りが高専入試合格のためには重要です。
高専入試の必勝対策!
高専入試の仕組みを理解したところで、次はどうやって高専入試に挑めばいいのか、対策方法を解説します!
過去問を制する者は入試を制す!傾向と対策
国立高専の学力選抜は問題が全国で統一されているため、傾向から対策が立てやすくなっています。そのため、過去問を調べ、繰り返し演習することこそが合格への鍵です。高専入試の過去問は、単なる知識の暗記力を問うものではなく、長い問題文や複雑な条件を正確に読み解き、応用する力を試す問題が多く、スピードと正確性の両方が求められます 。
科目別出題傾向の分析
- 数学: 最重要科目です。
大問1は配点40点を占める小問集合で、幅広い単元から出題されます。
大問2から4は、関数、平面・空間図形、規則性などをテーマとした応用問題で構成され、設問が進むにつれて難易度が急激に上昇します 。
単純な公式の暗記では歯が立たず、論理的な思考力が問われます。 - 理科: 物理(力学、運動、電気)と化学(化学反応式、濃度計算)の分野からの出題が中心です 。
実験器具の操作や結果の考察など、実験に基づいた問題が多く、現象の根本原理を理解しているかが問われます 。 - 英語: 長文読解問題が非常に大きなウェイトを占めます 。
200語を超える長文も珍しくなく、速読速解能力が必須です。
文法や語彙も、長文の文脈の中でその知識を正しく使えるかが試されます。 - 国語: 小説などの文学的文章は少なく、科学技術や社会問題をテーマとした論理的・説明的な文章(評論文・説明文)が中心です 。筆者の主張や論理の展開を正確に捉える読解力が求められます。
- 社会: 地理・歴史・公民からバランス良く出題されます。単に用語を覚えるだけでなく、統計資料やグラフ、地図を読み解く問題や、歴史的な出来事の因果関係を問う問題が多く、知識のつながりを意識した学習が不可欠です 。
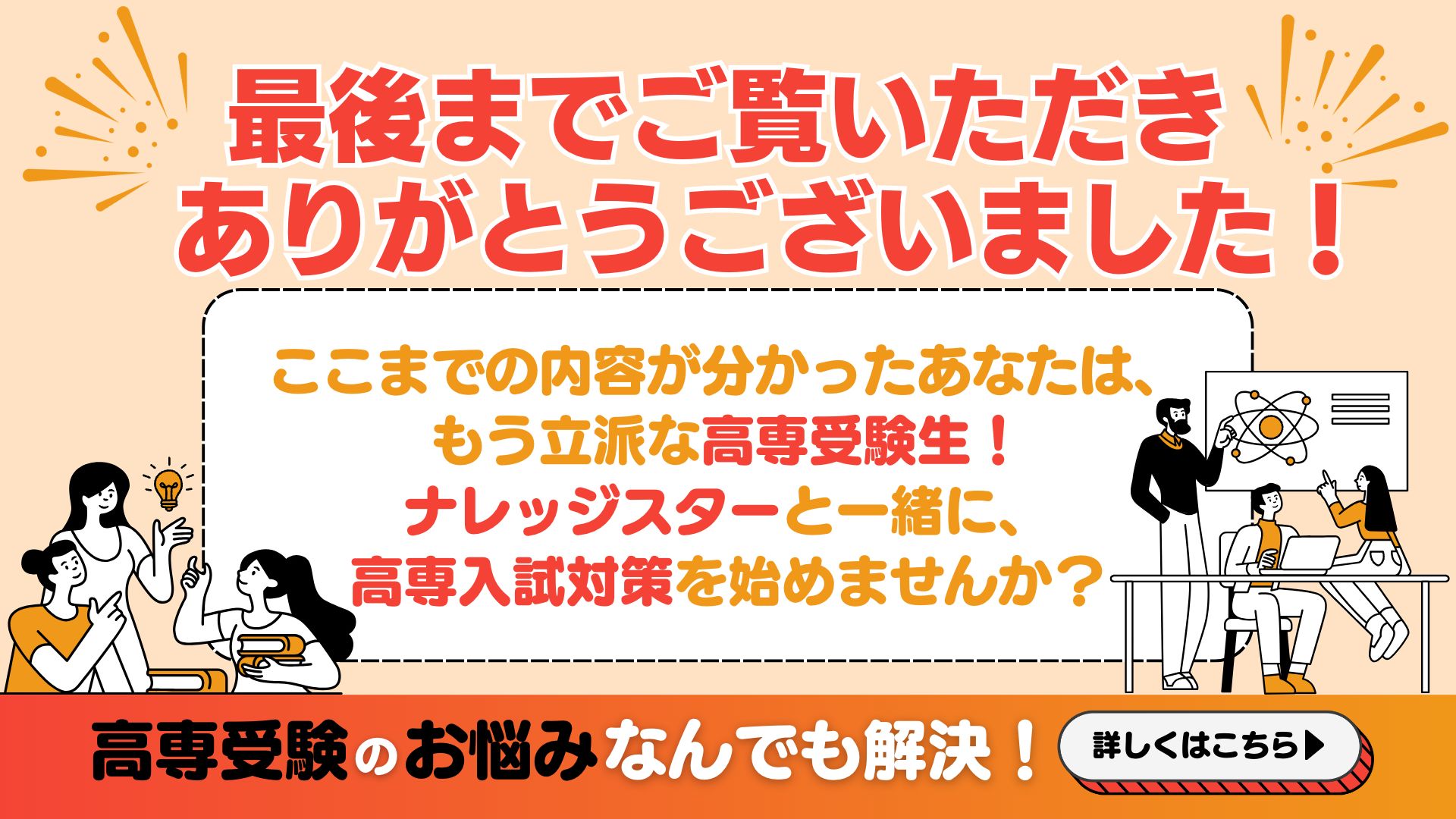
面接・口頭試問対策で論理的思考力をアピール
面接は、ペーパーテストでは測れない「専門分野への適性」と「人間性」を評価されます。暗記した答えを棒読みするのではなく、自分の言葉で、論理的に情熱を伝えましょう。
よく聞かれる面接の質問
- 志望動機に関する質問:
「なぜ高専か」「なぜこの学科か」「将来の夢は」などです 。自身の具体的な体験(例:ロボット製作の経験)と、学科で学びたいこと、そして将来の目標を一貫したストーリーとして語りましょう。 - 自己分析に関する質問:
「長所と短所」「中学校で頑張ったこと」など 。短所を述べる際は、それを克服するためにどう努力しているかを付け加えるなど、前向きな姿勢を示して自己アピールに繋げましょう。 - 学力・知識を問う質問(口頭試問):
「ボイルの法則を説明しなさい」「家庭用電源の仕組みは」「二次関数の応用問題を解いて説明してください」など、理数科目の基礎的な理解度を問われます 。 問題を解けるかだけでなく、それをわかりやすく伝える能力があるか否かが問われるので、しっかりと人に伝える練習を重ねましょう。 - 社会性・時事問題に関する質問:
「最近気になったニュースは」「SDGsについてどう思うか」など、社会への関心度や自分なりの考えを持つ力が試されます 。 自身の志望動機とつながるトピックを話せるとより高評価になりやすいです。
面接の対策では、ありきたりな答えではなく、「小学校の自由研究で〇〇を作った経験から、建築技術に興味を持ちました」のように、具体的なエピソードを準備しておくことが重要です 。学校や塾の先生に協力してもらい、模擬面接を繰り返し行うことで、本番の緊張にも対応できるようになります。
高専入試に関するよくある質問
ここでは、受験生や保護者から寄せられることの多い質問に回答していきます。
内申点はどのくらい必要ですか?
必要な内申点は、選抜方法と志望校の難易度によって大きく異なります。
推薦選抜の場合、一般的な目標ラインは「9教科の3年間合計評定が135点満点中108点以上(平均4.0以上)」です。 また、久留米高専のように「中学2・3年の9教科合計が77点以上」といった独自の基準を設けている場合もあるため、募集要項をしっかり確認しましょう
学力選抜の場合は出願要件として評定については明記がありませんが、3年間の9教科の評定平均が3.5~4.0以上あれば試験で大きくマイナスになることは少ないです。
上記の評定を目標に、日頃の学校での学習にも力を入れることが重要です。
推薦と学力の併願は可能ですか?
可能です。一部の高専では推薦選抜に不合格になった場合自動的に学力試験にも出願できるシステムになっていることもあるので、募集要項をしっかりと確認しましょう。
試験当日の服装や持ち物で気をつけることは?
服装
中学校の制服がある場合は、制服を着用しましょう。制服がない場合は、清潔感のある落ち着いた私服が望ましいです。また、試験室は換気のために窓を開けることがあるため、体温調節がしやすいように上着などを持参すると良いでしょう 。 必須の持ち物については、以下のリストを参考にしてください。
持ち物リスト
- 受験票
- HBの黒鉛筆(複数本)、プラスチック製消しゴム(カバーは外す)、鉛筆削り(電動式は不可) ※シャープペンシルは不可の場合が多いです。
- 学生証などの身分証明書
- 昼食、飲み物
- 腕時計(計算機能などのないシンプルなもの)
学科の選び方がわかりません。
自己分析→情報収集→体験の手順で考えてみましょう。
まず自己分析として自分が本当に好きな科目や熱中できること、興味のある仕事などを書き出してみましょう。そして、各高専の学科や授業内容などから、本当に好きなことについて知識や経験を深めることができるのかを調べましょう。最後にオープンキャンパスなどのイベントに参加し、実際に先輩や先生の話を聞き、授業などを体験しながら自分のイメージと相違がないかを確認し、見極めましょう。また、一部の高専では、入学後の1年間は共通の基礎科目を学び、2年生に進学するタイミングで本人の希望と成績に応じて学科を決めるような制度になっているため、どうしても決断できない場合はそういった高専も選択肢になります。
まとめ
ここまでで、高専入試を受けるために必要な情報について解説しました。高専入試のこれらの情報を知ることは、入試突破の第一歩となります。 是非、これらのポイントを参考にして、自分に合った対策を行い、合格をつかみましょう!
高専塾ナレッジスターでは、現在の成績や高専入試、入学後の不安・悩みを無料で相談できます。無理な勧誘は一切いたしませんので、ぜひお気軽にご相談ください!
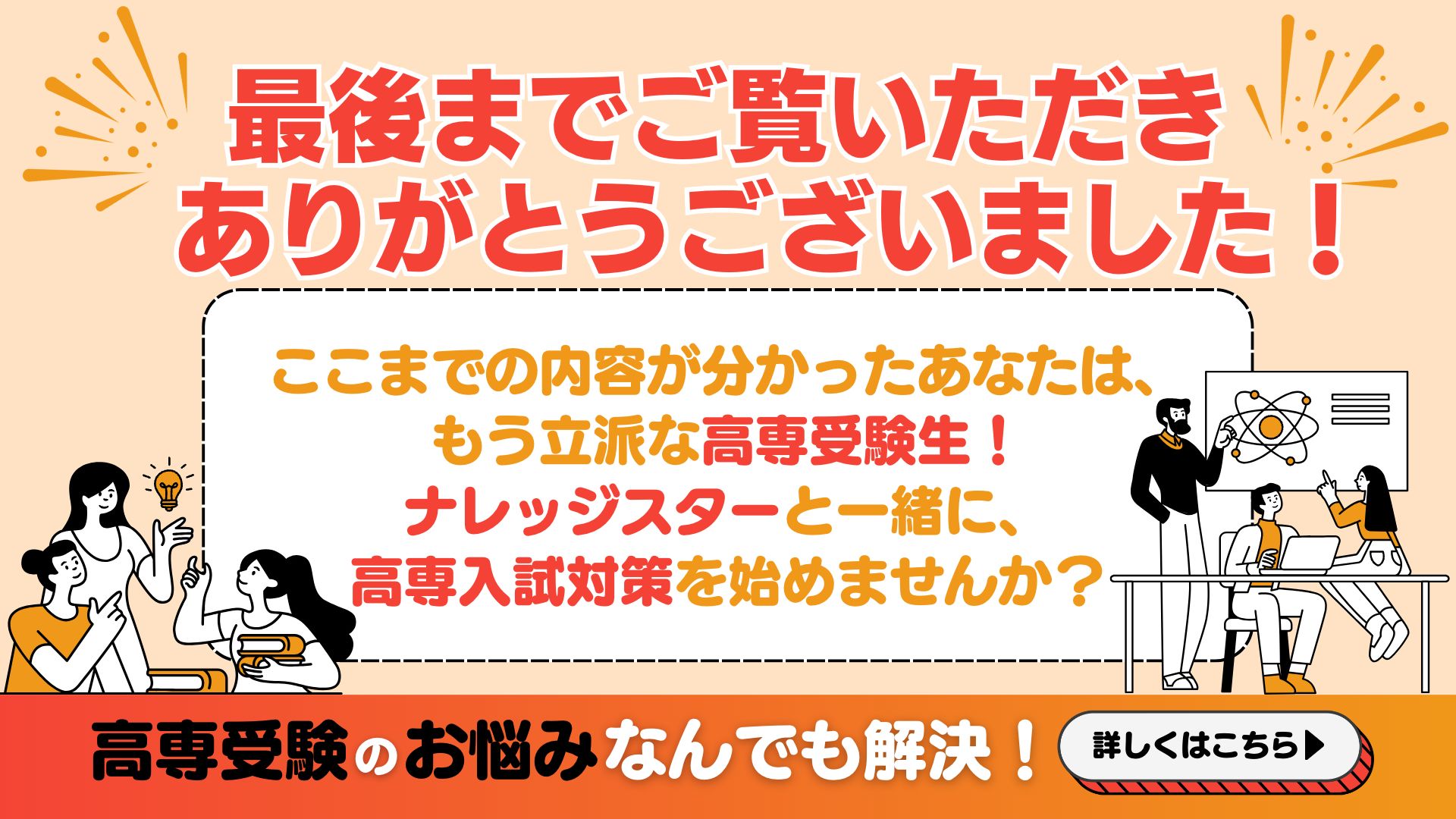
執筆者情報
[出身高専 学科] 佐世保高専電気電子工学科 卒業
筑波大学在学中
[氏名] 山下立仁
[自己紹介] ナレッジスター塾講師。佐世保高専では電気電子工学をまなび、現在筑波大学で1年生から学び直し中。趣味はダーツ。