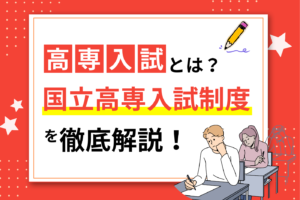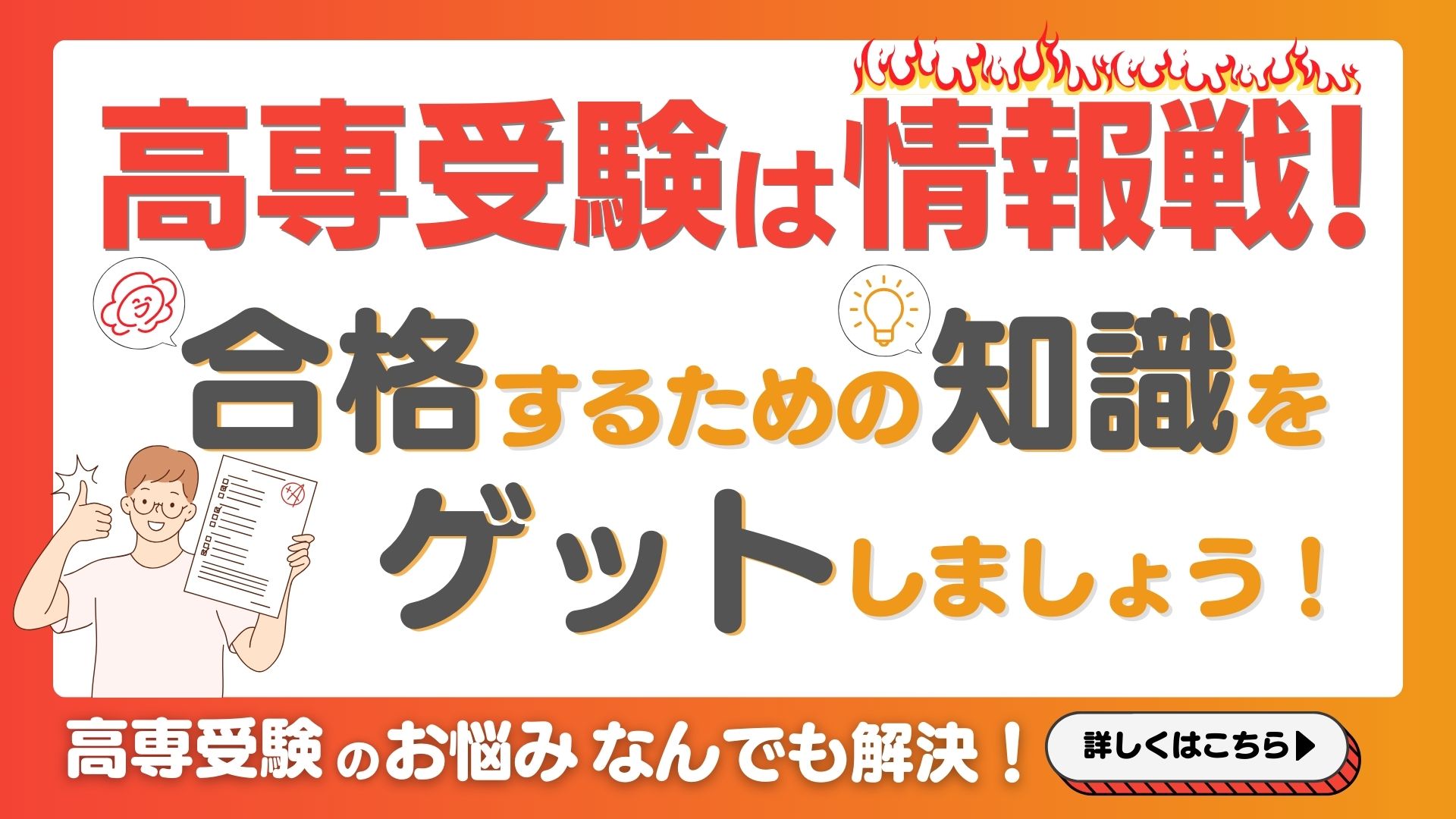
実データで判明!高専に受かる人の11月の勉強時間
「今の勉強量でほんとうに受かるのかな…」と不安になりやすいのが11月です。昨年、ナレッジスターが11月に実施した高専模試のアンケートを取ったところ、受験生全体の平均が1日2.8時間、合格した子の平均が1日3.4時間でした。差はたった0.6時間、つまり36分です。けれども、この36分が100日たまると約60時間になります。60時間あれば、数学の苦手分野を1周し直したり、理科の暗記を一気に仕上げたりできます。ですから「3.4時間もやらないとダメなの?」ではなく「+36分を足せば合格者のラインに近づく」と考えてOKです。
まずは数字で見て安心しよう(2.8時間と3.4時間)
2.8時間という数字を見て「思ったより少ない」と感じた人もいると思います。平日でこれくらいできていれば、中学3年生としてはがんばっているほうです。それでも合格者は3.4時間でした。これは「ものすごく長時間勉強していた」というより、日常のどこかに30分~40分の時間を上乗せしていた、というイメージです。たとえば学校から帰ってすぐに30分、夕食後に90分、寝る前に30分で合計150分。ここに朝の15分、休み時間の10分を足すと3時間を軽く超えます。こま切れでも合格者の時間になる、というのが今回のポイントです。
なぜ11月にスピードを上げると強いのか
季節の変化で体が重くなったり、模試の結果が出て気持ちが下がったりしやすいからです。ここで手をゆるめると、12月に「やばい!」となって一気に勉強時間を増やすことになります。ところが12月~1月は周りもがんばるので、そこで増やしても差になりにくいんですね。だから、周りがまだ本気になっていない11月に、先に1日3.4時間のペースをつくっておくことが大事です。冬休みや直前講座は「質を上げる場」なので、いまのうちに「量」を整えておくと吸収が早くなります。
合格者は「たった36分」積み上げていた
合格した子が特別なことをしていたわけではありません。やっていたのは「ゼロの日をつくらない」ことと「あと1問」を毎日つけ足すことです。動画の中でも「0分と5分は全然ちがう」と強調していました。机に5分座れた日は、そのまま30分・60分と伸ばしやすいからです。逆にゼロの日があると、その次の日もゼロになりやすく、入試までの総勉強時間が一気に減ってしまいます。「今日は英単語10個だけ」「ワーク1ページだけ」でいいので、机に向かうきっかけをつくりましょう。
36分×100日=60時間になる仕組み
入試まであと100日あるとすると、36分の差は3,600分、つまり60時間です。これは数学なら大問レベルの対策がいくつもできる量ですし、理科なら物理分野をまるごとやり直せる量です。この「60時間分の追加練習」があったからこそ、合格した子は得点を安定させられたと考えられます。60時間を最後の1か月で取るのは大変ですが、100日に分ければ1日36分で済みます。
ゼロの日をつくらないための小さな工夫
ゼロを防ぐには「勉強前にスマホを触らない」「帰宅したらまず机に座る」「寝る前に単語帳を開いたらその日はOK」というように、行動を決めてしまうのが有効です。家族がいるご家庭なら「いまから30分やるね」と宣言してしまうとサボりにくくなります。
勉強時間だけ増やしても伸びない理由
ナレッジスターがいちばん強く言っていたのが「量だけではダメ」という点です。高専入試は、普通高校と比べて数学・理科・英語の比重が高く、学校によって出やすい単元も違います。全部をモレなくやるのが理想ですが、それを11月からやるのは現実的ではありません。そこで「高専入試に合った勉強をする」ことが必要になります。
高専入試に合った範囲にしぼる
まずは、よく出る単元を先に終わらせます。数学なら計算・関数・図形の基本、理科なら電流・力・イオンなどの頻出分野、英語なら長文の読み方と文法の基本です
過去問と模試で弱点を見つける
どこをやるか迷う子は、過去問か高専模試を1回解いてしまうのがいちばん早いです。ナレッジスターの「高専模試」は結果シートが出るので、自分の得意・不得意がすぐにわかるのが特徴です。これをもとに、弱い単元に36分をあてていけば、増やした時間がそのまま得点になります。
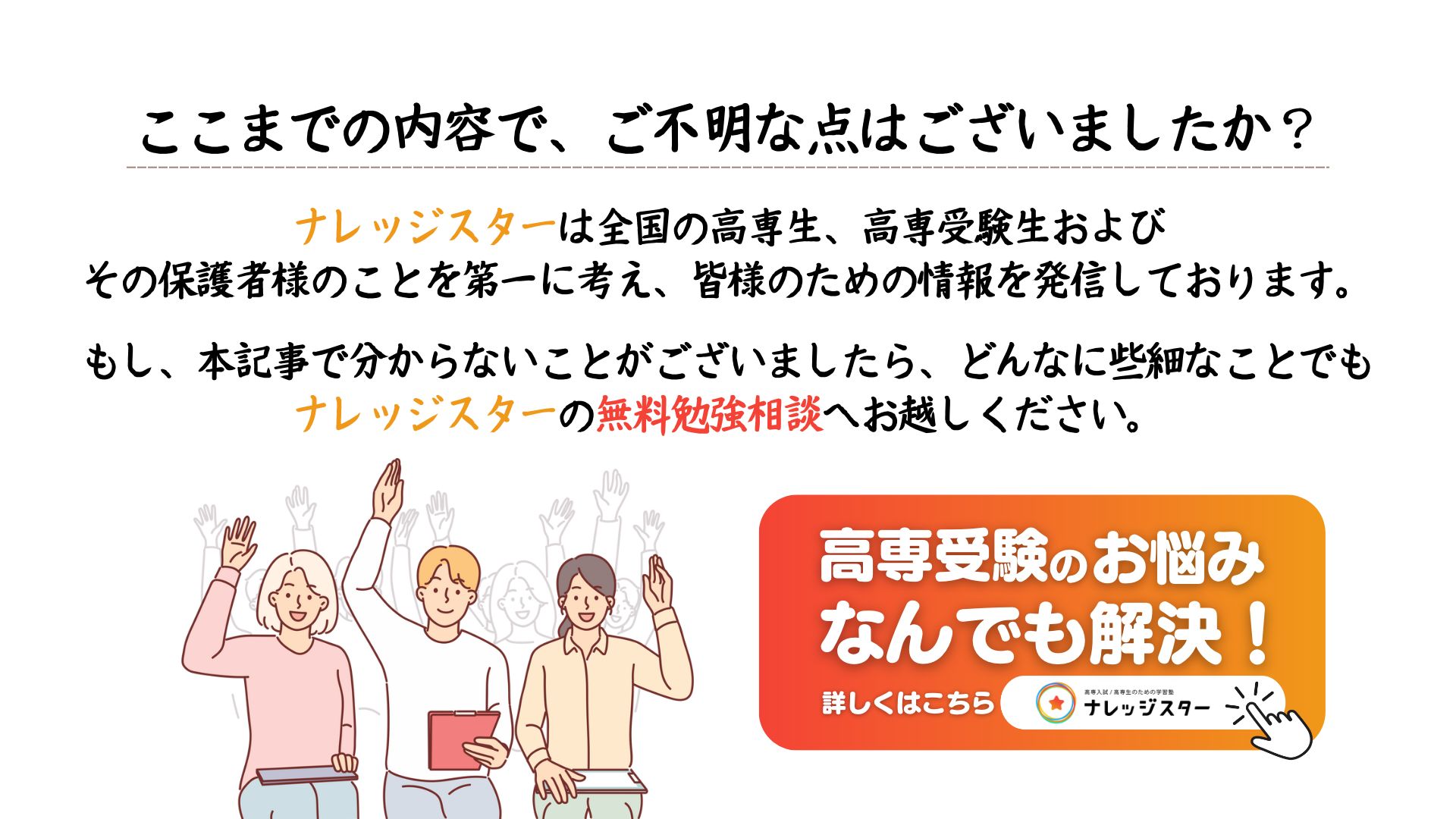
1日3.5時間を確保するモデルスケジュール
ここでは、合格者の平均3.4時間をとるための現実的なモデルを紹介します。部活がある人は開始時間をずらしてください。
平日版:登校前・放課後・夜で3本立て
- 朝:15分(英単語・理科用語・暗記)
- 放課後:90分(数学か英語。学校ワーク+高専用の問題)
- 夜:60分(理科・社会・技術家庭など手をつけにくい所)
- 寝る前:30分(その日やった内容の見直し、過去問1問)
合計で約3時間15分~3時間30分になります。最初はここまで行かなくても、朝15分と寝る前30分だけは固定しておくと「今日はぜんぜんやってない」が起こりにくくなります。
休日版:週20時間に乗せるやり方
平日にどうしても時間がとれない人は、土日で5~6時間ずつを目標にします。午前中に2時間、午後に2時間、夕方に1~2時間で分けてとると集中が切れません。このときは「高専入試とは?」「高専合格への花道(過去問活用)」などの内部記事を見ながら、やる単元を決めてから勉強に入るとムダがなくなります。
保護者向け:11月に「サボってる?」と感じたときの見方
11月はほんとうに体が重くなりやすい月です。机に向かうまでに時間がかかっているだけで、やる気がゼロになったわけではありません。そこで「今日は何分やれた?」と具体的に聞いてあげると、子どもも答えやすくなります。「合格した子は1日36分多かったんだって」と数字を見せると、本人も納得しやすいです。
具体的に「+30分」を声かけする
「もっとやりなさい」だと終わりが見えません。「今日はあと30分やったら終わりにしよう」「あと1ページだけやろう」のように言うと、子どももがんばりやすくなります。36分という数字は、動画に出てきた実データをもとにしているので、保護者目線でも説得力があります。
勉強している時間を見える化してもらう
見た目で「今日はやってないな」と感じても、学校で自習していたり、スマホで暗記カードをやっていることがあります。1週間分を紙やアプリで見せてもらい、「この日はがんばったね」とほめるほうが続きます。
冬講習・直前講座をどう使えばいい?
動画の最後では、ナレッジスターの後期・冬講習の話がありました。ここは「何をやればいいか」をプロ側が用意してくれる部分なので、質の心配をせずに済みます。だからこそ、自宅学習では「時間を増やす」ことに集中しましょう。
質は塾・量は自宅で分担する
塾やオンライン講座で出された課題を、自宅の36分にのせるだけでも伸び方が変わります。講座で「今日はここをやる」と決まっているなら、その日に家で復習するぶんを確保しましょう。
模試のある子は結果をすぐ学習に反映する
高専模試や現地開催の模試を受けた子は、結果が返ってきた日に、間違えたところを36分でいいのでやり直してください。1日空くとやらなくなります。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ:今日から+36分で合格ラインに近づく
- 11月の受験生平均…2.8時間
- 実際に合格した層…3.4時間
- 差は0.6時間=36分
- 36分を100日で60時間
- 60時間あれば1教科をまるごと底上げできる
この5つだけ覚えておけばOKです。あとは「今日はゼロにしない」「まず5分だけやる」「高専に出るところからやる」の3つを毎日続けてください。
Q&A(よくある質問)
Q1. まだ2時間しか勉強できていません。間に合いますか?
間に合います。今日から+30~40分にしましょう。2.0h→2.5h→3.0h→3.4hと、2週間~3週間あれば慣れてきます。ゼロの日をつくらないのが最優先です。
Q2. 部活や習い事で3時間とれません。どうしたらいいですか?
朝15分・昼10分・帰宅後90分・寝る前20分で2時間ちょっとは作れます。足りないぶんは土日に2~3時間ずつのせて「週20時間」を目指してください。
Q3. 何から勉強すればいいか迷います。優先順位は?
①高専でよく出る科目(数学・理科・英語)→②自分の苦手単元→③過去問・高専模試のやり直し、の順で進めるとよいです。
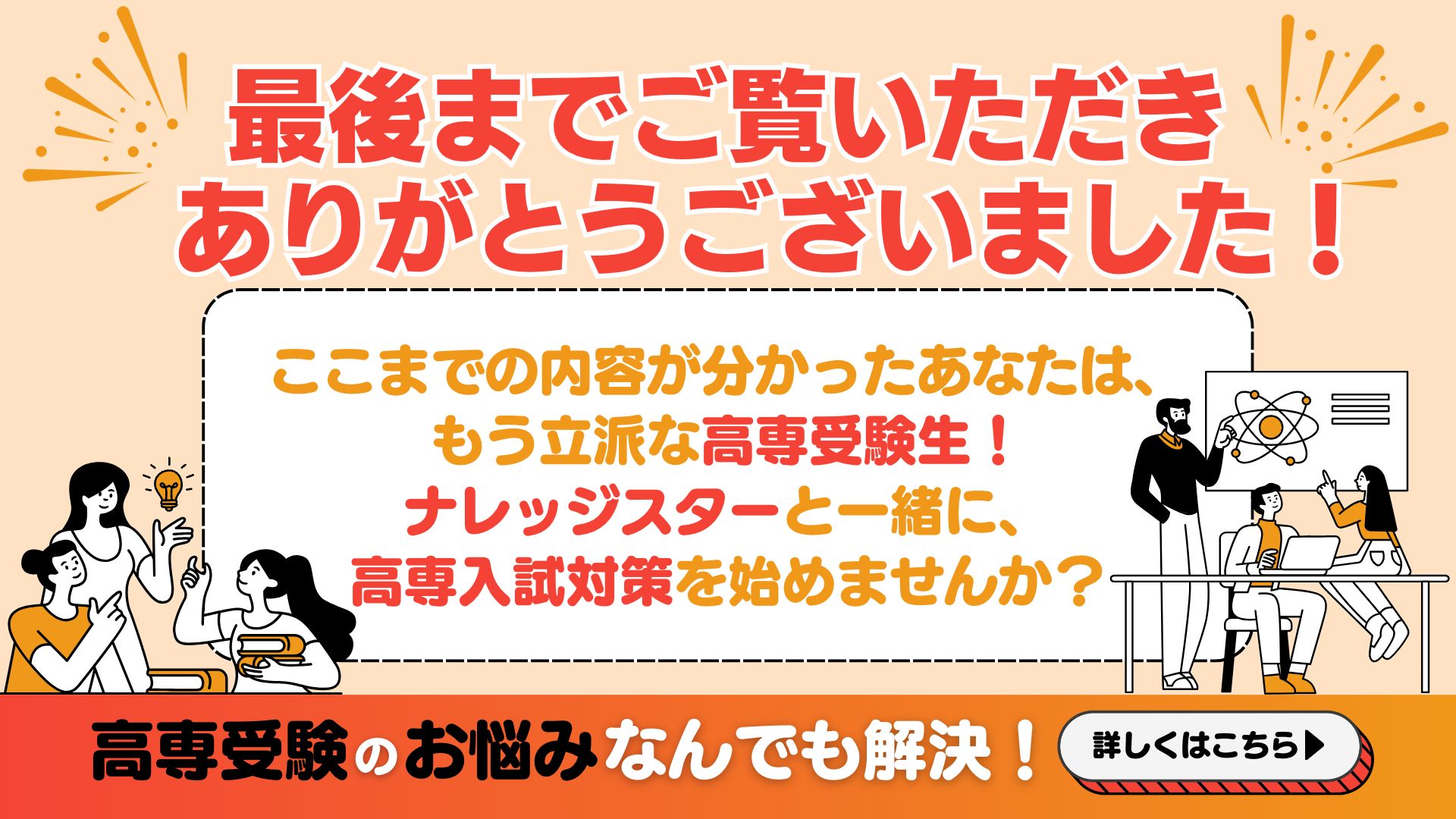
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。