- 面接と口頭試験の違いって?
- 具体的にどんな準備をすれば合格率が上がるの?
- もし不合格だったら、次に何をすればいい?
編入試験の面接対策は何をする?いつから?
こんな疑問や不安を持っている人に読んでほしいです!!
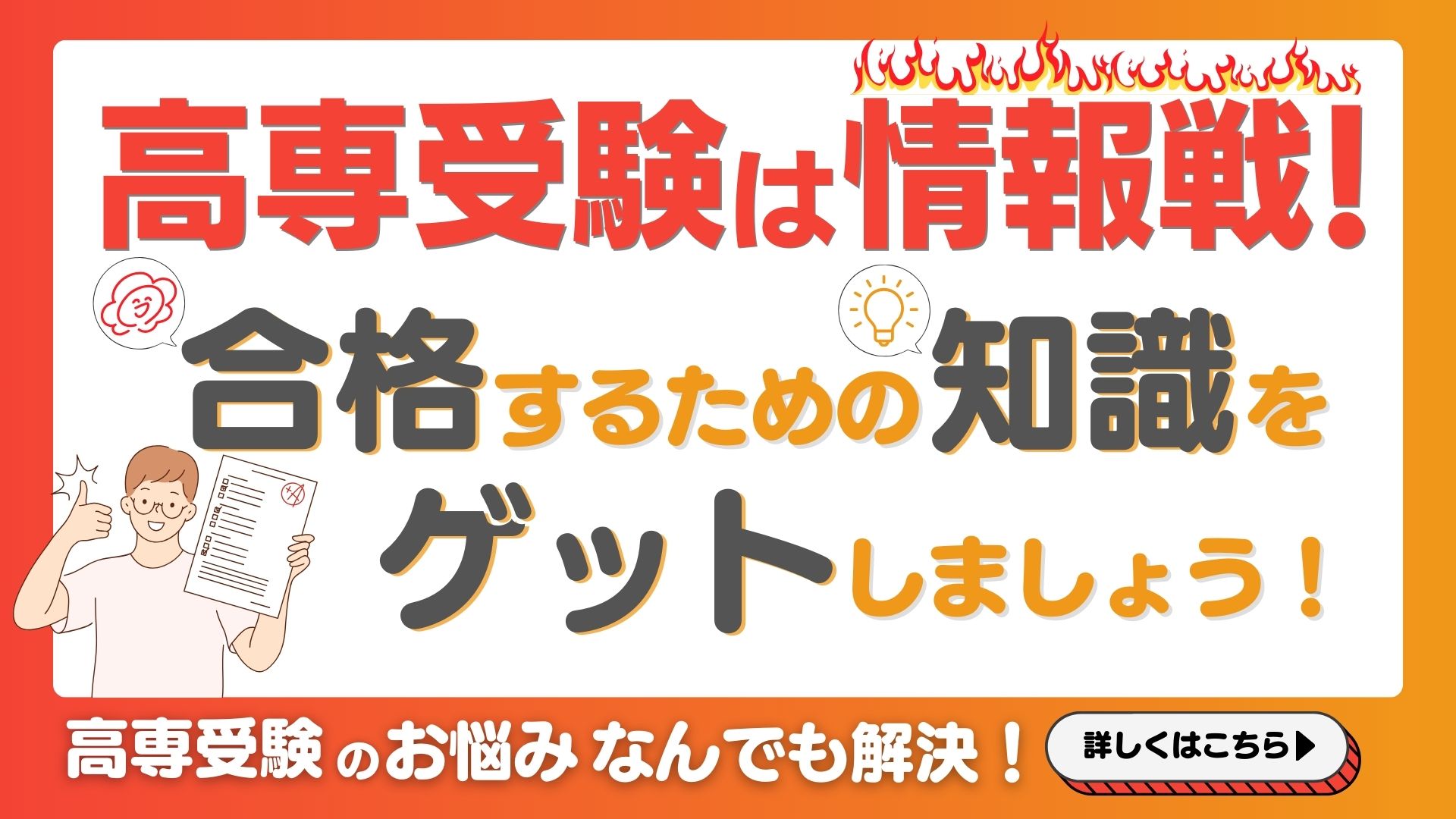
編入試験における面接とは
編入試験では、筆記試験に加えて、面接(または口頭試験)が実施されることが多いです。面接は、受験生の人柄や意欲、志望動機、さらにはこれまでの学びや経験をどのように今後の学問・研究に活かすかを評価する重要な試験形式です。単に知識を問うだけでなく、「自分の考えをどう表現するか」、「質問に対して論理的に答えられるか」といったコミュニケーション能力も求められるため、事前対策が不可欠となります。
次に、口頭試験は志望動機に加え、専門分野に関する問題について口頭で答える必要があります。
大学編入学試験における面接試験と口頭試験は、どちらも受験生と試験官が直接対話を行う形式の試験ですが、その定義、目的、そして評価基準には明確な違いが存在します。これらの違いを理解し、それぞれの試験に適切な対策を講じることが、編入試験を成功させるための重要な第一歩となります。
面接試験、口頭試験その他の編入試験の違い
編入試験の評価方法としては、主に以下の3パターンがあります。
面接試験:
対面での質問に対し、受験生が自らの言葉で回答する試験です。質問された内容について答えているか、内容に筋が通っているか、自分の経験を織り交ぜつつ答えているか、などコミュニケーション力が評価対象となります。
口頭試験:
面接試験と似ていますが、違いは質問される内容の多くが専門分野に関する質問であるという点です。志望動機など基本的な内容を質問された後に、志望動機に関連する分野の問題を口頭で質問され、数学や物理、化学などの問題を解く必要があります。大学によってはホワイトボードを使って、質問されながら解くといった場合もあるようです。
その他の編入試験:
書類審査や筆記試験と組み合わせた形式も存在します。面接や口頭試験は、その中で受験生の意欲や適性を判断するための要素と捉えられ、全体の総合力として評価されます。
各形式の違いを理解した上で、対策方法を学ぶことが大切です。
面接の内容
面接でよく聞かれる質問
面接では主に以下のような質問が多くなっています。
- 志望動機・自己紹介
- 高専での学び・卒業研究内容
- 将来のキャリアプラン
- 長所・短所/失敗・成功体験
- 併願校状況や入学意志の有無
- TOEICについて
これらは、受験生の熱意や将来の展望を確認するための質問です。
面接で実際に聞かれた質問
実際の面接では、例えば次のような具体的な質問が寄せられています。
志望動機
- 志望動機について教えて下さい
- なぜ他の大学ではなくこの大学・学部・学科なのですか?
自己分析について
- 自己PRをしてください(あなたの長所について教えて下さい)
- 何故、本科卒業後に進学を選んだのですか?
- 技術者にとって必要な事は何だと思いますか?
- あなたの性格に関してどのように評価していますか?
- あなたの強みは何ですか?(自己PR?)
- あなたの弱みは何ですか?
- 座右の銘はありますか?好きな言葉はありますか?
- あなたを一言で表すとどうなりますか?
高専在学中のこと
- チームワーク(人と協力したこと)についての経験を教えてください
- 失敗、成功した経験について教えて下さい
- 高専で取り組んだ卒業研究について教えて下さい
- 研究をするにあたって難しいところを教えて下さい
- 高専では何を学びましたか?
- なぜそれを学びたいと思ったのか?
- 好きな科目は何ですか?
- 嫌いな科目は何ですか?
- 力を入れた科目は何ですか?
- 成績の良い科目、興味のある科目を教えてください。
- 現在の成績に満足していますか?
- 高専で何か特別なことを成し遂げましたか?あるいは何かに打ち込んだことはありますか?
- 部活・ボランティア活動について教えてください
- アルバイトの経験について教えて下さい。そこで何を学びましたか?
- インターンシップの経験を教えて下さい。その後、研鑽したことを教えて下さい。
- あなたの成功体験を教えて下さい。
- あなたの失敗体験を教えて下さい。
- あなたのチャレンジ体験を教えて下さい。
- 学生生活で一番嬉しかったことは何ですか?
- 学生生活で一番苦しかったことは何ですか?
今後のキャリアプラン
- 大学院に進学する予定はありますか
- 大学で取り組みたい研究テーマについて教えて下さい
- 志望動機。将来、どういう仕事をしたいですか(業界、業種、企業)?
実際の体験談や先輩のエピソードを参考にすると、どのように自身の経験や意欲を語ればよいかイメージしやすくなります。
面接で気をつけるべきこと
面接時の注意点としては、以下のポイントが挙げられます。
時間厳守と服装:
清潔感のある服装で、第一印象を良くすることが重要です。
男女ともにスーツが良いでしょう。
はっきりとした発声と適切な言葉遣い:
落ち着いて、緊張しすぎず、論理的で明瞭な回答を心がけましょう。
面接は誰しもが緊張するものです。面接官は、受験者が緊張していることは知っているので焦らず受け答えしましょう!
自身の考えを具体的な事例を交えて説明する:
できるだけ具体的な経験や実績を踏まえながら話すと、説得力が増します。例えば機械系の学科を志望している場合、高専で取り組んできた実験・演習・ロボコン等の大会の経験を踏まえて志望動機を説明するとより筋が通って説得力が増します。
事前準備の徹底:
志望理由や自己紹介は、予行演習を重ねて自然に話せるようにしましょう。また、内容を深掘りされても答えられるよう準備しましょう。ただし、内容を丸暗記して棒読みにならないように注意してください。面接試験のスタイルの違い:
自分の回答に対して深堀りされる前提で面接練習を行うと、もし深堀りがされなかった場合に薄い回答のみで面接が終わってしまう場合があります。これでは十分に自分のアピールができないので、深堀りの有無に対応できるように面接練習をしておきましょう。
面接の対策方法
効果的な面接対策としては、以下の方法がおすすめです。
模擬面接の実施:
先輩や先生、友人と模擬面接を行い、フィードバックを得ることで改善点を見出します。
自己分析と志望動機の整理:
自分がなぜ編入を志望するのか、これまでの経験や実績を具体的に整理し、話せるようにしておくことが重要です。
質問リストを作成し、回答を準備する:
よくある質問を列挙し、それに対する自分なりの答えを用意しましょう。答える練習も同時に行うと効果的です。
受け答えの時間は1分程度に抑えられるように意識しましょう。長く話して多くのことを伝えたい気持ちは分かりますが、長すぎると何を伝えたいのかが分からなくなり、面接官が困ってしまいます。
実際の面接の雰囲気を体験する:
学校で開催される説明会や、模擬面接イベントに参加し、現場の雰囲気に慣れておくと自信がつきます。
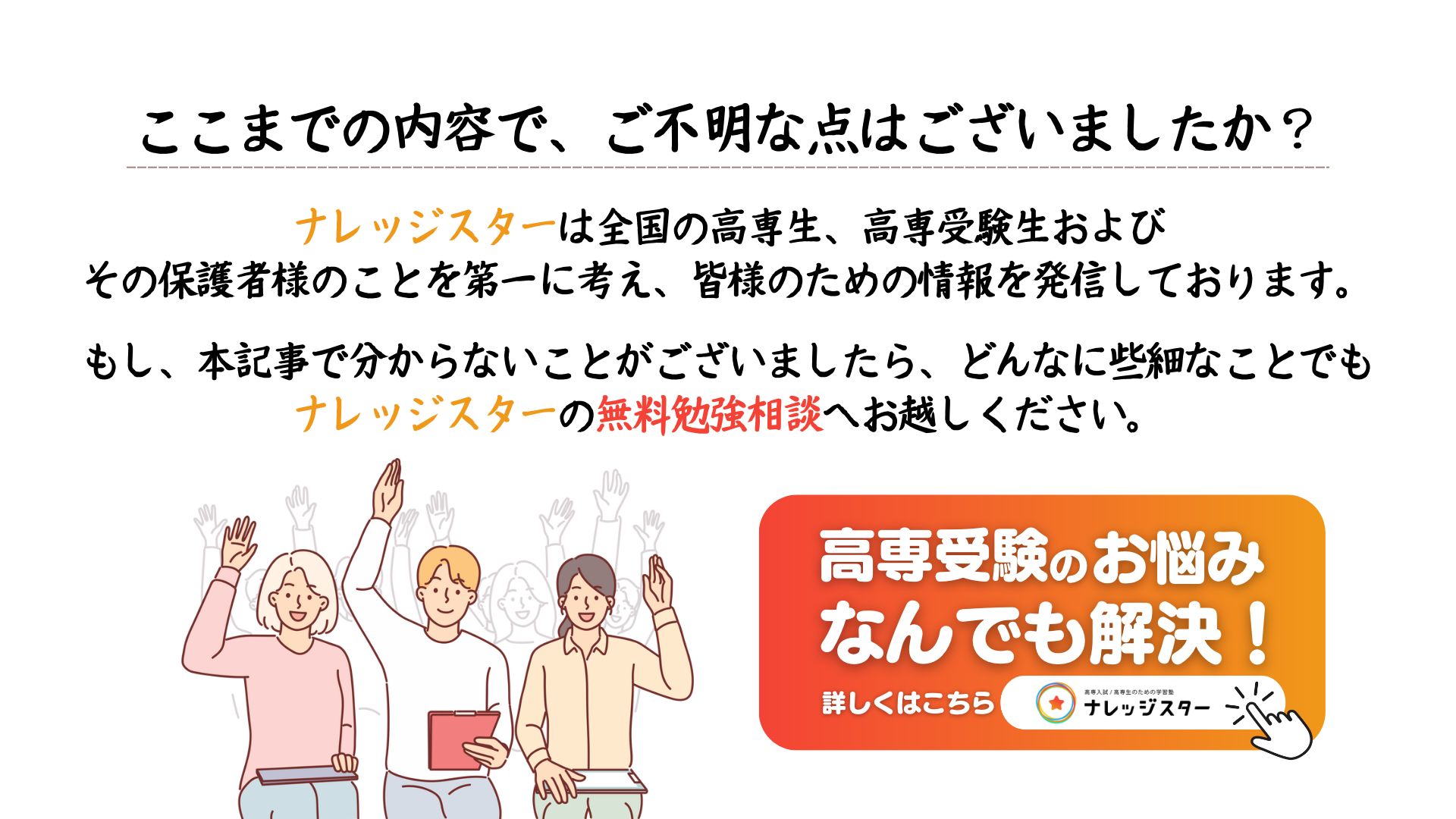
口頭試験の内容
口頭試験でよく聞かれる質問
口頭試験では、面接と似た形式で質問がされることが多いですが、特に技術的な知識や学科に関する具体的な質問が中心になります。
- 〇〇について説明して
- 〇〇の定義を答えよ
- 〇〇を前提とした上で、証明せよ
- 〇〇を解け
このような定義とその本質が理解できていないと答えることが難しい問題が多いです。
口頭試験で実際に聞かれた質問
実際に口頭試験で聞かれた例としては、このような質問があります。
数学
- 行列の対角化の公式について説明と証明
- 確率分布を一つあげる
- 条件付き確率の意味と変形した形
- フーリエ変換とフーリエ級数展開の違い
- sin(ωt)と直交する関数は何か
- ソートの種類と計算量
- アルゴリズムとは
物理
- サンプリング定理について説明
- サンプリングした際に周波数が高すぎる時はどうするか(ローパスフィルタが正解)
- 電磁波の波長と用途
- 色の三原色とは
- 単振動の運動方程式
化学
水の入った容器の図とグラフが4つ書かれている。
- 100℃で、液体の水を全て気体に変えるのに必要なエネルギーのことをなんといいますか?
- 4つのグラフの内、縦軸が装置内部の圧力を表しているのは?
- エントロピーを表しているのは?
- ギブズエネルギ-を表しているのは?
- 蓋を固定した状態で100℃にすると水はどのような状態になりますか?
- ウィリアムソンエーテル合成とフリーデルクラフツ反応、ニトロ化反応の反応式があり、適した試薬等を答えさせる問題。
- 1×10の-8乗Mの塩酸の25℃でのおおよその水素イオン濃度を教えてください。
- 水酸化ナトリウム標準液の作成には、濃度既知の酸で滴定し、濃度を求める必要があります。なぜでしょうか?
口頭試験で気をつけるべきこと
正確で論理的な回答:
知識の正確性はもちろん、論理的に話すことが評価されます。
試験官とコミュニケーションをとる:
もしその問題の解き方がわからない場合、試験官の先生がヒントを出してくれる場合があります。そのヒントを見逃さず問題に取り組んでみましょう。
口頭試験の対策方法
専門知識の復習:
自分の専門分野に関する基本的な知識を再確認し、関連するキーワードや理論を整理しておくことが重要です。どんな用語・公式を言われても説明できるようにしておきましょう。
模擬試験の実施:
高専の先生に依頼し、模擬的な口頭試験を実施し、質疑応答の流れを体験することで、本番の雰囲気に慣れることができます。
いつから面接の練習をすればいいの?
面接の準備は、できるだけ早めに始めるのが効果的です。多くの先輩や対策講座では、編入試験の1次試験が始まる3〜4ヶ月前には、最低でも自己分析や模擬面接の練習を開始することを推奨しています。早めに準備を始めることで、繰り返し練習する時間が確保でき、本番で自分の考えを自信をもって伝えられるようになります。また、日々のニュースや学校の情報も取り入れながら、最新の話題や自分の興味・関心を整理しておくと、面接での回答に説得力が増します。
もし面接試験で落ちてしまったら
編入試験は、面接の結果が合否を大きく左右します。もし第一志望の大学で不合格となってしまった場合、落ち込みすぎる前に「次の一手」を冷静に考えることが大切です。
もしもの想定
受験においては、「万が一」のケースに備えておくことも戦略の一つです。
第一志望に落ちた場合の進路を事前に考えておく:
試験本番を迎える前に、「落ちたらどうするか?」という視点で、他の大学や進路も視野に入れておきましょう。
複数受験のスケジュールと注意点を確認しておく:
編入試験は大学ごとに日程がバラバラ。試験日が重複していないかのチェックは必須です。また、推薦入試で合格した場合は、基本的にその大学へ進学する必要があるため、他校との併願はできません。受験順や優先順位は慎重に考える必要があります。
滑り止めの大学も検討しておく:
志望度がやや下がるとしても、自分の将来にとってプラスになる大学を複数検討しておくと、精神的な余裕にもつながります。
次のチャンスに向けて切り替える
面接で不合格になってしまったとしても、その時点で編入チャンスが終わるわけではありません。多くの大学では編入試験が複数の時期に分かれて実施されているため、スケジュール的に可能であれば、次の試験に向けてすぐに準備を再開しましょう。
就職という選択肢も
どうしても大学が決まらなかった場合、就職に切り替えるという選択肢もあります。ただし、ここで注意すべきなのは就職活動のスケジュールです。
多くの企業は10月1日に内定式を行います。この日を過ぎてから就活を始めると、すでに採用活動が終了している企業も多く、選択肢が大きく減る可能性があります。
そのため、9月末の段階で編入試験が思うようにいかなかった場合は、すぐに方向転換できるよう、早めに企業研究や履歴書の準備を始めておくのがベストです。
まとめ
編入試験の面接や口頭試験は、受験生の人間性や学ぶ意欲、専門知識だけでなく、コミュニケーション能力や論理的思考力をチェックする重要な評価手段です。対策としては、模擬面接や自己分析、専門知識の復習・プレゼンテーションの練習が不可欠であり、早期からの準備が合格への鍵となります。また、万が一不合格となっても、その経験を次への貴重なフィードバックとして、今後の改善に生かす姿勢が大切です。自分自身の成長を実感しながら、次のチャンスへと向かって準備を進めましょう。
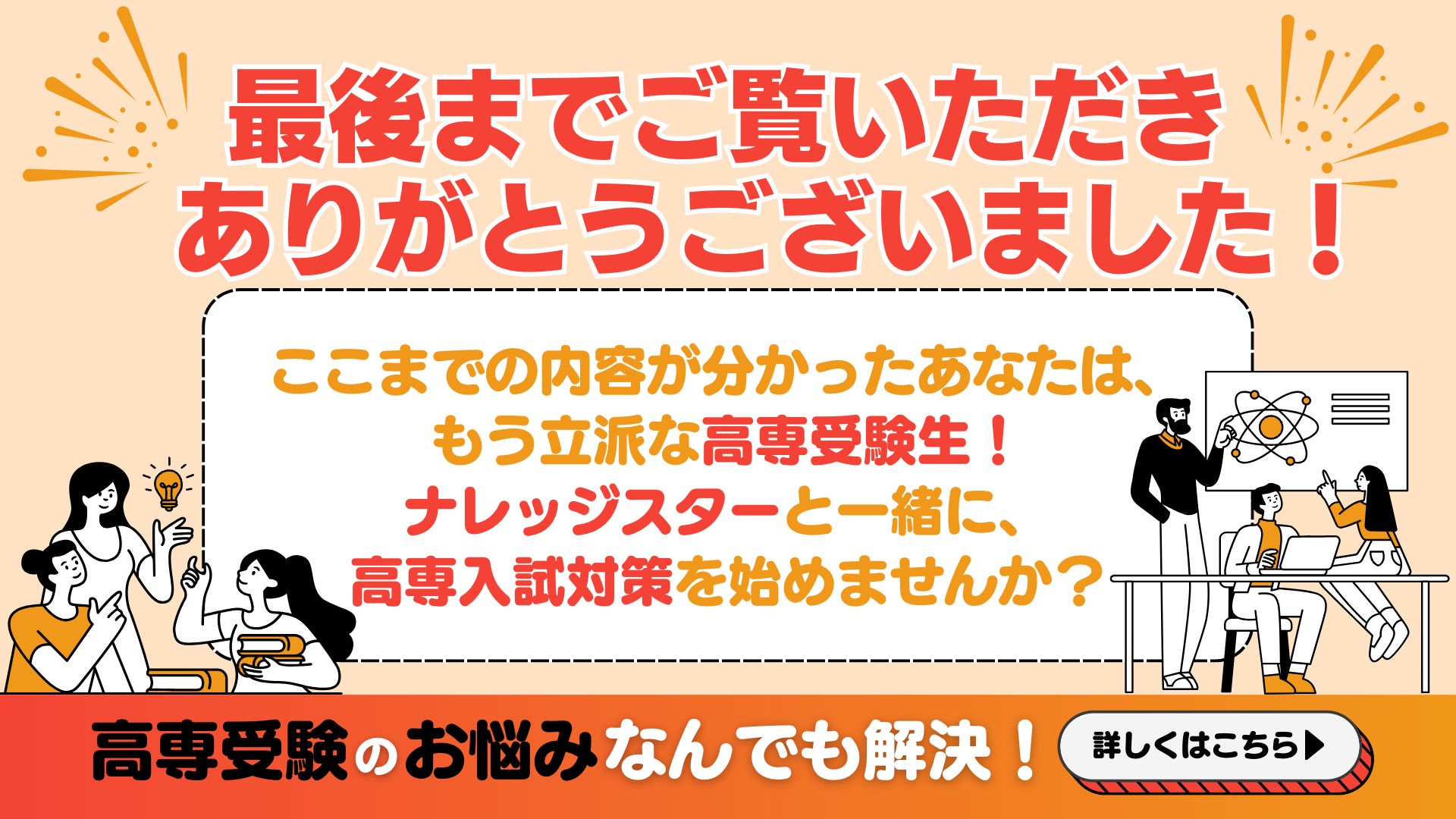
ライター情報
熊本高専 人間情報システム工学科
ハルキ
情報系の高専生。趣味は写真。




