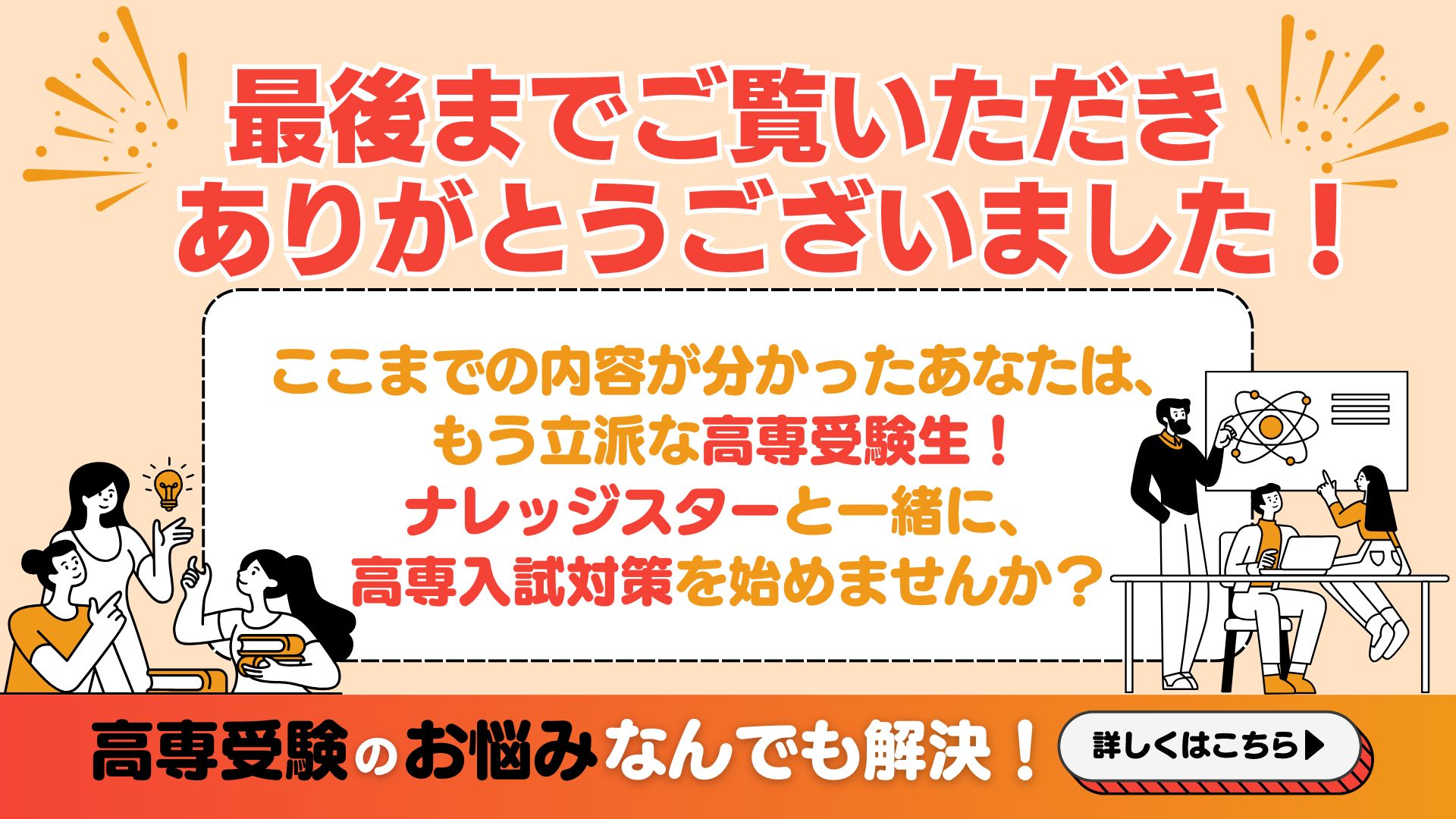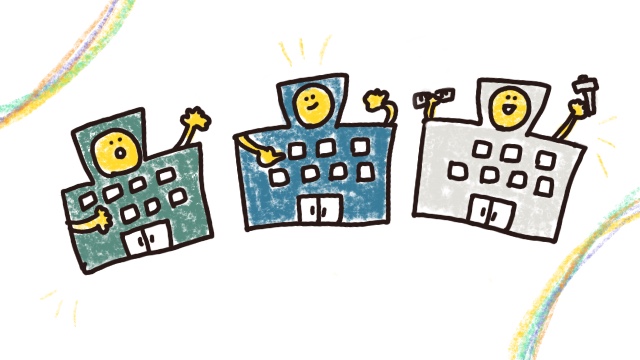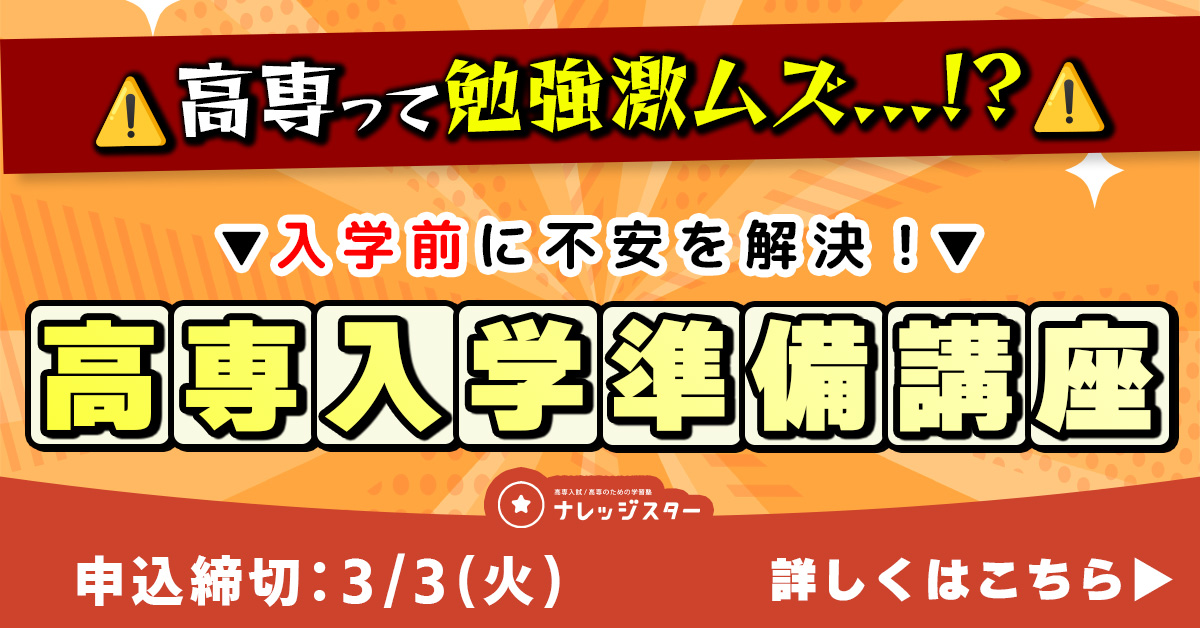※本記事は例として仙台高等専門学校名取キャンパスと宮城県工業高等学校の情報を基に記述しています。
あなたは高専(高等専門学校)と工業高校の違いを説明できますか?
高専と工業高校の大きな違いは、在学期間(5年制か3年制か)と卒業時の学歴(準学士か高卒か)の2つです。
この記事では、まず高専とはどんな学校かをざっくり紹介し、そのうえで学費・偏差値・就職率といった部分を最新データを使って工業高校と比較します。
読み終えるころには、「自分に合うのはどちらか」がすぐに見えてくるはずです。
▼ナレッジスターではオンライン無料勉強相談も行なっているので、高専入試対策に不安のある方は、ぜひお申し込みください!
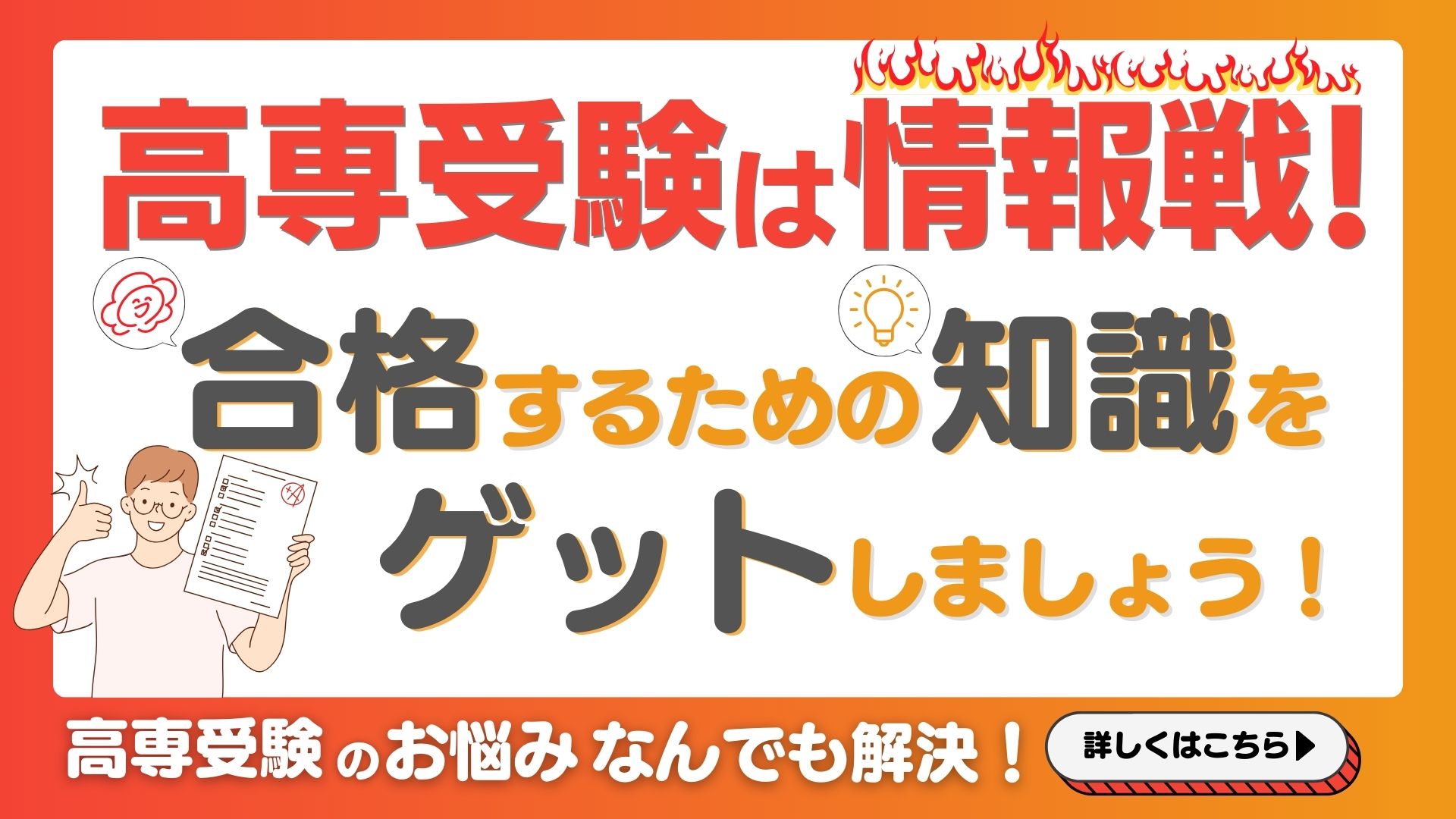
高専と工業高校の違いを一目で比較【早見表】
| 項目 | 高専 | 工業高校 |
|---|---|---|
| 修業年数 | 5年 | 3年 |
| 最終学歴 | 準学士(短大卒相当) | 高卒 |
| 学費(5年総額) | 約126万円※1 | 約137万円※2 |
| 偏差値の目安 | 55〜68 | 40〜58 |
| 就職率(直近実績) | 99.1% | 96.8% |
※1 国立高専:授業料計約126万円(寮費等を除く)。自宅通学なら約130〜150万円。
※2 文科省「子供の学習費調査2024」に基づく公立工業高校3年間の平均学習費。
高専とは?5年制・準学士が取れる工業系学校を解説
まずは高専について解説します。高専とは5年制の工業系学校です。高専の一番の特徴として、高校1年生の内から受けられる専門的な授業が挙げられます。実習の授業も多く最新の先端機器の実験設備も整っており、実践的なキャリア教育を施しています。
現場で即戦力として扱われるエンジニアとしての力を育むことを目的とした授業を行う。
そのため、技術を身に着けられるように積極的にインターンや工場見学を行ったり、実技の授業や試験など現場を想定した授業を行ったりするカリキュラムが組まれています。
その授業も教授や准教授が教鞭を取ります。懇切丁寧に解説されるので基礎から理解が深まりやすく、生徒にも好評です。
その若いうちから培われた実践的な高い能力は、企業や大学から高く評価されています。
それに伴って進路にも大きな特徴があります。
進学を選ぶ場合、工業系の大学への編入と専攻科と呼ばれる学科に進むことができます。
難関と言われる国立大学や東大京大東工大などへの編入ができる所は高専の強みです。
就職を選択する場合、学校からの手厚いサポートと多くの求人を得られます。
高専に中小零細企業から大企業まで求人が1人に対して30社ほど大量に届きます。
大学生の就職活動と比べると享受できるメリットが分かります。
2024年の情報では大学生が10.7社にエントリーシートを提出し2.5社程度から内定が出されている、という調査結果があります。
しかし、高専では自らエントリーシートを出さずとも1人当たり約13社から求人が出されます。
即戦力として扱える高専卒を求める会社は多いためこの求人量を例年保っています。
学校側の手厚いサポートも相まって就職難と冠されている今でも就職率が100%と高水準を維持しています。
高専は高等教育機関なので大学と同じ扱いをされます。そのため、高専に在籍している人は”生徒”ではなく、”学生”と呼ばれます。進学せずに卒業した場合は、短大・専門卒と同等の称号(準学士)を得ることができます。
学科は機械、材料、電気、情報、化学、建築系などが主です。しかし、商船や経営など工業ではない学科も存在します。
また、専攻科という、同じ校舎で2年間さらに勉強と研究ができる学科が存在します。そこを卒業すれば大学卒業と同等の称号(学士)を取得できます。その後、大学院にへ進学することも可能です。
▼高専の特徴はこちらの記事で徹底的に解説していますので、興味のある方はぜひ!
高専の雰囲気|授業・校則・キャンパスライフを体験談付きで紹介
高校と大学が合わさったような学校で、両方の特徴が盛り込まれています。
高校寄りの特徴としては、3年生まではほぼ全ての単位が必修で時間割が元々定まっているところです。
大学寄りの特徴としては、赤点の基準が60点と高く、考査ごとに決して少なくはない数の補習者が出る点です。理系の科目は難易度が高く、平均点が60点を切ることが多々あります。赤点による単位の不足で留年する人も毎年出てきます。
普通高校の場合、元センター試験である共通試験に向けた勉強がありますが、高専生は大学受験をしないのでそれがありません。そのため高校で勉強する範囲を1年半で終わらせます。普通高校よりも浮いた時間で専門科目を学ぶようになっています。
多くの高専は授業時限が1時限あたり90分と大学と同等の長さとなっています。授業時間を45分としている高専もありますが、2コマ連続で同じ授業を続ける科目、時間割は各高専によって違いますが、大まかに1コマ90分の4時限制の学校と1コマ45分の8時限制の学校に分けられます。
しかしその全てが授業というわけではなく、早く終わる曜日もあれば2時限目から始まる日や全ての時限を使って授業をする曜日もあります。
4年生からは単位制度が変わり、必修の単位だけでなく選択科目の単位が多くなるようになります。資格を取得することで単位を得ることができる外部単位という制度でも単位を取得できます。英語検定やTOEICなどの一般的な資格や、危険物取扱者などの専門的な資格など、多岐にわたります。
高専には校舎に下駄箱が無く、精密機械がある部屋と体育館以外は土足で生活します。
大体の高専では校則も自由で髪染め、ピアス、メイクなどもできます。1年生の内から髪の毛を染めたりピアスの穴をあける人もいます。制服も指定されていないため私服で登校します。※高専によっては制服が指定されている学校もあります。
また4年生からは研究室に配属されて、卒業研究に勤しみます。高校は中等教育機関に分類されますが、高専は高等教育機関と呼ばれる大学と同じ分類に含まれます。そのため、高専生は“生徒”ではなく“学生”と呼ばれます。
高専の偏差値分布(55〜68)と入試倍率【2025年最新版】
高専の偏差値は55から68と幅があります。しかし全国58校中の56校の高専が偏差値50以上を保っています。
偏差値が違うからといって偏差値が高い高専が良いと言うわけではありません。偏差値は異なりますが、カリキュラムは統一されています。
どこの高専を卒業しても社会からの評価は変わらず、高専卒として一括りに評価されることが多いです。
高専の学費はいくら?入学金・授業料・寮費を完全開設
高専の入学金は高校よりも圧倒的に高く84,600円 もします。公立高校の入学金は5,650円 と差額が78,950円 も差額がでます。
授業料は高専の場合年額で234,600円 です。公立高校の授業料相当額(118,800 円)との差は 115,800 円 です。
もっとも、高専は短大相当の専門教育(準学士課程)まで含む 5 年一貫制です。参考までに 公立短期大学の平均授業料は 377,357 円 で、高専より 142,757 円 高くなります。 短大レベルの専門教育を受けられることを考えると、学費面で高専はむしろ割安 と言えます。
さらに本科 1~3 年生は 「高等学校等就学支援金制度」 の対象。
世帯年収の目安が 約 1,090 万円未満 の場合、年額 118,800 円 が国から支給されるため、実質的な授業料負担は 234,600 円 − 118,800 円 = 115,800 円 に下がります。
高専を選ぶメリット3選|就職率・大学編入・研究環境
大学へ簡単に編入できる
大学編入試験は共通試験よりも科目数が少ないです。理系科目と専門科目、英語だけが試験科目になるので、文系が苦手な人でも合格しやすいです。
進学も就職も選びやすい
専攻科や大学への編入と就職率100%を兼ねそろえている高専は、進学も就職もどちらの選択肢も選びやすいです。
卒業研究ができる
大学で行う印象が強い卒業研究。大学では21歳から始まる卒業研究ですが、高専では19歳から卒業研究ができます。高専卒業後、専攻科や大学に編入するした場合、大学卒業までに2本も論文を書き上げることになります。高校から大学に入学した人に比べて経験値が2倍以上も違います。
高専のデメリットと対処法|留年・通学・進路の壁
通学時間が長い
高専は全国に58校しかなく、高専が存在しない県もあります。
また交通の要から外れた場所に立地しているため通学時間が伸びやすいです。
家の近くに高専がない場合、寮に入れなかったり寮がない高専に入学したりしたときは通学時間が長くなる覚悟が要ります。
入学を検討している場合は、家から通う場合のシミュレーションが必須です。
工業系以外の進路に進みにくい
高専は工業系の5年制の学校です。共通試験を受ける生徒がいないため、それに向けた授業が行われません。
よって、共通試験を受けて高専3年生から大学1年生に編入することが難しいと言われています。
留年、退学率が高い
高専は赤点のラインが60点と高く、勉強していても赤点を取ってしまうことがあります。
そのため、補習や追試などで挽回できずに留年してしまう人が毎年1名ほどいます。
そのまま退学してしまう人もいます。
工業高校とは?3年で就職力を付ける専門高校を解説
次は工業高校について解説していきます。
工業高校は工業や産業などについての専門技術や知識を習得できる高等学校です。特徴は、高専と同じように実践的な授業が多く技術職などへの就職が強い高校です。そのため工業に関連した学科が多く存在します。例えば機械科や電子機械科、電気科、インテリア科や化学工業科、情報技術科など専門的な学科などです。学校の授業として資格取得のための勉強ができるところも強みです。
高専と同じように専門的な技術を身に着けられる学校です。
普通高校との違い|授業科目・資格取得
一言で表すならば、普通高校と比べると基本科目の授業数が少ないけれども専門科目を15歳から勉強できる部分です。
普通高校と比べると専門分野の授業があるので、それに伴い日本史や現代国語のような基本科目の授業日数が少ないです。習っていない範囲も多く含まれるため大学受験の際には不利になりやすいと言われています。また、先ほども述べた通り、資格取得にも力を入れています。講習会を開く検定もあるので普通高校よりも取得しやすい環境ですね。
工業高校の雰囲気|校則・実習・ジュニアマイスター制度
校則は厳しいところが多いです。就職を選ぶ人が多いので素行が悪いと学校全体のイメージが悪化するので頭髪検査をする学校が大多数と言えます。
制服が指定されているところが多く存在します。制服ではありませんが、危険な薬品を扱ったり火花が飛ぶような実習の授業があるので作業着を着用することも多々あります。
普通高校と似たような雰囲気の学校ですが、実習の授業があるので学校指定の作業着や専門科目の授業があるなど特殊な特徴があります。
また、工業高校にはジュニアマイスター顕彰制度というものが存在します。高校在籍中に取得した国家職業資格や各種検定、コンテストで賞を取った場合などを点数化して表彰する制度です。30点以上で“ジュニアマイスターシルバー”が、45点以上で“ジュニアマイスターゴールド”が生徒に送られます。
工業高校の偏差値(40〜58)と入試倍率
工業高校の偏差値は おおむね 40〜55 程度 が中心です。たとえば宮城県工業高校(情報技術科 54、電気科 48)や福島工業高校(47〜53)など、地方の県立校でも 45〜50 台がボリュームゾーン 。例外的に都市部の人気学科では 55 前後になるものの、60 を超えるケースはほぼありません。
大学進学を前提にした学科が少なく、就職希望者が多数派のため、学力レベルは普通科進学校より低めに安定しやすい傾向があります。また 入試倍率も 1.0〜1.3 倍前後と比較的穏やかで、都市部の情報技術系などでも 1.5 倍程度が上限です 。そのため、入学しやすい学校を探す受験生には選択肢が広いと言えるでしょう。
授業料は年額で118,800円ですが、在学期間が36月、つまりは留年しなければ高等学校等就学支援金制度によって実質無償です。
入学金も5,650円と高専と比べると15分の1ほどと安いことが特徴です。
工業高校のメリット3選|早期就職・資格取得・進路の柔軟性
早く就職できる
高専に入学した場合5年間学んでから就職という形になります。
しかし工業高校ならば3年間学んだらすぐに就職できるので、高専と比べると2年間も早く働くことができます。
進路の変更がしやすい
高専に入学した場合、工業系以外の大学に進みにくく夢が変わった場合苦労します。
しかし工業高校ならば、共通試験を受けて文系などの大学に入学することができます。
高専よりも進路が幾ばくか自由です。
入りやすい
倍率が低く高専よりも入学しやすいのがメリットです。
生徒募集する人数が高専に比べると多く、比較的倍率が低くなりやすく入学しやすい特徴があります。学科によっては定員割れを起こす年度もあるほどです。
工業高校のデメリット|大学進学・就職先・校則の注意点
大学への進学が普通高校より難しい
工業高校は普通高校よりも受験科目の授業時間が少ないので、共通試験の難易度が高くなります。場合によっては受験科目の範囲を学習しない場合もあります。自主的な学習や塾の授業などで学習量を増やさないといけません。
高専と比べて就職先が狭まる
高専と工業高校の共通点まとめ|5つの似ているポイント
中学校卒業後から工業系のことが学べる学校であり、男子の比率が高く専門的な知識を会得しやすい環境を構築していて、就職しやすい点が類似していますね。
分かりやすく羅列すると、高専と工業高校の共通点は、
- 工業系の学校
- 女子が少ない
- エンジニア系の就職に有利
- 資格が取りやすい
- 高額な実験設備が整っている
- 15歳から専門的なことを学べる
などが代表的です。
高専と工業高校では卒業後の扱われ方が大きく違うことが分かります。
まとめ|高専と工業高校どっちを選ぶ?
高専と工業高校の相違点の一覧です。
| 高専 | 工業高校 | |
| 進学 | 大学へ編入、専攻科へ進学 | 3割が大学に進学 |
| 修業年数 | 5年 | 3年 |
| 卒業後の学歴 | 専門・短大卒と同等 | 高卒 |
| 教育機関の分類 | 高等教育機関 | 中等教育機関 |
| 資格の扱い | 単位が取れる | ジュニアマイスターの点数になる |
| 学費 | 部分的にみると高いが大学進学まで目途に入れると安い | 授業料は実質無償 |
| 偏差値 | 55-68で60以上の学校が多い | 40-58で50代の学校が多い |
| 学校数 | 58校 | 250校 |
工業高校と比べると高専は進学や就職の面で有利といえます。
しかし学費や定期代も工業高校と比べると高くなるので経済的にも負担が重くなります。
しかも工業高校よりも倍率が高かったり入試問題が比較的難しかったり、入学のハードルが高くなります。
高専は理数科目に力を入れているので、理系の授業が難しいです。そのため理系が苦手だと授業についていけない人が出てきます。入学当初は赤点を取らなくても、年度が上がるごとにさらに難易度と専門性が上がっていくため授業の理解が追いつかない可能性が出てきます。
定期テストで赤点を取り続けると単位が足りず留年してしまったり、補習を受けなければならなくなってしまいます。
さらに授業についていけずに不登校になってしまい、出席日数が足りずそのまま退学という流れもあるため入学する際の懸念点となるでしょう。
高専に入学したい!けれども合格するか不安、授業についていけるか不安、という方もいらっしゃいますよね。
ナレッジスターではそのような方のために、高専入試や高専の定期テスト、大学編入に特化した、高専のためだけの学習指導を行っております。
高専独自のカリキュラムを経験している高専在学生や卒業生が教鞭を取ります。高専に特化した塾だからこそできる専門的な教育を受けられるのはここだけ!
さらに、ネット個別指導や教材通信販売などを実施しており宮城県外、全国どこからでも授業を受けることができます。
お問い合わせはこちらから↓
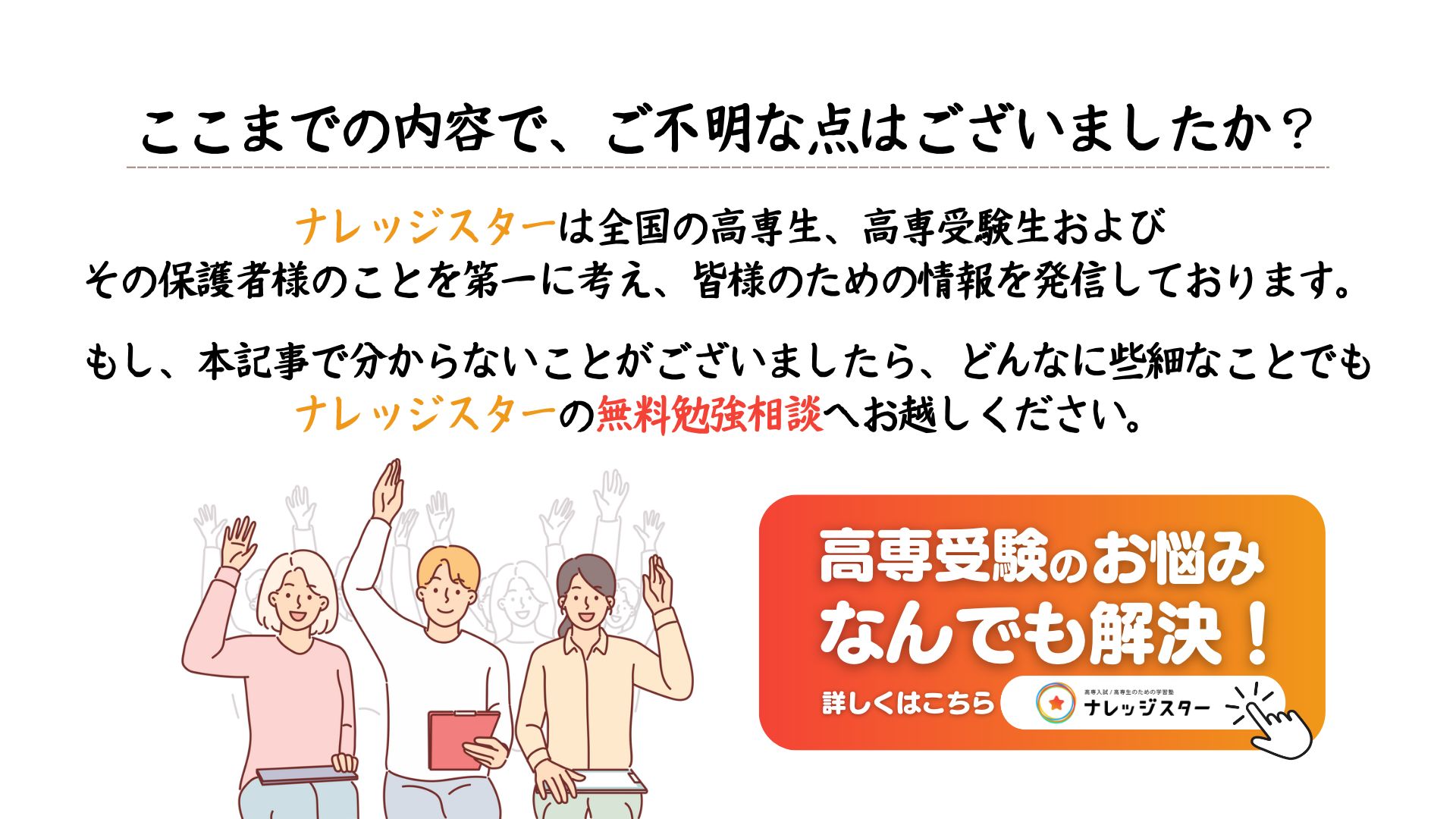
高専に向いている人
主体的に行動できる人
高専では自分で考えて自分で行動することが求められます。また、自由に使える時間が多いのが特徴です。
そのため、やるべきことを把握して自主的に勉強できる人が向いています。
技術職に就きたい人
毎年、高専に技術職の求人が大量に送られます。就きたい職業が明確に定まっている場合、高専に向いている性格です。
高専に向いていない人
数学が苦手な人
理系科目はどれも計算が必須となっています。物理や化学も数学で習った公式を活用しないと解けません。したがって数学が解けないと全ての理系科目の難易度が大幅に上がります。
怠けてしまう人
高専は自由時間が多いうえに、大量の課題も出されます。自己管理ができないと授業についていけなかったり、テストで赤点を取ったりしてしまいます。
工業高校に向いている人
すぐに就職したい人
高専の場合就職までに5年間掛かりますが、工業高校の場合3年間学べばすぐに就職することができます。2年間早く就職することができるので一刻も早く働きたい人におすすめできます。
進路に迷っている人
工業系と理系、どちらにも興味があって迷っている人には工業高校が向いています。高専よりも工業高校の方が文系の進路へ方向転換しやすい事が特徴です。
工業高校に向いていない人
旧帝大などの難易度の高い大学に進みたい人
工業高校は就職に特化している学校です。大学への進学も可能ですが、学校推薦で進学している場合がほとんどです。
よくある質問(FAQ)
高専卒は大学編入に有利ですか?
はい。全国の高専本科卒業生のうち約25%(3,000 名超)が国公私立大学の 3 年次へ編入しています。 数学・英語の基礎力と学校推薦枠があり、一般高校卒より受験科目や受験人数が少ない点では有利なことが多いです。
高専の留年率はどのくらいですか?
文科省調査では本科全体の平均留年率は約 3.7 %です。主因は単位不足ですが、追試や補講で翌年度に進級できるケースも多くあります。
工業高校から国立大学に進学できますか?
できます。共通テスト対策と評定平均 4.0 以上の確保で、指定校推薦や総合型選抜による合格例が多数あります。
工業高校の主な就職先はどこですか?
自動車・電機・インフラ・建設など大手企業の高卒採用が中心です。 求人倍率は最新調査で過去最高 20.6 倍、就職内定率 99.3 % と需要は非常に高い状況です。
高専で利用できる奨学金はありますか?
あります。日本学生支援機構(JASSO)の第一種・第二種に加え、各高専独自の授業料減免や寮費補助制度が用意されています。
- 文部科学省「公立短期大学授業料等について」令和6年度
- 国立高等専門学校機構『KOSEN概要2023』進路状況
- 全国工業高等学校長協会「令和5年 全日制工業科卒業者進路状況調査」
- 文部科学省「高等専門学校における教育改善状況等調査」留年率データ