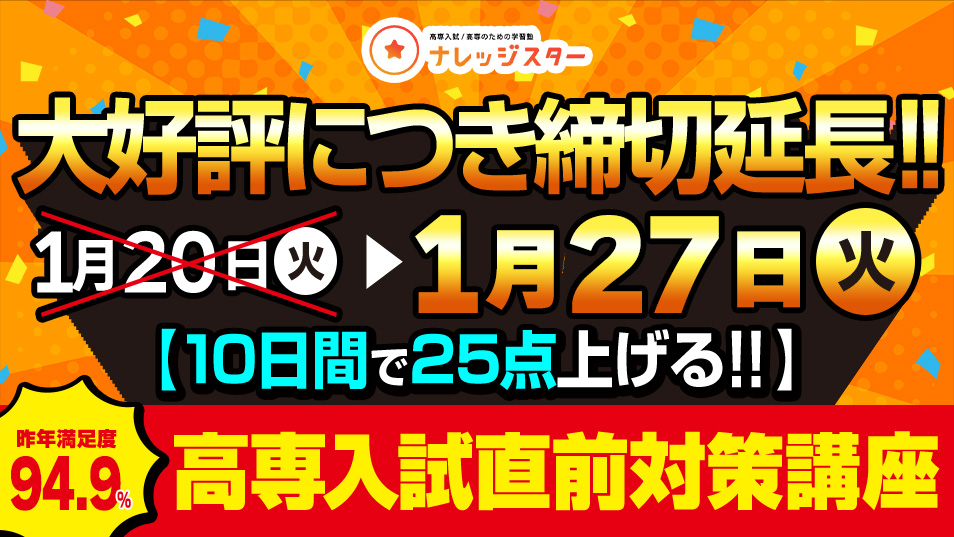全国の高専には、工場、もしくはそれに準じた施設があります。皆さんは工場と聞いて、どのような施設を思い浮かべますか?
大量の産業用ロボットで自動化された製造ラインでしょうか。あるいは立ち並ぶのこぎり屋根でしょうか。
高専にある工場は、そんなイメージとはちょっと違った施設です。町工場といった方が皆さんのイメージに近いかもしれません。なんだ町工場かと、肩を落とさないでください。町工場、そして高専の工場こそ、工業の始点にして加工技術の入門書的位置にあります。高専の工場とはどのような施設で、何をしており、何を学ぶことができるのか。
ぜひ最後までご覧ください!
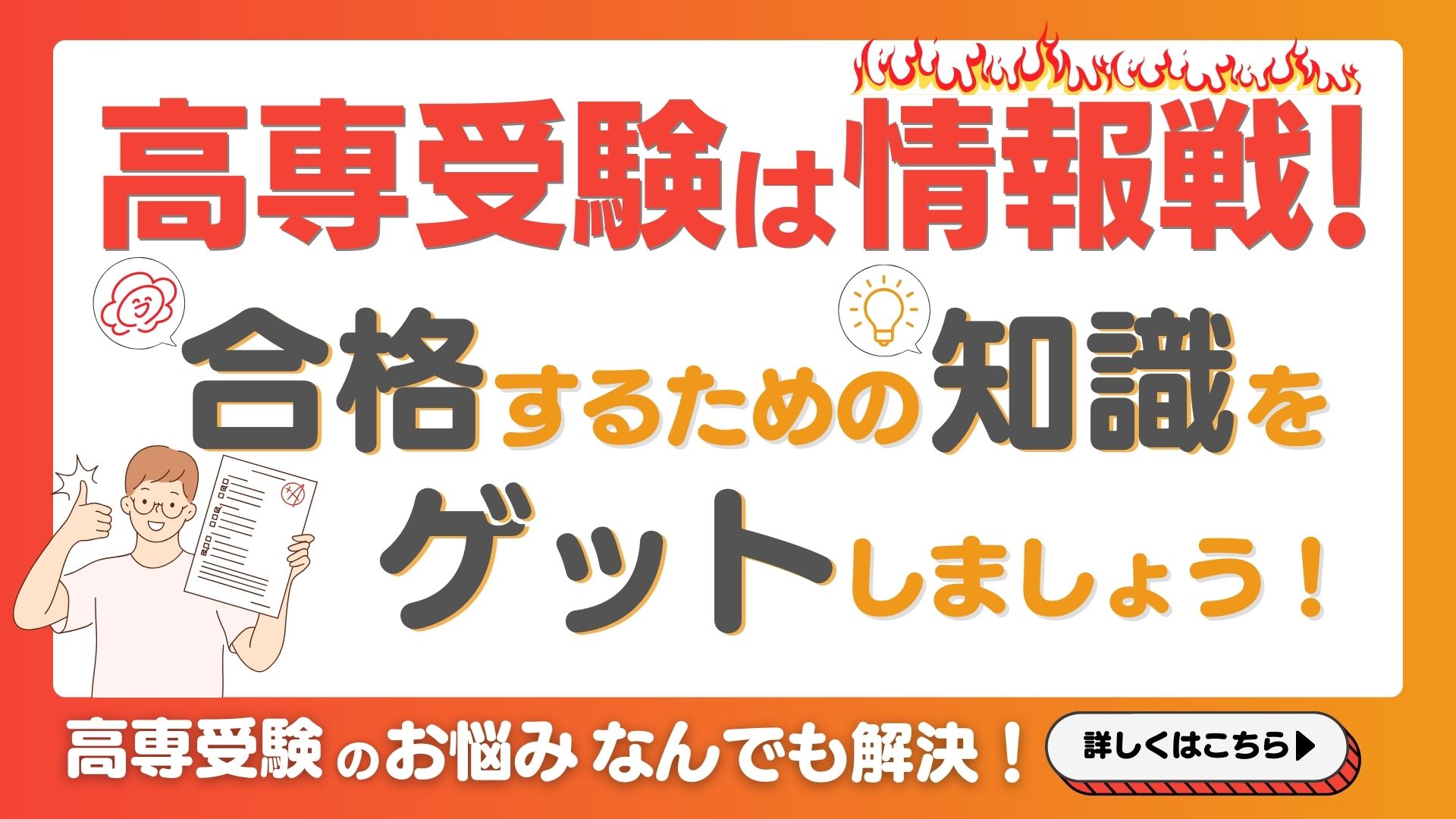
高専の工場って何をするところ?学科別の実習内容をチェック!
高専生の多くが工場に抱いている印象は、「実習を行う場所」でしょう。
では実際にどのような実習が行われるのか、私の出身である木更津高専のカリキュラムを参考に紹介します。
機械工学科
機械工学科は1年ではボール盤とアーク溶接について学びます。
ボール盤とは、ドリルで垂直に穴をあけるための工作機械。アーク溶接とは、放電現象で金属を溶かしながらつなぎ合わせる手法です。
2年では溶接と基本加工に加え、鋳造と旋盤について学びます。
鋳造とは溶かした金属を型に流し込み成型する手法。旋盤については次の章で解説します。
3年では鋳造、旋盤に加え、フライス盤とレーザ加工機について学びます。この2つも後で紹介いたします。
4年ではこれまでの内容に加え、新たにガス溶接を学びます。
ガス溶接は電気ではなく可燃性ガスと酸素を用いて、燃焼時の熱で金属を溶かしてつなぎ合わせる手法です。
電気電子工学科・電子制御工学科
電気電子工学科では3年、電子制御工学科では2年で工場での実習を行います。内容はともにアーク溶接、旋盤、NCフライス盤、基本加工を学びます。旋盤、NCフライス盤については次の章で紹介します。
環境都市工学科
環境都市工学科では、他の学科とは異なり金属加工の実習はありません。その代わり、材料実験や土質実験などの科目を工場で行います。特に材料実験では、コンクリートの供試体を製作し強度試験を行います。
工場に並ぶ「工作機械」ってどんなもの?
工場には、様々な工作機械が揃えられています。年季の入ったものから、1000万円を超える高額なものまで様々です。ここでは、そんな中から代表的なものをピックアップして紹介します。
旋盤・フライス盤などの汎用工作機械
旋盤は円筒形の材料を回転させ、そこに刃物をあてて切削する工作機械です。高専の工場で単に旋盤と言った場合は汎用旋盤を指し、実習で主に学ぶのもこれです。動作のほとんどが手動ですので、使用者の腕が出来栄えを大きく左右する機械でもあります。実習ではアルミを切削し、小さなコマなどを製作します。旋盤で製作したコマはとても精度が高く、小さくてもよく回転します。
フライス盤はドリルのように工具を回転させ、それを切削したい形状に添わせるように動かすことで加工する工作機械です。旋盤同様に工場では汎用フライス盤を主に学びます。実習ではアルミの切削を通して使い方を学びます。
プログラミングで加工する!NC工作機械
NC工作機械とは、NC加工を行うことのできる工作機械を指します。NCとは「Numerical Control」の略であり、数値制御の意です。NC工作機械はプログラムで加工することができ、汎用工作機械よりも複雑な形状を正確に早く繰り返して加工することができます。実習ではNC加工プログラムを学ぶとともに、機械工学科ではレーザ加工機、電気電子工学科・電子制御工学科ではNCフライス盤を用いて実際に加工を行います。
レーザ加工機
レーザ加工機は名前の通り、レーザを用いて切断などを行う工作機械です。細いレーザ光により加工するため、微細な加工にも対応できます。工場にあるものは、主にアクリルなどの樹脂やMDF等比較的熱に弱く加工が簡単な材料を加工することができます。木製の板からパーツを抜き出して組み立てるパズルは断面が黒く焦げていますが、これはレーザ加工機によるものです。
NCフライス盤
NCフライス盤はNC加工プログラムにより自動で加工できるフライス盤で、手加工では難しい複雑な曲線や3次元形状を加工することが可能です。金属加工も可能ですが、実習ではアクリル板に溝を掘って模様を作ります。アルミ削り出しと言われる場合、そのほとんどがNCフライス盤やその発展の工作機械によって製作されています。
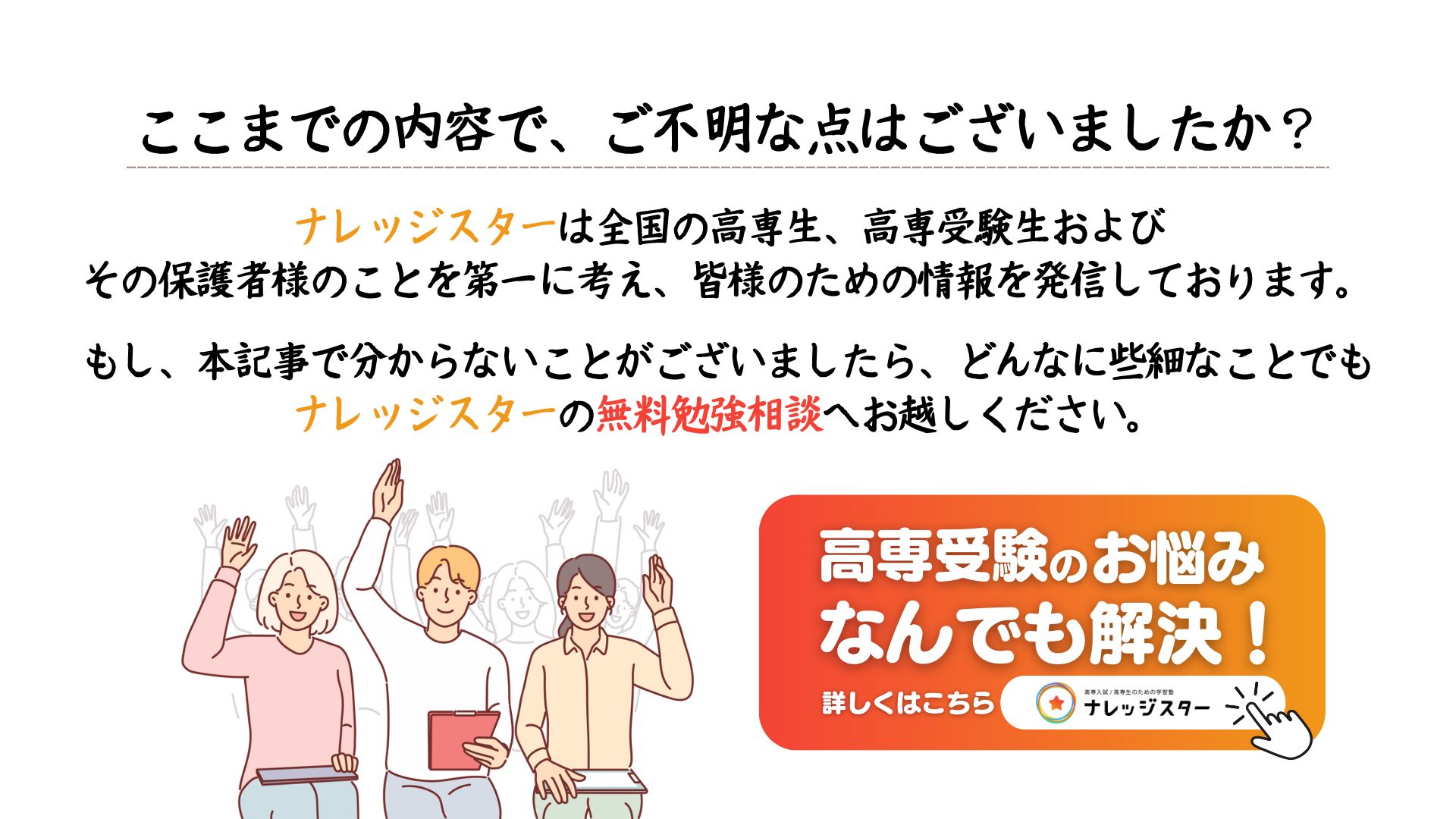
ロボコン・研究室御用達、ものづくりを支える技術
高専の工場は、実習を行うだけの場所ではありません。他にも存在する重要な役割を紹介します。
自分達では作れないものを作ってくれる
ロボコン団体や研究室などで欲しい部品があった際、自身で製作できたり安く購入できたりすれば良いのですが、製作できない・購入できない場合というのは多くあります。そんな時に工場の設備を借りて製作したり、あるいは代わりに製作してもらうことがあります。すぐに、難しい加工のできる環境があるというのは、ものづくりにおいて大きなアドバンテージとなります。
工具・機械をメンテナンスしてくれる
工場内にある工作機械や道具の管理はもちろんのこと、工場以外の工作機械や道具のメンテナンスも工場が行うことがあります。私の例を挙げますと、ロボコンの会室内にあった旋盤のメンテナンスやドリルを研ぐ作業を工場にお願いしていました。
実はすごい!高専を支える「技術職員」さんの職人技
ここまで工場とひとくくりに書いていましたが、工場の技術とはすなわち、工場で働く技術職員さんの技術です。技術職員さんはそれぞれが熟練した技術と豊富な知識を持っており、学生を技術で支える重要な役割を担っています。技術職員さんをその風体から敬遠してしまう学生は一定数います。常に作業着で、いかにも職人といった雰囲気の方もいますので無理はないですが、話してみると皆優しくて親身な方ばかりです。普段の座学を教えてくれる教員とはまた違った話が聞けるはずですので、ぜひ臆さずコミュニケーションをとってみてください。
まとめ-高専のものづくりの一番の味方
この記事では、高専の工場について紹介しました。どのような施設か、想像していただけたでしょうか。工場は学生のものづくりを支えてくれる、一番の味方といっても過言ではありません。技術職員さんも質問をすれば熱心に答えてくれます。皆さんも高専でものづくりをする際には、工場を最大限活用してください。必ず助けになるはずです。私もまた技術職員さんと同じように、皆さんのものづくりを応援しております。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
無理な勧誘は一切いたしませんので、ぜひお気軽にご相談ください!
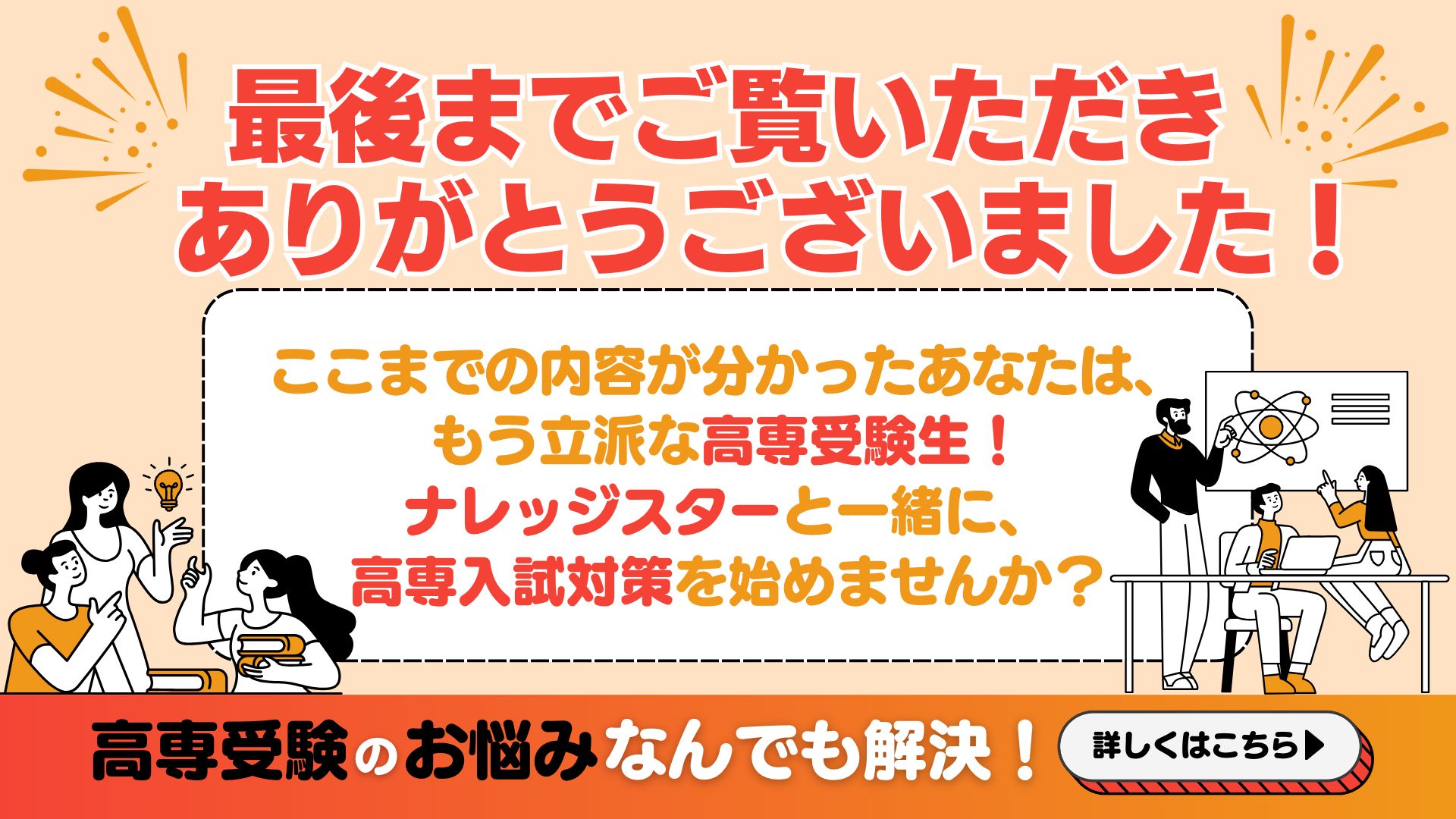
ライター情報
[出身高専 学科] 木更津工業高専 電子制御工学科 卒業
[氏名] 鈴木利久
[自己紹介]
木更津高専ではロボコンに取り組み、機械設計を行っていました。その後編入した大学でもロボコンに取り組み、大学院ではロボット分野の研究をしています。機械・電気・情報を問わず、ものづくりの楽しさが広まると嬉しいです