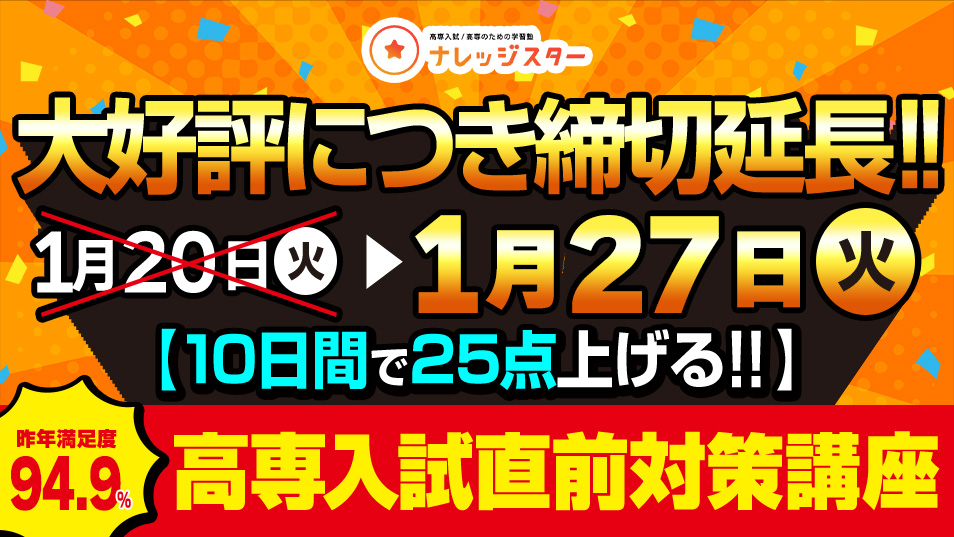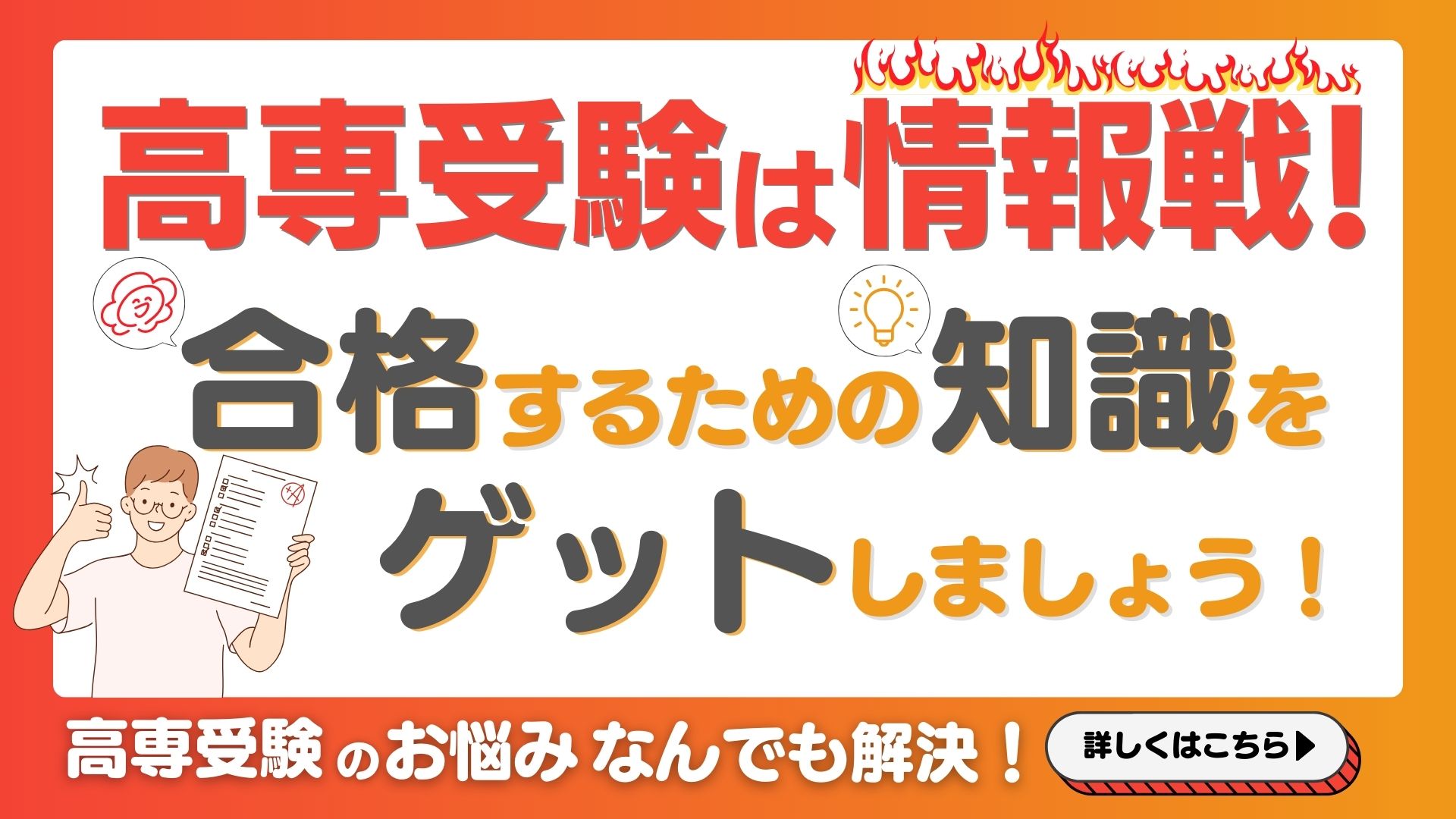
はじめに
- 卒業研究(卒研)、何から手をつけていいか分からない…
- 研究がうまく進まないけど、これで卒業できる?
- そもそも、卒研の成績ってどうやって決まるの?
高専生活の集大成であり、卒業するためのラスボスとも言える卒業研究。5年生になってから約1年間、研究室に配属され、研究、データ収集、まとめ、発表、そして論文作成と、長い道のりを進むことになります。高専で学んだことの集大成と分かっていても、初めての経験ばかりで不安に感じるのは当然です。この記事では、多くの高専生が抱く評価の不安に焦点を当て、先生たちがどこを見てどのように点数をつけているのかを徹底解説します。評価の仕組みを知れば、不安は解消できます。何を頑張ればいいのか、その指針を手に入れて、自信を持って研究を進めましょう!
卒業研究の評価とは
まず知っておいてほしいのは、卒業研究の評価はテストの点数とは全く違うということです。
卒業研究の評価は、多くの場合減点法ではなく、日々の頑張りを積み重ねていく加点法で決まります。学校や学科によって比率は異なりますが、評価は大きく分けて以下の3つの要素で構成されています。
- プロセス(日々の取り組み)
- 成果物(卒業論文)
- 最終発表(プレゼンテーション)
注目すべきは、多くの先生が日々の取り組みを非常に重要視していることです。最後の発表だけで全てが決まるわけではないのです。
では、具体的に各項目で何が見られているのか、解剖していきましょう。
点数のつき方
ここがこの記事の核心です。先生たちが各項目でチェックしているポイントを具体的に解説します。
① プロセス(日々の取り組み)点:配点の約30%〜40%
主な評価者: 指導教員(あなたのことを一番近くで見ている先生)
研究室に配属されてから発表が終わるまでの日々の行動が評価されます。
報・連・相(ほうれんそう)ができているか
- 「今、何に困っているか」「どこまで進んだか」を定期的に報告していますか?(先生は「報告がないこと」が一番困ります)
- 先生からのメールやチャットに、最低限の返信をしていますか?
自主性・積極性
- 言われたことだけをやる作業者になっていませんか?
- 自分で関連する論文や資料を調べようとしましたか?
- 「次はこれを試してみたい」と(下手でもいいから)自分で考えて提案しようとしましたか?
計画性
- (完璧に守れなくても)スケジュールを立てようとしましたか?
- 中間発表や論文提出などの締め切りを意識して行動していますか?
- 研究室での態度
- 研究室の仲間と協力したり、議論したりしていますか?
- 真面目に実験や分析に取り組んでいますか?
② 成果物(卒業論文)点:配点の約30%〜40%
主な評価者: 指導教員 + 他の教員(副査、学科の先生方)
最終的に提出する卒業論そのものの評価です。
最重要
すごい結果が出たかではない!
- 先生が見ているのは、ノーベル賞級の発見をしたかではありません。行ったプロセスを、論理的に説明できているかが全てです。
論理性と構成
- なぜこの研究をしたのか(背景・目的)
- 何を使ってどうやったのか(方法)
- 何が起きたのか(結果)
- なぜそうなったか(考察)
- この「背景→目的→方法→結果→考察」という型がしっかり守られていますか?
考察の深さ
- 「なぜこの結果になったのか?」「うまくいかなかった原因は何か?」を自分の頭で考えられていますか?
- (超重要!)失敗したならなぜ失敗したかを分析できていれば、それは100点満点の成果です。 失敗を隠す必要は全くありません。
体裁(フォーマット)
- 誤字脱字、図表の見やすさ、参考文献の書き方など、学校や学科のルールを守れていますか?これは仕様書や報告書を正しく書けるかという基本スキルのチェックでもあります。
③ 最終発表(プレゼン)点:配点の約20%〜30%
主な評価者: 指導教員 + 学科の全教員
最後の卒業研究発表会でのプレゼンテーションの評価です。
分かりやすさ
- あなたの研究を全く知らない、専門外の先生が聞いても、何をやったかが最低限伝わる内容ですか?
- スライドのデザインは見やすいですか?(文字が小さすぎないか、色はチカチカしないか等)
時間厳守
- 決められた発表時間(例:8分)を守れていますか? オーバーしたり、逆に短すぎたりしませんか?
- ここで「ちゃんと練習してきたか」がバレます
質疑応答
- (超重要!) 完璧に答えられる必要はありません。
- 大事なのは質問の意図を理解しようとすること。見当違いの回答をしていませんか?
- 本当に分からない場合は、ごまかさずに「勉強不足で分かりません。調査します」と正直に言える誠実さも評価ポイントです。
よくある質問
Q1. 研究が思うように進みません。結果が出ないと点数は低いですか?
A. 低くなりません!断言します。
上記で何度も繰り返した通り、先生が見ているのは結果ではなく、そこに至るまでの思考のプロセスです。
例えば「光触媒の効率が上がらなかった」という結果でも、「Aという方法を試したがダメだった。原因はおそらくXだと考え、次はBの方法を試した。それでもダメだった。今後の課題はYだ」と、試行錯誤の過程を論文や発表で論理的に説明できれば、評価はむしろ高いです。
Q2. 誰が最終的な成績(S, A, B, C…)を決めるんですか?
A. 指導教員だけでなく、複数の教員(学科会議など)で話し合って決めることがほとんどです。
指導教員が「A(優)だな」と思っていても、他の先生が最終発表や論文を見て「B(良)が妥当では?」と評価すれば、それらを総合的に判断して最終成績が決定されます。
だからこそ、指導教員しか見ていないプロセスだけでなく、他の先生方の目にも触れる成果物(論文)と最終発表も、手を抜かずにしっかり準備することが大切なのです。
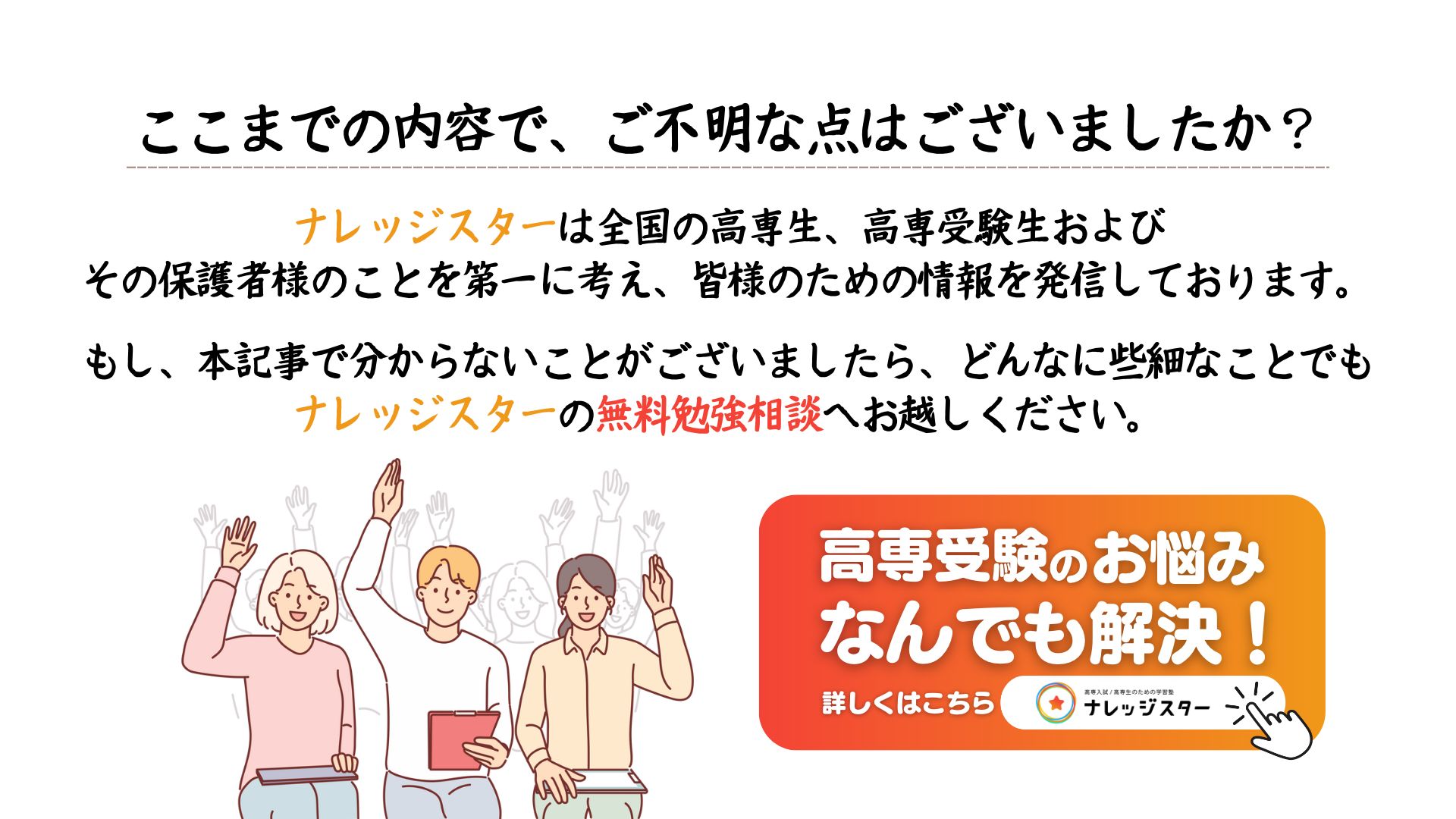
高評価を受けるためには
最後に、卒業研究を乗り切り、良い評価を得るために、これだけは守ってほしい3つのルールを伝えます。
1.先生とこまめに相談する
一番やってはいけないのが、一人で抱え込んで音信不通になること。先生は進捗が分からないことが一番不安です。進んでいなくても「今、ここで困ってます」と相談するだけで、プロセス点は加算されます。
2.失敗を考察に変える
研究に失敗はつきものです。うまくいかない時こそ「なぜ?」「どうすれば?」を考えるチャンス。実験失敗レポートではなく、失敗原因の分析レポートに昇華させましょう。
3.発表練習は他人に見てもらう
自分では完璧なスライドだと思っても、他人には伝わらないことがよくあります。研究室の仲間はもちろん、できれば家族や友人など研究内容を全く知らない人に一度見てもらいましょう。「何を言ってるか分からない」と言われたら、そこが改善点です。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ
卒業研究は、高専5年間(専攻科含め7年間)で学んだ知識や技術を総動員して、未知の問題に立ち向かう問題解決能力の集大成です。評価を恐れすぎる必要はありません。この記事で解説したように、先生たちはあなたの結果ではなく、悩み、考え、行動したプロセスを見ています。ぜひこの記事を参考にして、自信を持って、高専生活最後のプロジェクトを最後まで走り抜けてください!
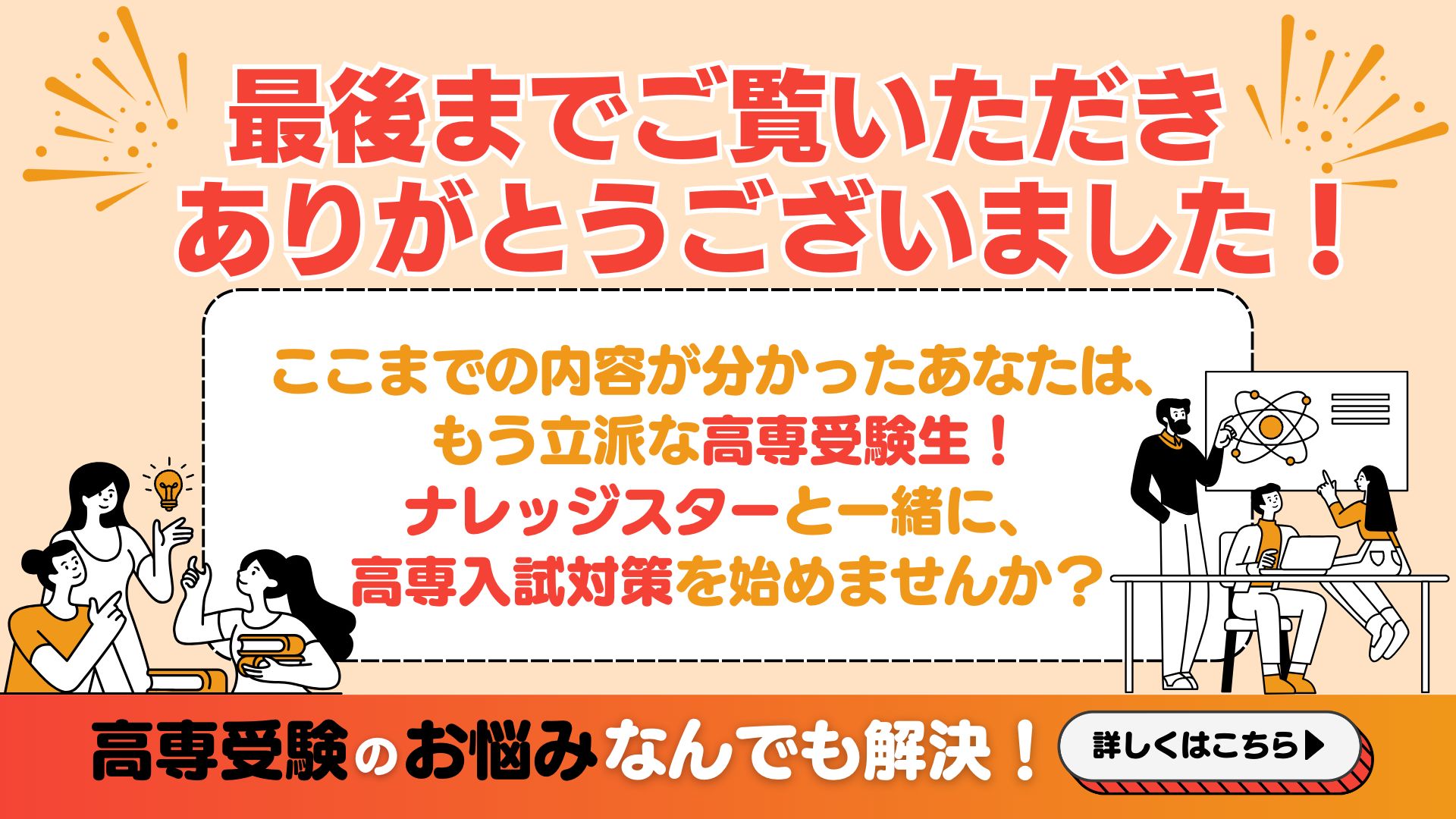
ライター情報
熊本高専 人間情報システム工学科
ハルキ
情報系の高専生。趣味は写真。