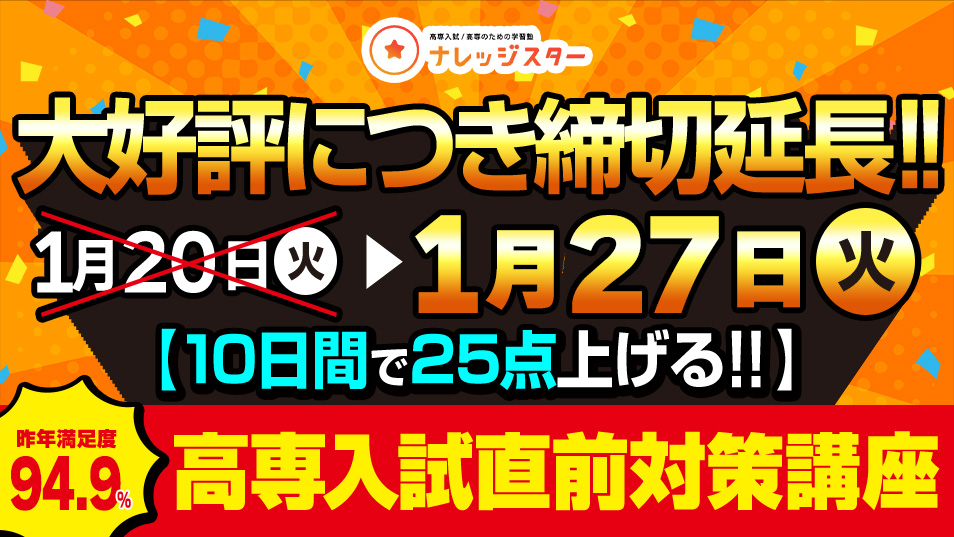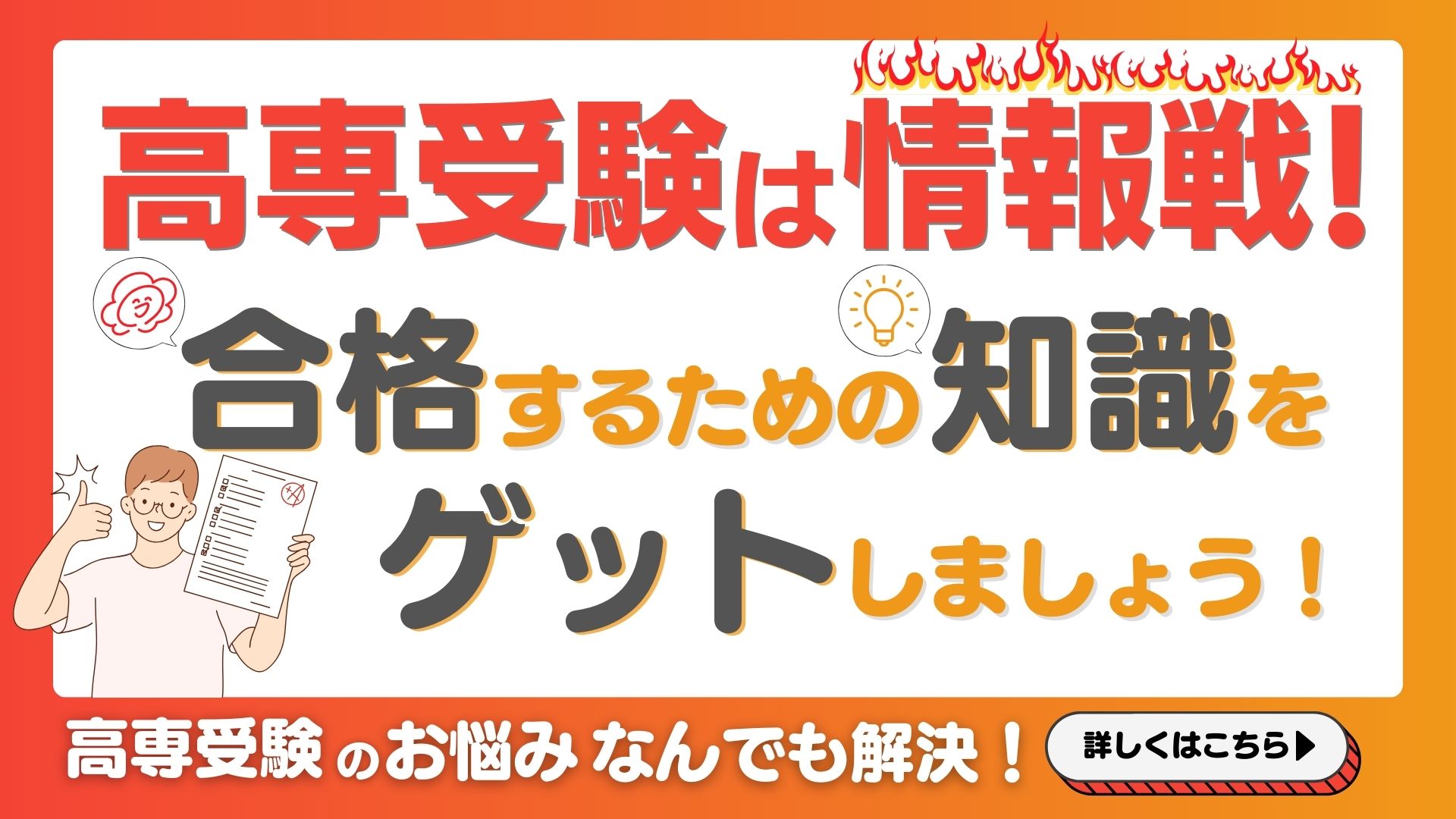
はじめに
高専生活にも慣れてきた中学年の方や、これから高専を目指す受験生にとって、「研究室」という言葉は少し遠い未来のように聞こえるかもしれません。
しかし、断言します。高専における「研究室配属」は、5年間の学びの価値を決定づける、まさに集大成ともいえる超重要イベントです。
「友達と同じ研究室でいいや」「なるべく楽なところがいいな」
そんな風に考えているとしたら、非常にもったいない選択をしてしまうかもしれません。
この記事では、高専の「研究室配属」とは何なのか、そして、その選択があなたの未来にどれほど大きな影響を与えるのかを、卒業生の視点から詳しく解説していきます。
そもそも高専の「研究室配属」って何をするの?
まずは、「研究室配属」がどのようなものか、基本的なところから説明します。
高専の先生方は、授業を行う教育者であると同時に、それぞれの専門分野で研究活動を行う研究者でもあります。そして、先生一人ひとりが自身の「研究室」を持っています。
研究室配属とは、学生がそのいずれかの研究室に所属し、指導教員となる先生のもとで約1年間(4年生配属の場合は2年間)、研究活動に取り組むことを指します。これは、高校にはない、高専ならではの非常に専門的で実践的な学びの場なのです。
卒業研究:5年間の学びを形にするラストイベント
研究室に配属された学生の最も大きなミッションは「卒業研究」です。
これは、指導教員の先生が持つ研究テーマに基づき、学生自身が主体となって研究を進め、その成果を最終的に一本の卒業論文にまとめるというもの。
この研究を進める上では、1年生から4年生までに学んだ数学、物理、そして専門科目の知識が不可欠となります。
「あの授業で習ったことは、この分析に使うためだったのか!」
といった発見の連続で、点と点だった知識が線として繋がる瞬間を何度も味わうことができるでしょう。
研究室配属はいつ?学年や時期について
研究室配属の時期は、高専や学科によって多少異なりますが、一般的には4年生の後期に配属先が決定し、本格的な活動は5年生の1年間を通して行われることが多いです。
高専によっては、4年生の前期から配属されることもあります。
面接や志望理由書、抽選を併用する学校もありますが、多くの高専では成績を重視するので日々の勉強も頑張りましょう!
5年生になると授業のコマ数はぐっと減り、学生生活の大半を研究室で過ごすことになります。実験、データ解析、論文調査、先生や仲間とのディスカッションなど、これまでの受け身の授業とは全く違う、能動的な学びが中心となる1年間が待っています。
失敗しない!後悔しないための研究室選びのコツ
5年生のほとんどの時間を過ごすことになるのは研究室です。その選択は、あなたの高専生活の満足度を大きく左右します。
どんな研究室を選ぶかによって、得られる知識やスキル、経験の質は天と地ほど変わってきます。ここでは、将来のあなたのために、後悔しないための研究室選びのポイントを具体的にお伝えします。
【要注意】やってはいけない研究室の選び方
まず、絶対に避けるべき選び方からお伝えします。
- 「仲の良い友達がいるから」
- 「『単位が取りやすく楽そうだから』という理由だけで選ぶ」
もちろん、気の合う仲間がいる環境は楽しいかもしれません。しかし、あなたの興味や成長に繋がらないのであれば本末転倒です。
また、「楽さ」を求めて研究室を選ぶと、何もスキルが身につかないまま卒業を迎えることになりかねません。社会に出てから本当に価値を持つのは「楽して卒業した」という事実ではなく、「何を学び、何ができるようになったか」です。
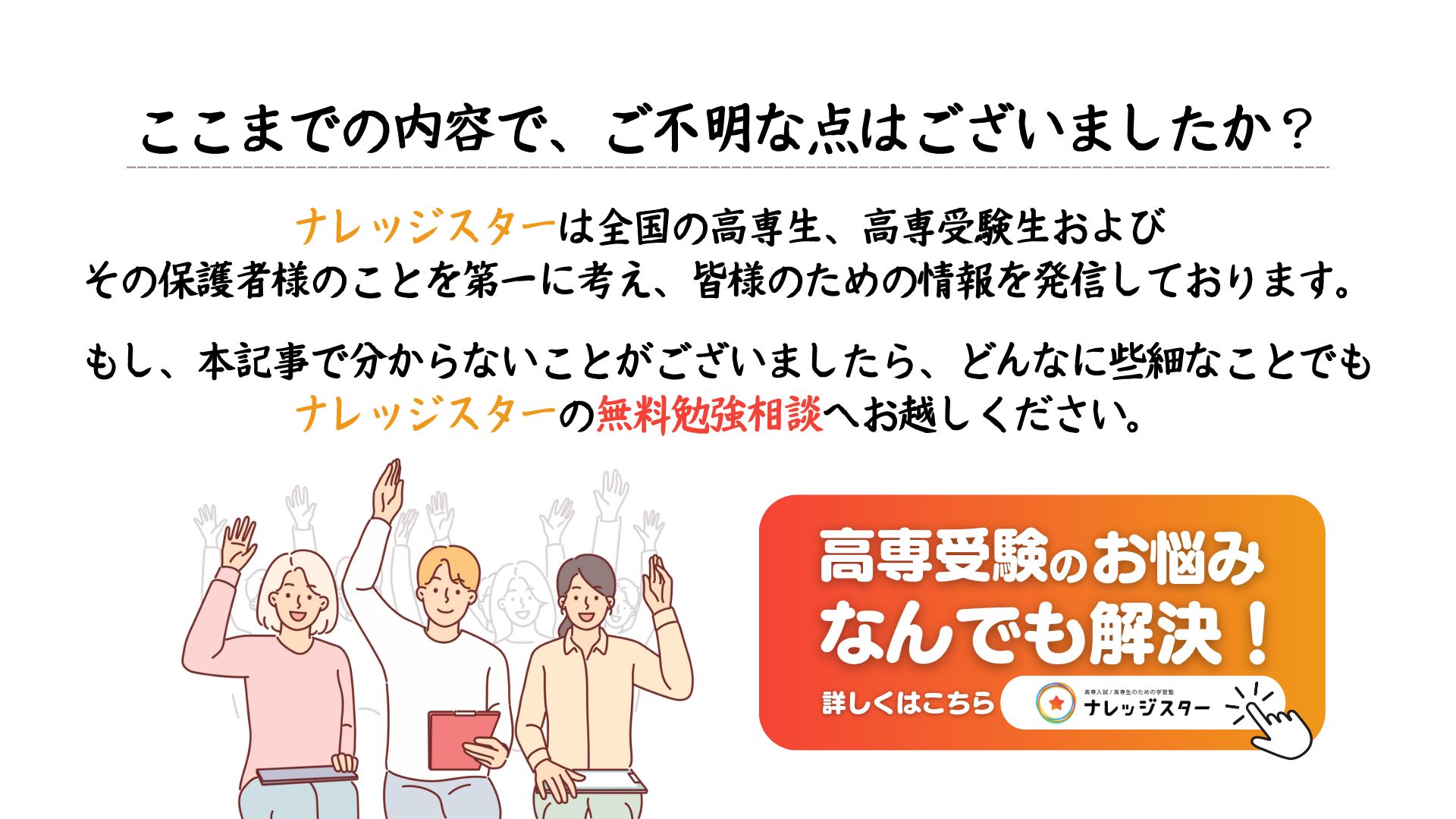
重要なのは「研究テーマ」と「先生」の2つ
では、何を基準に選べばいいのか。ポイントは2つです。
- その研究テーマに、あなたが心から興味を持てるか
- 指導教員となる先生が、学生に対して熱心に指導してくれるか
1年間という長い時間を費やすのですから、知的好奇心をくすぐられるテーマでなければ、モチベーションを維持するのは難しいでしょう。
また、いくらテーマが面白くても、先生が多忙で放置気味だったりすると、研究はなかなか進みません。先輩などから情報を集め、親身に相談に乗ってくれる先生の研究室を選ぶことが非常に重要です。
先生との相性が良いかは、非常に重要です。ミスマッチを防ぐためにも必ず研究室訪問に行くようにしましょう。
研究室での経験が進路(進学・就職)に影響する理由
研究室での活動は、単に卒業するための単位取得だけが目的ではありません。
そこで得た経験や実績は、大学編入や就職といった、あなたの将来の進路選択において、非常に強力な武器となります。
大学編入試験で圧倒的な強みになるワケ
高専からの大学編入を考えている学生にとって、研究室での経験は絶大なアドバンテージになります。
編入試験の面接では、「卒業研究で何に取り組みましたか?」という質問がされることが多いです。その際、自分の研究内容を論理的に、そして情熱を持って語ることができれば、他の受験生と圧倒的な差をつけることができます。
就職活動でも評価される「探求心」と「実践力」
就職活動においても、研究経験は大きなアピールポイントです。
一つのテーマに対して仮説を立て、実験や調査を行い、結果を考察するという研究のプロセスは、企業で働く上での問題解決プロセスと非常によく似ています。
研究活動に真剣に取り組んだ経験は、あなたが「未知の課題に対して粘り強く取り組める人材」であることの何よりの証明になります。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ:研究室配属はあなたの未来を変えるターニングポイント
今回は、高専生活の集大成である「研究室配属」の重要性について解説しました。
研究室での1年間は、決して楽なものではないかもしれません。しかし、そこで得られる知識、経験、そしてやり遂げたという自信は、あなたのその後の人生を支える大きな財産となります。
「友達と一緒」「楽だから」という理由で、この貴重な機会を無駄にしないでください。
自分の興味を信じ、熱意ある先生のもとで、5年間の学びを爆発させましょう。研究室配属は、あなたの未来を大きく変えるターニングポイントなのです。
【Q&A】高専の研究室に関するよくある質問
Q1. いわゆる「ブラック研究室」ってあるんですか?
A1. 残念ながら、存在する可能性はあります。例えば、先生の指導が厳しすぎたり、逆に完全に放任主義だったり、コアタイム(研究室にいなければならない時間)が非常に長いなど、学生にとって負担が大きい研究室を指すことが多いです。こうした情報を避けるためにも、配属前に先輩から話を聞くなど、情報収集をしっかり行うことが大切です。
Q2. 希望の研究室に入れないことはありますか?
A2. はい、あります。人気の研究室には希望者が殺到するため、成績順で配属が決まることが多いです。GPA(成績評価値)が高い学生から順に希望が通るシステムを採用している高専が一般的です。希望の研究室に入るためにも、1年生の時からの普段の授業や試験にしっかり取り組むことが重要になります。
Q3. 研究テーマは自分で決められるのですか?
A3. ケースバイケースですが、多くは指導教員の先生が持っている大きな研究テーマの枠組みの中で、より具体的な小テーマを学生が担当する形になります。先生と相談しながら、自分の興味やスキルに合わせてテーマを決めていくことが多いです。完全に自由にゼロからテーマを決めることは稀だと考えておくと良いでしょう。
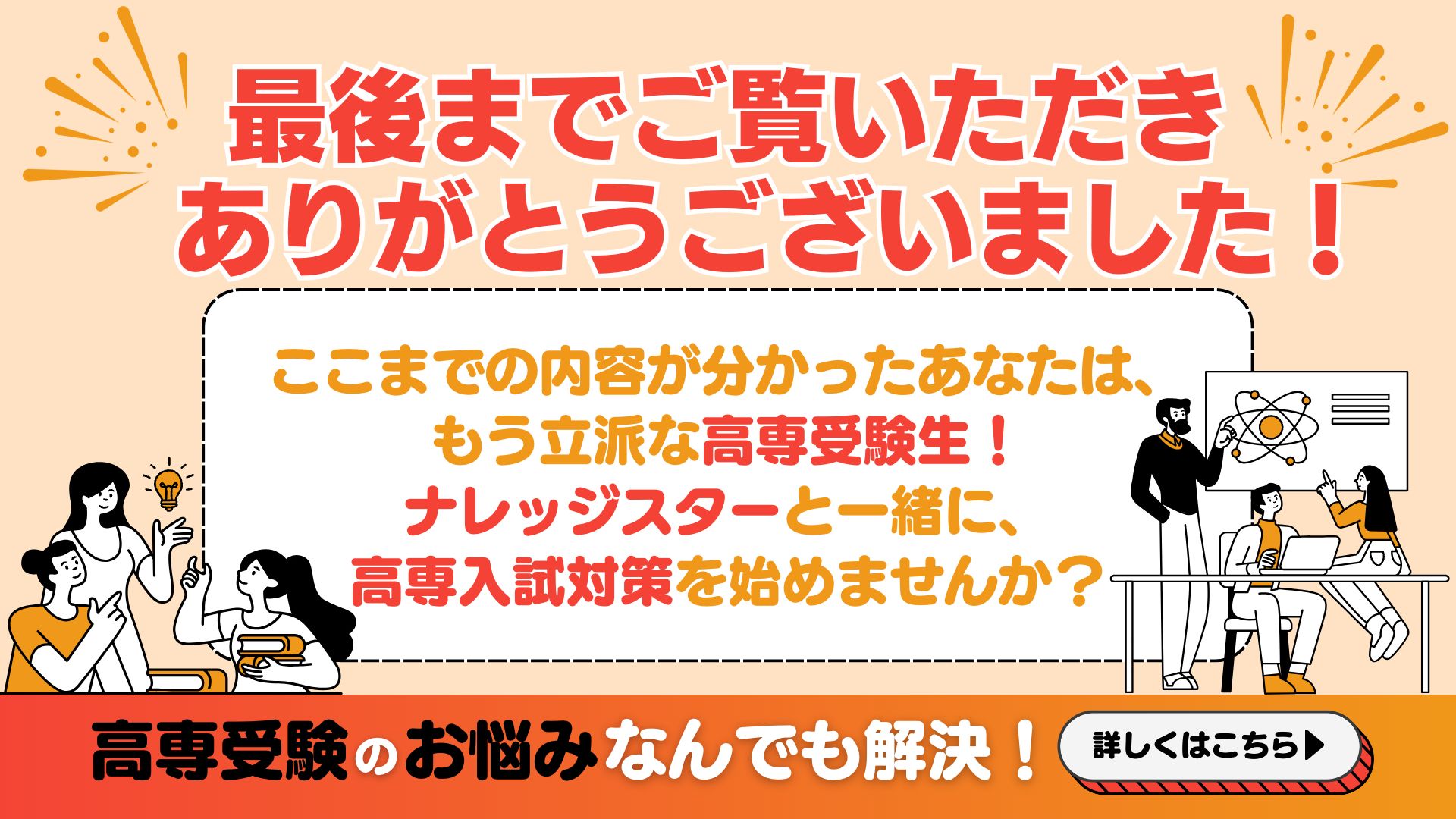
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。