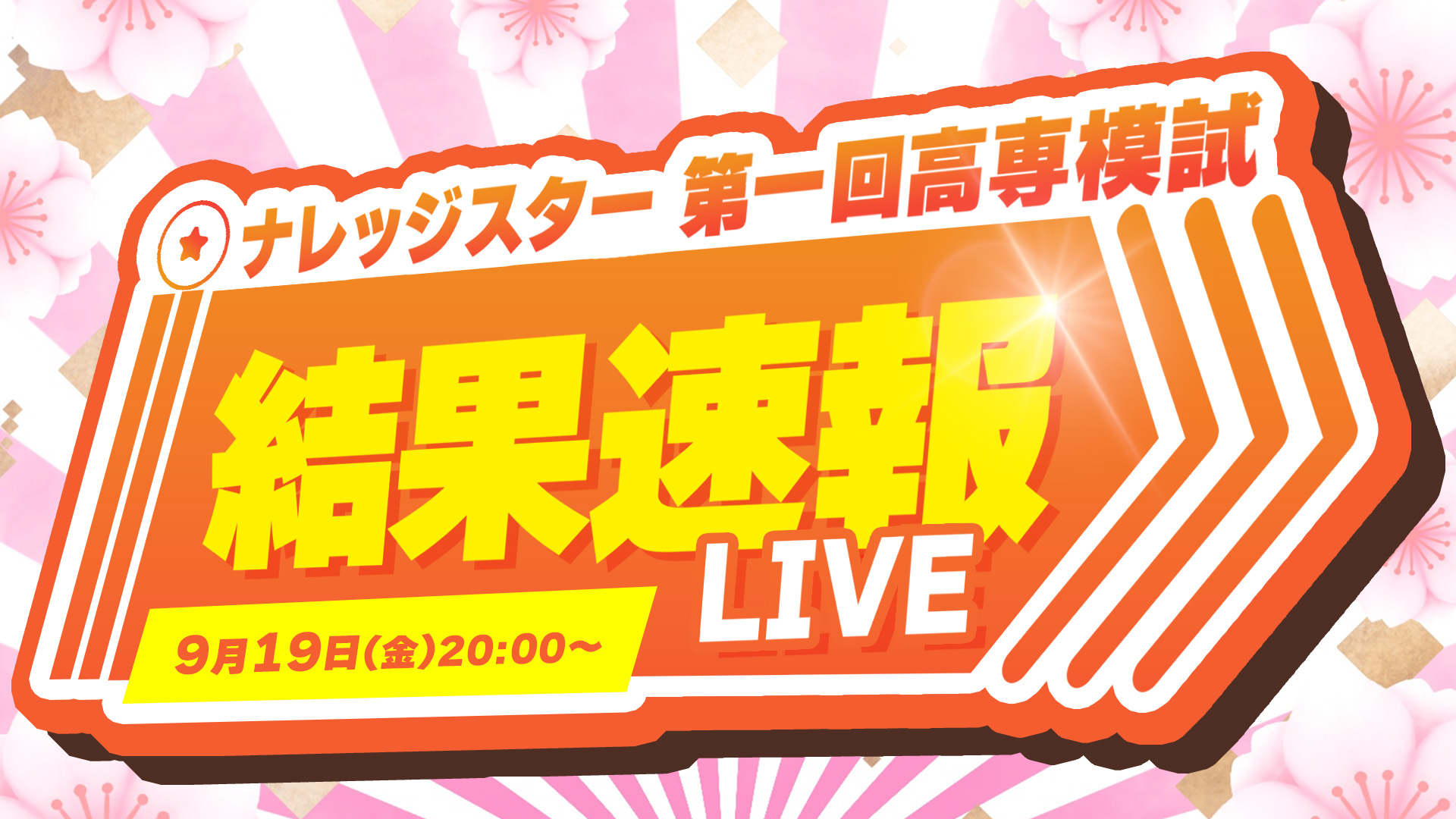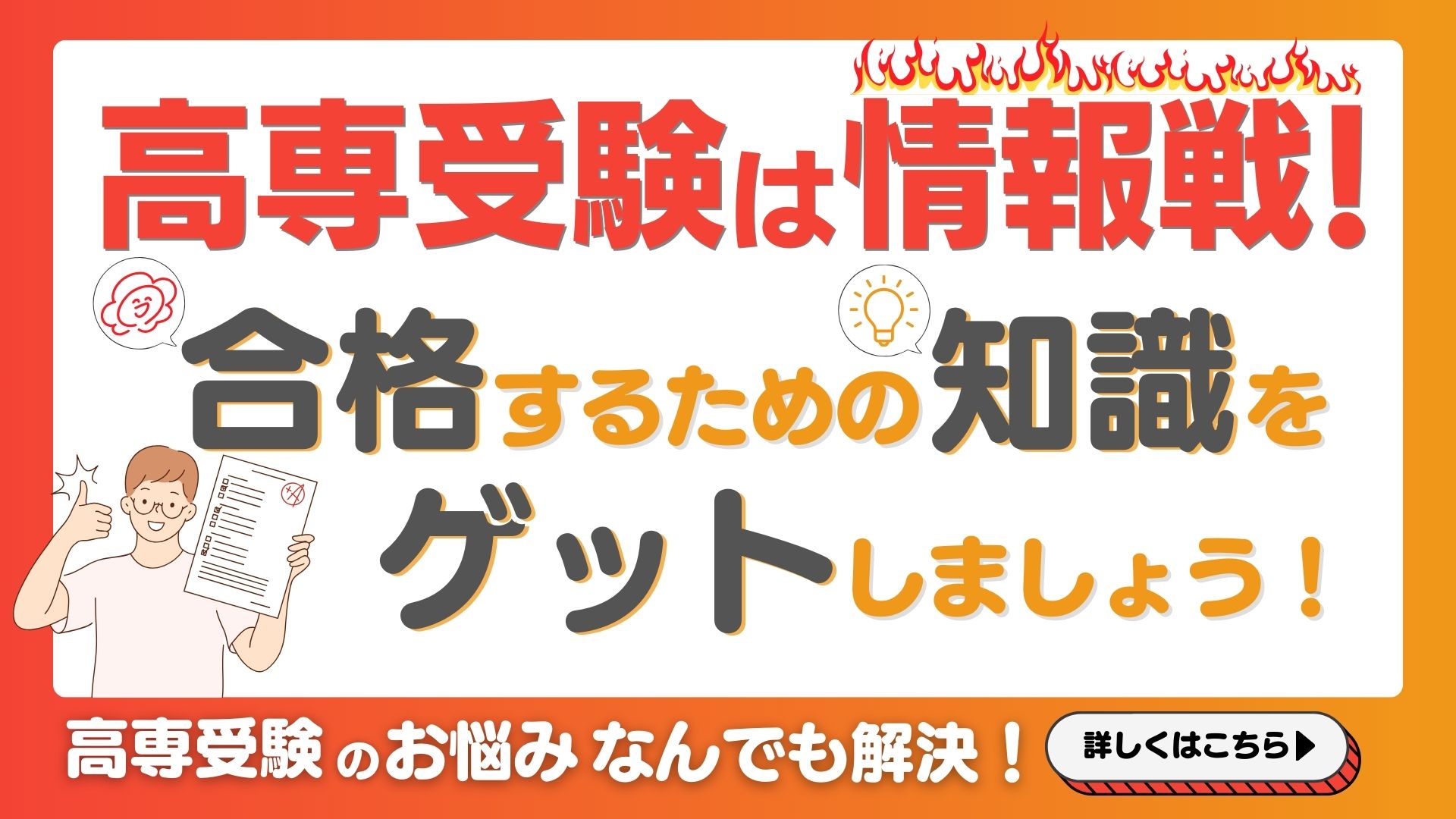
高専入試の全体像を把握
勉強を始める前にまずは高専入試の全体像を正確に把握することが重要です。
高専が求める人物像(アドミッション・ポリシー)
まずはじめに知っておかないといけないことは高専は高校と比較して大きく異なっているということです。一言で高専を説明すると「技術者や研究者を育てるための、5年制の高等教育機関」です。そのため高専が求める人材像(アドミッション・ポリシー)が高校と比べて大きく異なります。
一例として以下に熊本高専と熊本高校の求める人材像(アドミッション・ポリシー)を紹介します。
熊本高専の求める人材像(アドミッション・ポリシー)
熊本高校の求める人材像(アドミッション・ポリシー)
2つの求める人材像(アドミッション・ポリシー)を比較すると熊本高専は技術者や技術に対して書かれていますが、熊本高校は技術などの特定の分野によらず広く抽象的に書かれています。
そのため、入試問題も、単に知識を問うだけでなく、「技術者としての素養」や「論理的思考力」を見極める意図を持って作成されています。この視点を持つだけで、問題への向き合い方が変わるはずです。
高専の筆記試験の範囲
高専入試において、数学と理科は非常に重要な科目です。これは多くの高専で配点が高く設定されていることからも明らかですが、理由はそれだけではありません。
高専の入試問題、特に数学は、中学校の教科書の章末問題レベルを超え、複数の単元を融合した応用問題が多く出題される傾向にあります。例えば、一次関数と図形、確率と方程式といったように、1年生から3年生までの知識が体系的に繋がっていないと解けないように設計されています。これは、知識の暗記量ではなく、知識を活用して未知の問題を解決する「思考力」を試しているからです。
なぜこれほどまでに数学と理科が重視されるのかというと、数学が工学の基礎であり、理科がすべての科学技術の導入だからです。高専での5年間の専門的な学びは数学と理科の基礎の上に成り立っています。入学試験は、その厳しいカリキュラムについていけるだけのポテンシャルがあるかを見極めるための、最初のテストと位置づけられています。この試験の構造を理解することは、学習計画を立てる上で重要な指針となります。
内申点の重要性
高専入試は、学力検査一発勝負ではありません。多くの場合、学力検査の点数と内申点(調査書点)を合算して合否が判定されます。そして、この内申点の比率が、時には全体の50%近くを占めることもある、非常に重要な要素です。
内申点は、単なる学校の成績以上の意味を持ちます。これは、受験生の素質を示すスコアと考えることができます。高専の先生たちが見ているのは、テストの点数だけではありません。日々の授業に真面目に取り組む姿勢、提出物をきちんと出す責任感、そして3年間を通じて安定した努力を続けられる継続力。これらはすべて、将来、長い期間を要する研究やチームでのプロジェクト開発に不可欠な資質です。
つまり、日々の宿題や授業への集中といった取り組みそのものが、すでに入試の一部なのです。そして、これから紹介する「勉強ルーティン」は、学力検査対策であると同時に、3年生の2学期という最も重要な時期の内申点を最大化するための戦略でもあります。
勉強のルーティン作る上で大切なこと
これから勉強のルーティンを作る上で大切なことを4つ紹介します。
①具体的な目標設定
成功は、具体的な目標設定から始まります。勉強における設計図は「目標設定」です。しかし、「数学を頑張る」「毎日3時間勉強する」といった曖昧な目標は、達成が難しい傾向にあります。なぜなら、何をすれば「頑張った」ことになるのか、基準が曖昧だからです。
ここで役立つのが、「SMART」と呼ばれる目標設定のフレームワークです。
- S (Specific): 具体的に
- M (Measurable): 測定可能に
- A (Achievable): 達成可能に
- R (Relevant): 関連性がある
- T (Time-bound): 期限を設ける
これを、高専受験に当てはめてみましょう。
- 曖昧な目標: 夏休み中に数学を頑張る。
- SMARTな目標: 「夏休みの終わり(8月31日)までに、中学1年・2年生の数学の教科書にある『方程式』と『関数』の章末問題を、すべて9割以上正解できる状態にする」
この目標は、具体的で(方程式と関数)、測定可能で(9割正解)、達成可能で(1・2年の範囲)、高専入試に関連性があり(数学の基礎)、期限も明確です(8月31日)。このような目標を立てることで、毎日「何をすべきか」に迷うことがなくなります。
②時間の管理と記録
目標が決まったら、日々の行動に落とし込みます。ここで重要なのが、勉強の「計画」と「記録」です。
- 計画を立てる: まずは1週間の大まかな計画を立て、前日の夜か当日の朝に「今日やることリスト(To-Doリスト)」を作成しましょう。「数学の問題集 P.10-15」「英単語50個覚える」のように具体的に書くのがコツです。
- 時間を区切る: 25分集中+5分休憩のように時間を区切ると、集中力が持続しやすくなります。
- 記録をつける: 勉強時間記録アプリや手帳を使って、「何を」「どれくらい」勉強したかを記録しましょう。自分の頑張りが可視化されることで、達成感が得られ、モチベーションに繋がります。
③科目別の勉強方法
目標設定と時間管理の術を身につけたら、各科目を攻略するための戦略を立てましょう。高専入試の特性に合わせたアプローチが不可欠です。
- 数学:「積み上げ」の科目 高専数学は、積み上げるような科目です。1年生の土台が不安定だと、その上に2・3年生の知識を安定して積み上げることはできません。3年生の応用問題でつまずく原因の多くは、1・2年生の範囲にあります。夏休みは、焦って先の単元に進むのではなく、徹底的に1・2年生の教科書に戻ることが重要です。「正負の数」「文字式」「方程式」「関数」「図形の証明」といった基礎を完璧にすることが、高専レベルの応用問題に取り組むための土台となります。
- 理科:「つながり」の科目 物理、化学、生物、地学を、それぞれ独立した科目として捉えるのは非効率です。高専では、分野を横断して物事を理解する力が求められます。例えば、物理で学ぶ「電気」の知識は、化学で学ぶ「イオン」の理解を深めます。勉強する際は、常に「なぜそうなるのか?」「他の単元とどう関係しているのか?」という「つながり」を意識することで、知識が単なる暗記から、生きた知恵へと変わっていきます。
- 国語・英語・社会:「反復」の科目 これらの科目は、知識の定着に「反復」が効果的です。特に、英単語、漢字、古文単語、歴史の用語などは、一度で覚えようとせず、何度も繰り返し触れることが重要です。短い時間でいいので、毎日コツコツと触れる習慣をつけましょう。
④復習
どれだけ集中して勉強しても、復習をしなければ、その努力の効果は薄れてしまいます。ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」によると、人は学習した内容を、1日後には74%も忘れてしまうというデータがあります。
しかし、これは脳の仕組みを理解し、適切な戦略を立てれば克服できます。
今日学んだことを、寝る前か翌朝に軽く見直す。そして1週間後、さらに1ヶ月後に確認する。この習慣が、忘却を防ぎ、確実な学力の土台を築きます。
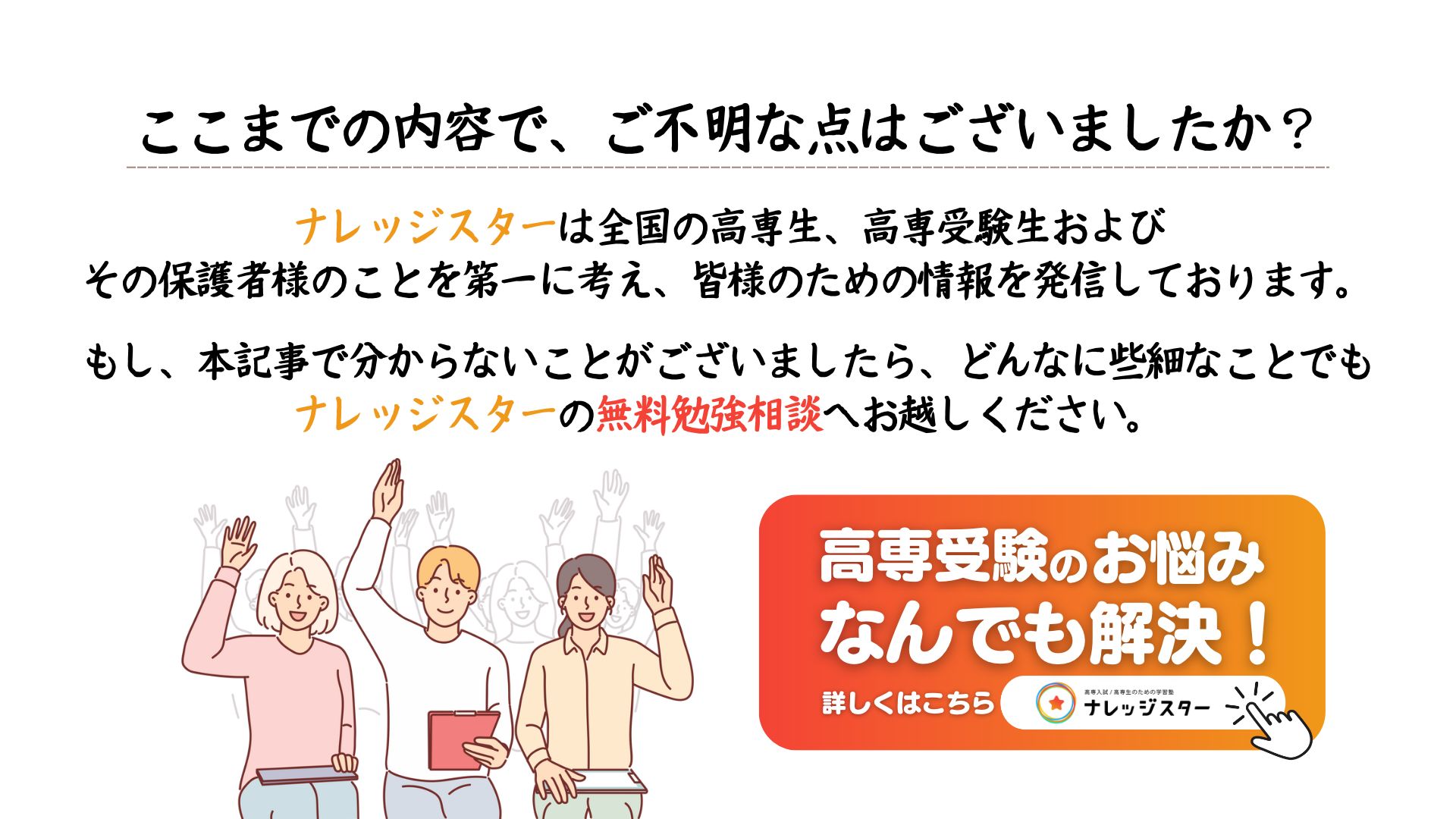
スケジュールを立ててみる
スケジュールの例として一日のスケジュールを紹介します。
| 時間 | 内容 | できたか |
| 朝(8:00) | 英単語・漢字の反復学習 | No |
| 午前中 | 学校 | No |
| 午後 | 学校・部活 | No |
| 夜(19:00-20:30) | 数学:二次関数、相似(教科書20-30p) | No |
| 夜(21:00-22:00) | 理科:化学変化、イオン式(問題集10-14p) | No |
毎日、または一週間の期間でスケジュールを作ってみましょう。
ここで、スケジュールを作る上で以下の3つに気をつけてください。
- 事前にスケジュールを立てる
- 具体的(どの単元で、どのページを勉強するのか)に内容を書く
- 決めた通りできたのか、どの程度できたのか、きちんと記録をつける
モチベーションの維持
やる気を待つのではなく、まず行動してみることが大切です。高専に入って何をしたいか(例:「ゲームを作りたい」「環境問題に役立つ開発をしたい」)を具体的に想像し、目の前の勉強と結びつけることで、それは単なる「作業」から、夢を実現するための「プロジェクト」へと変わります。これが、自発的な学習意欲に繋がります。
SNSなどで他の人の様子を見て焦りや落ち込みを感じる必要は一切ありません。比べるべき相手は、他人ではなく「昨日の自分」です。昨日より少しでも成長できた点に目を向け、自分のペースで学習を進めることが大切です。
そして何より、睡眠、食事、運動を大切にしてください。これらは最高のパフォーマンスを発揮するための、最も重要な要素です。計画的な休息こそが、合格への近道となります。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ
夏を前にして、「何から手をつければいいんだろう…」「計画通りに続けられるかな…」と不安に感じるかもしれません。しかし、この記事で紹介した目標設定のコツ、具体的な計画の立て方、そして科学的な学習法を一つひとつ丁寧に押さえていけば、必ず自分に合った「学習の型」が見つかり、自信を持って勉強を進められるようになります!
勉強の習慣化を通じて、ぜひ以下のことを意識してみてください。
- 目標を具体的に立てて、やるべきことを明確にしよう!
- 「計画」と「記録」を続けることで、自分の努力を可視化し、モチベーションに変えよう
- 他人と比べず「昨日の自分」の成長を認め、自分のペースを守ろう!
- 完璧を目指さず、まずは「机に5分向かう」から始めてみよう!
夏までに勉強ルーティンを確立するという経験は、単に志望校に合格するためだけのものではありません。ここで培われる「自分で目標を立て、計画し、実行する力」は、将来皆さんが社会の様々な分野で活躍するための、大きな力となるはずです。
受験勉強は長い道のりですが、その本番である夏を最高のものにするために。まずは準備運動として、新しい習慣作りを、楽しむくらいの気持ちで積極的に始めてみてください。
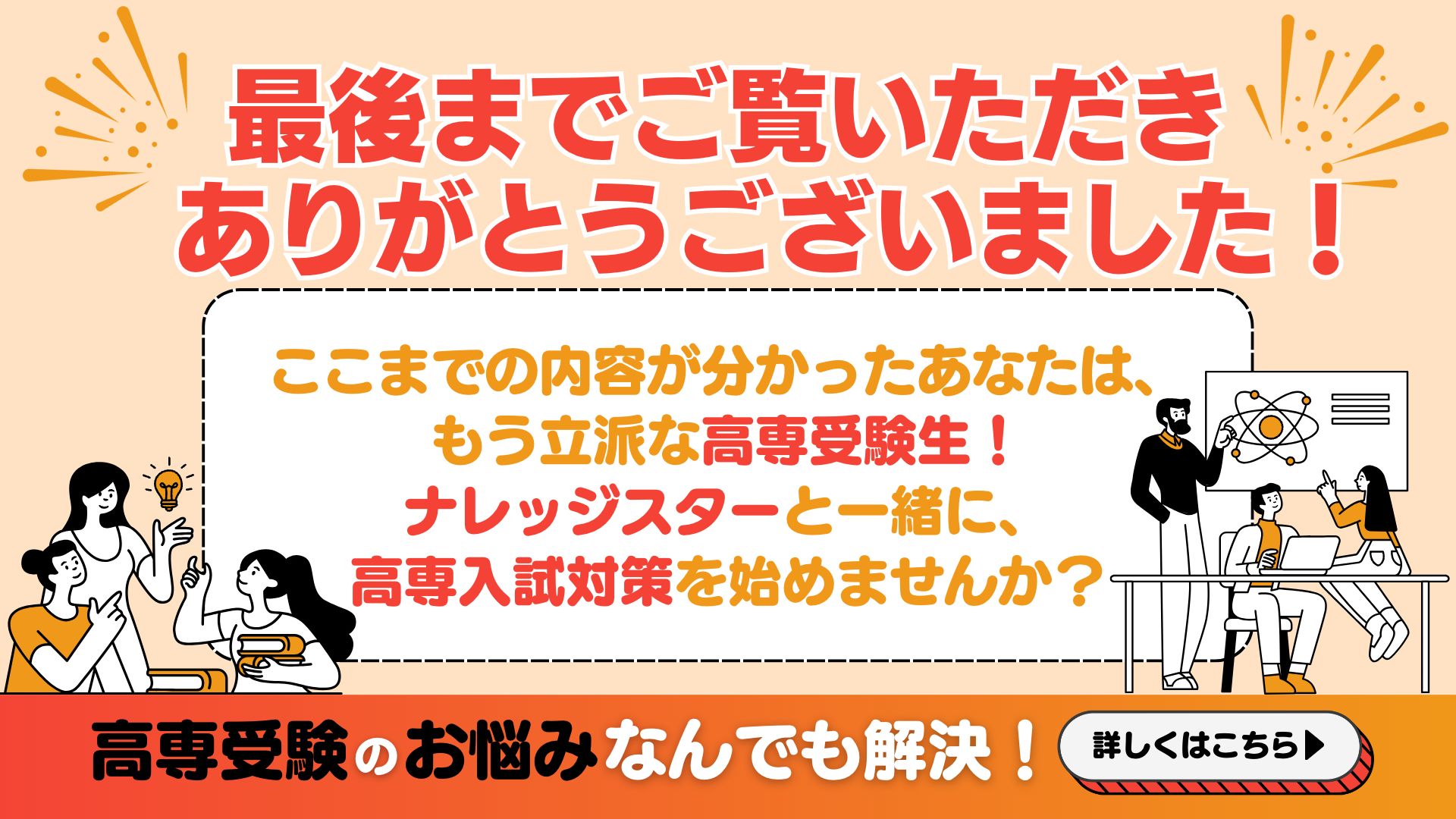
ライター情報
熊本高専 人間情報システム工学科
ハルキ
情報系の高専生。趣味は写真。