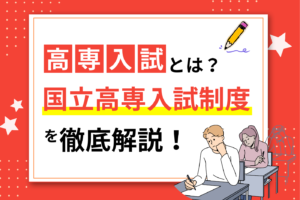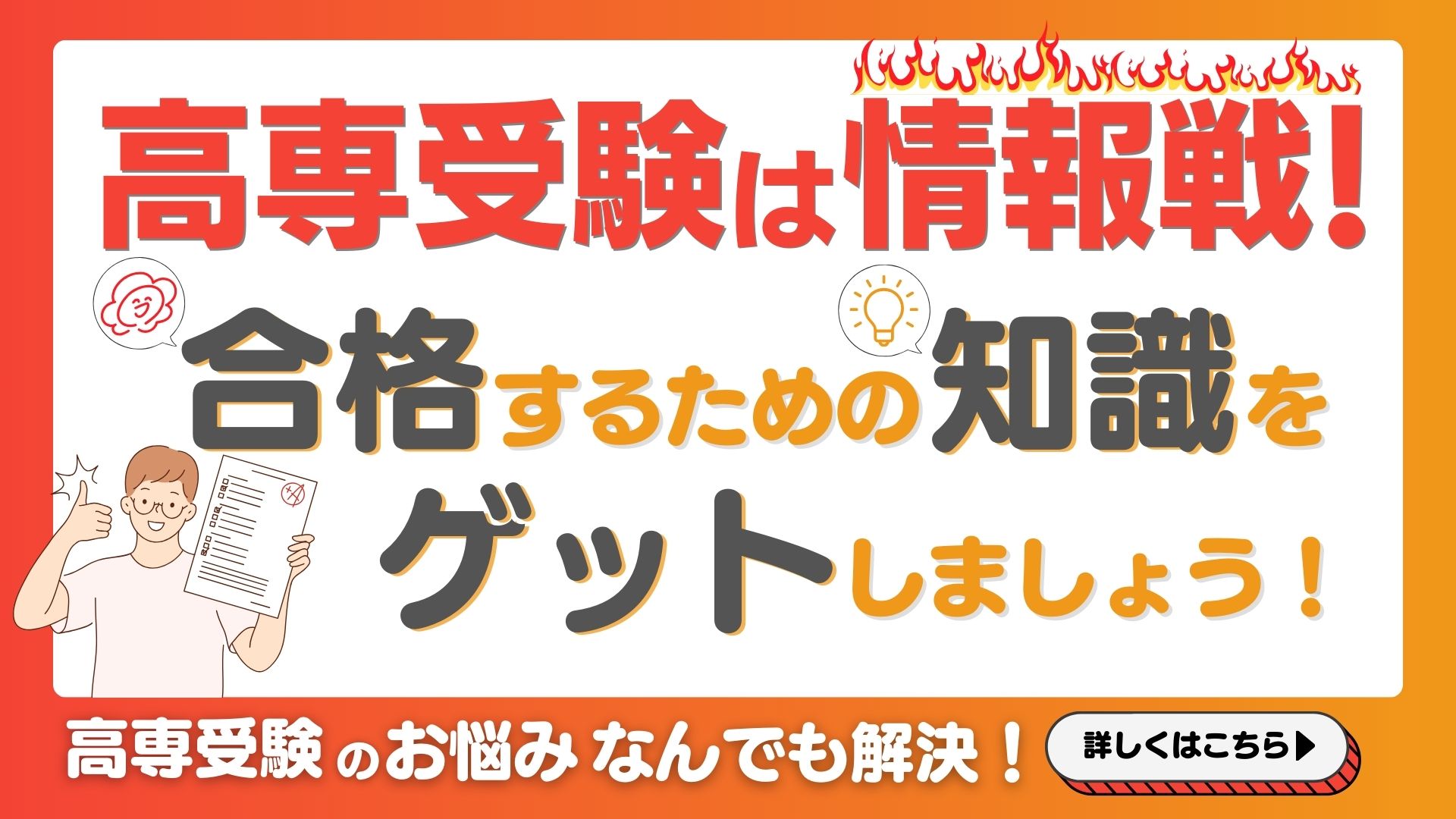
はじめに
「高専の推薦入試を受けたいけど、評定(内申点)がギリギリで不安…」
「もう推薦は諦めるしかないのかな…」
中学3年生の夏を過ぎ、進路が本格化してくるこの時期、こうした悩みを抱えている受験生や保護者の方は多いのではないでしょうか。高専の推薦入試は、学力試験を避けられる魅力的なルートですが、その鍵を握るのが「評定」であることは間違いありません。
この記事では、評定がギリギリな状況からでも高専合格を目指すための、具体的な戦略と戦術について詳しく解説します。
諦めるのはまだ早いです。あなたの現在地から合格を掴むための道筋がきっと見つかります。
まずは敵を知る!高専推薦入試の仕組みとは?
具体的な戦略を立てる前に、まずは高専の推薦入試がどのようなルールで行われているのかを正しく理解しましょう。特に重要なのが「評定の重み」と「募集要項の確認」です。この2点をしっかり押さえることが、逆転合格への第一歩となります。
推薦入試では『評定の比重が高い』高専が多いという現実
高専の推薦入試では、面接や小論文などが課されることもありますが、合否を左右する最も大きな要素は、実は「評定(内申点)」です。
高専にもよりますが、評価全体の8割から9割が評定で、残りの1〜2割が面接やその他、という配点の高専が非常に多いのが実情です。この事実をまずは冷静に受け止めましょう。
超重要!最初に「募集要項」を確認すべき理由
「評定が大事なのはわかったけど、具体的にどれくらい必要なの?」
その答えは、あなたが受験したい高専の「募集要項」にしか書かれていません。
推薦の基準は、全国の高専で全く異なります。「中学3年間全ての評定平均が4.2以上」という厳しい学校もあれば、「中学3年生の評定のみを見る」という学校もあります。自分のこれまでの成績表と募集要項を照らし合わせ、「そもそも出願資格があるのか」「あとどれくらい評定を上げればいいのか」を正確に把握することが、全ての戦略のスタートラインになります。
あなたはどっち?今すぐ評定を計算して戦略を立てよう
募集要項を確認し、自分の現在地が把握できたら、次はいよいよ具体的な戦略を立てるフェーズです。どちらの道を選んでも、それは合格に向けた正しい一歩です。
①評定が推薦基準に満たない場合の「一点集中戦略」
計算してみた結果、「次の学期でオール5を取っても、推薦基準には届かない…」ということが判明した場合。落ち込む必要は全くありません。むしろ、これはチャンスです。
あなたが進むべき道は、「推薦入試を潔く諦め、学力入試の対策に全てのエネルギーを集中させる」ことです。
多くの推薦受験生が面接練習に時間を費やす12月〜1月を、あなたは丸々学力アップのために使えるのです。この時間の差が、本番での逆転劇を生みます。
②あと少しで評定が推薦基準を満たし、まだ挽回可能な場合の「評定アップ戦略」
「次の学期、主要教科で5、副教科で4を取れれば、なんとか基準に届く!」というあなたは、「評定を1でも多く上げるための最大限の努力をする」戦略を取りましょう。
目標が明確になったことで、日々の学習へのモチベーションは格段に上がるはずです。具体的にどの教科をどれだけ上げなければならないのかをリストアップし、計画的に勉強を進めましょう。
もし、評価が3の科目がある場合はその科目を優先的に勉強しましょう。
評定が4の科目を5に上げるよりも、3から4に上げる方が簡単だからです。意識するようにしましょう!
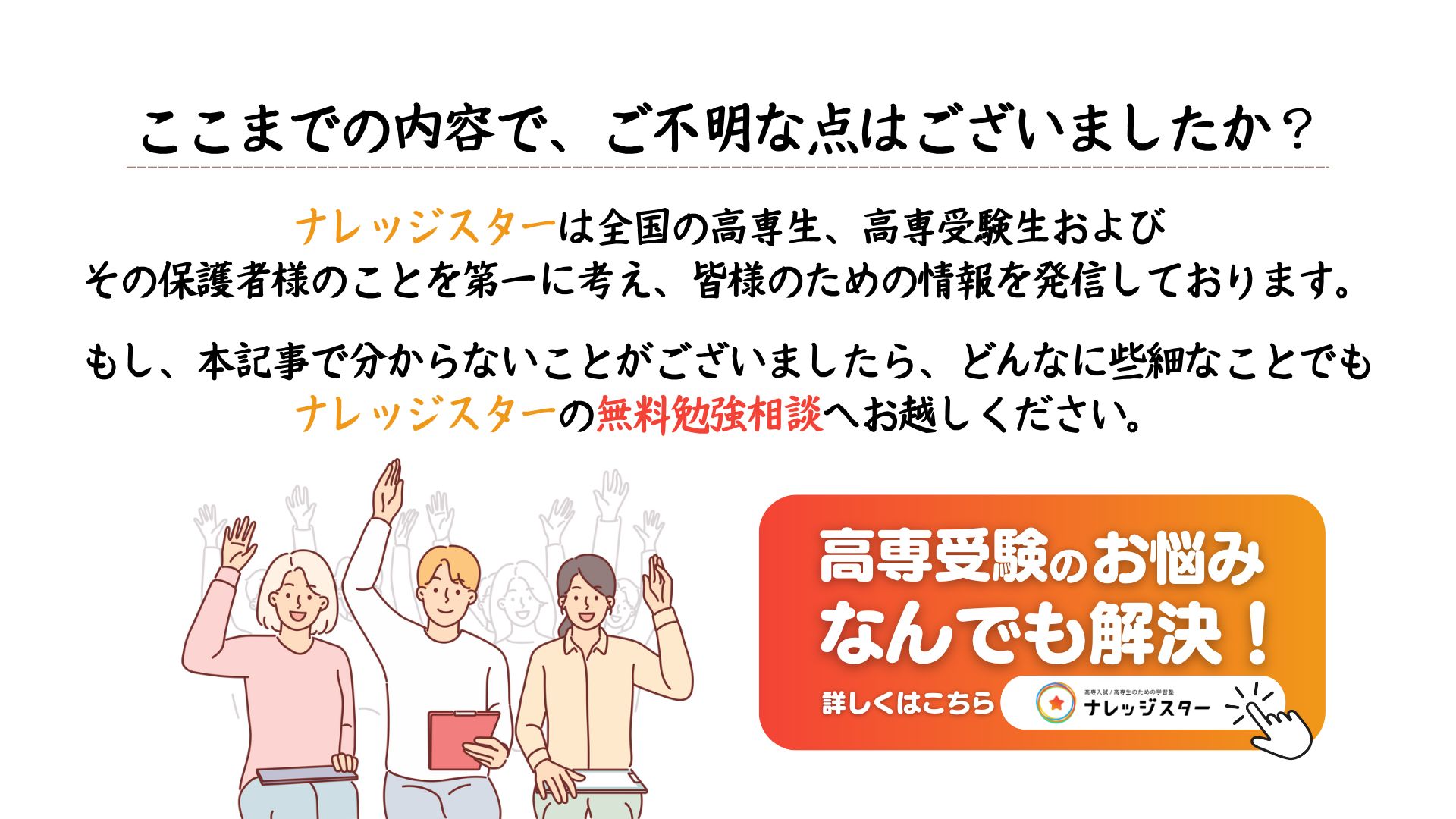
テクニックも重要!内申点を上げるための具体的な方法
評定アップの基本はテストの点数ですが、評定をつける「先生」の心を動かす少しの工夫が、結果を大きく左右することがあります。
①苦手科目の定期テストの点数を上げる
言うまでもありませんが、評定アップの基本は定期テストの点数です。特に、これまで評定が3だった科目を4に上げるなど、苦手科目の克服は必須です。
わからない箇所を放置せず、授業後すぐに先生に質問に行く、提出物は完璧な状態で期限前に出す、といった基本的な行動を徹底しましょう。
②先生に熱意を伝えるアピール術
テストの点数に加えて効果的なのが、「熱意」のアピールです。
例えば、どうしても評定を上げたい科目の先生のところに直接行き、「〇〇高専の推薦を受けたいのですが、どうしても先生の教科の評定が必要です。どうすれば5が取れますか?」と真剣に相談してみましょう。
また、授業中に目を輝かせて頷きながら聞く、体育の準備運動で誰よりも大きな声を出すなど、他の人が手を抜くところで全力を出す姿勢も、先生は意外と見てくれているものです。
推薦を諦めきれない君へ。2つの「別ルート」
「計算上は厳しいけど、やっぱり推薦の可能性を捨てきれない…」そんなあなたのために、視点を変えた2つのアプローチを紹介します。
① 推薦基準が違う他の高専を探してみる
あなたの志望校の推薦基準が厳しいだけで、他の高専ならクリアできる可能性は十分にあります。評定平均の基準値が低い学校や、中学3年生の成績しか見ない学校、さらには「部活動の実績」で推薦資格が得られるユニークな高専も存在します。少し視野を広げて全国の高専の募集要項を調べてみる価値はあります。
②「受かったらラッキー」精神で学力入試と両立する
推薦基準をギリギリ満たせそうな場合、最も賢い戦略は「推薦入試は受かったらラッキーと考え、勉強の主軸は学力入試に置く」ことです。合否のほとんどが評定で決まる以上、面接や小論文の練習に膨大な時間を費やすのは非常に効率が悪いです。最低限の対策はしつつも、日々の勉強は学力入試を見据えて進める。この冷静なスタンスが、最終的な合格の可能性を最も高めます。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ:推薦入試はゴールじゃない。自分に合った戦略で合格を掴もう
今回は、評定がギリギリな状況から高専の推薦合格を目指すための戦略についてお話ししました。
大切なのは、まず自分の現状を正確に把握し、感情的にならずに最適な戦略を選択することです。
推薦入試は魅力的な制度ですが、それが全てではありません。どんなルートを辿るにせよ、今の時期から評定を意識して日々の学習に取り組むことは、決して無駄にはなりません。自分に合った戦略で、春の合格を掴み取りましょう。
【Q&A】高専の推薦入試に関するよくある質問
Q1. 面接や小論文の対策はいつから始めるべきですか?
A1. 本格的な対策は、推薦入試の1ヶ月前くらいからで十分です。それ以前の時期は、合否に直結する評定を上げるための定期テスト対策や、学力入試の勉強に時間を使いましょう。合否の8〜9割が評定で決まるという事実を忘れず、時間配分を間違えないことが重要です。
Q2. 部活動や資格は推薦で有利になりますか?
A2. 高専や学科によりますが、全国大会レベルの実績や、専門分野に直結するような高度な資格は、評価の対象となる場合があります。しかし、多くの場合、評定ほどの決定的な影響力はありません。募集要項に加点対象として明記されているかを確認しましょう。
Q3. 学力入試でも評定(内申点)は見られますか?
A3. はい、多くの高専で学力入試の合否判定にも評定(調査書点)が加味されます。その比率は高専によって大きく異なります。いずれにせよ、高い評定を持っていて損をすることはありません。推薦を狙うかどうかにかかわらず、定期テスト対策はしっかり行いましょう。
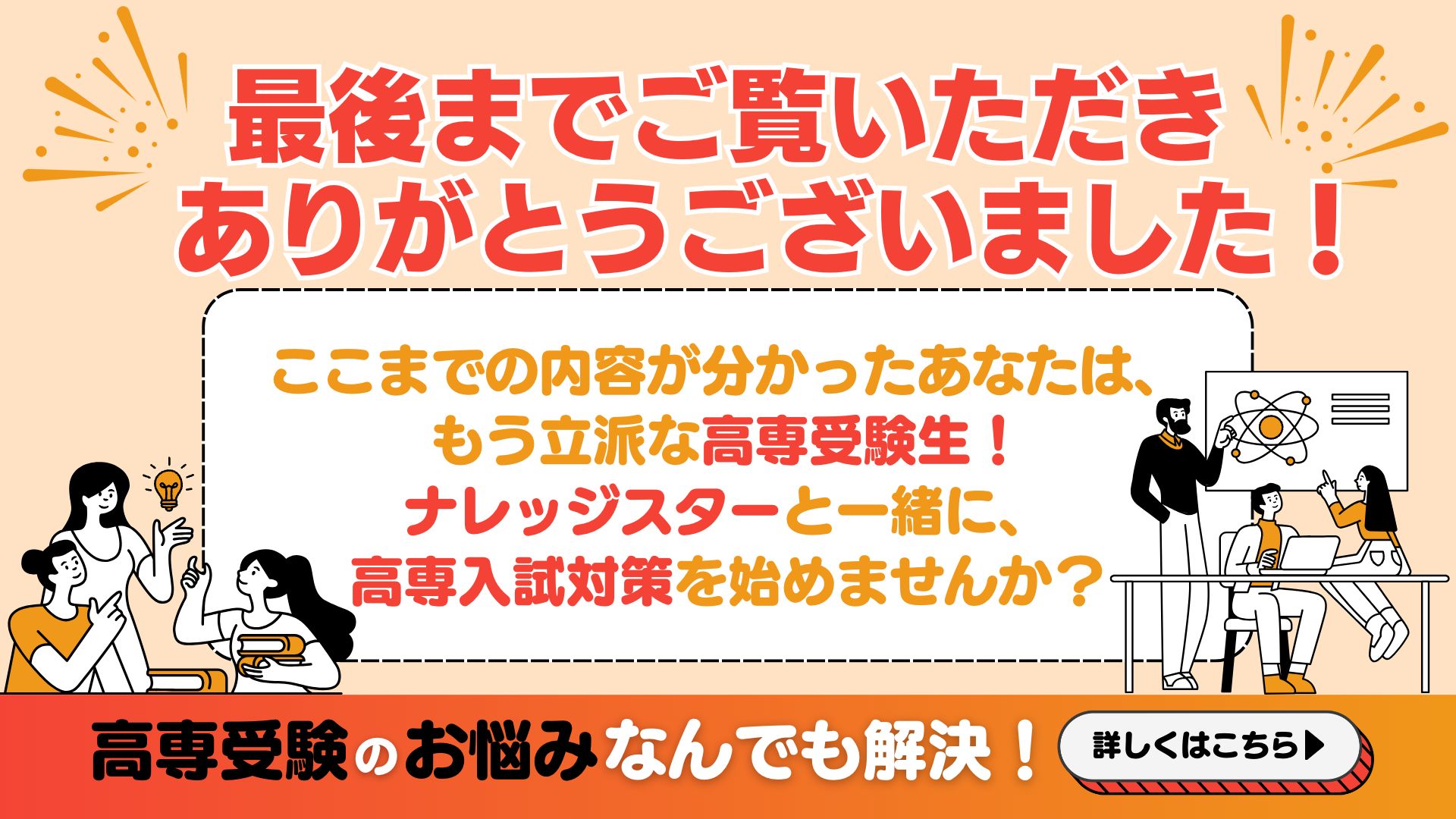
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。