はじめに
大学編入試験は、高専生にとって“短期間で大卒資格を得る”大きなチャンスです。しかし、試験科目や受験方式、時期、編入学年などは大学によってさまざまで、情報不足のままでは思わぬ失敗を招きかねません。本記事では効率的に合格を目指すポイントをまとめました。
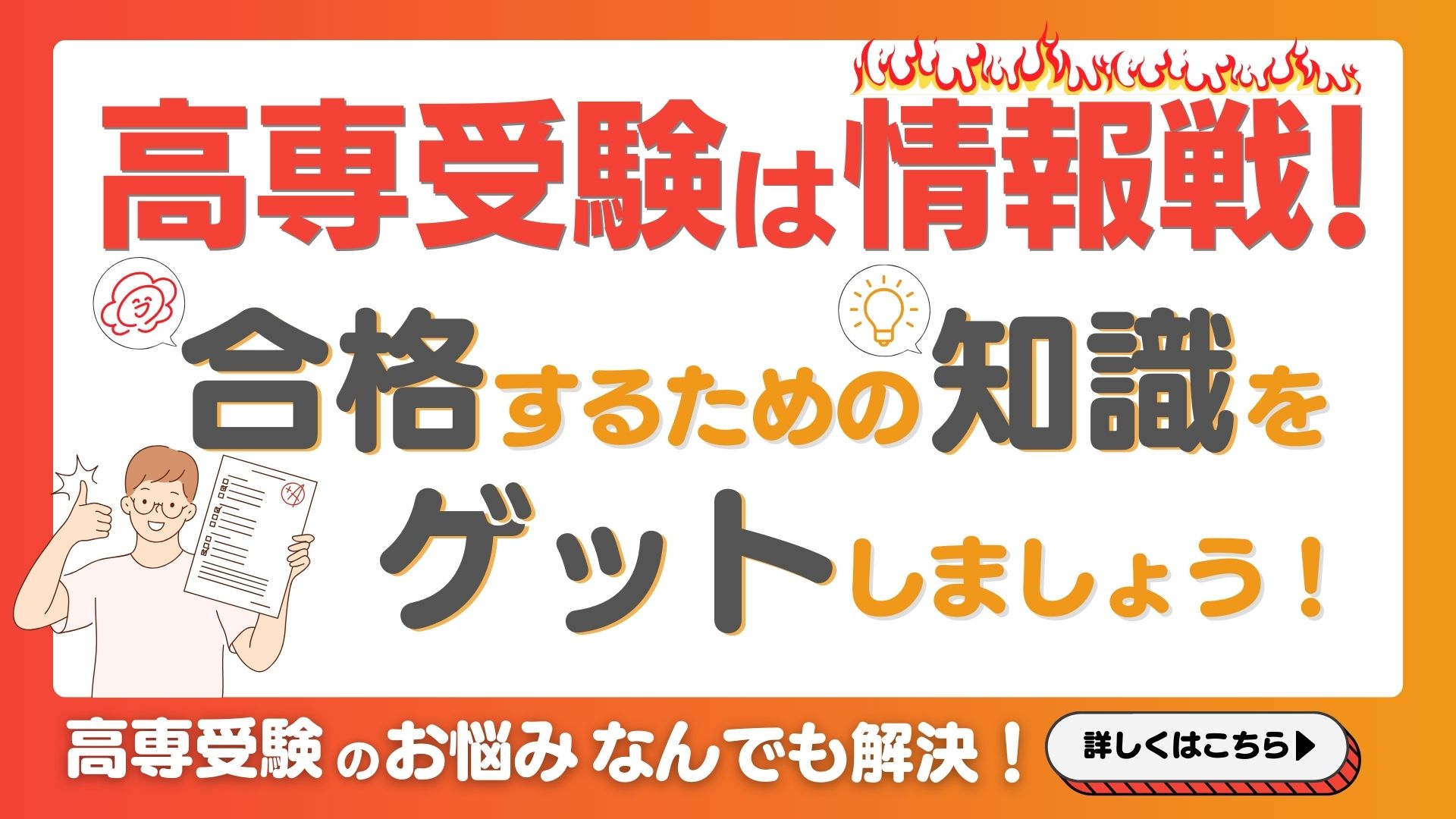
1.編入試験の概要について
大学編入試験は、共通テストを経ずに各大学の試験を直接受けるため、科目数や出題範囲が大学ごとに大きく異なります。多くは一般入試の場合、数学・物理・専門科目が基本で、一部は英語をTOEICスコアで代替する場合もあります。推薦入試の場合、筆記試験はなく面接試験のみ(口頭試問を含む)の場合が多いです。推薦入試でもTOEICスコア提示の大学が多いです。
たとえば東京工業大学では数学と物理が中心ですが、名古屋工業大学では化学が加わるケースがあります。これらの情報は公式サイトや募集要項で随時更新されるため、必ず最新の要項を確認しましょう。
対策としては、まず志望校を3~4校に絞り、各大学の過去問を集めることが重要です。過去問は大学の入試広報ページで公開されているほか、ナレッジスターの大学編入試験対策コースでも入手方法が詳しく解説されています。
一校ごとに異なる科目構成を把握し、計画的に学習すると効率よく点数を伸ばせます。
2.複数大学併願受験できる編入ならではのメリット
大学編入試験は日程が大学ごとにバラバラなため、併願受験が可能です。試験日が被らなければ、国立・私立を問わず複数校を同時に受験できます。こちらは編入学ならではの大きな特徴の一つです。
併願する際は「挑戦校」「適正校」「滑り止め校」の3つに分類しましょう。挑戦校は難易度高め、適正校は現状実力に合う大学、滑り止め校は合格可能性が高い大学を選びます。
リスク分散を図ることで、万が一の不合格リスクを軽減できるうえ、自分に合った学びの場を落ち着いて選べます。
併願校リストは最低3校は用意し、出願書類や試験対策の準備を並行して進めるのがおすすめです。
滑り止めとして専攻科を視野に入れておくのもいいでしょう。
私の場合、本命校1つと滑り止め校1つで出願をしました。滑り止め校があると受験料はかかりますが、安心さを得ることができるのでいくつか考えておくことをおススメします!
3.推薦入試と学力入試の違いとは?
推薦入試のポイント
高専からの編入学試験で推薦受験を受けられるかどうかは受験校が定める基準を満たしているかどうかで決まります。その基準とは「高専での席次が上位〜%」であったり、「成績が上位な者」であったりします。主に高専在学中の成績で推薦受験を受けられるかどうかが決まります。4年次の成績が対象であったり、3〜4年次の成績が見られたりと大学によって様々です。条件は大学によりけりなので必ず確認しましょう!面接重視の大学も多いため、卒業研究を早い段階で進め、研究テーマの理解度を深めて面接練習を重ねましょう。詳しいメリット・デメリットは専攻科と大学編入の比較記事も参考になります。
学力入試のポイント
筆記試験中心の学力入試では、数学・物理の高度な問題が出題されます。学科に特化した科目が数学や物理とは別に設けられている大学もあります。大学の共通テストに比べて科目数は少ないものの、専門科目の内容が多く問われるため、高専1年生の基礎の内容から5年生で学ぶ応用の内容まで幅広く復習することが必要です。
英語はTOEICスコアで免除・換算される場合があるので、早めに受験しておくことをおススメします!3年から4年にかけてTOEICの勉強が終わっていることが理想です!
4.編入試験の時期と注意点
大学編入試験はおもに6月〜8月に集中します。
企業の早期選考とも重なるため、編入試験と就活の両方を検討している場合はスケジュール調整が不可欠です。試験直前期は勉強と企業説明会が同時進行になることもあるため、志望順位を明確にし、優先度の高いイベントを見極めて日程を組みましょう。
5.編入学年は3年次でない可能性も…??
大学編入学年は、2年次・3年次・1年次編入など、大学や学科によって異なります。高専で取得した専門科目の単位がどれだけ認定されるかで決まるため、募集要項で必ず確認しましょう。
単位変換については、募集要項に記載されていないこともあるので大学に問い合わせたり、実際に大学に行ったりして単位変換について聞くことを必ずしてください!!
大学によって単位変換される数は異なります。私が編入した大学は90単位認められましたが、高専の同級生が編入した大学の学科では70単位未満しか認められていませんでした。
なかには30単位程度しか認められなかったことも、、、
単位認定が厳しい=ストレートで卒業することが厳しくなるということです。卒業単位は125単位以上が多いです。
また、単位認定されない分、編入後の履修する科目が増え忙しくなりかねません。
高専で専門していた分野から違う分野に進もうとするとそのようになりますので注意してください!
3年次編入は大学に2年間通うため学費負担は軽くなりますが、授業内容が難易度高めです。2年次編入は3年間在籍となり、基礎から学び直す余裕があります。どちらもメリット・デメリットがあるので、将来設計と照らし合わせて選ぶことが重要です。
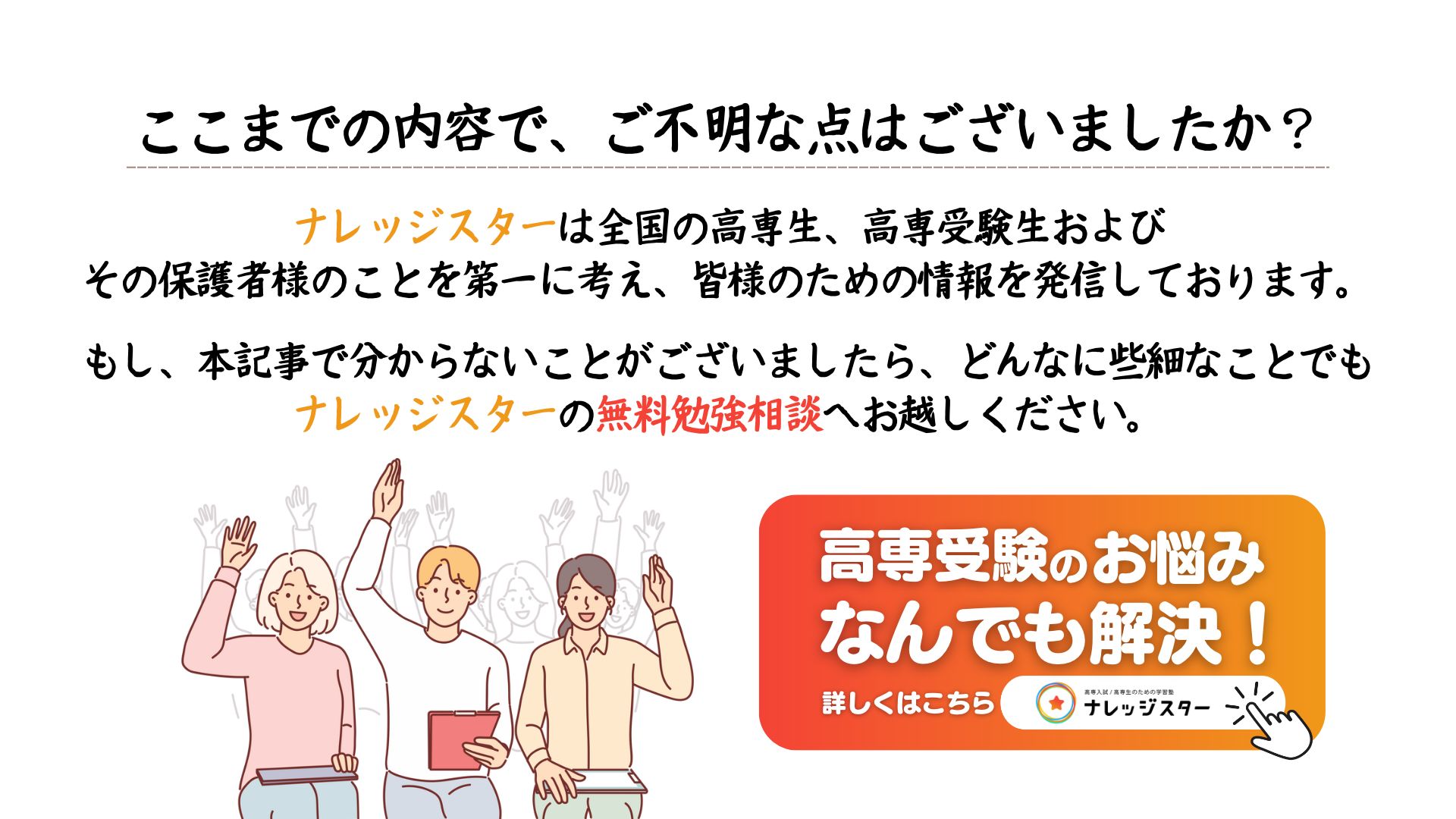
6.数学・物理・英語を効率的に勉強するには?
数学・物理対策のコツ
数物は積み重ね科目のため、1年生内容から着実に基礎を固めるのが大前提です。おすすめは「単元別完成ノート」を作り、弱点単元を集中補強する方法です。大学が提示している過去問を通じて頻出パターンを把握し、類題演習を繰り返しましょう。
英語対策のコツ
英語はTOEICスコアを利用できる大学が多いので、まずはTOEIC公式問題集で形式に慣れ、毎日リスニング30分+リーディング30分の学習習慣をつけましょう。
大学によっては、600点以上のスコアがあるとかなり余裕ができます!
過去問分析で出題傾向を把握する
大学編入試験には傾向があるため、過去問分析は必須です(大学による)。数学ではベクトルや微分・積分、物理では力学・電磁気、英語では技術文書読解、技術者に特化した英単語が頻出です。
過去問は大学公式サイトで公開されているほか、ナレッジスターの大学編入試験対策コースでも扱っています。資料を揃えたら、年度ごとの出題単元を一覧化し、重点対策リストを作成すると効率アップします。
7.受験校を挑戦・適正・滑り止めに分けて考える
併願校リストは「挑戦」「適正」「滑り止め」の3段階でまとめましょう。挑戦校は偏差値や過去問難易度が高い大学、適正校は過去数年の合格可能性が見込める大学、滑り止めは安全圏の大学・専攻科です。
受験校の選定は学科の研究内容やキャンパス立地、就職実績も加味して総合的に判断するとよいでしょう。情報収集には高専から大学編入への道のりも参考にしてください。
8.万が一全部不合格だった場合の選択肢って?
浪人・秋入試の選択肢
もし全ての試験に不合格となった場合は、1年間の浪人や秋入試のある大学を検討しましょう。秋入試は募集校が限られますが、志望校の幅を広げる保険になります。
就職活動に切り替える
高専生は推薦枠での就職が強みです。就活を並行する選択肢も視野に入れ、自分の市場価値を確かめてみるのも有効なプランです。夏ごろになると2次募集もあるため、まだまだ希望はあります!
9.どうやって情報収集する?
研究室訪問に行く
一番はやはり実際に大学に行き話を聞くことです。
大学の雰囲気を肌で感じたり、単位変換、研究内容について話しを聞いたりできることはとても重要です。また、研究室訪問に行ったことは面接試験の話しのネタにもなります。
第1希望の大学には一度行くことをおススメします!
先輩からの情報収集
高専内の先輩や部活動・研究室のOB/OGから過去問や面接対策を聞き出しましょう。
SNS・コミュニティ活用法
X(旧Twitter)や編入コミュニティ「ZENPEN」などで情報共有イベントが頻繁に開催されています。積極的に参加し、最新の募集要項や体験談を手に入れましょう。
編入生向けのイベントも開催しています。確認しましょう!
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ:大学編入成功のポイント
大学編入は「情報戦」と言われるほど、早期の情報収集と戦略立案がカギです。低学年のうちから志望校リストを作り、科目別の学習計画を練りましょう。過去問演習と面接練習を徹底すれば合格率は大きく高まります。情報が整ったら、あとは継続した努力あるのみ。自信を持ってチャレンジしてください!!
FAQ:よくある質問
Q1. 推薦入試と学力入試、どちらを選ぶべきですか?
A. 成績上位なら推薦入試、基礎学力重視なら学力入試がおすすめです。推薦は面接重視、学力入試は筆記重視と心得ましょう。
Q2. 併願できる大学の上限はありますか?
A. 特に上限はなく、試験日が被らなければ複数校の併願が可能です。事前に日程調整を必ず行ってください。
Q3. 過去問はどこで入手できますか?
A. 大学公式サイトなどで入手できます。
Q4. 編入後の卒業時期はいつになりますか?
A. 編入学年によって2年後または3年後の卒業になります。募集要項で「何年次編入」かを必ず確認しましょう。
Q5. 情報収集はいつから始めるべきですか?
A. 低学年(1~2年生)から志望校リストと過去問の収集を始めると、余裕を持って対策が進められます。
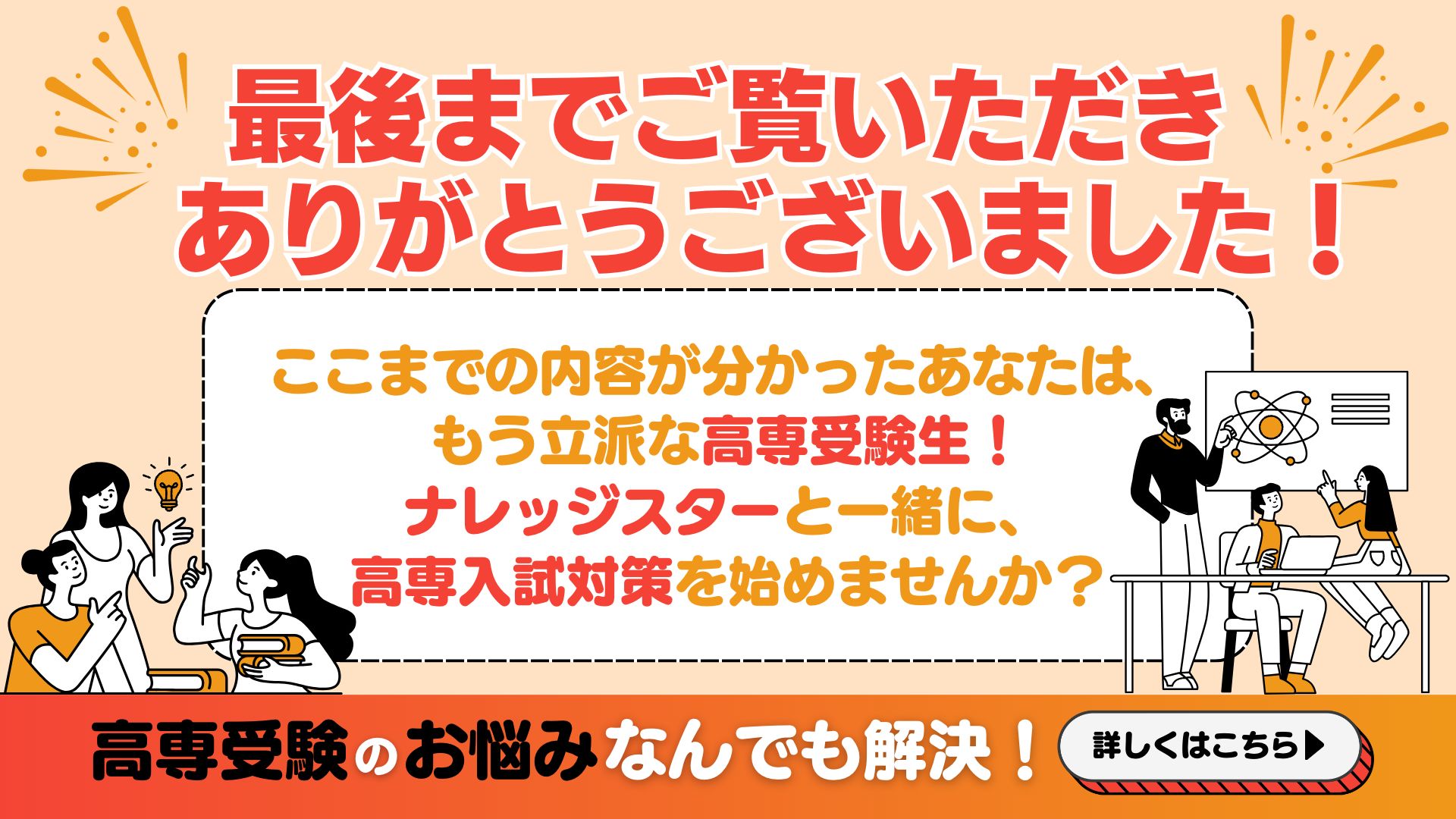
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。










