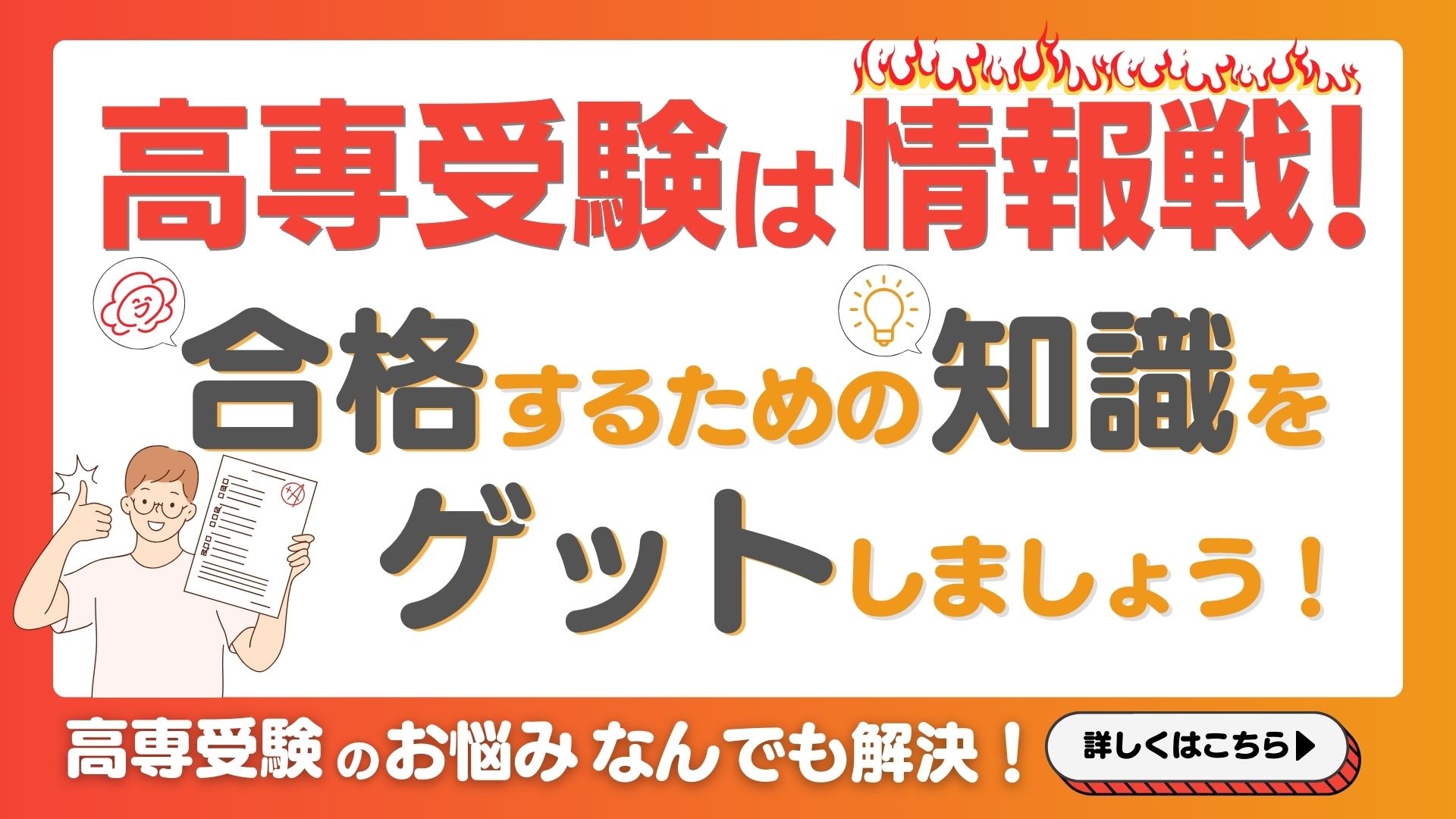
はじめに
高専卒から大学院に進学すると、研究に集中できる2年間で専門性を飛躍的に高め、「修士号」という国際的に評価される学歴を取得できます。就職後、研究開発・設計への配属機会への参加チャンスも大きく広がります。一方、早期就職を選ぶと早い段階で収入を得られ、早く実務経験を積めるものの、専門研究や上流工程での活躍機会は限定されてしまうことが多いです。自分のキャリアビジョンや経済状況を踏まえ、進学か就職かを検討しましょう。全体的な進路選択については進路ガイド|高専からの進路はどんな選択肢がある?をご覧ください。
高専から大学院進学するメリット
進学ルートを知る
大学院進学は大きく3つのルートがあります。
- 大学卒業後に大学院へ進学
- 高専から大学編入して4年次から大学院へ進学
- 専攻科から大学院入試で大学院に進学
研究を深掘りできる2年間
大学院では授業より研究がメインとなり、自分の研究分野の実験や論文執筆を重ねます。
同じ領域を極める仲間や指導教員と議論し続けることで、専門知識と課題解決力が飛躍的に向上します。
ここで得た経験は、そのまま卒業研究や就職後仕事で必ず活かされます。
修士号がもたらすこととは?
修士号は学士・博士の中間に位置し、世界共通の学歴証明として認められます。海外の大学院や国際共同研究への参加がしやすく、社会での評価は高いです。国内でも大手メーカーや研究機関では「修士以上」を要件とする求人が増える傾向があります。入社後の待遇アップにもつながります。
よく考えて大学院への進学を考えましょう。
上流工程で働くチャンスが広がる
製品開発は「研究→設計→生産→品質管理→サービス」の5工程に分かれます。
研究・設計の上流工程ほど高い専門性と責任が求められ、年収や待遇が良い傾向です。
大学院修了者は上流ポジション(研究・開発)へ配属されやすく、長期的なキャリア形成に有利です。早期に上流を経験する意義は大きいでしょう。
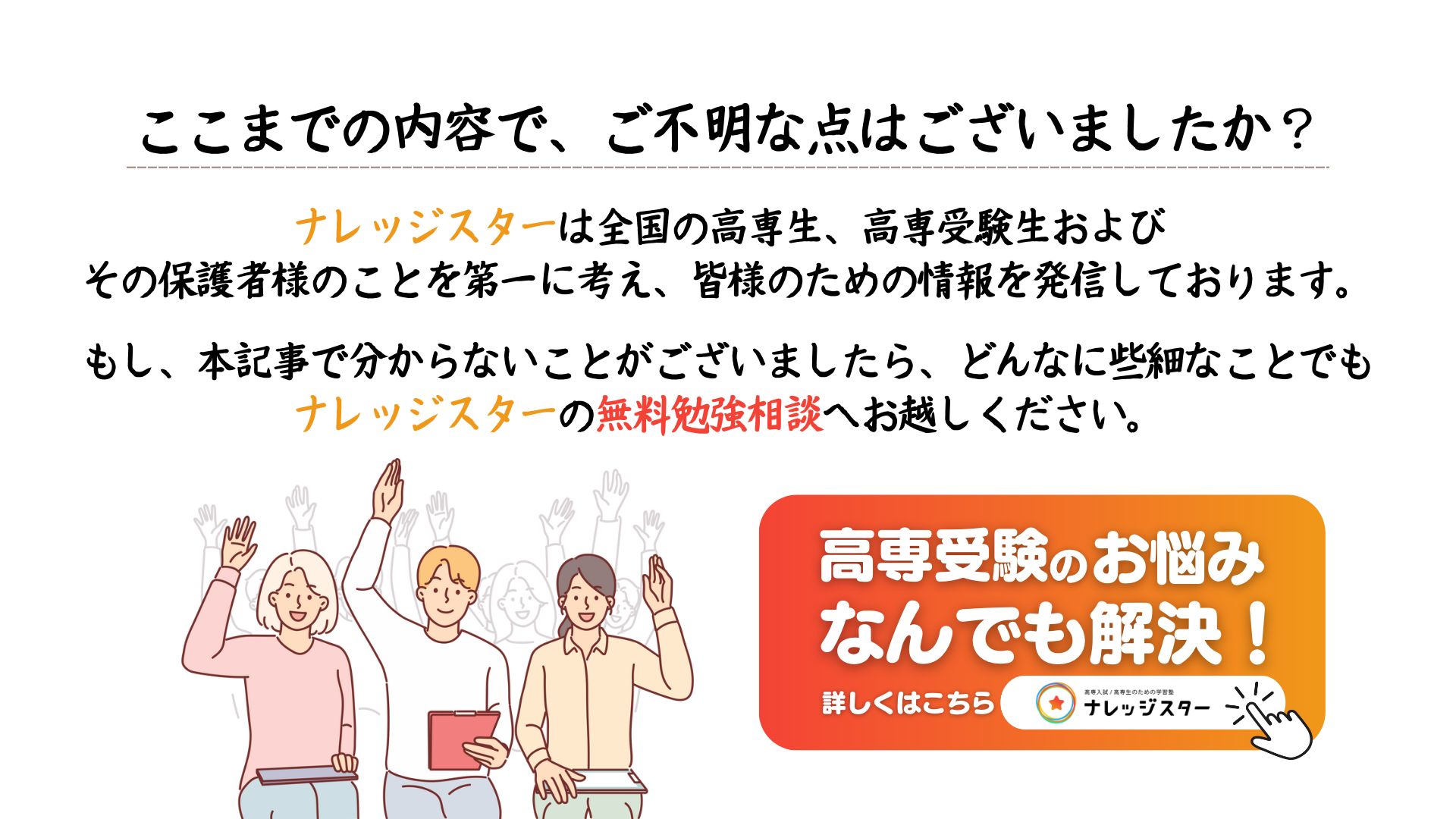
AI時代に必要な高度人材になる
AIやデータサイエンスの進化で単純作業はAIが行うようになりつつあり、現代では研究開発人材の需要が急増しています。大学院で培ったデータ解析力や論文発表経験、プログラミングスキルは、様々なプロジェクトで即戦力として評価されます。スタートアップやベンチャーでも高い関心を寄せられ、多様な企業からオファーが届く可能性が高くなります。
大学院進学しない選択肢と注意点
早期就職のメリット・デメリット
メリット
- 収入開始が早く、経済的負担が軽減される。
- 実務経験を積みながらキャリア形成が可能。
デメリット
- 研究開発や設計など上流工程での仕事が限定されることがある。
- AI自動化の波で下流作業の需要が減少するリスクがある。
自分が希望する業務内容をしっかり見極めることが重要です。
経済的負担と時間的制約
大学院2年間は授業料と生活費が重なるため、年間約200~300万円が必要になります。
学費負担を抑えるには、高専5年間の学費はぶっちゃけいくら?奨学金制度も解説!を参考に、日本学生支援機構や各種奨学金を活用しましょう。入学前から情報収集をおすすめします。
ベンチャー企業からみる大学引率
大企業では研究開発部門の上流工程に「修士以上」を要件とする求人が多い一方、ベンチャー企業では高専卒でも上流工程に携われるチャンスがあります。大企業の安定感や福利厚生と、ベンチャーの裁量権やスピード感にはそれぞれメリット・デメリットがあります。自分の将来像に合わせて企業選びを行いましょう。
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ:進学か就職かの選択指針
高専卒から大学院に進むと、研究スキルと修士号を武器に上流工程で活躍できる道が開けます。また、学士卒に比べて給料に差があります。大学卒または高専卒での就職は収入開始が早く実務経験を積みやすい反面、専門研究機会は限られます。自分の興味・関心、将来像を考えて進学か就職かを判断するようにしましょう。高専全般の情報は高専とは?特徴を徹底解説もご覧いただくと理解が深まります。
FAQ
Q1. 高専から直接大学院に進む方法は?
A1. 専攻科進学後、大学院入試を受験し、面接・小論文・TOEICなどで合格を目指します。募集要項を確認し、必要な試験科目を計画的に準備しましょう。
Q2. 進学にかかる費用はどれくらい?
A2. 授業料と生活費で年間200~300万円程度が目安です。奨学金や教育ローンを活用すると負担を軽減できます。
Q3. 就職と進学、どちらが向いている?
A3. 「専門研究や設計に強くなりたい」なら進学、「即戦力として実務経験を積みたい」「早く収入を得たい」なら就職がおすすめです。まずは将来像をイメージしてみてください。
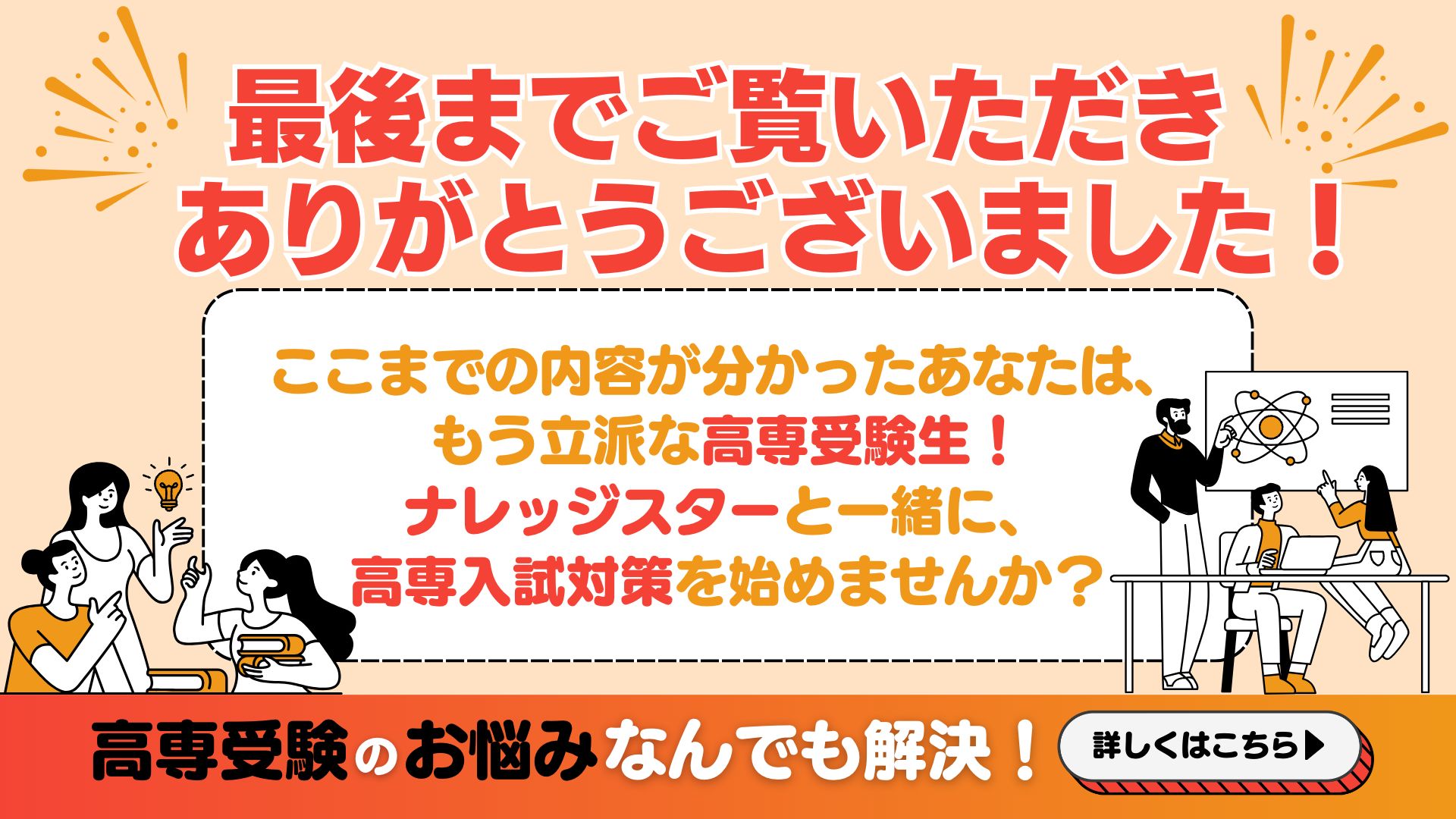
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。










