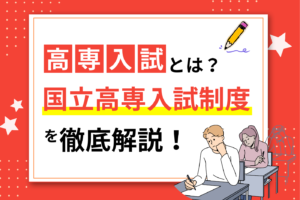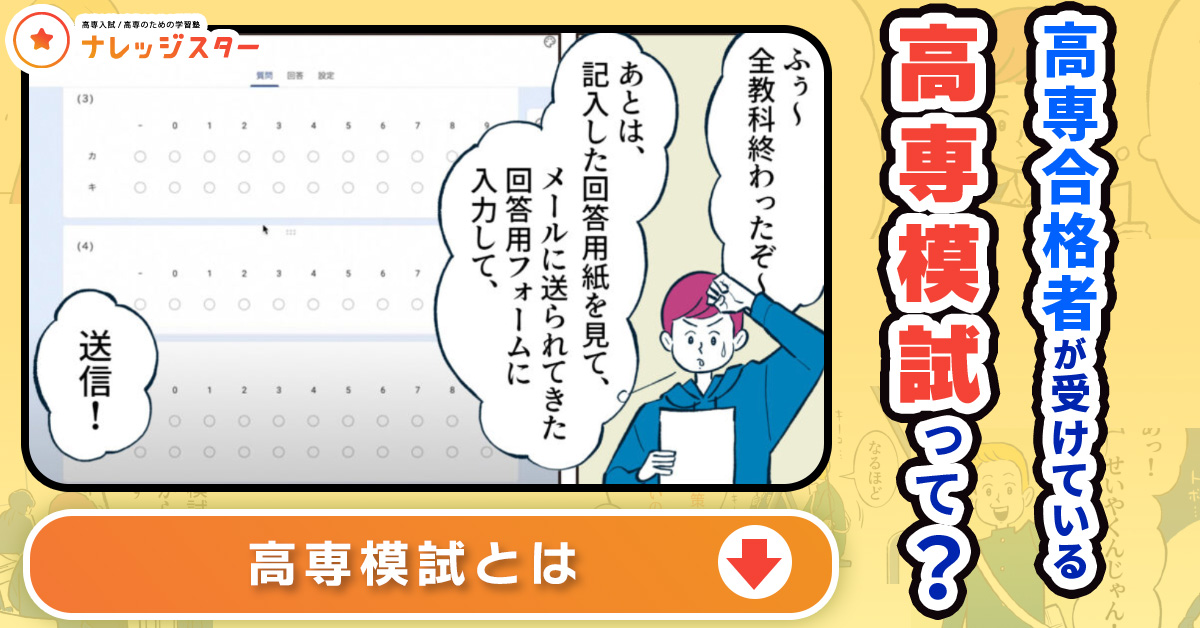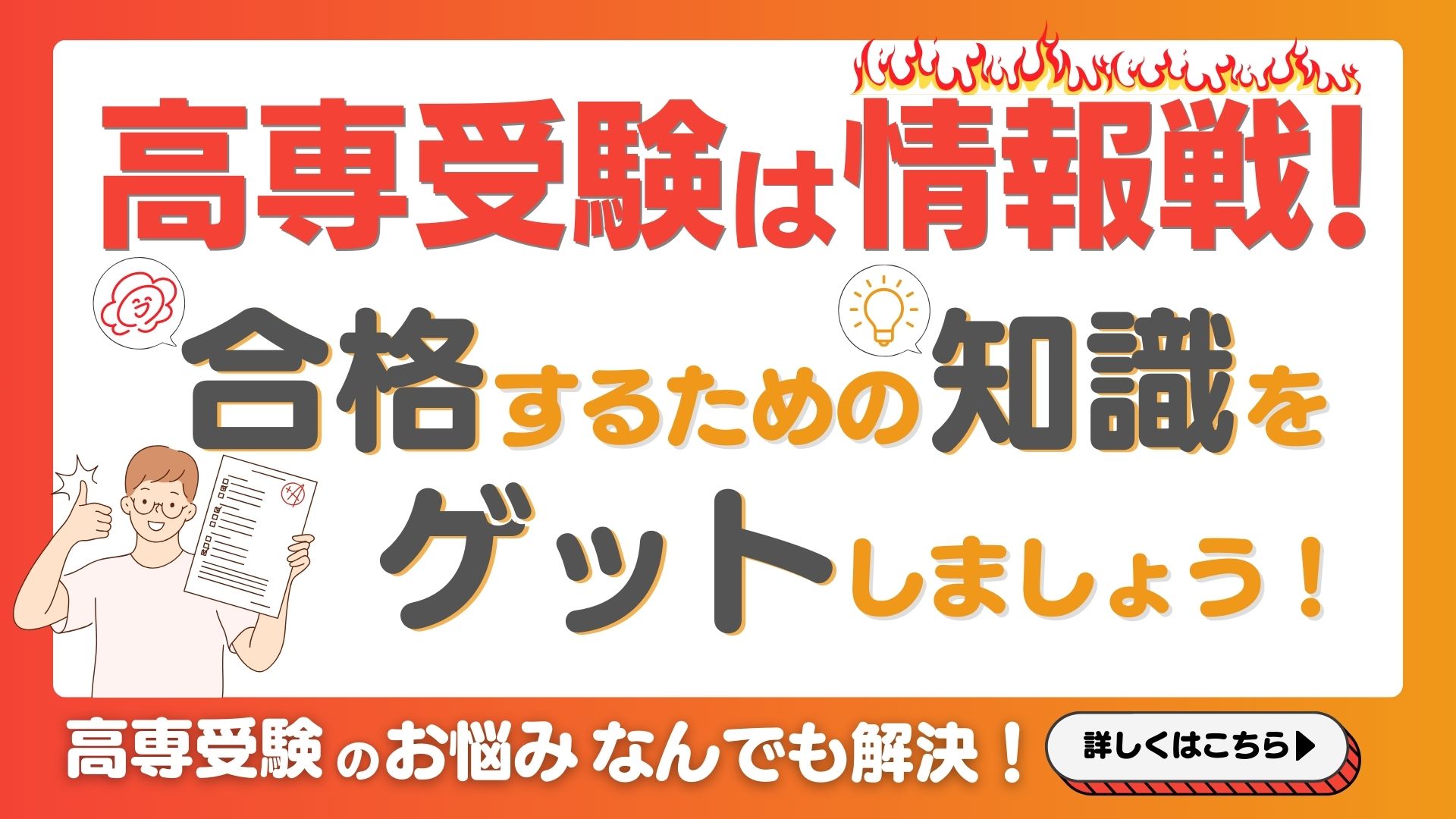
はじめに
10月の高専受験生は、定期テストの直前期に入ります。結論から言うと、この時期は定期テスト対策を最優先にするのが最も効率的です。理由は2つあります。
第1に、評定(内申点)が推薦入試で大きな比重を占めるためです。
第2に、最近は学力入試でも調査書点を得点化する高専が増えており、定期テストの積み上げが合否に直結しやすいからです。もちろん例外もありますが、多くの受験生にとっては「テスト前は定期テスト全振り→終わったら入試演習に復帰」が最短ルートです。悩む時間を減らし、切り替えの早さで差をつけましょう。なお、入試制度の全体像は学内成績と当日点の両輪で考えると整理しやすいです。
受験全体のゴールと10月の優先順位
受験のゴールは「合格確率の最大化」です。この視点で見ると、10月は評定を押し上げる最後のチャンスになりやすく、テスト前の2週間を定期テストに集中する価値が高まります。中3後半単元は入試の頻出領域なので、定期テストの勉強そのものが入試力を底上げします。テスト終了後は48時間以内に入試演習へ切り替え、定期テストで見つかった弱点を「過去問→解き直し」で補強します。模試の結果は次の学習計画に反映し、弱点の科目・単元を数値で管理しましょう。
定期テスト重視の理由(評定と入試の関係)
評定は推薦入試で最大の決定要素です。評定の基本は日々の提出物や授業態度、そして定期テストの得点です。ここで稼げるかどうかで推薦の土俵に立てるかが大きく変わります。さらに、学力入試でも調査書点を得点化する高専があり、当日点だけでは届かない差を埋める「上乗せ」になります。したがって10月の定期テストは「推薦の合否」と「学力の上乗せ」の両方に効くということです。定期テスト前は「学校ワーク完遂→学校プリント→授業ノート整理→予想問題」の順で仕上げ、評定に直結する作業へ集約しましょう。
推薦で評定が効く理由
多くの高専は推薦の受験資格として平均評定4.0前後を求め、選抜でも評定の比重が大きくなります。面接や小論文は重要ですが、評定の土台が不足すると厳しい戦いになります。だからこそ、定期テスト直前の2週間は提出物の質と期限厳守、授業で扱った範囲の反復で「取りこぼしゼロ」を狙います。評定は一朝一夕では上がりませんが、直前の丁寧な準備で下振れを防ぐことはできます。出欠や態度も評価対象なので、生活リズムも整えて本番に臨みましょう。
学力入試でも評定が影響する最新事情
近年、一部の高専は学力入試でも評定を加点します。比重や算出法は学校ごとに異なるため、募集要項の確認は必須です。もし評定が不安なら、評定を加算しない高専を選ぶという戦い方もあります。いずれにせよ「評定は無関係」と決めつけず、まずは自分の志望校の方式を把握しましょう。今からでも間に合う評定アップの行動として、提出物の精度向上、期限厳守、定期テストの得点底上げが効果的です!
例外ケース:学力全振りで良い場合
例外は2つです。①推薦を受けないことが確定している受験生、②志望校が学力入試で評定を用いない(調査書点を加点しない)ケースです。この場合は、テスト前であっても「入試で得点が伸びる学習」に軸足を置けます。ただし、学校課題の未提出や極端な低得点で評定を下げるのは得策ではありません。最低限の提出と授業理解は守りつつ、時間の大半を過去問演習や弱点補強に回しましょう。判断に迷うなら、まず募集要項で評定の扱いを確認し、自分の立ち位置から逆算してください。
推薦を受けない人
推薦を受けないなら、模試→過去問→弱点単元の反復で当日点の最大化を狙います。具体的には、週あたりの演習量を「数学30題・理科20題・英語長文2本」を目安に設定し、丸付けと解き直しに同等時間を使います。得点の伸びは「間違いの質」を変えた回数で決まるので、間違い直しノートを必ず使いましょう。
評定加算なしの高専を受ける人
評定を加算しない高専を受ける場合、対策はよりシンプルです。試験本番で取る力=タイムマネジメントとケアレスミス削減が鍵になります。時間を測った本番条件の演習を週3回入れ、「できない理由」を言語化して再発防止策を1行で決める運用にしてください。英語は文法の穴を先に塞ぎ、長文は設問先読み→段落要旨取りの型で処理速度を上げます。
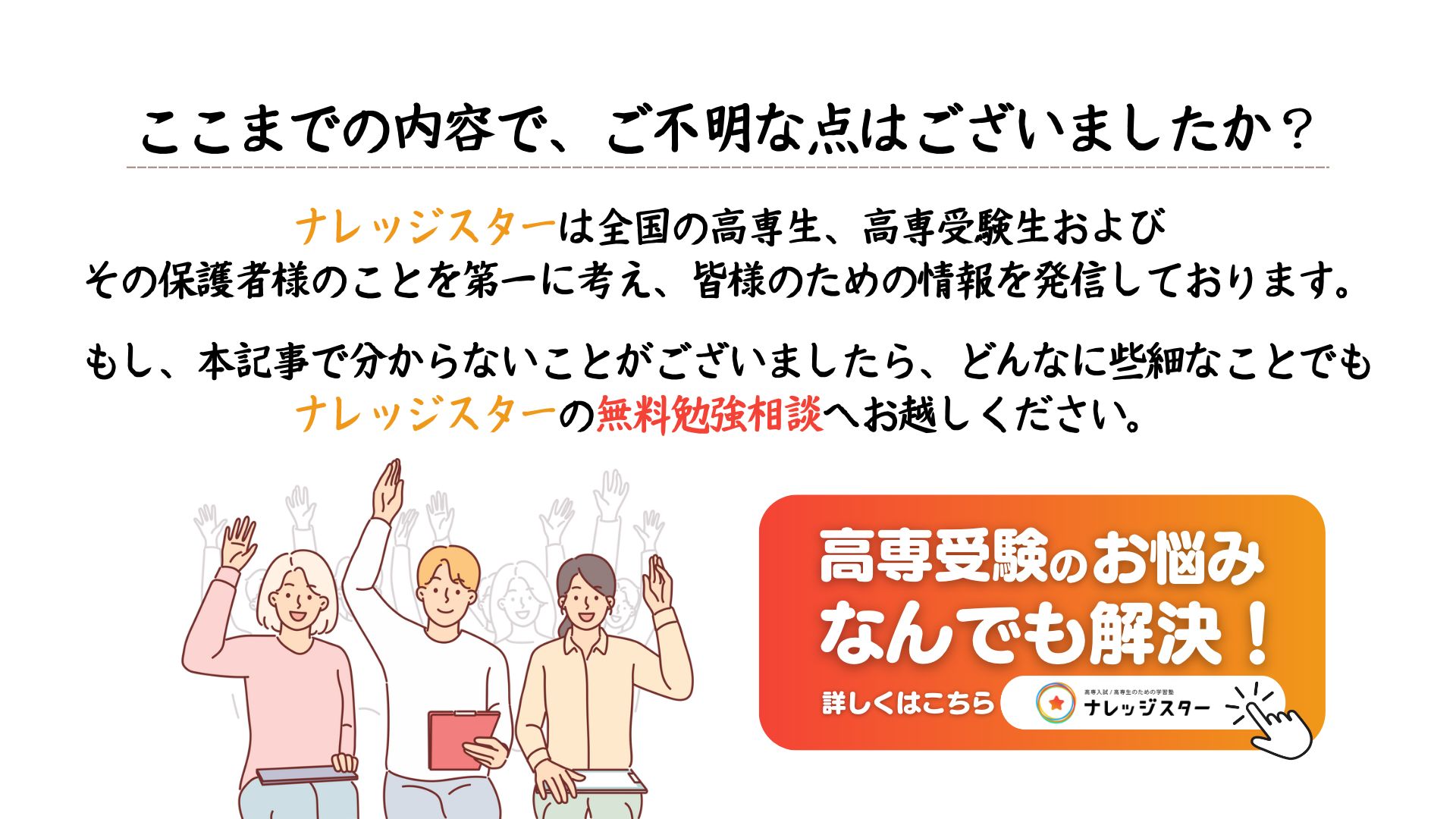
2週間前ルール:学習スケジュールの作り方
テスト2週間前からは、学習を「定期テスト対応」に全面シフトします。最初の3日で学校ワークの1周目を終え、以降は間違いだけを抜き出して2〜3周目を解きましょう。授業ノートとプリントは「出題要点→根拠ページ→解き方」の3点メモに整形し、前日までに予想問題で通し演習を1回。提出物は期限の48時間前までに仕上げ、忘れ物ゼロを徹底しましょう。テスト終了後48時間はリカバリー期間として、間違い直し→入試過去問へ切り替え、弱点単元を入試仕様で対策しましょう。
テスト前2週間の時間の使い方
1週目は範囲の概観把握と既習単元の穴埋め、2週目は得点化の仕上げに充てます。毎日「数学45分→理科45分→英語30分→提出物15分」の短い回転を3セット行うと、集中と復習のリズムが作れます。社会は重要語の暗記カード、国語は授業範囲の教科書精読と設問パターンの確認で得点の下振れを防ぐことができます。夜は必ず丸付けと間違い直しを行うのを徹底しましょう!
テスト後48時間の切替え術
テストが終わった直後は疲労で学習が散らばりやすいので、「テストで落としたところのチェックリスト」を先に作ります。次に、間違ったところと同じ分野の入試過去問を3問だけ解きましょう!
教科別の優先度と勉強法
数学・理科・英語は入試得点に繋がりやすいです!
数学は定義と定理の理解→教科書例題→見ない演習の順に進め、途中式のテンプレを決めて手を止めないことがコツです。
理科は計算系と用語系を分け、計算は「公式→代入→単位」をチェックし、用語は図とセットで覚えましょう。
英語は文法の穴埋めが大切です。文型・時制・関係詞のミスを先になくし、長文は設問先読みで根拠となる部分を線引きします。
社会は暗記カードと年表整理で時短、国語は授業範囲の精読と設問パターン対応で評定の取りこぼしを防ぎましょう。
数学・理科・英語を伸ばすコツ
数学は「例題→演習→解き直し」の3周を短周期で回すと伸びが速いです。理科はグラフ問題の軸と単位、英語は品詞と句・節の見分けを最初に固めると得点が安定します。どの科目も、答え合わせ直後に「なぜ間違えたか」を5〜10字でメモし、同型問題で再現できるかを24時間以内に再テストしましょう。
社会は暗記で時短、国語は評定対策で調整
社会は用語と因果のセット暗記で短時間でも得点化できます。国語は入試との形式差があるため、評定が不足している場合に重点配分し、授業範囲の得点取りを確実に。入試目線では、国語は語彙と要旨取りの基礎だけ維持し、時間は数学・理科・英語に寄せるのがおすすめです。
定期テスト対策=入試対策にする工夫
前項にも書きましたが、中3後半単元は入試頻出です。定期テストの勉強を、同単元の入試過去問で仕上げれば、二重取りができます。やり方は簡単で、学校ワークで基礎→同範囲の高専過去問を時間計測で1回→間違い直しの順に回すだけです。過去問はまず3年分を通して解き、傾向と弱点を掴んだら、同一論点を100%まで仕上げます。
中3後半単元の攻略と過去問の使い方
10月時点で未習の単元がある人は、教科書→例題→入試過去問の最短動線で予習を進めましょう。配点の重い数学は、方程式・関数・図形の頻出3本柱を毎週ローテーションし、英語は文法と長文読解を1:1で配分するとバランス良く伸びます!
無料勉強相談って??
「高専に行ってみたいけど、勉強についていけるか心配…」、「受験対策は何から始めればいいの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。そんな方のために、高専入試に特化した学習塾・ナレッジスターでは無料の勉強相談を実施しています。高専受験のプロである講師陣が、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスしますので、安心してご相談ください。あなたもナレッジスターと一緒に、高専合格への一歩を踏み出してみませんか?きっと夢への道筋が見えてくるはずです!
まとめ
10月は定期テスト対策を最優先にすることで、評定アップと入試力強化を同時に狙える重要な時期です。評定は推薦・学力入試の双方に影響し、直前の丁寧な準備が合否を左右します。テスト終了後は48時間以内に入試演習へ切り替え、弱点を補強しましょう。定期テストと入試対策を連動させ、限られた時間で効率よく実力を伸ばすことが合格への近道です。
Q&A よくある質問
Q1. テストと受験勉強の比率は?
A1. テスト2週間前はテストと入試勉強の比率を9:1、直前3日はテストと入試勉強の比率を10:0でOKです!テスト終了翌日から入試勉強と学校の勉強の比率を7:3へ切り替えましょう。
Q2. 過去問は何年分やるべき?
A2. まず3年分を通しで勉強し、間違い直しを行い、100%全問題を解けるようにしましょう。
Q3. 模試はいつ受ける?
A3. 月1回ペースが目安です。結果を学習配分に反映して弱点をなくしていきましょう。
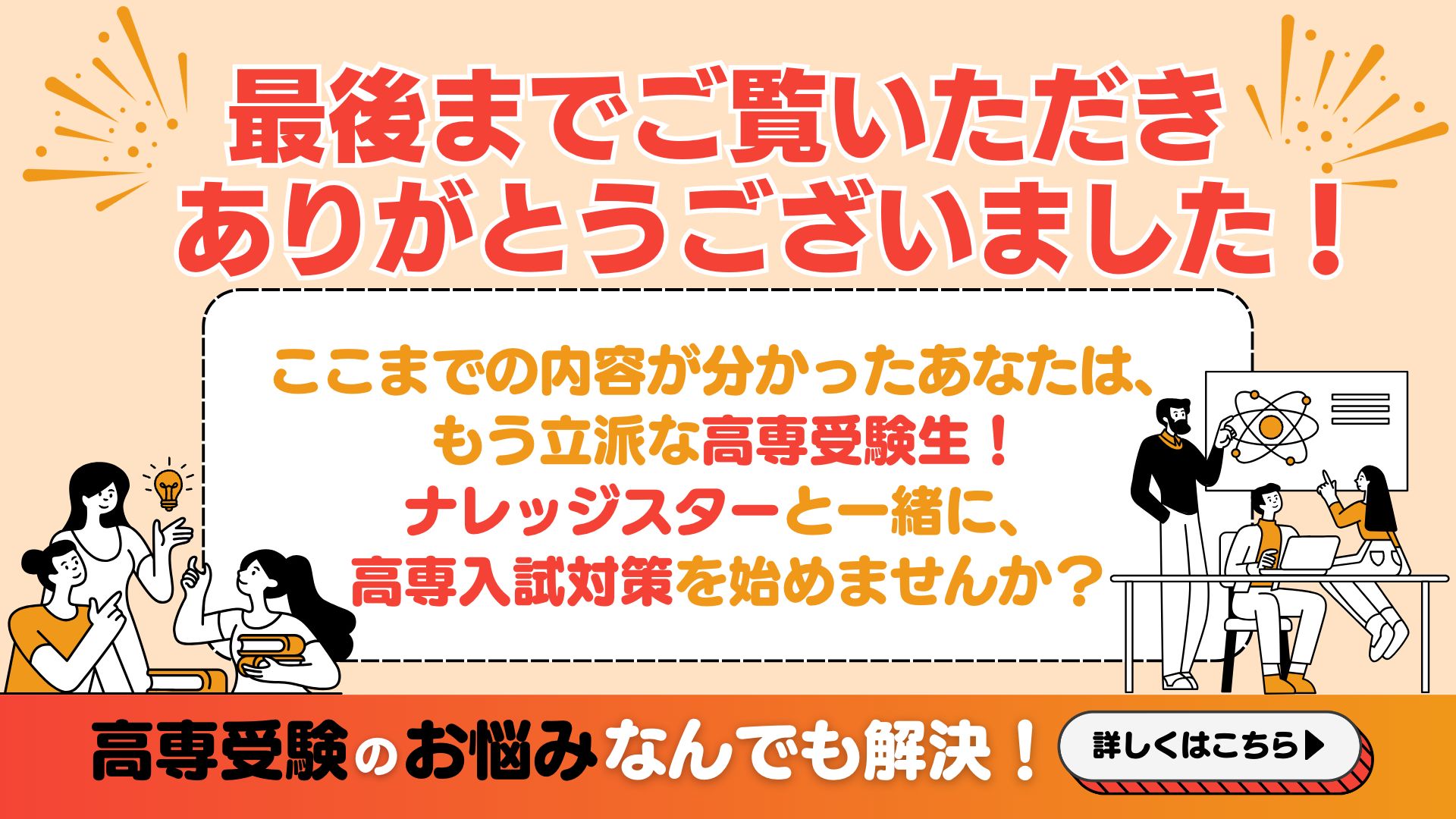
ライター情報
仙台高専マテリアル環境コースを卒業。
ニックネーム:nao
研究室では化学を専攻。コガネムシの研究をしていました。
趣味は野球観戦。楽天イーグルスを応援している仙台っ子です。